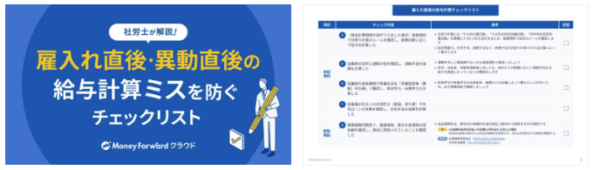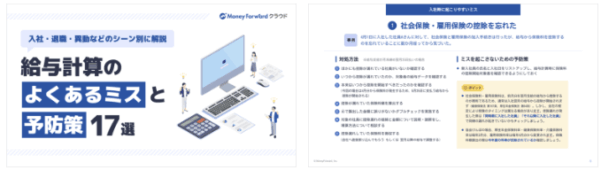- 更新日 : 2025年8月26日
部署異動・社内異動とは?スムーズな進め方や伝え方のポイントを解説
部署異動は、組織の活性化や人材の育成において重要な役割を果たす人事戦略の一つです。新しい環境での経験を通じて、従業員の能力を引き出し、企業の成長を促進するためには、異動の進め方や伝え方が大切です。本記事では、部署異動を成功させるためのポイントやスムーズに進めるための流れを解説します。
目次
部署異動とは
部署異動は、組織の活性化や人材育成、事業戦略の推進など、さまざまな目的で実施されます。ここでは、部署異動の具体的な目的と、検討すべきタイミングについて解説します。
部署移動の目的
部署異動の主な目的は、以下のとおりです。
- 事業戦略の推進
- 業務効率化と組織活性化
- 人材育成とキャリア開発
- 不正防止とリスク管理
それぞれについて、見ていきましょう。
事業戦略の推進
部署異動は、企業が事業戦略を推進するために行われる施策です。新規事業の立ち上げや組織の再編に伴い、適切な知識やスキルのある人材を既存の部署から選出し、新たな役割への配置により、効率的な目標達成を目指す目的で行われます。
部署異動では、挑戦をいとわず経験豊富な人材が求められる場合も多く、対象者の選定が重要なポイントといえます。
業務効率化と組織活性化
部署異動は、業務効率化と組織活性化を促進する有効な手段です。従業員のスキルや適性に応じた部署への異動は、個々の能力を大いに引き出すとともに、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
さらに、部署間の交流を活発化させることで、知識やノウハウの共有が円滑に進み、新たな発想やイノベーションが生まれる可能性も高まるでしょう。
また、部署の固定化によるマンネリ化を防ぎ、組織の新陳代謝を促すことで、従業員のモチベーション向上と組織全体の活性化にもつながります。
人材育成とキャリア開発
人材育成とキャリア開発を目的とした部署異動は、従業員のスキルアップや幹部候補の育成に効果的です。新たな業務経験により、柔軟性のある人材を育成できます。
さらに、経験豊富な社員を育成担当に据えることで、チーム全体のスキル向上も期待できます。こうした部署異動の活用により、多様な業務に対応できる人材を育成する基盤が整うでしょう。
不正防止とリスク管理
部署異動の目的の一つに、不正防止とリスク管理があります。同じ担当者が、長期間にわたり同一業務を担当すると、ミスの隠蔽や横領といった不正が発生しやすくなります。
業務に流動性を持たせるための部署異動により、不正のリスクを抑える効果が期待できるでしょう。さらに、欠員発生時の迅速な対応を可能にするなど、組織運営の柔軟性を高める効果もあります。
人事異動を検討すべきタイミング
人事異動を検討するうえで、適切なタイミングを見極めることは重要です。ここでは、人事異動に適した時期と、一般的な異動の周期について解説します。
人事異動に適したタイミング
多くの企業では、決算月や半期決算月に人事異動を実施する傾向が見られます。決算月は事業戦略を再検討する時期であり、組織再編の必要性が生じやすいためです。
新しい事業の開始や業務拡大の際には、人員配置の見直しが求められます。次年度の目標達成に向けた動き出しとして、決算月に人事異動を行うことは合理的といえるでしょう。
人事異動の周期は3〜5年が多い
独立行政法人労働政策研究・研修機構の「企業における転勤の実態に関する調査」によれば、3年周期が最も多く、次に5年周期が多いとされています。
この3〜5年の周期は、ジョブローテーションの一環として、多様な経験を通じた人材育成に適している期間といえるでしょう。一部の企業では、若手社員の育成を目的に1年未満の短い周期で実施されることもあります。
参考:企業の転勤の実態に関する調査|独立行政法人労働政策研究・研修機構
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
部署異動を行うメリット・注意点
部署異動のメリットは、企業にとっては、適材適所の人材配置が可能となり、組織の活性化と新たな視点や発想の創出につながります。
従業員個人にとっては、多様なスキルの習得やキャリアアップの機会となり、異なる部署での経験を通じて視野を広げられるでしょう。また、業務の属人化を防ぎ、組織全体のリスク管理にも役立ちます。
部署異動を実施する際の注意点として、従業員のモチベーションや生産性が一時的に低下する可能性があります。新しい環境への適応には時間がかかるため、十分なサポート体制が必要です。
また、異動の意図や目的を明確に伝えない場合には、従業員の不安や不満を招く恐れがあります。さらに、個人の希望や適性を無視した異動は、ミスマッチや退職リスクを高めるおそれもあります。そのため、異動後も従業員の状況を定期的に確認し、必要に応じたフォローアップが必要となるでしょう。
部署異動を進める流れ
部署異動を円滑に進めるための流れは、以下のとおりです。
1.組織の現状把握とニーズ分析
まず、組織の現状把握が重要です。各部署責任者へのヒアリングでニーズや問題点を把握します。次に、現場の社員などからも情報収集し、多角的な視点を得ましょう。
次に、異動ニーズを整理します。受け入れ部署で、異動の目的や対象職務、求める人物像を明確にします。目的は、増員や課題解決などさまざまです。対象職務や求める人物像は、採用・評価・育成の観点からも整理するとよいでしょう。
2.異動計画の立案
組織目標達成に必要な人材の能力や人数を管理するため、計画は不可欠です。計画立案にあたっては、経営層と連携し、組織の経営戦略と連動させる必要があります。
従業員のスキル・経験・適性・キャリア志向などのデータを集め、分析しリスト化します。データ収集を怠ると、適切な人材配置ができません。収集データにもとづき、人事異動計画を策定しましょう。
3.異動候補者の選定
人事異動の候補者選定は、計画にもとづき行いましょう。異動は、会社からの打診と本人の希望による場合があります。
会社からの打診では、なぜその人が適任なのかについて期待を込めて説明します。本人の希望の場合は、異動理由やキャリアプランを確認しましょう。
候補者の選定後、異動後の組織全体のバランスを考慮し、問題が予想される場合には、候補者の再検討が必要です。
4.関係者との調整
会社からの打診では、まず異動候補者の上長や部門長に異動の意図や必要性を明確に伝え、協力を得ることが重要です。本人の希望にもとづく場合は、希望を把握したうえで、異動先候補となる部門やチームの責任者と協議を進めます。
一方の受け入れ部門では、判断材料として面接や試験を実施する場合があります。受け入れ判断は採用と同様のため、選考基準がある場合には、比較的容易に進められるでしょう。
5.内示と辞令
人事異動では、まず「内示」で異動の意思を非公式に伝えましょう。内示は異動を事前に知らせるものであり、「辞令」は異動を正式に通知するものです。
内示は口頭の場合が多いものの、内示書を使うこともあります。その後、準備期間を設け、正式な辞令を交付します。
内示から辞令までの期間は、業務の引き継ぎや転居準備に必要な時間を考慮し、余裕をもって設定しましょう。
6.引き継ぎとオンボーディング(定着・戦力化の促進)
引き継ぎとオンボーディングでは、まず異動元で業務内容や進行中の案件を明確にし、新担当者への円滑な引き継ぎをします。
その後、異動先部門では、受け入れ計画を立て、必要に応じてメンターを選任しましょう。また、異動前後のマネージャー間で評価や目標の共有を進め、情報の連携を図ります。
オンボーディングでは異動者が新環境に迅速に適応できるよう支援体制を整え、早期の定着と戦力化を目指します。
7.フォローアップ
フォローアップは、異動者が環境に適応し業務を円滑に進めるために重要です。定期的な面談や研修を実施することで、不安やストレスを軽減し、モチベーションの維持が期待できます。
また、節目ごとにアンケートやインタビューを行い、業務上の課題や改善点を把握すると効果的です。
さらに、チームビルディング活動(組織のパフォーマンス向上を図るための活動)や、歓迎会などを通じた新しいメンバーとの関係構築の支援により、職場での定着と活躍を促すようにします。
部署異動をスムーズに進めるコツ
部署異動は、企業が組織運営上の必要性に応じて人員配置を柔軟に行うための重要な手段である一方で、従業員の業務内容や勤務地、労働条件に実質的な変更をもたらす場合もあるため、企業には法的な配慮と慎重な対応が求められます。ここでは、企業として取るべき配慮のあり方について解説します。
異動命令の根拠を明確にする
企業が従業員に異動を命じるためには、まずその根拠が就業規則や雇用契約に明記されている必要があります。多くの場合、就業規則に「業務上の必要がある場合には配置転換を行うことがある」といった条項が設けられており、これが異動命令の基本的な根拠となります。ただし、記載があるからといって、すべての異動命令が無条件で認められるわけではありません。業務上の合理的な必要性があること、命じられた異動内容が社会通念上相当と認められること、従業員にとって不当な不利益がないこと、など複数の条件を満たしている必要があります。これらの基準を満たしていない場合、異動命令が無効と判断される可能性もあるため、企業側は法的な根拠を明確にしたうえで対応することが重要です。
従業員の意向に配慮する
法的に異動命令が認められる範囲であっても、実務上は従業員の意向に配慮する姿勢が不可欠です。たとえば、家庭の事情や健康上の問題などにより勤務地や勤務時間に制約がある場合、その状況を無視した一方的な異動は、従業員の生活に著しい影響を及ぼす可能性があります。そのため、異動を通達する前に本人と十分に話し合い、背景や希望を確認した上で判断することが望まれます。
なお、労働契約法第3条第3項では仕事と生活の調和に配慮するように定められています。
トラブルを未然に防ぐ仕組みを整備する
異動に関するトラブルを防ぐためには、企業として事前に制度やルールを整備しておくことが有効です。たとえば、就業規則や人事異動に関する社内ポリシーの中に、異動の判断基準や手続き、従業員との対話のあり方などを明文化しておくことで、透明性のある運用が実現できます。また、異動に関する相談窓口を設置し、従業員が不安や疑問を安心して相談できる環境をつくることも重要です。さらに、異動後のフォローアップとしてアンケートや定期面談を実施することで、従業員の満足度や適応状況を把握し、早期に課題を特定して対応することが可能となります。制度と運用の両面からサポートを行うことで、企業と従業員の間に信頼関係が築かれ、健全な人事運営が維持されやすくなります。
部署異動を拒否・希望された場合の対応
従業員からの異動拒否や希望への対応は、適切に行わなければなりません。相互理解を深め、納得を得ることでスムーズな異動を目指しましょう。
拒否された場合
まず、従業員が拒否する理由を把握しましょう。正当な理由(介護や病気治療など、やむを得ない事情)がある場合、異動を強行すると違法になる可能性があります。
次に、就業規則や雇用契約書などに問題がないかの確認です。人事異動は契約条件の範囲内で行う必要があり、範囲を超える場合は訴訟リスクがあります。
正当な理由がない場合は、異動の必要性を説明します。従業員自身へのメリットを伝え、納得を得るよう努めましょう。
それでも拒否する場合は、昇給や昇格、解雇などの検討も必要です。ただし、解雇は最終手段であり、慎重に対応する必要があります。専門家への相談も、視野に入れるべきでしょう。
希望された場合
社員から部署異動の希望があった場合、企業として必ずしも応じる義務はありません。しかし、希望が通らないと判断されれば、社員が転職してしまう可能性もでてくるでしょう。
異動希望の理由が、現在の部署の問題にある場合には、会社として適切な対応が求められます。ハラスメントが原因であれば、事実確認を行い、関係者への措置と再発防止策を講じる必要があります。
部署異動を行う時の伝え方のポイント
部署異動を円滑に進めるには、適切な伝え方が重要です。本人への説明や異動先への連絡など、各段階で配慮すべきポイントがあります。以下で、見ていきましょう。
本人へ伝えるポイント
配置転換を知らせる際には、配置転換の意図が前向きなものであることをしっかりと伝えることが大切です。そして、個人と会社の双方にとってメリットがある点を説明しましょう。
次に、配置転換を行う理由や背景を具体的に説明する必要があります。企業の方針や目標、業務上の必要性などをわかりやすく示すことで理解を促しましょう。
さらに、新たな役割やポジションにおいて期待する内容を伝えることで、従業員の納得を得やすくなります。
異動先の従業員や関係部署へ伝えるポイント
異動の挨拶は、まず正式な辞令後に行います。伝える相手は、現部署、異動先、取引先です。手段は対面、電話、メールですが、可能な限り対面が望ましいでしょう。
メールの場合は、個別送信を心がけ、内容は感謝と今後の抱負を述べます。ネガティブな言葉は避け、前向きな姿勢を示します。
異動は、新たな関係を築く機会でもあるため、丁寧な挨拶で円滑なスタートを切れるように心がけることが大切です。
部署異動におけるメンタルケア
部署異動は、企業が経営資源を最適に配分し、組織全体の生産性や柔軟性を高めるための重要な手段です。しかし、従業員にとってはこれまで築いてきた人間関係や仕事の進め方、業務知識などを一度リセットし、新たな環境で一からスタートするような経験を意味します。このような状況は、心理的な不安を引き起こすことがあり、メンタル面での影響も見逃せません。組織としては、異動を業務上の措置として済ませるのではなく、従業員の心理的側面にも配慮した支援体制を整備し、新たな組織への円滑な適応を促す取り組みを行うことが求められます。
環境変化に伴う心理的影響
部署の変更や勤務地の移動といった社内異動は、従業員の生活に大きな変化をもたらします。業務内容だけでなく、一緒に働くメンバー、職場の雰囲気、使用するツールや進捗管理の方法など、あらゆる要素が変わることで、これまでの経験や知識がそのまま通用しないという感覚を抱くことがあります。その結果、自信を失ったり、自己評価が下がったりすることもあります。周囲と上手くコミュニケーションが取れないと感じた場合には、孤立感を深めやすく、精神的なストレスが蓄積されていきます。こうした心理的影響は、放置しておくと離職意向の高まりにもつながりかねないため、初期段階での対応が重要です。
サポート体制の整備方法
メンタル面での負担を軽減し、従業員がスムーズに新しい環境へ適応できるようにするためには、企業としての明確な支援体制が必要です。たとえば、異動前にオリエンテーションや職場見学の機会を設けておくことで、事前に雰囲気や仕事内容を把握でき、不安の軽減に繋がります。また、異動直後には上司との定期的な1on1ミーティングを通じて、業務上の課題だけでなく心理的な側面についても対話する機会を設けることが効果的です。さらに、社内カウンセラーへの相談窓口を整備したり、経験豊富な社員によるメンター制度を活用したりすることで、従業員の精神的な支えとなることができます。こうしたサポートを組織として明示的に提供する姿勢が、従業員にとっての安心感を生み出します。
人間関係の構築のフォロー
異動を成功させるうえで鍵となるのが、新しい職場における人間関係の構築です。異動者自身が順応しようと努力することはもちろん大切ですが、それ以上に受け入れ側のチームが協力的な姿勢を示すことが、信頼関係を築くためには欠かせません。例えば、初日に歓迎のあいさつや紹介の機会を設けるだけでも、心理的なハードルが大きく下がります。また、異動直後に小さな業務や共同作業を通じて交流を深めることで、自然なコミュニケーションが生まれやすくなります。お互いの価値観や仕事の進め方の違いを認め合い、理解を深めていく過程が、チームの結束を高めることにもつながります。こうした関係性が築かれることで、異動者は新しい環境に安心して身を置くことができ、業務にも早期に集中できるようになります。
部署異動の対象になる従業員の選び方
部署異動の対象者を選定する際は、人材の最適配置と組織の活性化を目的とすることが重要です。まず、優秀な人材については、キャリア形成を支援するために異動を通じて、幅広い経験を積ませます。次に、現職に適性が見られない従業員には、新たな職種への異動の検討が必要となるでしょう。
若手社員には、ジョブローテーション制度(スキル向上や能力開発を図るため戦略的に部署や業務の異動を行い、成長を促す制度)を活用し、成長を促す目的で異動を実施します。一方で、問題行動が見られる従業員に関しては、組織の秩序を保つ観点から、配置転換を検討する必要があります。
部署異動をキャリア形成につなげるための考え方
異動は、従業員の能力を多角的に引き出すための仕組みとして、組織の中で重要な役割を担っています。単に人手の足りない部署への配置換えと考えるのではなく、長期的な視点で見たときに、従業員の成長やキャリア開発を促進する手段として機能させることが重要です。異動を通じて異なる分野の業務に関与することで、従業員は視野を広げるだけでなく、自らの可能性や志向性を再確認する機会を得ることになります。
幅広い経験が視野の拡大をもたらす
異動によって従業員が新たな職務を担うようになると、これまでとは異なる立場や視点から業務に向き合う必要が生じます。たとえば、営業部門から企画部門へ異動した場合には、顧客との対話を通じて得た知見を活かして、商品やサービスの改善案を検討することが求められるようになります。
また、現場での実務経験を持つ社員が人事や総務などの管理部門に異動することで、組織全体の仕組みを把握する視点が加わります。こうした異動を経験することで、業務の相互関係や組織全体の流れを理解する力が培われ、より柔軟かつ多面的な思考が可能になります。結果として、経営視点に近い判断ができる人材としての成長にも繋がります。
モチベーションを維持し成長を実感できる
新たな環境に身を置くことは、従業員にとって刺激となり、仕事に対する意欲を高める契機になります。これまで経験したことのない業務や、新しい人間関係の中で自分の力を試すことができるため、挑戦心や達成意識が自然と育まれます。自分のスキルが異動先で役立っていることを実感できたときには、自己肯定感や仕事への満足感が高まります。
また、苦手意識のあった分野においても、努力を重ねた結果として成果が表れたときの喜びは大きく、次の目標への原動力となります。こうした一連の経験が、継続的な自己成長を支える精神的な基盤を形成していきます。
組織としてキャリア支援を制度化できる
社内異動をキャリア形成に結びつけるためには、企業がその意義を従業員に対して明確に伝える必要があります。ただ単に「業務上の都合による異動」と説明されるだけでは、本人の納得感や成長意欲に繋がらない可能性があります。そのため、人事制度の中にキャリアパスの概念を明確に組み込み、どのような経験がどのような成長に繋がるのかを見える化することが大切です。キャリア面談や個人の志向を反映した配置計画を行い、異動が将来的なポジション獲得に向けたステップであることを伝える取り組みが効果的です。
また、異動後のフォローアップを通じて、個々の課題や不安を早期に把握し、必要なサポートを行うことで、従業員の成長を組織全体で支える仕組みを築くことができます。
部署異動に関する社内コミュニケーションの工夫
部署異動の円滑な実施は、異動対象者本人だけでなく、送り出す部署や受け入れ先の部署、さらには人事部門を含む関係者すべての協力によって支えられています。異動が単なる事務的な通知として処理されると、異動者は孤立感を抱いたり、受け入れ先のチームとの間に認識のズレが生じたりする可能性があります。そのようなリスクを回避するためには、異動に関する社内コミュニケーションを丁寧に設計し、情報共有や信頼関係の構築を意識的に進めていく必要があります。
情報共有を徹底する
異動が決定した段階で、まず優先すべきは関係者間での情報共有を徹底することです。異動元の部署は、現在の業務内容や進捗状況、引き継ぎに必要な資料などを整理し、異動先の担当者とすり合わせを行う必要があります。この段階で業務の優先順位や過去の対応履歴なども共有しておくことで、引き継ぎ後の混乱を防ぎやすくなります。異動者本人についても、新たな役割や期待されている業務内容について説明を受けることで、自分の置かれる環境への理解が深まり、不安を軽減できます。準備期間をしっかり確保し、関係者が共通の認識を持って異動日を迎えることが、スムーズな業務開始につながります。
歓迎する姿勢を示す
異動者が新しい職場に安心して溶け込めるかどうかは、受け入れ側のチームがどのように対応するかに大きく左右されます。歓迎の気持ちを行動で示すことは、異動者の適応スピードを高める効果があります。たとえば、初出勤日に全員の前で正式に紹介する場を設けたり、昼食を共にしてカジュアルな雰囲気で交流したりすることで、職場の雰囲気に早く慣れてもらうことができます。
また、異動先のメンバーが業務の進め方や使用ツールの特徴などを丁寧に説明することで、異動者の理解が深まり、業務に対する安心感も高まります。こうした取り組みを通じて、チーム全体に一体感が生まれやすくなります。
フォローアップを継続する
異動が実施された後も、継続的なフォローアップを行うことが重要です。異動者は、新しい業務や人間関係に適応しながら日々を過ごしているため、表面上は問題がないように見えても、内心では戸惑いや負担を抱えている可能性があります。そのため、直属の上司は定期的に1on1の面談を設け、業務の理解度や心身のコンディションについて確認する姿勢が求められます。
また、人事部門も必要に応じてサーベイや面談を実施し、異動全体の運用状況を把握する役割を担うと効果的です。適切なタイミングでの声かけやサポートが、異動者にとって大きな安心材料となり、早期の定着と活躍へとつながります。
適切な部署異動で、組織全体のパフォーマンスを高めよう
部署異動は企業の成長や組織の活性化に重要な役割を果たしますが、その進め方には慎重な計画と従業員への配慮が必要です。異動を円滑に進めるには、正確な現状把握とニーズ分析、関係者との調整が欠かせません。
従業員が新しい環境に適応できるようサポートし、フォローアップを徹底することも大切です。部署異動を効果的に活用することで、組織全体の活力が向上します。適切なタイミングと綿密な計画で、部署異動を円滑的に進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
人材版伊藤レポートとは?人的資本経営との関係やポイントを解説
人的資本経営における伊藤レポートは、企業が持続的成長を実現するための戦略的な指針として、人的資本の活用方法やサステナビリティ達成のための重要な指針です。 経済産業省が提唱した伊藤レ…
詳しくみるパワハラ加害者のよくある言い訳は?パワハラの判断基準や対応方法を解説
パワハラの加害者は、自分の行為が全て正しいと思っている傾向があり、その意思表示と強気な態度がパワハラ行為の言い訳につながる可能性があるでしょう。 本記事では、パワハラ加害者のよくあ…
詳しくみる社宅とは?メリット・デメリットや制度を作るプロセスを解説
社宅を設けている企業は少なくありません。しかし、従業員に提供される住宅には、社員寮、賃貸住宅、寄宿舎などと呼ばれるものもあります。これらに違いはあるのでしょうか。この記事では、社宅…
詳しくみる【テンプレート付】退職辞令とは?様式や書き方を解説!
退職辞令は、従業員に退職を命じる際に発する辞令です。法律は退職に際して退職辞令を出すことを規定していないため、出さなくても問題はありません。フォーマットも定められたものを使う必要は…
詳しくみる借り上げ社宅の契約における注意点は?法務・税務など押さえるべき点を徹底解説
借り上げ社宅制度は、従業員の福利厚生や採用力強化に有効な施策ですが、成功の鍵はすべて「契約」段階にあり、契約内容がその後の運用を左右します。契約時の見落としが、将来の追徴課税や法務…
詳しくみる就業規則の作成費用の相場は?社労士に依頼する場合や自分で作成する場合を徹底比較
従業員を雇用し、健全な企業運営を目指す上で不可欠な「就業規則」。しかし、その作成には専門的な知識が求められ、「一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」「できるだけ安く済ませたいけど…
詳しくみる