- 更新日 : 2025年11月20日
パワハラで内部通報制度の利用があったらどうする?匿名や退職後のケースについても解説
公益通報者保護法の改正により、アルバイト、派遣労働者、契約社員なども含め常時301人以上の労働者を使用する企業には内部公益通報制度の整備が義務付けられました。
本記事では、内部通報制度の概要と、パワハラによる内部通報を受けた場合の対応策を中心に解説をします。
目次
内部通報制度とは
公益通報者保護法の改正により、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、①内部通報に対する対応体制の整備、②内部通報に関わる業務を行う公益通報対応業務従事者(従事者)の指定が義務付けられました。
公益通報制度と内部通報制度
内部公益通報制度とは、労働者または役員が、犯罪行為や過料対象行為または刑罰や過料につながる行為を知ったときに、その事実を勤務先、取引先事業者などに迅速かつ安心して通報できることを保証する制度です。
法改正により従業員301人以上の全事業者に整備が義務付けられた
企業に義務付けられた内部通報制度の整備内容は次の通りです。
- 内部公益通報への対応体制の整備
内部公益通報受付窓口を設置し、事実調査や是正措置を行う部署・責任者を定めます。トップや幹部に関する事案では、これらの者からの独立性の確保も必要です。 - 対応体制を実効的に機能させる措置
内部通報に関する教育・周知、規程の策定を行うほか、事実調査の結果や是正措置の内容を通報者に速やかに通知します。また、通報に対する対応を記録・保管し、制度の運用実績を開示します。 - 公益通報者の保護体制の整備
公益通報者の情報は対応業務に必要最小限の関係者だけが共有し、この範囲を超えてはいけません。
通報による不利益処分に対しては適正な救済・回復を行います。
社内の窓口
内部通報受付窓口には、①社内窓口、②社外窓口、③社内窓口と社外窓口の併用という3つのパターンがあります。消費者庁が2023(令和5)年度に行った調査(「民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」)によると、①社内窓口のみを採用しているのは、常時使用者数301人~1000人規模の企業が25.4%、1001人以上の規模では10%前後でした。
窓口の所属部署においては、法務・コンプライアンス部門が45.3%、総務部門が30.1%となっており、監査部門・機関や人事部門がこれに続いています。これらの数値を読み解くと、社内窓口は、通報者にとっては組織内部の人物が対応することへの抵抗感があると考えられるでしょう。
外部の窓口
前述の同調査によれば、外部窓口の設置場所は、顧問弁護士が44.0%、顧問以外の弁護士が23.2%、通報専門会社への委託が22.3%でした。社外窓口のメリットとしては、通報者の匿名性が確保しやすく、不正の早期発見が可能となる点や、通報内容についての公正な判断を期待できる点が挙げられます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
パワハラの判断基準と実務対応
従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。
本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。
ハラスメント調査報告書(ワード)
本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。
ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。
パワハラのNGワード&言い換えまとめ
職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。
パワハラで内部通報を受けた場合の対応の流れ
内部(公益)通報制度は、公益通報者保護法の中の制度であるため、通報対象となる行為とは、犯罪行為や過料の対象となる行為、刑罰や過料につながる行為です。パワハラの場合は、犯罪行為に該当する場合とそうでない場合があります。ここでは、パワハラの内部通報が公益通報制度の保護対象である場合の流れを説明します。
通報者へ通報の受領を通知する
まずは、内部通報窓口で通報を受けたときは、通報者に対し通報事案を受け受け付けたことを通知するとともに、通報者に事実関係の聞き取りなどを行います。聞き取りの結果、パワハラが暴行、脅迫、侮辱罪に当たる暴言などの犯罪行為の場合には公益通報制度に基づく対応に、それ以外の場合はパワハラ防止法などに基づく対応に移行します。
公益通報制度の対象とならない場合には、その理由や企業内のパワハラ対応手続きなどを丁寧に説明することが重要です。
通報内容の事実調査
公益通報制度に基づく調査を行う場合は、その旨を通報者に通知する必要があります。調査者は、当事者の所属セクションとは異なる部署に所属する者が適切です。また、具体的な調査方法に指定はありません。事実調査に際しては、公益通報による調査であることは伏せる、該当者以外の人物にもダミー調査を行うなどの配慮が必要です。また、通報者が誰であるかを特定されることのないよう、注意を払いましょう。
パワハラの判定
通報を受けた段階で、事案が公益通報制度の対象となるかどうかの判断をしますが、調査した結果によって、法令違反行為でないことが明らかになる場合があります。一方で、パワハラの事実が確認できた場合は、通報者が受けた被害の状況や加害者の悪質性などを考慮し、就業規則に基づく適切な措置を取るようパワハラ委員会などに案件を移管します。
加害者に対する処分や是正措置
通報のあったパワハラが犯罪行為に該当すると確認できた場合は、速やかに不正行為を是正する措置を取ります。行為者本人に対する厳重な指導、役職者への事例報告(プライバシー保護などに配慮すること)と注意勧告などが考えられます。また、是正措置を取ったあとも、その是正措置の効果に関する確認や被害を受けた通報者へのケアなどを行うことが必要です。
通報者への結果通知
公益通報から加害者に対する是正措置までという一連の流れが終わった時点で、通報者に対して結果を通知することは内部通報制度に対する信頼性を高めるうえでも大きな効果があります。特に、不測の事態によって通報者の情報が漏えいしたり、不利益な処分が行われたりしないよう、細心の注意を払う必要があります。また、通報者への適切なケアを行うとともに、是正措置の効果を確実に確認し、問題解決に繋げることが重要です。
内部通報が匿名だった場合の対応
公益通報者保護法では、通報者の顕名・匿名の区別はなく、通報手段の指定もありません。内部公益通報は通報者が匿名の場合でも受け付ける必要があります。また、匿名だという理由によって事実調査を行わないことは認められません。
ただし、通報者の情報が得られないと、事実調査を迅速かつ正確に実施することが困難な場合がありえます。そのため、通報者の秘密を保持しながら、必要な情報を得る対策として、個人を特定できないメールアドレスの利用、匿名での連絡が可能な専用システムの導入などを検討することが効果的です。
退職した社員から内部通報があった場合の対応
退職した労働者の場合、退職後1年以内であれば内部公益通報の通報者となることができます。退職後1年以内に行った内部通報については、1年を経過したあとでも期間の定めなく公益通報者保護法の対象です。ただし、退任1年以内の役員にはこのような決まりがないため、注意しましょう。
公益通報者保護法の保護対象外の通報だったらどうする?
通報内容が保護対象事案でない場合は、それぞれの内容に適した対応が必要です。例えば、パワハラではあるものの、犯罪性は見られない場合には、通報者への説明を行い、了解を得たうえで、ハラスメントの相談窓口に確認できた事実関係を引き継ぎましょう。公益通報窓口とハラスメント相談窓口を併設していれば、事案の移管を円滑に行うことが可能です。
適切な制度運用は会社のメリットにつながる
内部公益通報制度の目的は、社内の違法行為を早期に発見し、適切に改善することです。通報された情報への適切な対応や通報者の保護などに関する社内の体制を整備し、制度を効果的に運用することは、会社のコンプライアンスの向上にもつながります。
制度の運用においては、パワハラ相談制度などと連携し、組織秩序の全体的な向上を考慮することが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
育休中の給付金が手取り10割とは?期間や支給要件、申請方法など網羅的に解説
育児休業給付金は、育休を取得する際に賃金が支払われなかったり、減額されたりした場合に、安心して育児に取り組めるよう支援する制度です。雇用保険の被保険者であれば、男女問わず育児休業給…
詳しくみる退職証明書は何に使う?目的や具体的な利用シーン、 注意点など解説
「退職証明書」とは、従業員が退職した事実を企業が公的に証明する、人事労務手続きにおいて重要な書類です。しかし、この退職証明書を「具体的に何に使うのか」、また公的な「離職票」と法的に…
詳しくみる会社のストレスチェック義務化とは?いつから?50人未満企業が進める実施手順も解説
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を目的とし、労働安全衛生法に基づいて企業に義務付けられています。とくに50人未満の事業場も令和10年度には義務化される見込み…
詳しくみるパート社員の雇用契約書とは?記載事項や正社員との違いを解説
パート社員の雇用契約書は、会社とパート社員の間で雇用条件や業務内容、勤務期間、雇用契約期間などを記載した書面です。パート社員を雇用する際は、事前に書面で契約を交わしておかなければ、…
詳しくみる生産年齢人口とは?日本の割合や推移、減少している理由を解説!
生産年齢人口とは生産活動を支える15〜64歳の人口層のことです。就業者や完全失業者を指す労働力人口とは異なります。少子高齢化によって日本の生産年齢人口は年々減少を続けており、企業の…
詳しくみる異動したいのはわがまま?希望を通すコツや気まずくならないポイントも解説
部署異動を希望しているものの「自分のわがままではないか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、異動希望を通すためのコツや言いづらい場合の対処法、異動後に気まずくな…
詳しくみる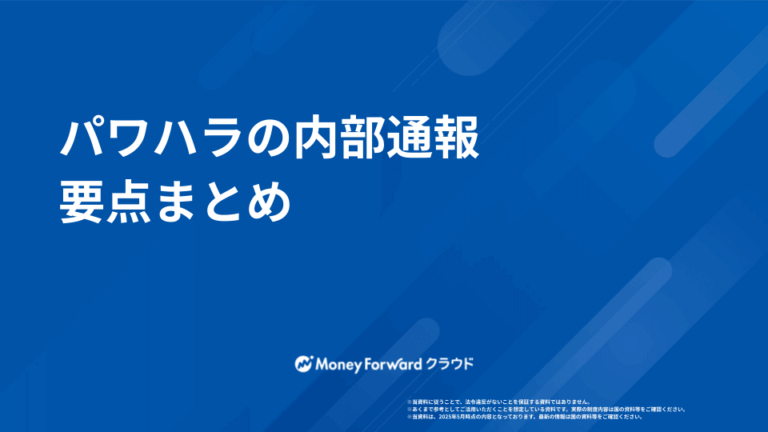


-e1762259162141.png)
