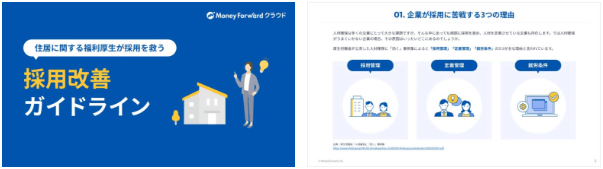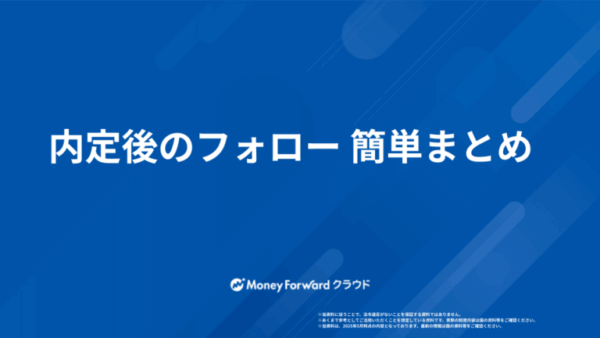- 更新日 : 2025年8月18日
試用期間とは?労働条件や注意点を解説!
会社は労働者を採用して雇用契約書を取り交わす際に、本採用の前段階として試用期間を設ける場合が多くあります。試用期間を設けることが、採用した労働者の適性や能力、勤務態度などを把握するために有効な期間だということがわかっているからです。
試用期間のルール、そのメリットやデメリット、注意点などについて確認していきましょう。
目次
試用期間とは
試用期間とは、採用した労働者について会社が一定期間を定めて能力・適性や人柄などを確認する期間です。逆に、労働者が自分の希望した業務内容や会社の雰囲気を確認して長く勤められるかどうかを判断する期間ともいえます。
では、試用期間の目的や期間の設定、言葉が似ていてよく間違える「研修期間」、「見習い期間」などとの違いについて見ていきましょう。
試用期間の目的
試用期間は、採用した人について、いきなり本採用ではなく一定の期間を定めてその人の能力・適性や人柄などを確認して本採用しても良いかどうかを判断することを目的として設けられます。
人材の長期雇用を考える中で採用した労働者のチェックを行うための期間といえます。
試用期間の一般的な期間の定めは?
試用期間の長さについては法律で明確に決められているわけではありません。一般的には3ヶ月〜6ヶ月の期間を設定する場合が多いです。しかし、会社によっては1ヶ月や1年とする会社もありますし、試用期間の延長が可能なように規定している会社もあります。
試用期間の設定は義務?
試用期間を設けることについては、労働基準法やその他の法律ではっきり定められているわけではありません。
ただし、会社のルールとして試用期間を設ける場合には、就業規則や雇用契約書に試用期間がある旨を明記しておく義務が発生します。
仮採用との違い
仮採用は会社によっては試用期間と同じ意味で使われることがあります。また、本採用の仮決定と同じ意味合いで使われることもあるため、会社がどのような意味で使用しているのかを確認することが必要です。
研修期間との違い
研修期間は仕事をしていく上で必要になる技術や知識について、教育を受けながら独り立ちできるまで学ぶために設けられる期間です。それに対して試用期間は従業員の適性などを見極める期間です。よって試用期間とは目的が異なります。
見習い期間との違い
見習い期間も会社によっては試用期間と同じ意味で使われることがあります。この呼び方も会社によって試用期間と同様の意味で使っているのか、そうでないのかは会社に確認してみないとわからないので注意が必要です。
インターンとの違い
インターンは学生が就業体験や業界の研究目的で行うために設けられている制度で、継続雇用が前提ではありません。試用期間との違いは継続雇用になっているかどうかです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間のメリット
試用期間にはどのようなメリットが考えられるでしょうか。まず、採用試験の時にはわからなかった労働者の適性を判断することができます。採用試験時の筆記試験や面接試験だけでは、その人の人柄までを確認することができないからです。
また、労働者の実務を行う能力やスキルのレベルなどを試用期間の間に確認できるというところもメリットです。試用期間中の仕事ぶりが、今後長く勤めてもらうにあたっての適材適所を判断する一つの材料になることもあります。
試用期間のデメリット
試用期間のデメリットとしては、あまりにも試用期間を長く設定した場合には求職者に敬遠されるということがあります。働く側にとっては、試用期間が長いということは試用期間中に解雇の判断をされる期間が長くなるのではないかという不安が長く続くことになります。
また、労働者には試用期間中は解雇されるという不安があるので、委縮して本来の実力が発揮できない場合もあります。会社には、労働者が本来の実力を発揮しているかどうかを見極める必要が出てくるのです。
試用期間中の労働条件の明示と労働契約書の作成
試用期間であっても、労働契約が成立している以上、企業には労働条件を明示する義務があります。
試用期間中も労働契約は成立している
試用期間中の従業員であっても、雇用契約が締結された時点で労働者としての権利が発生します。つまり、試用期間は「本採用前の仮契約」ではなく、「本採用を前提とした労働契約の一形態」と解釈されており、正社員と同様に労働基準法の適用対象となります。
このため、賃金や勤務時間、休日、福利厚生などの労働条件を明示しないまま試用を開始することは、法的にも不適切であり、万が一解雇等の処分を行う際には不当解雇と判断されるリスクが高くなります。
労働条件通知書または労働契約書の作成が必須
労働基準法第15条では、労働契約の締結時に使用者は労働者に対して、賃金、労働時間、休日などの「労働条件を書面で明示する」義務があると定められています。これには、試用期間中の条件も含まれます。
「試用期間中は時給1,100円、3か月間、社会保険加入あり」といった内容を記載した労働条件通知書、または労働契約書を交付する必要があります。本採用後に賃金や雇用形態が変わる場合は、その変更点についても事前に明記しておくことが重要です。
また、労働契約書は双方署名を行い、1通を労働者に渡すことで契約の成立を明確にし、トラブル予防につなげることができます。
試用期間の位置づけや本採用の判断基準も記載する
労働契約書や就業規則には、試用期間に関する規定も明確に記載しておくことが望ましいです。たとえば、「試用期間は3か月とし、期間満了時に本採用の可否を判断する」「試用期間中の勤務態度・能力等を評価基準とする」といった内容です。
これにより、労働者も自分が評価対象となっていることを理解し、企業側も判断基準があることで合理的な評価・採否決定が行えます。本採用に切り替える際には、条件変更がある場合に改めて通知または契約の更新手続きを行うのが望ましいです。
試用期間の注意点
ここからは、会社が試用期間を設けるうえで注意しておかなければならないことについて見ていきます。
試用期間中にクビ・解雇になることはある?
会社が試用期間中に労働者を解雇(クビ)にすることについては労働基準法で厳しい制限があります。
解雇(クビ)については「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が認められなければ、労働者から訴えられた場合は無効になります。試用期間中であるからといって、会社は一方的に労働者を解雇(クビ)にすることはできないのです。
試用期間中の解雇に予告や手当は必要?
試用期間中の解雇であっても、原則として「解雇予告」または「解雇予告手当」の支払いが必要です。労働基準法第20条では、労働者を解雇する際には30日前に予告するか、または平均賃金30日分以上の予告手当を支払うことが定められています。
試用期間中であっても、労働契約が成立している以上、これらの義務は免除されません。ただし、雇入れ後14日以内であれば、予告や手当の支払いは不要です(同法第21条)。この「14日以内」はカウントに注意が必要で、就業日数ではなくカレンダー上の暦日数で数えます。
ただし、解雇理由が労働者の責に帰すべき重大な事由に該当し、労働基準監督署の除外認定を受けた場合には、予告・手当が免除されることもあります。
試用期間が過ぎた後の対応
試用期間が終了し、特に問題がなければ、通常はそのまま本採用となります。この場合、労働条件については、試用期間の開始時に取り交わした労働契約がそのまま引き継がれるのが一般的です。
ただし、試用開始時の雇用契約書や就業規則において特別な取り決めがされている場合は、本採用時に改めて労働契約について協議が行われることもあります。本採用後のトラブルを防ぐためにも、試用期間の契約内容をあらかじめ正確に労働者へ説明しておくことが重要です。
試用期間満了時に本採用を拒否する場合の注意点
試用期間満了時に本採用を拒否する場合でも、実質的には「解雇」と同様の法的扱いを受けます。そのため、安易な判断は不当解雇とされる可能性があるため注意が必要です。
まず、本採用拒否には客観的かつ合理的な理由が必要です。たとえば、明確な業務能力の不足や勤務態度の著しい不良など、採用時に知り得なかった重大な問題がある場合に限られます。
また、就業規則や労働契約書に「試用期間中に本採用を拒否する可能性がある」旨を明記しておくことも重要です。これがないと、労働者が「当然に本採用される」と期待したと主張し、トラブルに発展する恐れがあります。
さらに、本採用を拒否する場合でも、解雇と同様に30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。事前に評価基準を明確にし、十分な説明と記録を残すことが、企業側のリスクを防ぐポイントです。
試用期間の延長に関するルールと手続き
試用期間の延長は、企業の判断だけで自由に行えるものではなく、労働契約や就業規則に基づく正当な理由と手続きが必要です。不当な延長はトラブルや無効判断の原因となるため、注意が求められます。
試用期間の延長には合理的な理由が必要となる
試用期間の延長が認められるためには、「労働者の能力や適性を判断するために、やむを得ず評価期間を設ける必要がある」といった合理的な理由が必要です。たとえば、入社後に長期の病気や介護で出勤できなかった場合、業務に支障が出るようなトラブルが発生したが評価を決定するには情報が不足している場合などが該当します。
一方、評価の結果が「やや不十分」といった曖昧な理由での延長は、後に無効とされる可能性があり、特に労働者本人の勤務実績が一定期間積み重ねられている場合は慎重な判断が求められます。
延長を行うには就業規則や契約書の明示が必要
法的には、試用期間の延長を可能にするには、あらかじめ労働契約書や就業規則などに「延長の可能性がある」旨を明記しておく必要があります。記載がなければ、延長自体が認められない、または解雇とみなされる可能性が高まります。
契約書には「通常3か月、必要に応じて最長6か月まで延長する場合がある」といった記載例がよく見られます。また、就業規則にも同様に、延長の上限や判断基準、手続き方法などを明文化しておくと、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。
延長の際は本人への説明と同意を必ず得る
試用期間を延長する際には、労働者本人に対してその理由と期間、今後の期待・評価基準などを丁寧に説明し、書面で同意を得ることが望ましいです。口頭だけの通告では、後に「一方的な不利益変更」として無効とされるリスクがあります。
説明の際には、単に「延長する」と伝えるのではなく、「○月○日まで延長し、この期間中に改善を期待する点は◯◯である」といった具体性を持たせることが大切です。同意書を交わす、または労働条件通知書を再発行することで、企業としてのリスク管理にもつながります。
試用期間中の有給休暇の付与と取得条件
「試用期間中に有給休暇は使えるのか?」という疑問は多くの職場で見られます。ここでは有給休暇の付与時期と取得条件について詳しく解説します。
有給休暇の付与は入社日から起算する
労働基準法第39条では、「雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して年次有給休暇を与えることが義務とされています。この「雇入れの日」は、試用期間開始日を含みます。つまり、試用期間中の勤務も6か月間の「継続勤務」に含まれるため、本採用の有無に関係なく、基準を満たせば有給休暇が発生します。
たとえば、4月1日に試用期間として入社し、10月1日に本採用となった場合でも、10月1日の時点で6か月間継続勤務していれば、通常通り有給休暇が付与されます。
試用期間中の有給取得は制限できるか?
制度上、有給休暇の取得は「使用者の時季変更権(業務に著しい支障がある場合に取得時季を変更できる)」を除き、試用期間中でも自由に請求することが可能です。ただし、入社から6か月が経過する前は法的な付与義務が発生していないため、その間に「私用での休みを有給扱いしてほしい」と申し出ても、会社が任意に認めるかどうかの問題になります。この場合、通常は欠勤扱いまたは無給となります。
一方で、6か月経過後に有給が発生したにもかかわらず、「試用期間中だから取得させない」というのは違法行為です。試用期間中でも、取得条件を満たしていれば、正社員と同じように有給休暇の取得が認められます。
試用期間を有効に活用しましょう
試用期間を設定するメリット・デメリットを理解して正しく活用することにより、人材を定着させ、会社のために活躍する人材を育成できるよう取り組んでいきましょう。
よくある質問
試用期間とはなんですか?
試用期間とは、採用した人について、一定の期間を定めてその人の能力・適性や人柄などを確認して本採用しても良いかどうかを判断するために設ける期間になります。詳しくはこちらをご覧ください。
試用期間のメリットはなんですか?
試用期間のメリットは、採用試験の機会だけではわからなかった労働者の適性や能力を判断できること、労働者の実務を行う能力やスキルのレベルなどを試用期間中に確認できることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
パートで育休が取れなかった場合どうすればいい?取得条件と対応を解説
パートの方でも育休は取れます。育休や産休は、雇用形態に関係なく取れることが労働基準法により定められています。 万が一、パートで育休が取れなかった場合は、育休を取得できる条件に満たし…
詳しくみる育休から早めに復帰はできる?復帰に必要な手続きや準備を解説
育児休業(以下、育休)からの早期復帰は、個々のライフプランやキャリアプラン、家庭の状況など、様々な理由から検討される選択肢です。近年、働き方の多様化や育児と仕事の両立支援への関心の…
詳しくみる【チェック付】スメハラとは?どう伝える?職場の具体例や対策を解説
スメハラ(スメルハラスメント)は、体臭や香水、タバコなどの「臭い」が原因で他者に不快感を与えることを指します。 本人に悪意がなく、体質や文化の違いも絡むため対応が難しく、集中力低下…
詳しくみる無期雇用とは?正社員との違い、無期転換ルールやデメリット、契約の注意点
無期雇用とは、雇用期間に定めのない労働契約のことです。有期雇用との違いは契約期間に定めがあるかどうかであり、正社員とも異なります。有期雇用労働者は、一定の要件を満たした場合、雇用主…
詳しくみる就業規則の変更には届出期限がある?必要書類や忘れた場合の罰則を解説
就業規則を変更した場合、届出は「遅滞なく」行う必要があります。法律上、明確な提出期限は定められていませんが、実務では施行日までに労働基準監督署へ届け出ることが求められます。提出が遅…
詳しくみる契約社員とは?メリット・デメリットや給与・待遇についても徹底解説
契約社員とは、企業と「契約期間の定めのある労働契約(有期雇用)」を結んでいる社員のことです。 正社員との最大の違いは雇用期間が決まっている点にあり、パートとの違いはフルタイム勤務が…
詳しくみる