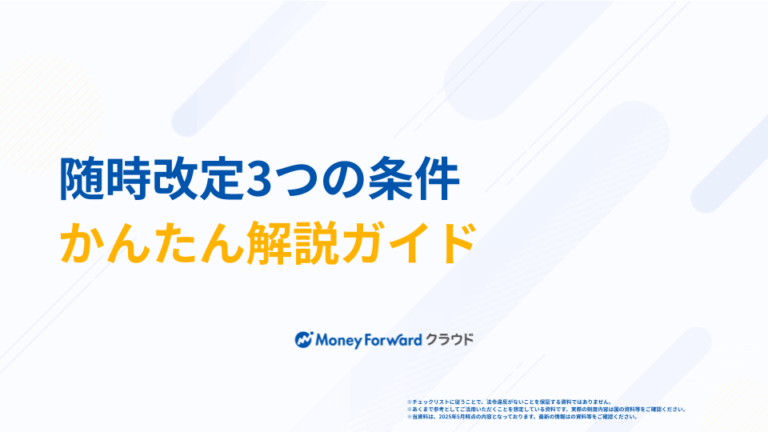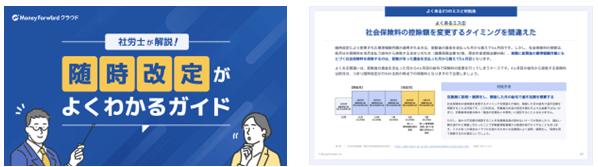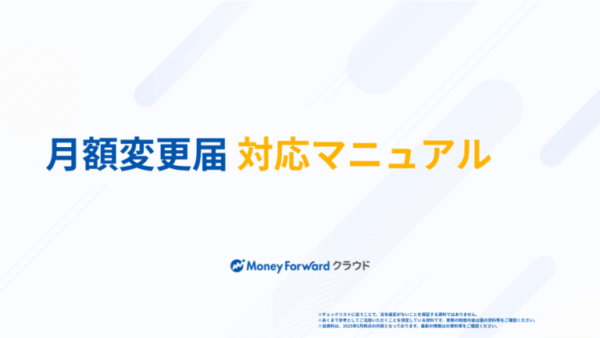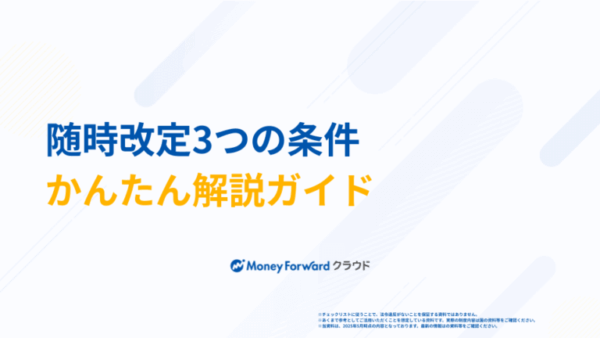- 更新日 : 2025年11月17日
社会保険の随時改定を行う3つの条件!月額変更届の書き方や残業の影響を解説
昇格などで賃金に大幅な変動があれば、それに伴い社会保険の保険料も改定が必要になります。この手続きを社会保険の随時改定といいます。ただし、臨時手当により1ヶ月だけ賃金が増加したり、残業代によって給与が増えたりする場合は随時改定の対象外です。
ここでは、随時改定の条件や変更時期についてわかりやすく解説します。
目次
社会保険の随時改定とは?
健康保険や厚生年金などの社会保険の保険料は、給与に応じて区分された標準月額報酬をもとに算出されます。この保険料の算出は、毎月の給与によって変動するのではありません。資格取得時に決まった社会保険料が改定されるのは、「年に1回の改定」と「給与に大きな変動があったとき」の2つです。具体的には、以下の手続きになります。
- 年に1回の改定(定時決定):算定基礎届
- 給与に大きな変動があった時など(随時改定):月額変更基礎届
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
社会保険の随時改定はいつ行われる?変更時期について
社会保険の定時決定は、その名の通り年に1回提出の時期が決まっています。6月中旬以降に年金事務所から送られてくる算定基礎届に、必要な内容を記入し、毎年7月10日までに管轄の年金事務所に提出します。
一方、随時改定は、いつからといった決まった時期はありません。随時改定とは、昇給や降格に伴い、給与額に大きな変動があったときのみ必要となる手続きです。従業員の個別の状況に合わせて必要となるため、変更時期が固定されている定時決定と比べて人事が手続きを失念しやすく、「どんなときに」月額変更届の提出が必要なのか、きちんと理解しておくことが大切です。
社会保険の随時改定をすべき3つの条件
では、どのようなときに随時改定が必要となるのか、具体的な条件と範囲を見てみましょう。
社会保険の随時改定は、以下の3つの条件を全て満たすときに行います。
- 昇給または降格等により固定的賃金に変動があった
- 賃金変動以降3ヶ月間の給与の平均額に基づく標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき
- 賃金の変動があった月以降3ヶ月間連続して、支払基礎日数が一定基準を越すとき
逆にいえば、給与に変動があったとしても、上記いずれか一つでも当てはまらない条件がある場合は、随時改定の必要はありません。
6月までに随時改定があった場合、再び随時改定がない限りその年の8月まで各月の社会保険料に適用されます。7月以降に随時改定が発生した場合は、同様のケースで翌年の8月まで適用されます。
1.固定的賃金の大きな変動
ここでいう「固定的賃金」とは、支給額や支給率が決められたものを指します。イメージが浮かびやすいものは基本給ですが、それ以外に通勤手当や家族手当など、月々の支給額が決まっているものも固定的賃金に含まれます。
また、日給や時間給に変更があったときや、割増賃金率や時間単価の変更により、時間外手当の支給割合・支給単価が変更になった際は、固定的賃金の変動とみなします。人事考課制度による昇給や降格だけでなく、結婚による家族手当の支給、引っ越しでの通勤手当の変更なども対象となるため注意が必要です。
2.標準報酬月額で2等級以上の差がある
固定賃金の変動により、改定後の標準報酬月額と改定前の標準報酬月額に2等級以上の変動が生じる場合を指します。
社会保険料を算出する基礎となる標準報酬月額は、現在は厚生年金が32等級、健康保険は50等級に分かれ、保険料率表(例・東京都)に記載されています。
報酬月額をこの保険料率表の等級区分にあてはめ、変動前と変動後に2等級以上の差が生じていることが要件です。
たとえば、厚生年金保険の標準報酬月額が25等級の従業員が昇給し、以降の継続した3ヶ月の報酬の平均が27等級以上になると、要件に該当します。
賃金の変動により、以降3ヶ月間2等級以上の差が生じたとき随時改定が必要となりますが、以下に当てはまるケースは対象には含まれません。
- 固定的賃金は増えたが、残業手当などの非固定的賃金が減ったため、結果として新たな標準報酬月額が2等級以上下がった場合
- 固定的賃金は減ったが、非固定的賃金が増えたため、結果として新たな標準報酬月額が2等級以上上がった場合
また、標準報酬月額の上限・下限に該当する従業員の等級変更では、1等級の変更でも随時改定の対象となるため注意が必要です。
3.3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上
支払基礎日数とは、給与を計算するときの対象日数のことです。
支払基礎日数とは、給与を計算するときの対象日数をいいます。随時改定の対象となるのは、支払基礎日数がひと月あたり17日以上の場合です。賃金の変動があったあと、1ヶ月でも17日未満の月があれば、随時改定の対象にはなりません。
支払基礎日数の数え方は、給与形態により異なります。月給制・週給制の場合は、休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数になります。
日給制・時間給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数です。
社会保険の随時改定に残業代は含まれる?
企業によっては月ごとに業務量が変動し、繁忙期には残業代が大幅に増えることもあるでしょう。しかし、残業代が増えるだけでは、随時改定の対象にはなりません。
ここでは、随時改定の対象外になる場合を解説します。
随時改定の対象外となるケース
随時改定の要件のひとつは、昇給・降給等により固定的賃金が変動した場合です。
非固定的賃金の変動は対象になりません。非固定的賃金とは、勤務状況や成果などによって支給金額が変動する賃金のことです。
残業代は個人の勤務状況に応じて毎月変動する非固定的賃金であり、随時改定の対象外になります。
残業代のほか、非固定的賃金で随時改定の対象外となるケースは、精皆勤手当や育児・介護休業手当があげられます。
賞与が支給される場合
賞与が支給される場合、随時改定に含まれるかは、支給回数によります。
支給回数が年3回以下であれば、賞与の支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。この届出によって決まる標準賞与額をもとに、賞与の保険料額が決定されます。
一方、年4回支給する場合、賞与は「賞与にかかる報酬」とみなされ、標準賞与額ではなく標準報酬月額の対象になる点に注意が必要です。
「賞与にかかる報酬」は、毎月7月の定時決定で提出する「算定基礎届」に含めて計算します。
随時改定の手続きの流れ、月額変更届の作成
健康保険や厚生年金などの社会保険の随時改定の対象となる従業員がいる場合、月額変更届を事業所を管轄する年金事務所に提出します。必要書類と提出時期は以下の通りです。
- 必要書類:月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届)
- 提出時期:速やかに
- 提出方法:郵送、窓口または電子申請
添付書類は原則必要ありませんが、年間平均の標準報酬月額で随時改定の申し立てを行う場合には、以下の2つの書類が必要になります。
- (様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)
- (様式2)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書(随時改定用)
1.月額変更届の作成

月額変更届は、上部の「項目名」に合わせて必要事項を記入します。以下、注意が必要な箇所について解説します。
- 改定年月:標準報酬月額が改定される月を指します。変動後の「賃金を支払った月」から4ヶ月目を記入します。
- 給与支給月:変動後の賃金を支払った月から3ヶ月間を記入します。
- 通貨によるものの額:給与や手当といった名称をとわず、対象の月に労働の報酬として金銭で支払われたすべての金額を記入します。
- 現物によるものの額:報酬のうち食事・住宅・被服・定期券などの、金銭以外で支払われるものを記入します。
- 修正平均額:昇給がさかのぼったため、対象月に差額分が含まれている場合は、その差額を引いた平均額を記入します。
たとえば、給与の支払いが月末締め翌月20日払いの会社で、1月に昇給がありその後の3ヶ月間の状態から随時改定の条件に合致する場合には、以下のようになります。
- 賃金変動の決定:1月
- 改定年月:5月
- 給与支払月:2月、3月、4月(変動後の賃金が支払われた月)
2.書類の提出
月額変更届は、地域ごとに設置されている事務センターか、管轄の年金事務所に提出します。提出方法は窓口に直接持参するほか、郵送や電子申請などがあげられます。
事務センターの受付は郵送のみで、封筒に送付先の事務センター名と郵便番号(大口事業所個別番号)を記載すれば、住所は記載しなくても届きます。各地域の事務センターの一覧は、日本年金機構「全国の事務センター一覧」で確認してください。
窓口に持参できるのは、管轄の年金事務所のみです。管轄は日本年金機構の「全国の相談・手続き窓口」から確認できます。
電子申請は、「e-Govポータル」を利用します。なお、特定の法人については、2020年4月から電子申請の義務化が始まっており、次に該当する法人が対象です。
- 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
- 相互会社
- 投資法人
- 特定目的会社
3.決定通知が届く
月額変更届の提出後、1〜2週間程度で日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通書」が届きます。
決定通知が届いたら、社会保険料の等級が変更になったことを従業員へ速やかに通知しなければなりません。正当な理由なく通知しなかった場合には、事業者に罰則が課せられるため、注意してください。
4.標準報酬月額の変更に伴う社会保険料を反映
標準報酬月額の変更に伴い、新しい社会保険料を反映します。新たな社会保険料は、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい保険料率が適用されます。
たとえば、2月に報酬の変動があった場合、新しい保険料が適用されるのは2月を含めて4ヶ月目の5月(5月分の社会保険料は6月に支給する給与から控除)です。
社会保険の随時改定をしなかったら?遡及などある?
社会保険の随時改定は、「速やかに」という提出指示があるだけで、定時決定の算定基礎届のような明確な提出期限がありません。そのため、昇給や降格などにより賃金が変動した従業員がいたら、変動月から4ヶ月目を提出期限として、「10日までには必要な届出を確認し終わらせる」など、自分なりのスケジュールを立てることが重要です。
月額変更届の提出が遅れ、随時改定をしなかったら、賃金変動が社会保険料に正しく反映されないことになります。つまり、社会保険料を多く払いすぎたり、不足したりという事態が発生してしまいます
月額変更届の提出忘れがあった場合は、気づいた時点で管轄の年金事務所・健康保険組合に確認し、指示に従いましょう。基本的に保険料は遡及され改定されます。本人負担分についての過不足があれば精算する作業も発生するので注意が必要です。
随時改定を忘れず月額変更届を提出しよう
社会保険料の随時改定は、タイミングを忘れずに届出を行うことが大切です。随時改定の対象と範囲を理解し、月額変更届の提出漏れがないように注意しましょう。
よくある質問
社会保険の随時改定とはなんですか?
随時改定とは、社会保険料を変更する手続きです。通常は年に1回の定時決定で保険料が決まりますが、昇給や降格などの賃金の変動に伴い標準報酬月額が変動した場合、随時改定で保険料を変更します。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険の随時改定について、条件を教えてください。
本給や手当などの固定的賃金が変動したこと、変動が生じた月から3カ月間連続で2等級以上の標準報酬月額の差が生じていること、当該3カ月の支払基礎日数がいずれも17日以上あることです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
過労死とは?定義や症状および防止策を解説
繁忙期や納期の短縮などにより、どうしても長時間労働を行わざるを得ない状況となることもあるでしょう。しかし、長時間の労働は労働者の心身の健康を蝕み、最悪の場合は過労死という痛ましい結…
詳しくみる新卒で雇用保険被保険者証は受け取れる?発行条件や必要なタイミングを解説
新卒の入社手続きで「雇用保険被保険者証」という言葉を初めて聞く方も多いでしょう。雇用保険の加入を証明する大切な書類の1つで、転職時や教育給付金の申請手続きを行う際に、提出を求められ…
詳しくみる所定給付日数とは?雇用保険における基本手当の観点から
自己都合による退職や会社の倒産など、失業しても生活の心配をしなくてよいよう、雇用保険では被保険者に対して基本手当(いわゆる失業等給付)を支給しています。この基本手当には、受給できる…
詳しくみる社会保険資格取得届とは?必要な添付書類や提出先を解説!
社会保険資格取得届は、社会保険被保険者となる従業員を雇用した場合に必要な届出です。提出先は、持参する場合は所轄の年金事務所、郵送する場合は事務センターで、資格取得日から5日以内に添…
詳しくみる従業員が退職したら何をすべき?社会保険手続きや必要書類の書き方まとめ
従業員の退職が決まったら、人事がするべき手続きが数多くあります。なかでも健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険は、手続きの期限が決まっているため、迅速に必要書類を提出しなけ…
詳しくみる職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説
Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…
詳しくみる