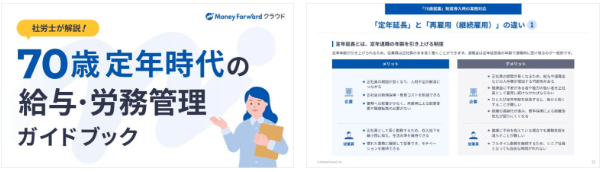- 更新日 : 2025年4月4日
再雇用をやめてほしいと感じる理由は?法的義務や解決策なども解説
近年、多くの企業で導入されている再雇用制度。しかし、その制度の効果や運用方法に対して疑問や不満の声も増えています。この記事では、「再雇用をやめてほしい」と感じる理由を掘り下げながら、法律的な観点や実際のメリットも含めた最適な人材活用方法について解説します。
目次
再雇用をやめてほしいと感じる理由は?
再雇用制度には、企業や働く人々にとって多くの課題があります。ここでは、課題を深掘りしながら再雇用制度を辞めさせたい理由について解説します。
職場の年齢構成が偏る
再雇用制度を継続すると、高齢層が増える一方で若年層の採用が制限される場合があります。これにより、職場内での年齢構成が偏り、世代間の考え方や働き方の違いが顕著になります。
例えば、若手社員は新しいやり方や柔軟な発想を好む傾向がありますが、再雇用されたベテラン社員は過去の経験や従来のやり方を重視する傾向があります。その結果、業務の進め方や意思決定で対立が生じやすくなり、チームの協調性や組織の一体感が弱まる可能性があります。
減給によりモチベーションが低下する
再雇用の場合、給与水準が現役時代よりも低く設定されることが一般的です。これは企業側のコスト削減策としては合理的ですが、働く側の立場からすると、同じような業務をしているにもかかわらず、給料が減少するという状況になります。
そのため、再雇用された人は「自分の働きが正当に評価されていない」と感じやすく、やる気を失う傾向があります。モチベーションが低下すると、仕事への責任感や意欲が減少し、結果的に生産性の低下や業務品質の低下につながります。
新しい技術への適応が難しい
再雇用世代の多くは、急速に進化するIT技術やデジタルツールへの適応が難しい場合があります。現役時代に培った経験やスキルがあっても、新しい技術を短期間で習得し、業務に取り入れることは容易ではありません。
例えば、業務がクラウドベースのシステムに切り替わったり、リモートワークで必要なデジタルツールの利用が求められたりする中で、再雇用者がこれに対応できない場合、業務のスピードが低下したり、周囲の社員がフォローに回る負担が増えたりします。企業側も十分な研修や教育制度を整えなければ、こうした課題を克服することは難しくなります。
キャリアの先行きに不安を感じる
再雇用制度は定年後の一定期間の延長措置であるため、多くの場合、その後のキャリアの見通しがありません。そのため、再雇用されると「これが自分の最後の職場だ」という意識が強まり、将来に向けての目標や新たなキャリア展開を描きにくくなります。
このような心理状態になると、仕事に対する前向きな取り組みや自己成長意欲が低下する可能性があります。さらに、再雇用者自身が「職場に貢献できていない」と自己否定感を感じるケースもあり、メンタルヘルスの問題にもつながりかねません。
職場の世代間ギャップが広がる
再雇用された社員と若手社員の間には、働き方や価値観、使用する言葉や表現などに大きなギャップが生じる場合があります。例えば、若手社員はメールやチャットなどデジタルコミュニケーションを主に使いますが、再雇用者は対面や電話でのコミュニケーションを好むことがあります。
こうした違いが、意図せぬ誤解や情報伝達ミスを引き起こし、業務遂行に悪影響を及ぼすことがあります。結果として、チーム内の信頼関係が希薄になったり、業務の効率が低下したりするリスクが高まります。そのため、双方の理解を深めるための企業の取り組みが必要になります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
再雇用は法律で義務付けられている?
高年齢者雇用安定法では、従業員の希望があれば 65歳までの雇用を確保することを企業に義務付けています。具体的な措置として、企業は以下の3つの方法のいずれかを選択する必要があります。
- 定年の引き上げ
例:60歳定年を65歳へ引き上げる - 再雇用制度の導入
例:60歳で一度定年退職した従業員を65歳まで再雇用する - 定年制の廃止
例:定年をなくし、年齢に関係なく雇用を継続する
これらの措置の中で、特に多くの企業が選択しているのが、再雇用制度の導入です。
企業が法的義務(65歳までの雇用措置)を守らない場合、厚生労働大臣から指導や勧告、社名公表といった行政措置を受ける可能性があります。現時点では、違反に対して直接的な罰金や罰則はありませんが、社会的評価が下がるなどのリスクがあります。
再雇用した社員を辞めさせたい場合はどうする?
再雇用制度を導入したものの、実際には制度の運用が難しくなり、「再雇用した社員を辞めさせたい」「制度そのものを廃止したい」と感じる企業もあります。
しかし、再雇用した社員を企業側の一方的な都合で辞めさせることは困難です。なぜなら、再雇用された社員は法律上「労働契約」を結んでいるため、正当な理由がない限り契約解除は認められないからです。
ただし、次のような状況では辞めてもらうことが可能になる場合があります。
- 本人との合意による退職勧奨
- 勤務態度や能力不足を客観的に証明でき、指導・改善の機会を提供しても改善されない場合
- 契約期間満了時に更新しない旨を契約時に明確に示していた場合
再雇用社員の退職を進める際には、本人と円滑に話し合いを進め、労使トラブルを防ぐ配慮が必要です。
再雇用制度自体を廃止・縮小する方法
再雇用制度自体を廃止または縮小したい場合は、高年齢者雇用安定法に基づき、65歳までの雇用を確保するための代替策(定年延長、定年制の廃止など)が求められます。
具体的には、以下のような手順が必要です。
- 再雇用制度に代わる代替案(定年延長、雇用延長措置など)を検討し決定する
- 就業規則を改定し、労働者に周知・同意を得る
- 社員とのコミュニケーションを十分に取り、変更の目的を説明する
再雇用制度を辞めたい場合でも、法的なルールを遵守しつつ進めることで、企業・従業員双方の納得を得ながら制度変更を行うことが可能になります。
再雇用を辞めさせる際のトラブルを防ぐポイント
再雇用社員を辞めさせたり、制度を廃止したりする場合、以下のようなポイントを押さえるとトラブルを避けることができます。
- 一方的に通知するのではなく、社員本人と十分な話し合いを行う
- 契約内容や辞めてもらう理由を明確にし、書面など記録を残す
- 社労士や労働問題の専門家に相談し、法的リスクを把握しておく
再雇用の問題でお悩みの場合は、専門家のアドバイスを活用し、法的リスクを回避することが重要です。
再雇用制度を導入するメリットは?
再雇用を望まない人もいますが、制度自体には以下のようなメリットもあります。
経験豊富な人材を活用できる
再雇用制度により、長年培ったスキルや経験を持つ社員が継続的に企業内で働くことが可能になります。特に専門知識や技術を必要とする職種においては、経験豊かな人材が残ることで、新入社員の教育指導や若手のサポートを効果的に行えます。これにより、新人育成の効率化や技術伝承が進み、企業の生産性向上につながる可能性があります。
人手不足を解消できる
少子高齢化が進む現代社会では、多くの企業が慢性的な人手不足に悩まされています。再雇用制度を導入することで、人材不足を補うことが可能になり、労働力を安定的に確保できます。特に中小企業や地方の企業においては、新規採用が難しい状況下で再雇用は貴重な人的資源となります。
採用コストを削減できる
再雇用制度は労働力を維持しつつ、採用コストを削減する効果があります。経験豊富な人材を手軽に確保できるため、新しい人材を採用して育成する手間を省くことが可能です。特に、日本では少子高齢化が進行しており、若年層の労働力が減少しています。総務省のデータによれば、2023年時点で65歳以上の雇用者人口はおよそ900万人で、これは全労働者の13.9%に相当します。再雇用は、このような状況で貴重な人材を有効活用する手段と言えるでしょう。
企業の社会的評価が向上する
再雇用制度を積極的に取り入れる企業は、高齢者の社会参加を促進しているとして、社会的評価や企業イメージの向上につながります。特に持続可能な社会やダイバーシティを重視する風潮の中で、再雇用制度を設ける企業は好意的に評価されやすくなります。
再雇用制度に代わる新しい人材活用のアイデア
再雇用制度に代わる選択肢として考えられるのは、多様な人材活用と柔軟な組織運営です。これにより、より効率的で活気ある職場環境を実現できます。具体的な施策を以下で紹介します。
柔軟な働き方の導入
柔軟な働き方とは、社員の年代や状況に合わせて、働く時間や場所を自由に選べる仕組みのことです。例えば、リモートワーク・在宅勤務や、勤務時間を柔軟に調整できるフレックスタイム制などがあります。社員の生活に合わせた働き方ができるため、仕事の満足度が上がり、仕事への意欲や生産性の向上につながります。
ジョブシェアリングの活用
ジョブシェアリングとは、一つの仕事を複数の社員が分担して行う働き方のことです。この方法なら、それぞれが限られた時間に集中して仕事を行えるため、仕事とプライベートをうまく両立できます。また、複数人の異なる視点を取り入れることで、業務の質や新しいアイデアの向上にもつながります。
社員のスキルアップ・キャリア支援
社員のスキルアップを継続的に支援することは、企業の長期的な成長に役立ちます。そのためには、定期的な研修やトレーニングを実施し、一人ひとりが新しいスキルを身につけられる環境を整えます。また、具体的なキャリアプランを提示することで、社員が目標を持って働きやすくなり、やる気や貢献意欲が高まります。
世代を超えたチーム編成
年齢や世代が異なる社員でチームを作ると、それぞれの得意分野をうまく組み合わせることができます。例えば、若手社員の最新のデジタル知識と、ベテラン社員の経験や知恵を融合させれば、アイデアや問題解決力が向上し、チーム全体の能力が高まります。多様な視点を取り入れることで、組織がより柔軟になります。
評価制度の見直し
社員の評価方法を見直すことも重要です。成果だけでなく、仕事の進め方や挑戦する姿勢も評価対象に含めます。こうすることで、社員は失敗を恐れず新しいことに挑戦しやすくなります。また、社員が働きやすい職場環境となり、優秀な人材の離職を防ぐことにもつながります。
再雇用制度に関してよくある悩みと解決策
再雇用には多くの方が抱える一般的な悩みが存在します。ここでは、それぞれの悩みを取り上げ、解決策を考えていきます。
再雇用制度を続ける必要はある?
高年齢者雇用安定法で65歳までの雇用確保が義務付けられているため、再雇用制度を続けることが一般的です。しかし、他にも柔軟な勤務体系や仕事の分担など、新しい方法を導入して負担を減らすことも可能です。
再雇用された社員の仕事がスムーズに進まない…
高齢社員と若手社員とのコミュニケーション不足や価値観の違いから問題が生じることがあります。解決策としては、双方が定期的に話し合う場を設けたり、業務の役割分担を明確にしたりすることが効果的です。また、年齢に関係なくお互いが尊重し合える環境づくりが大切です。
再雇用された社員は本当に戦力になっている?
社員の評価は個人によって差があります。ただ、再雇用された社員には長年の経験やノウハウがあり、若手社員の育成やアドバイザーとして重要な役割を果たしているケースもあります。一方で、再雇用後の役割が適切でない場合は、改善が必要です。
再雇用制度は若手社員にどのような影響がある?
若手社員にとっては、ポストや昇進の機会が減ったり、年齢によるコミュニケーションギャップが生じたりする可能性があります。一方で、再雇用された社員の豊富な経験から学べるメリットもあります。会社側が世代間交流を積極的に促すことで、双方に良い影響を与えることが可能です。
再雇用制度を見直し、柔軟な人材活用を進めましょう
再雇用制度を完全にやめるのは現実的に難しいですが、制度を柔軟に改善したり、新しい働き方を導入したりすることで、社員と企業双方の満足度を高めることが可能です。世代を超えたコミュニケーションや人材活用を積極的に進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【チェック付】スメハラとは?どう伝える?職場の具体例や対策を解説
スメハラ(スメルハラスメント)は、体臭や香水、タバコなどの「臭い」が原因で他者に不快感を与えることを指します。 本人に悪意がなく、体質や文化の違いも絡むため対応が難しく、集中力低下…
詳しくみる外国人労働者を派遣社員として雇用できる?メリットや注意点も解説
外国人労働者を派遣社員として雇用することは可能です。適切に派遣を活用すれば人手不足の解消やコスト削減につながりますが、法的リスクや契約内容の確認が重要です。 本記事では、外国人労働…
詳しくみる配置転換の拒否で退職勧奨されたら違法?判断基準と適切な対応方法を解説
「突然配置転換を命じられたけど、拒否したら退職勧奨を受けるのでは?」と不安や悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。 このような不安を解消するために、本記事では配置転換拒否と…
詳しくみるワクハラとは?ワクチン強制は違法?職場での注意点
ワクハラとは、ワクチンの接種を強要したり、ワクチン未接種であることを責めるような言動をしたりすることをいいます。ワクチン・ハラスメントの略称であり、新型コロナウイルスの影響下におい…
詳しくみる外国人雇用に人数制限はある?特定技能の受け入れ上限や雇用時の注意点を解説
外国人労働者の雇用を考えている企業は、受け入れ人数に制限はあるのか気になる方も多いでしょう。 原則として外国人労働者の雇用に人数制限はありません。しかし、特定技能や技能実習制度にお…
詳しくみる人材版伊藤レポートとは?人的資本経営との関係やポイントを解説
人的資本経営における伊藤レポートは、企業が持続的成長を実現するための戦略的な指針として、人的資本の活用方法やサステナビリティ達成のための重要な指針です。 経済産業省が提唱した伊藤レ…
詳しくみる