- 更新日 : 2025年11月6日
夜勤明けの次の日に日勤は可能!違法のケースや仕組みを解説
「夜勤明けの次の日に日勤は可能?」「法律的に違反ではないの?」
夜勤が続いた翌日、日勤が控えている状況は、シフト勤務の職場ではよくあることでしょう。
結論、夜勤明けの次の日の日勤は法律的には問題なく可能です。しかし、適切な労務管理が行われていない場合、法律違反や従業員の健康状態への影響等が懸念されます。
本記事では、夜勤明けの次の日に日勤を行う際のよくある疑問に答えつつ、労働基準法や健康管理の観点から適切なシフト作成方法を解説します。
従業員にとって働きやすい職場環境を実現するために、ぜひ参考にしてください。
目次
夜勤明けの次の日に日勤は可能
夜勤明けの次の日に日勤勤務を行うことは、法律上は可能です。割増賃金を支払うことで法的要件を満たせるため、法律上の違法性はありません。
しかし、労働者の健康や安全を守るため、実務上は最低限の休息時間を設ける必要があります。
たとえば、夜勤が22時から翌6時まで、日勤が翌日9時から始まる場合、3時間の休息時間しか取れません。この場合、従業員の負担が増大するため、法律に違反していなくても健康面でのリスクを考慮した配慮が求められます。
なお、働き方改革の一環として「労働時間等設定改善法」において、従業員の休息時間の確保を目的とした「勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上確保する取組)」の導入が努力義務として定められています。
日勤後の夜勤は始業日で残業扱い
日勤と夜勤が連続する場合、夜勤の始業時間が日勤と同日として扱われ、残業時間の対象となります。労働基準法第32条に基づき、法定労働時間を超えた労働が残業扱いです。
たとえば、日勤が9時から17時、夜勤がその日の22時から翌朝6時までの場合、日勤の終了後、夜勤開始までの間に中途の休息があるとしても、夜勤は日勤と同一日の労働時間に含まれます。この場合、残業代や深夜手当の適切な計算が必要です。
企業がこのような勤務形態を導入する場合は、適切な休息時間を確保し、従業員が過重労働にならないよう配慮する必要があります。残業代や深夜手当の計算方法は以下の通りです。
日勤後の夜勤にかかる賃金
- 所定労働時間(8時間)を超える部分:25%増
- 深夜労働(22時~翌5時):25%増(時間外労働+深夜労働の場合は50%増)
1日8時間または1週40時間を超える労働には、割増賃金を支払う義務があります。また、日勤と夜勤が連続する場合、それぞれの勤務が1日の労働時間にカウントされるため、企業側は労働時間管理にとくに注意を払う必要があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
出勤簿(エクセル)
従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。
本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。
勤怠管理表(ワード)
従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。
本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。
夜勤明けの勤務で違法になってしまうケース
労働基準監督署への通報対象となる可能性があるため、企業はシフト設計や賃金計算を慎重に行うことが重要です。ここでは、夜勤明けの勤務が違法となるケースを見ていきましょう。
36協定が守られていない
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)が遵守されていない場合、企業には重大なペナルティが科される可能性があります。
36協定とは法定労働時間を超える労働をさせる場合、労働基準監督署に36協定を届け出る必要があります。この協定がなければ時間外労働を命じることは違法です。
例として、夜勤明けから24時間以内に再び勤務させること自体は違法ではないものの1ヶ月の残業時間が45時間、1年間の残業時間が360時間を超える場合、法律違反に該当します。
違反した場合、労働基準法第32条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
法定休日がない
労働基準法第35条では、1週間に1回以上の法定休日を与えることが義務付けられています。法定休日とは、労働基準法により定められた労働者に与えなかればいけない休日で、最低1週間に1回、または変形労働時間制の場合には4週間で4回以上必要です。
違法となる例
- 連続勤務が法定休日をまたぐ
- 法定休日に出勤しその分の代休を与えない
たとえば、夜勤明けの翌日に日勤が組まれ、さらにその後も連続勤務が続く場合、週に1日の法定休日が確保されていない可能性があります。法定休日を守られていない場合、労働者の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、企業は法律違反となります。
安全配慮義務に違反している
企業は労働契約法第5条に基づき、従業員の安全と健康を守る安全配慮義務があります。安全配慮義務とは、労働者が安全かつ健康に働ける環境を整備する企業側の義務です。
夜勤明けに十分な休息が取れず、そのまま連続勤務を強要される場合、過重労働による健康被害のリスクが高まり、企業の義務違反に該当します。
違反となる例
- 過重労働による健康被害が発生した場合
- 労働環境が適切でない場合(例:休憩時間が十分でない)
たとえば、夜勤後の疲労が原因で事故や疾病が発生した場合、企業には法的責任が問われる可能性があります。企業は従業員が安全に働ける環境を整備をしなければなりません。
割増賃金の未払いがある
夜勤や時間外労働に対して支払われるべき深夜手当や残業代が未払いである場合、労働基準法第37条違反となります。
対象となる割増賃金
- 時間外労働手当(25%増)
- 深夜労働手当(22時~翌5時:25%増)
- 法定休日労働手当(35%増)
たとえば、深夜(22時〜翌5時)に勤務した時間が適切に計算されておらず、賃金に反映されない場合が該当します。深夜労働手当や法定休日労働手当が反映されていないケースも同様です。
未払いが発覚した場合、労働者は労働基準監督署に相談でき、企業は、未払い分を遡って支払う義務があります。違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため、企業側は従業員の労働時間をこまめに管理する必要があります。
夜勤のシフトを作成する際の4つのポイント
夜勤のシフトを作成する際には、法律を遵守することはもちろん、労働者の健康や働きやすさにも配慮が必要です。ここでは、夜勤シフト作成時に押さえるべき4つのポイントを紹介します。
勤務間インターバル制度を導入する
勤務間インターバル制度は、前日の勤務終了から次の勤務開始まで一定の休息時間を確保する仕組みです。日本では、9〜11時間以上のインターバルを確保することが推奨されています。
たとえば、夜勤終了が午前8時の場合、次の勤務開始を午後7時以降に設定することで、十分な休息を確保でき、従業員が働きやすい職場に感じやすいでしょう。シフト表にはインターバル時間を明記し、従業員と共有することも効果的です。
勤務間インターバル制度を導入することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 労働者の疲労を軽減
- 生産性の向上やミスの減少
- 長時間労働を抑制し、職場環境を改善
勤務間インターバル制度を取り入れることで、労働者にとっても働きやすい職場環境を作り出せます。なお、勤務間インターバルは「労働時間等設定改善法」において制度導入が努力義務化されています。
シフトの偏りをなくす
公平なシフト管理は、従業員の不満を減らし、チーム全体の士気向上につながります。
特定の従業員に夜勤が集中すると、過労や離職の原因となるため、偏りを防ぐ工夫が必要です。シフトの偏りをなくすための具体的な対策は以下の通りです。
具体的な対策例
- ローテーション制を導入:夜勤の担当を公平に分配し負担を軽減
- 従業員の希望を反映:事前に希望シフトをヒアリング
- データを活用:過去の勤務履歴をもとに勤務回数や時間帯のバランスを管理
シフト管理の偏りをなくすことで、従業員の信頼感が高まり、職場の雰囲気が良くなります。企業側は、シフト管理が公平であることを明確に伝え、バランスの取れた労働環境を整備しましょう。
健康状態に配慮してシフトを組む
夜勤は従業員の健康に大きな影響を与えるため、体調を考慮したシフト調整が欠かせません。無理なスケジュールを組むことは避け、健康を優先した管理を心がけましょう。健康状態に配慮したシフトの組み方については以下の通りです。
具体的な配慮例
- 夜勤明けは休息日を確保:夜勤後に十分な休息時間を確保し、翌日の勤務開始を調整
- 短時間勤務を検討:高齢者や健康面で不安のある従業員には、短時間勤務を提案
- 定期的な健康診断を実施:従業員の健康状態を把握し、シフト調整に反映
なお、深夜業に従事する労働者については、6ヶ月以内ごとに1回「特定業務従事者の健康診断」を実施する必要があります。
従業員一人ひとりの状況を把握することで、健康を守りながら効率的なシフト管理が実現します。健康を重視した姿勢は従業員の安心にもつながり、企業の生産性アップにもつながるでしょう。
シフト作成アプリ・システムを導入する
効率的で公平なシフト管理を行うためには、シフト作成アプリやシステムなどのツールの活用が有効です。企業が人事や労務を管理するツールを導入すると、管理にかかる時間と手間を大幅に削減し、従業員の希望を反映した柔軟な管理ができるでしょう。
導入のメリット
- シフト作成にかかる時間を短縮可能
- 勤務履歴や希望を把握可能
- リアルタイムで変更や通知あり
従業員が働きやすくするためにも、適切なシフト管理で、労働者にとって働きやすい環境を整えると、企業の持続可能な運営につながります。マネーフォワードではクラウド上で組織情報を一元管理できる人事管理システムを提供しています。現在のシフト管理業務をさらに効率的に管理したい企業や担当者の方は、導入を検討してみてください。
夜勤明けの次の日の日勤に関するよくある疑問
夜勤と日勤が連続する勤務スケジュールについて、従業員や管理者からは多くの疑問が寄せられます。ここでは、よくある疑問を解説しながら、適切な労務管理について見ていきましょう。
夜勤の連続勤務は何日まで可能?
労働基準法上、夜勤の連続勤務に具体的な日数制限はありません。しかし、週1回法定休日を取得するというルールを考えれば、連続で11日勤務までは可能です。
たとえば、日曜日に完全な休日を取得し、翌月曜から、翌週の木曜まで連続深夜勤務に従事し、金曜に明け休日、土曜に完全休日を取得すれば、理論上は可能です。ただし、こうしたシフトを組む場合でも、以下の点に注意が必要です。
- 過重労働のリスク
- 勤務間インターバルの確保
- 深夜労働に対する割増賃金
- 健康管理と安全配慮義務
過重労働や従業員の健康を考えると、3〜5日を目安にすることが推奨されています。
日勤や休日を挟むことで、リフレッシュの機会を確保し、労働者の健康と業務効率の維持につなげられるでしょう。
夜勤から日勤の連続勤務に制限はある?
夜勤明けの次の日に日勤を入れる場合も、労働基準法上明確な規定はないため、適切な法定休日を組んだ勤怠管理であれば、法律違反にはなりません。
しかし、夜勤からの日勤をしてもらうには、勤務間インターバルの確保が必要です。インターバルを確保していない場合、長時間労働として違法となる可能性があります。
夜勤が午前8時に終わり、日勤が午後1時から始まる場合など、インターバルが5時間しか確保されていない場合は、労働者の健康を損なうリスクが高まります。
そのため、夜勤終了から11時間を目安に間隔を確保し、従業員が十分に休息できるように調整しましょう。
日勤から夜勤への連続勤務は問題ない?
日勤後に夜勤を入れることは、割増賃金を支払っていれば、法律上問題はありません。
しかし、労働時間の管理が不適切な場合には問題となります。日勤が午後5時に終了し、その日の深夜0時から夜勤が始まる場合、時間外勤務による割増賃金は発生しませんが、休息時間が不十分であり、従業員の健康管理に不安を残します。
日勤から夜勤の場合も、勤務間インターバルを設けることで、従業員が身体的・精神的に回復できるようにします。 シフト作成時には、労働時間が過度にならないように計画を立て、従業員の健康を最優先に考えましょう。
夜勤明けは休日扱いになる?
夜勤明けの日を休日として扱うことは、労働基準法第35条に基づき、原則として認められません。
労働基準法では、休日を「午前0時から午後12時までの暦日単位で与える必要がある」と規定しています。そのため、夜勤明けで午前8時に終了した場合、その日は休日とカウントされません。
夜勤終了後に丸1日休みを設ける場合は、翌日を休日として指定する必要があります。夜勤明けの時間帯を考慮した上で、労働者にとって適切な休息時間を確保し、次回勤務との間隔を調整することが大切です。
夜勤明けの次の日の日勤は可能!正しい労務管理を始めよう
夜勤明けの次の日に日勤を入れることは法律上可能ですが、従業員の健康と業務効率を守るためには、勤務間インターバルの確保や公平なシフト管理が不可欠です。
また、割増賃金の適切な支払いといった労務管理を徹底することで法令遵守を実現しながら、従業員のモチベーションや健康維持につなげられるでしょう。
労働基準法を遵守しつつ、従業員が安心して働ける環境を整えていきましょう。マネーフォワードでは、人事・労務管理システムを提供しています。現在のシフト管理の体制や勤怠管理をさらに効率的に進めたい企業は、ぜひ導入を検討してみてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
8連勤は違法? 連勤は何日まで可能かを解説
日本の多くの会社では1ヶ月に1回以上、休日が2日間ある週を設けるという、週休2日制を導入しています。したがって5連勤までは、一般的な働き方であると考えられます。 しかし、変則的な働き方を採用している会社では、8連勤や9連勤をしている方も少な…
詳しくみるシフト管理をペーパーレス化するには?電子化の進め方や成功事例を解説【無料テンプレつき】
シフト制を採用すれば、従業員は自分の生活スタイルに合わせて、希望する日時に働くことが可能となります。しかし、シフト制を採用した場合には、通常の勤務体制よりも複雑な勤怠管理が必要です。紙の管理では、管理ミスも発生しやすいでしょう。当記事を参考…
詳しくみる土曜出勤は休日出勤扱いにならない!36協定での扱いや注意点を解説
「土曜出勤って休日出勤扱いになるの?」「36協定での扱いは?」 上記のような疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。 土曜出勤の扱いが休日扱いになるかどうかは、企業の就業規則や36協定の内容によって異なります。 本記事では、土曜出勤に関する…
詳しくみる7連勤は違法?週またぎはOK?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
7連勤は、肉体的疲労と精神的なストレス、そしてプライベートの喪失が重なり、働く人にとって大きな負担となります。 表面的には仕事をこなせているように見えても、休息が取れないまま働き続ければ、心身の健康を損ない、最終的にはパフォーマンスの低下や…
詳しくみる法定内残業・法定外残業とは?違いや割増率と賃金の計算方法、具体例を解説
残業には法定内残業と法定外残業があります。法定内残業は労働基準法に定める法定労働時間内での残業、法定外残業は法定労働時間を超える残業です。法定内残業と法定外残業の違いは割増賃金の支払いと36協定が必要かどうかです。法定内残業時間に対しては法…
詳しくみる中抜けとは?テレワークや勤怠管理のルール設定と注意点【周知文テンプレ付き】
中抜けとは、業務時間内に一時的に仕事から離れて再度仕事に戻るまでの時間のことを言います。 私用によるものと会社都合によるものがあるので、勤怠管理上の扱いに注意が必要です。 この記事では、業務時間内の中抜けや勤怠管理上の中抜けの扱いと例、中抜…
詳しくみる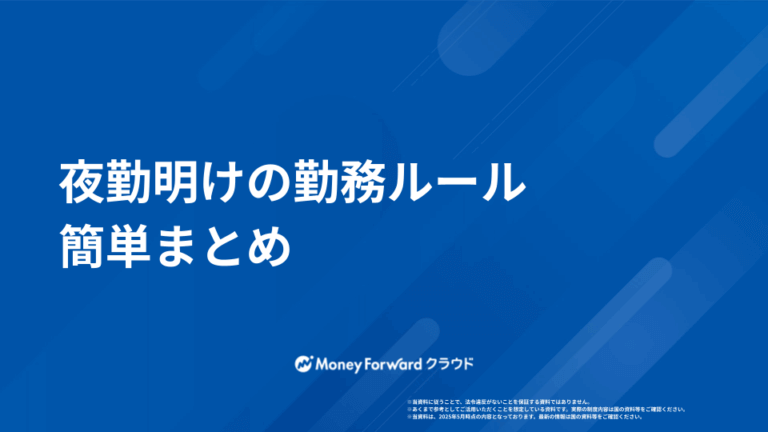


-e1762262472268.jpg)
-e1762262460348.jpg)