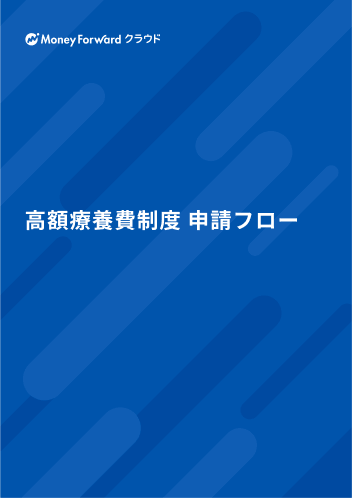- 更新日 : 2025年11月19日
高額療養費(高額医療費支給制度)とは?社会保険の観点から仕組みを解説!
「高額療養費制度」とは、高額な医療費負担を軽減するための制度で、医療機関で支払った自己負担額のうち限度額を超えた額が手続きによって還付されたり、事前申請によって支払わずに済んだりします。申請方法は加入している医療保険によって異なり、申請しなくても戻ってくるものもあります。
目次
高額療養費(高額医療費支給制度)とは?
健康保険などの高額療養費制度は、公的医療を受ける際の自己負担額が高額になる場合に負担を軽減する制度です。
高額療養費は月(歴月・1日から月末日まで)ごとに適用され、月をまたいだ場合は区切られます。例えば10月21日から11月5日まで医療機関で受診した場合、10月31日までは10月分、11月1日以降は11月分となります。
以前は同じ病院で複数の診療科で受診した場合でも分ける必要がありましたが、平成22年(2010年)4月からは1つの医療機関としてまとめることが認められるようになりました。69歳以下は2万1,000円以上の領収書が必要で、70歳以上は金額にかかわらず、合算して高額療養費を請求することができます。
高額療養費はいくらから支払われる?
高額療養費は、医療機関窓口に支払う自己負担額が定められた金額を超える場合に支給されます。定められた金額は、高額療養費制度(高額医療費支給制度)では高額療養費算定基準額で、一般的に限度額と呼ばれます。年齢や収入によって異なる限度額が定められていて、該当する限度額を超えると高額療養費が支払われます。
高額療養費の限度額
高額療養費の限度額は以下の表のとおりです。
▼ 70歳未満
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% |
| 標準報酬月額53~79万円 | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% |
| 標準報酬月額28~50万円 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% |
| 標準報酬月額26万円以下 | 5万7,600円 |
| 非課税所得者 | 3万5,400円 |
注)かかった医療費全額(10割)が総医療費です。
▼ 70歳以上
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% |
| 標準報酬月額53~79万円 | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% |
| 標準報酬月額28~50万円 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% |
| 標準報酬月額26万円以下 | 1万8,000円(1年間で14万4,000円) |
| 非課税所得者 | 8,000円 |
注)かかった医療費全額(10割)が総医療費です。
高額療養費の自己負担額
高額療養費制度を利用すると、自己負担額は限度額までに抑えることができます。ただし、以下のような費用は高額療養費の対象にはなりません。
- 医療を受けない場合でもかかる費用
食事代や居住費 - 希望によって受けるサービスにかかる費用
差額ベッド代や先進医療費
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック
人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。
40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。
入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル
従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。
本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
高額療養費の申請方法
高額療養費を受けるには、定められた方法で申請する必要があります。申請には、事前申請と事後申請があります。
事前申請の場合
高額療養費は一定の条件を満たす場合、事前申請が可能です。本来は医療機関窓口で医療費の自己負担分を一旦支払わなければなりませんが、高額療養費の事前申請を利用することで一時的な支出も不要になります。あらかじめ認定証を受け取り、医療機関の窓口で提示することで高額療養費限度額を超える支払いがなくなります。認定証の交付を受ける場合は、各都道府県支部に健康保険限度額適用認定申請書を提出して申請します。
事後申請の場合
高額療養費は基本的に事後申請です。その月に支払った医療費を合計し、限度額を超えた場合に申請します。所定の申請書を必要とされる添付書類と一緒に提出して申請します。
社会保険における高額療養費の申請方法の違い
社会保険の高額療養費を受け取るには、基本的に公的医療保険への申請が必要です。加入している公的医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に必要書類を提出して申請します。申請方法は医療保険によって異なり、病院や薬局など、かかった医療機関の領収書が求められることがあります。
会社で社会保険に加入している場合
会社で社会保険に加入している場合の医療保険は、協会けんぽか健康保険組合です。高額療養費の申請は、協会けんぽか健康保険に申請書類を提出して行います。協会けんぽの場合、高額療養費の申請は各都道府県の支部に対して行います。
任意継続をしている場合
任意継続をしている場合でも、高額療養費の申請方法は会社で社会保険に加入している場合と同じです。任意継続として加入している協会けんぽか健康保険組合に必要書類を提出して、高額療養費を申請します。協会けんぽの場合は、各都道府県の支部に対して申請します。
高額療養費は申請しなくても戻ってくる?
高額療養費の還付を受ける場合は申請が必要ですが、申請しなくても戻ってくることがあります。高額療養費の申請方法は加入している公的医療保険によって異なり、医療保険によっては高額療養費の支給対象であることを通知してくれたり、申請なしで自動的に支払ったりしているものもあります。
また、マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、認定証がなくても医療機関窓口での高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費の仕組みを理解し、必要な対応をしっかり行おう
多額の医療費がかかる治療を受け、医療機関で支払った自己負担額が一定額を超える場合、高額療養費の還付を受けることができます。申請書を提出して高額療養費の還付を受けますが、支給対象になったことを通知して申請を促してくれるところや、申請なしで自動的に支給してくれるところもあります。会社が加入している公的医療保険(協会けんぽ・健康保険組合)の高額療養費制度を確認し、申請方法をしっかり理解しておくことが大切です。
特に多額の費用がかかる医療を受けている従業員やその家族がいる場合は、高額療養費について正しい知識を持つ必要があります。しっかり対応できるよう、仕組みをよく理解しておきましょう。
よくある質問
高額療養費とは何ですか?
医療機関で支払った自己負担額が高額となった場合、限度額を超えた金額が申請によって戻ってくる制度のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
社会保険の任意継続でも高額療養費制度を使用できますか?
退職後に健康保険を任意継続している場合でも、高額療養費制度を利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
所定労働時間における週20時間とは?計算方法や超える場合の対応について解説
人事労務管理において「週20時間」は、社会保険・雇用保険の適用ラインを決める最も重要な分岐点です。しかし、これが実労働時間ではなく「所定労働時間」で判断される点は、意外と正しく理解…
詳しくみる社会保険の後期高齢者医療制度とは?切り替え手続きを解説
社会保険の後期高齢者医療制度とは、主に75歳以上の後期高齢者を対象とした公的医療制度のことです。それまで社保に加入していた場合は、脱退手続きを行わなくてはいけません。なお、後期高齢…
詳しくみる厚生年金の受給に必要な加入期間 – 10年未満の場合はどうなる?
日本の公的年金制度は2段階です。会社勤めで厚生年金保険に加入していた方は、国民年金の制度で受け取れる老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金が上乗せされます。 国民年金の支給額が年間約78…
詳しくみる失業保険とは?手当の受給資格と手続きを解説!
毎月の給与から天引きされている「失業保険」ですが、どのようなときに受け取ることができるのでしょうか。一般的には、急な解雇や会社が倒産した際に受け取ることが可能です。また、転職のため…
詳しくみる労災保険料の計算方法とは?2025年料率と年度更新をわかりやすく解説
事業主にとって、年に一度の労働保険の「年度更新」は重要な手続きです。とくに労災保険料の計算は、事業の種類によって料率が細かく分かれており、正確な計算方法がわからず不安に感じる方も多…
詳しくみる【申請書ひな形付】男性の育休とは?期間や給付金、法改正を解説
男性の子育て支援を目的に、産後パパ育休の新設などさまざまな法改正が行われているため、企業の担当者は育休に関する諸制度や法改正を正しく理解することが重要です。 本記事では、男性の育休…
詳しくみる