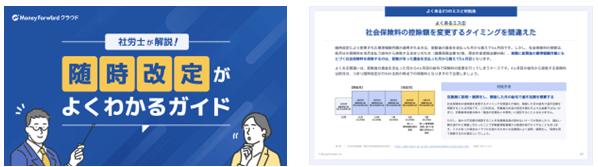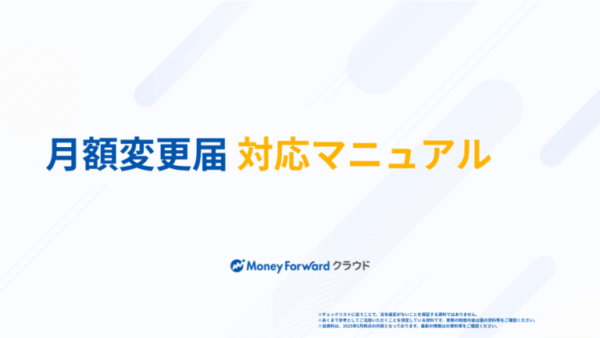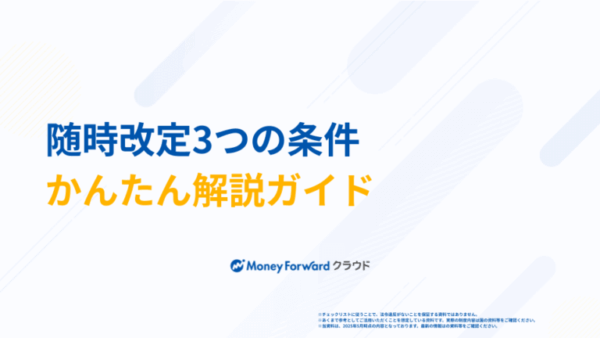- 更新日 : 2025年11月12日
随時改定に残業代は含む?標準報酬月額との関係や社会保険料に与える影響を解説
残業代が増減した場合、随時改定の対象になるのか疑問を抱く方もいるでしょう。
結論、残業代の増減だけでは随時改定の対象にはなりません。ただし、支給割合や固定残業代に変更があった場合は、対象となるケースがあります。
本記事では、随時改定の概要や随時改定に残業代が含まれるかについて、詳しく解説します。
目次
随時改定(月額変更届)とは?
随時改定とは、従業員の給与が大きく変動した場合に行う社会保険手続きのひとつです。ここでは、随時改定の概要について詳しく解説します。
以下の記事では、月額変更届について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
随時改定(月額変更届)の概要
随時改定とは、従業員の給与が大幅に変動した際に、標準報酬月額を見直すために行われる制度です。毎年行われる定時決定を待たずに、給与変動に応じて迅速に保険料負担を適正化することを目的としています。
通常は、毎年4〜6月の給与をもとに、9月から適用されます。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料を算出する基準額で、実際の給与額を一定の等級に分類したものです。
随時改定の手続きを行う際には、月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)を年金事務所へ提出する必要があります。
参考:
定時決定との違い
定時決定と随時改定は、どちらも社会保険料の確定を目的としています。ただし、提出するタイミングや対象者に違いがあります。
定時決定(算定基礎届)は、原則として毎年1回、すべての被保険者を対象に標準報酬月額を見直す制度です。4〜6月に支払われた給与をもとに7月に届出を行い、9月分の社会保険料から反映されます。
そして、1年間(9月〜翌年8月)にわたり、保険料が適用される仕組みです。
一方、随時改定(月額変更届)は、給与に大きな変動があった場合に、対象者ごとにその都度行われます。変動があった報酬に対して、即時に社会保険料を変更するために使用されるのが特徴です。
| 手続き名 | 提出時期 | 適用開始月 |
|---|---|---|
| 定時決定 | 毎年7月1日〜10日 | 9月分の社会保険料から |
| 随時改定 | 給与変動時に随時提出 | 変動月から4ヶ月目に適用 |
定時決定は全従業員を対象とする定期的な手続き、随時改定は個別の給与変動に対する柔軟な対応策といえます。
参考:
以下の記事では、社会保険料の定時決定について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
随時改定はいつから反映される?
随時改定が反映されるのは、固定的賃金が変更された月から数えて4ヶ月目の保険料からです。たとえば、4月に昇給があった場合は、8月の保険料に反映されます。
なお、社会保険料は通常、翌月払いとなります。そのため、実際に従業員の給与から保険料が控除されるのは、5ヶ月目になる点に注意が必要です。
また、企業によっては給与が当月払いと翌月払いで異なるため、反映のタイミングにも差が生じます。給与支払方法に応じて、適切な管理と通知が求められるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
随時改定に残業代は含む?
残業代のみが増減しても随時改定の対象にはなりません。ただし、残業代の支給割合(割増率)や、固定残業代の金額を変更した場合は、随時改定の対象となるケースもあります。
ここでは、残業代と随時改定の関係について詳しく解説します。
以下の記事では、社会保険の随時改定を行う3つの条件について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
残業代のみの変動は随時改定の対象にはならない
随時改定は、基本給や手当などの「固定的賃金」に変動があった場合に行われます。一方、残業代は労働時間に応じて支給額が変動する「非固定的賃金」に該当します。
そのため、残業時間が増えた・減ったといった理由だけでは、随時改定の対象とはなりません。
随時改定の対象となる条件
随時改定は、すべての給与変動が対象になるわけではありません。ここでは、対象となる条件3つについて詳しく解説します。
固定的賃金に大きな変動がある場合
固定的賃金に大きな変動があると、随時改定の対象となります。固定的賃金とは、支給額や支給率が決められた賃金のことです。
- 基本給
- 役職手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 住宅手当
昇給・降給のほか、新しい手当の支給や廃止も対象になります。また、日給や時間給の単価変更、割増賃金率の変更によって、実質的に固定的賃金が変わる場合も随時改定の対象に含まれます。
たとえば、結婚による家族手当の支給、引っ越しでの通勤手当の変更なども対象となるため、注意が必要です。
以下の記事では、固定的賃金について詳しく解説していますので、参考にしてください。
標準報酬月額で2等級以上の差がある場合
標準報酬月額に2等級以上の変動が生じた場合、随時改定の対象となります。具体的には、固定賃金の変動により、改定後の標準報酬月額と、改定前の標準報酬月額に2等級以上の変動が生じる場合です。
標準報酬月額は、健康保険は50等級、厚生年金は32等級に分かれています。賃金の変動によってこれらの等級に2段階以上の差があれば、随時改定の対象になります。
ただし、下記のようなケースは該当しません。
- 固定賃金は増えたが、残業代が減ったため、等級が下がった
- 固定賃金は減ったが、非固定的賃金(残業代など)が増えて等級が上がった
また、上限または下限等級に該当する従業員については、1等級の変動でも随時改定の対象となるため、注意しましょう。
以下の記事では、標準報酬月額の2等級以上の差について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上の場合
固定的賃金の変動があった月から、3ヶ月連続で支払基礎日数が17日以上であった場合は、随時改定の対象となります。
支払基礎日数とは、給与を計算するときの対象日数のことを指し、給与形態によってカウント方法が異なります。
- 月給制・週給制:暦日数(休んだ日も含む)
- 日給制・時間給制:出勤日数が支払基礎日数に該当
なお、日給月給制の場合、欠勤した日数は控除されるため、欠勤が多い月は17日未満になる可能性がある点に注意が必要です。
3ヶ月のうち1ヶ月でも支払基礎日数が17日未満になると、随時改定の対象外となるため、適切な勤怠管理が求められます。
随時改定の対象にならないケース
随時改定は、非固定的賃金が変動しただけでは適用されません。非固定的賃金とは、勤務状況や成果に応じて支給額が変動する賃金のことを指します。
具体的なケースは、下記のとおりです。
- 残業時間の増減により給与が変動した場合
- 成果報酬やボーナスの支給額が変わった場合
- 皆勤手当や夜勤手当などに変動があった場合
勤務状況や成果によって金額が変わる「非固定的賃金」とみなされます。そのため、たとえ給与総額に変動があっても、随時改定の対象とはなりません。
実務では、どの賃金が固定的かを把握することが大切です。
残業代の支給割合を変更する場合は随時改定の対象になる
残業代の金額は通常、労働時間に応じて毎月変動します。そのため、非固定的賃金に該当し、残業時間の増減のみでは随時改定の対象にはなりません。
しかし、企業が残業代の「支給割合(割増率)」を変更した場合は異なります。この場合は賃金体系の見直しに該当し、固定的賃金の変更とみなされるため、随時改定の対象になる可能性があります。
たとえば、法定の25%割増から、企業独自に法定割増率を超える30%に引き上げたら、毎月の給与支給の計算方法自体が変わるため、固定的賃金が変更されたと判断されるでしょう。このような割増率変更時には、随時改定の手続きを検討する必要があります。
参考:日本年金機構|標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
固定残業代の支給額を変更した場合も随時改定の対象になる
固定残業代は、あらかじめ決められた時間分の残業代を基本給とは別に、もしくは含めて一定額支給する制度です。具体的には「月30時間分の残業代を定額で支払う」といった形が該当します。
固定残業代は、勤務実績に関係なく毎月支給されるため固定的賃金に分類されます。したがって、固定残業代の金額を変更した場合は、随時改定の対象です。
一方、通常の残業代は、実際の労働時間に応じて支給されます。そのため、非固定的賃金として扱われ、随時改定の対象にはなりません。
注意すべきなのは、固定的賃金の変更がない場合です。残業代などの非固定的賃金が増減した結果、標準報酬月額が2等級以上変わっても、それだけでは随時改定には該当しません。
参考:固定残業手当の金額が変更になった際、社会保険の随時改定の対象となるか?
標準報酬月額と残業代の関係
随時改定は、基本給や手当といった固定的賃金に変動があった場合に適用される制度です。
しかし、標準報酬月額の算定には、固定的賃金だけでなく残業代などの非固定的賃金も含まれます。そのため、全体の給与額に変動があれば、結果として社会保険料が増減する可能性があります。
たとえ随時改定の対象とならない変動でも、保険料に影響を与える場合がある点には注意が必要です。ここでは、標準報酬月額と残業代の関係について詳しく解説します。
標準報酬月額の対象となるもの
標準報酬月額は、労働者が受け取る賃金のうち、一定の基準にもとづいて計算されます。基本的に、労働の対価として安定的に支払われる給与・手当が対象です。
【標準報酬月額の対象となる報酬】
| 金銭(通貨)で支給されるもの | 現物で支給されるもの |
|---|---|
| ・基本給(月給・週給・日給等) ・能率給 ・奨励給 ・役付手当 ・職階手当 ・特別勤務手当 ・勤務地手当 ・物価手当 ・日直手当 ・宿直手当 ・家族手当 ・扶養手当 ・休職手当 ・通勤手当 ・住宅手当 ・別居手当 ・早出残業手当 ・継続支給する見舞金 ・年4回以上の賞与 | ・通勤定期券 ・回数券 ・食事 ・食券 ・社宅 ・寮 ・被服(勤務服でないもの) ・自社製品 |
出典:日本年金機構|算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和6年度
固定的賃金だけでなく、残業代などの非固定的賃金も算定基礎に含まれます。勤務状況にかかわらず支給される手当と、月ごとに変動する給与の両方が反映される仕組みです。
標準報酬月額の対象とならないもの
すべての給与や支給額が、標準報酬月額の算定に含まれるわけではありません。一時的に支給されるものや、労務の対価ではない支給物は、標準報酬月額の対象外です。
| 金銭(通貨)で支給されるもの | 現物で支給されるもの |
|---|---|
| ・大入袋 ・見舞金 ・解雇予告手当 ・退職手当 ・出張旅費 ・交際費 ・慶弔費 ・傷病手当金、 ・労災保険の休業補償給付 ・年3回以下の賞与 | ・制服 ・作業着(業務に要するもの) ・見舞品 ・食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める額により算定した額の2/3以上の場合) |
出典:日本年金機構|算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和6年度
これらの支給は、標準報酬月額に含めずに報告・計算を行う必要があるため、実務では注意が求められます。
残業代が標準報酬月額・社会保険料に与える影響
残業代は非固定的賃金にあたるため、原則として随時改定の対象にはなりません。随時改定では、固定的賃金の変動があってはじめて見直しの対象となるため、残業時間の増減だけでは適用されないのです。
しかし、残業代は標準報酬月額の算定には含まれるため、給与総額の変動に影響を与えます。注意が必要なのは、定時決定です。定時決定では、4月〜6月に実際に支給された給与総額をもとに、標準報酬月額が決定されます。
この時期に残業が多くなると、標準報酬月額が上がり、結果として健康保険・厚生年金の保険料が増額される場合があります。健康保険料が上がっても、出産手当金や傷病手当金を除き保障内容は変わらず、負担だけが増える可能性があるため、企業・従業員ともに注意が必要です。
一方で、厚生年金保険料が上がれば、将来的な年金受給額が増える可能性があります。
随時改定に関する注意点
随時改定は、固定的賃金の変動があった場合に適切な手続きを行うことが義務付けられています。しかし、届出の遅れや見落とし、手続き後の対応が不十分な場合には、企業にも従業員にも不利益が生じる恐れがあります。
ここでは、随時改定における実務上の注意点を3つ解説しますので、参考にしてください。
随時改定の届出を怠るとどうなる?
随時改定が必要な従業員に対して届出を行わなかった場合、企業には法的・実務的なリスクが伴うため、注意しましょう。
事業主には「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」の提出義務があります。提出を怠ると、健康保険法にもとづき「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
実際に罰則が適用されるケースは稀です。ただし、年金事務所からの指摘により、遡って手続きや計算をやり直す必要が出る場合もあります。
また、厚生年金保険料は将来の年金額に影響するため、適切な届出をしなければ、従業員が不利益を被る可能性もあるため注意が必要です。
固定的賃金が変動しても欠勤がある場合は注意する
随時改定には、「給与が変動した月以降の3ヶ月間すべてで支払基礎日数が一定以上あること」という条件があります。具体的には、1ヶ月あたり17日以上の支払基礎日数が必要です。
固定的賃金が昇給や手当の変更で変動したとしても、欠勤が多く支払基礎日数が17日未満の月があれば、随時改定の対象外になります。
手続きを行う際は、事前に支払基礎日数を確認しましょう。
社会保険料が改定された際は速やかに従業員に周知する
随時改定によって標準報酬月額が変更になると、社会保険料の額も変更されるため、企業はその内容を従業員に速やかに通知する義務があります。
保険料が変わると、給与の手取り額が増減するため、あらかじめ説明しておくことでトラブル回避につながります。従業員への通知方法は、下記のとおりです。
- 給与明細での記載
- 社内メールや通知書の発行
- 社内掲示板や人事システムを活用
万が一、正当な理由なく通知を怠った場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。労使間の信頼関係維持のためにも、情報共有を怠らないようにしましょう。
以下の記事では、社会保険料変更のお知らせの作り方について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
随時改定と残業代の関係を正しく理解し、適切に対応しよう
随時改定は、固定的賃金の変動に応じて社会保険料を適正化する制度です。通常、残業代は随時改定の対象外ですが、固定残業代の変更や割増率の引き上げがある際は、対象となる場合があります。
また、標準報酬月額には残業代も含まれるため、残業が増えると社会保険料が上がる可能性もあります。標準報酬月額や社会保険料への影響を正しく理解し、企業も従業員も損をしないために、適切に対応しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働保険年度更新申告書の書き方
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度という。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払…
詳しくみる社会保険の出産手当金とは – 条件や期間も解説!
出産手当金とは、被保険者が出産により休職し給与の支払いを受けられない場合、休職期間の生活保障のために、社会保険の一つである健康保険から支給される手当のことです。今回は出産手当金の概…
詳しくみるアルバイトをする学生は社会保険に加入するべき?条件を解説
事業者に雇用されて働いている人は社会保険に加入していますが、同じように雇用されていても学生のアルバイトはあまり加入していません。アルバイトとして働く学生は基本的に社会保険への加入義…
詳しくみる社会保険料の対象・対象外になる手当一覧!適用促進手当も解説
給与計算時に支給する多くの手当は社会保険料の算定対象ですが、慶弔見舞金や実費弁償的な出張費など、一部は対象外です。この違いは、その手当が「労働の対償」と見なされるかどうかで決まりま…
詳しくみる雇用保険とそれ以外の社会保険との違いとは
社会保険にはいくつかの種類があります。雇用保険は社会保険と区別して考えられがちですが、雇用保険も社会保険のひとつです。雇用される方や、独立して事業を始める方にとって、雇用保険とそれ…
詳しくみる社会保険の資格喪失届とは
社会保険の資格喪失届とは、従業員が退職や解雇、死亡などにより社会保険のうちの健康保険・厚生年金保険の資格を喪失する場合に提出する書類です。なお、被保険者本人が資格喪失届を提出する必…
詳しくみる