- 更新日 : 2026年2月27日
会社で早退や遅刻をしたら欠勤扱いになる?正しいルールや計算方法を解説
早退や遅刻、欠勤によって働かなかった時間がある場合は、給与計算では該当時間分の賃金を差し引く処理が必要です。しかし、労働時間や給与は従業員にとって重要な問題であり、人事労務担当者が正しく処理できないとトラブルに発展することもあるでしょう。
そこで本記事では、早退・遅刻・欠勤の扱い方について、正しいルールや計算方法を解説します。
目次
会社で早退や遅刻をしたら欠勤扱いになる?
会社で早退や遅刻が欠勤扱いになるかどうかは、企業の就業規則によります。企業によっては「早退や遅刻を3回したら欠勤1日とカウントする」と定めている場合もあるでしょう。しかし、労働基準法第91条では、減給の制裁について以下のように規定を設けています。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
たとえば、10分の遅刻を3回した際に控除していいのは30分の賃金であり、1日分の欠勤扱いにはできないことになっています。1日分の欠勤として扱うまたは減給すると違法とみなされるケースがあるため、注意しておきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
出勤簿(エクセル)
従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。
本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。
勤怠管理表(ワード)
従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。
本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。
早退・遅刻・欠勤が発生した場合の対応方法
従業員が早退や遅刻、欠勤をした場合は「控除」によって不就労時間分の賃金を差し引くことが可能です。この給与計算の処理を「遅刻早退控除」や「勤怠控除」と呼ぶこともあります。控除金額は月給を基に計算するのが一般的であり、早退・遅刻・欠勤をした時間分の給与を減らす対応を行います。
遅刻早退控除の根拠|ノーワークノーペイの原則
「ノーワークノーペイの原則」とは、働いたら賃金を支払い、働かなかったら賃金は支払わないという給与計算の基本原則です。遅刻早退控除は、ノーワークノーペイの原則が根拠となっています。従業員が労働しなかった場合、企業はその時間分の給与を控除することが認められています。
たとえば、終業時間が18時の企業において、17時に退社したら1時間分は労働が提供されなかったとして控除の対象です。始業時間が9時の企業で9時15分に出勤すれば、15分が控除の対象です。
遅刻早退控除を上手に運用する3つのコツ
企業が遅刻早退控除を上手に運用する3つのコツを紹介します。
就業規則に早退や遅刻の基準を明記する
早退や遅刻、欠勤の基準やそれに伴う対応は労働基準法で定められていないため、ルールは企業ごとに設定する必要があります。早退・遅刻の定義や、早退・遅刻が発生した場合の連絡手段、連絡先まで明確化しておくといいでしょう。
たとえば「始業時刻を5分すぎた時点で遅刻とみなす」「早退や遅刻はメールで直属の上司へ連絡する(チャットでの報告は認めない)」「遅刻早退届の提出を義務とする」といった内容を規定します。具体的に明記することで混乱を防ぎ、従業員とのトラブルも回避できるでしょう。
遅刻早退控除の計算方法を定める
早退控除も遅刻控除も、計算方法は労働基準法で定められていません。控除の対応をする場合には、控除額をどのように計算するかまで企業ごとに決める必要があります。一般的には、早退・遅刻の場合は1時間あたりの基礎賃金に、早退や遅刻をした分の時間数を掛け合わせて算出します。欠勤の場合は、月給を所定労働日数で割って出した1日あたりの賃金を欠勤日数分控除しましょう。
| 控除の種類 | 計算式 |
|---|---|
| 遅刻早退 | 1時間あたりの基礎賃金×遅刻早退した時間数 |
| 欠勤 | 月給÷所定労働日数×欠勤日数 |
独自のルールを設けて減算や加算を行うことも可能ですが、必ず1分単位で処理しましょう。
従業員に対してきちんと周知する
遅刻早退控除のルールを設定し、就業規則に明記をしたら従業員全員へ周知しましょう。内容が更新された場合も必ず周知し、どのような内容のルールなのか説明する必要があります。周知を徹底することで、就業規則に則った給与控除の処理が可能になります。
また、説明後に質疑応答の時間を設けたり、同意を得てから運用したりすることで、従業員とのトラブル防止にもつながるでしょう。
遅刻早退控除の6つのルール
遅刻早退控除には、抑えておくべきルールが主に6つあります。
控除は1分単位で計算する
控除は、早退・遅刻・欠勤があった時間分だけ行うことが前提であり、労働が提供された時間分は賃金を全額支払う必要があります。当たり前のことですが、不就労の時間以上に賃金を控除するのは認められず、1分単位で計算するのが義務です。
もし15分や30分単位で切り上げて計算してしまった場合は、労働基準法第24条と第37条の違反に該当し、罰金や罰則が科せられる可能性もあります。
たとえば、18時が終業時間の会社で17時39分に退勤して早退した場合、働かなかった21分に相当する給与のみを控除する必要があります。この場合に17時30分で退勤したとして30分に相当する給与を控除してしまうのは、労働基準法に反するため注意しましょう。
減給による制裁は控除とは別の対処として考える
控除と似た対応に「減給」がありますが、別の処理として考えるべきです。控除は、労働しなかった時間分の賃金を給与から差し引くことであり、減給は従業員の勤務態度に問題がある場合の懲戒処分のひとつです。また、減給の制裁を行う場合は、以下の点を遵守する必要があります。
- 1回の減給額は1日の平均賃金の半額以下にする
- 減給額は一賃金支払期における賃金総額の10%以下にする
- 就業規則に懲戒規定を設けて周知する
控除が企業ごとにルールを定める一方で、減給は労働基準法によって規定が定められているため、対処方法を混同しないように注意しましょう。
早退・遅刻と残業は相殺できない
早退や遅刻による不就労の時間と、残業による所定労働時間以上の労働時間がある場合、相殺できないかと考える人もいるでしょう。しかし、早退や遅刻は控除として計算し、残業は割増賃金を上乗せして賃金計算する必要があるため、原則は相殺できません。
同日内であれば、遅刻と残業を相殺することも可能です。たとえば、同日内であれば、30分遅刻した日の終業時刻後に30分働いてもらっても、所定労働時間に足りない分を補ったに過ぎません。ただし、基本的には別々に処理する必要があると覚えておきましょう。
早退・遅刻を有給扱いすることはできない
有給休暇は労働者の権利であり、早退や遅刻をした際に有給消化としての処理ができません。「早退や遅刻を3回したら欠勤1日とカウント」することにより、その欠勤日を有休消化に充てるといった対応はできないことになっています。
また、有給休暇は早退や遅刻の回数によって減るものではなく、雇用されてから半年が経過していて、出勤率が8割以上であれば付与される休日です。早退や遅刻が多い従業員へ制裁を与えるのであれば、給与査定の項目として、早退や遅刻の回数を追加するようにしましょう。
控除対象となるのは原則基本給のみ
従業員によっては、基本給以外に「役職手当」や「資格手当」「扶養手当」などが支給されている場合もあります。しかし、遅刻早退控除の対象は基本給のみで、諸手当は計算に入れないのが原則です。ただし、諸手当を控除対象に含むことをルールとして就業規則に記載して、従業員に周知していれば、諸手当も含めて計算します。企業によって諸手当を含めるかどうかは異なるため、就業規則を確認したうえで控除の計算を行うようにしましょう。
控除が適用されない給与体系がある
以下のような給与体系の場合、給与の決め方が特殊なため、控除が適用されないことがあります。
- 完全月給制
- 年俸制
- 歩合制
- フレックスタイム制
「完全月給制」や「年俸制」では、あらかじめ一定の給与金額が定められているため、早退や遅刻による給与控除ができません。「歩合制」の場合は、歩合給の部分が成果や売上によって給与が算出されるため、控除の対象外となります。また「フレックスタイム制」では、総労働時間が規定を満たしていればいいため、早退や遅刻という概念がありません。
自社の給与体系を確認し、遅刻早退控除のルールを定めるようにしましょう。また、特殊な給与体系だと従業員自身も早退や遅刻による対処について理解できていない場合もあるため、きちんと説明することも重要です。
遅刻早退控除の計算方法
遅刻早退控除の計算方法について、具体例とあわせて詳しく解説します。
遅刻早退控除の計算式
「遅刻早退控除額」の計算式は以下のとおりです。
「月の給与額」とは1ヶ月間に支払う給与額のことであり、原則は基本給のみで、諸手当を含める場合は就業規則への明記と従業員への周知が必要です。
遅刻早退控除の具体例
以下の条件下の従業員における遅刻早退控除の計算方法を紹介します。
- 月給:30万円
- 役職手当:5万円
- 平均所定労働時間:160時間
- 早退・遅刻の合計時間:10時間
他に手当や控除対象がなければ、従業員の手取り金額は「350,000円-18,750円=331,250円」となります。
もし、就業規則に諸手当も含めることを明記している場合、計算式は以下のとおりです。
諸手当を含むほうが控除額は増えることがわかります。従業員の手取り金額は「350,000円-21,875円=328,125円」となり、結果的に手取り金額は少なくなるため、諸手当を含む場合は注意が必要です。
仕事における早退・遅刻・欠勤に関するよくある質問
最後に、仕事における早退・遅刻・欠勤に関するよくある質問を3つ紹介します。
早退を欠勤扱いにしたら違法になる?
ノーワークノーペイの原則や労働基準法を考慮すると、早退や遅刻を欠勤扱いにすると違法行為とみなされることがあります。たとえば、10分の早退を3回繰り返した場合、欠勤扱いにするのではなく、合計時間である45分を給与控除するのが原則です。早退や遅刻は欠勤扱いにはせず、時間分の控除として対処しましょう。
早退しても給料は減らない?
終業時間よりも早い時間で退勤し、早退をした場合は、不就労時間分の賃金を給与から差し引く処理を行います。たとえば、1時間早退した場合は1時間分の賃金が控除され、手取り金額は減ります。ただし、働かなかった時間は1分単位で計算する必要があり、従業員が働いた分の時間は賃金として支払うのが義務です。
会社で早退するのは何回まで許される?
会社における早退の許容回数は、企業ごとの就業規則や慣習によって異なります。一般的には、2回以上の早退や遅刻から懲戒処分対象となり、厳しい処分も認められます。会社として対象の従業員に対して注意や指導をしても改善されない場合は、懲戒処分も検討するといいでしょう。
早退は欠勤扱いにはならない!正しい対応方法で賃金を計算しよう
早退は欠勤扱いにはなりません。ノーワークノーペイの原則により、働いた時間分の賃金を支払い、働かなかった時間分の賃金は支払わないという決まりがあるためです。控除は早退や遅刻をした時間を1分単位で計算し、正しい給与額を支払えるようにしましょう。
また、控除対象となるのは原則基本給のみであり、早退や遅刻を有給扱いにはできません。ただし、就業規則に記載すればイレギュラーの対応が可能になるため、給与計算をする前に、自社の就業規則をきちんと把握しておくことも重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
副業・兼業してる人必見!…社労士がその留意点を解説
副業・兼業の現状 実態はいかに? 副業・兼業(以下「副業等」)を希望する人は年々増加傾向にあります。副業等を行う理由は、自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、資格の活用、十分…
詳しくみる【無料テンプレ付き】運転日報とは?書き方や保管期間を解説
運転日報は、配送などで車両を活用する物流系企業やさまざまな業種の営業などで社有車を保有している企業においては欠かせないものです。では、なぜ運転日報を記録する必要があるのでしょうか。…
詳しくみる派遣社員の勤怠管理の方法は?派遣先・派遣元の法律上の義務や責任なども解説
派遣社員の勤怠管理は、法律上の義務や給与計算、職場トラブル防止など、企業が必ず押さえるべき重要な業務です。しかし、派遣元と派遣先の役割分担が曖昧になりやすく、トラブルやミスも起きや…
詳しくみる労働基準法で定められている休憩時間は?15分ずつなどの分割は可能?
労働条件の最低基準を定めた労働基準法には、休憩についても定められています。 事業主は6時間を超える労働に対し45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません…
詳しくみるみなし労働時間制とは?メリット・デメリットや残業代、違法性もわかりやすく解説
みなし労働時間制という言葉を聞いたことがあっても、詳しい内容までは知らないという方は多いかもしれません。 この制度は、外回り営業や在宅勤務のように、会社が従業員の正確な労働時間を把…
詳しくみる【社労士監修】出勤率8割の計算方法|満たない場合の有給休暇は?日数の数え方や例外を解説
有給休暇の取得には「出勤率8割以上」という条件があるため、8割に満たない場合は付与されないのでしょうか。育児や介護などで休んだ日は出勤日数に含まれるのでしょうか。この記事では、有給…
詳しくみる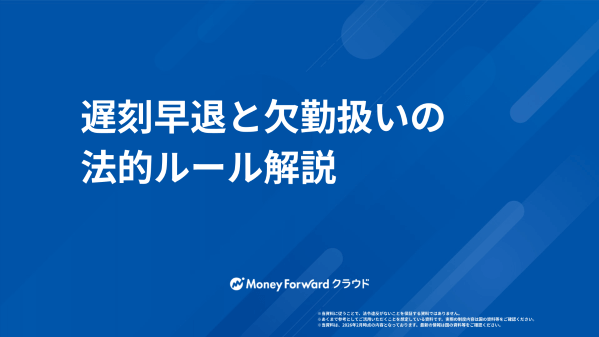


-e1762262472268.jpg)
-e1762262460348.jpg)