- 更新日 : 2025年11月13日
たまに自転車の場合、通勤手当はどうなる?基本ルールやリスクを紹介
たまに自転車通勤する場合、申請しないと不正受給とみなされたり、労災保険が適用されなかったりするリスクがあります。
会社は、通勤手当の税制上のルールや労災保険について理解しておくことが大切です。
本記事では、従業員がたまに自転車通勤をする場合に通勤手当の会社が取るべき対応やリスクについて解説します。
目次
たまに自転車通勤する場合、通勤手当はどうなる?
普段は電車やバスで通勤していても、天候や気分によって自転車通勤をする従業員もいます。たまに自転車通勤する場合の通勤手当について、会社のルールと手続きを確認しましょう。
会社の就業規則による
通勤手当の支給条件は、会社の就業規則に従います。また、自転車通勤を認めるかどうかも、会社ごとに異なります。多くの会社では、事前に届け出を行えば自転車通勤が可能です。
しかし、規則に違反して無断で通勤手段を変えた場合、手当の支給に影響が出ることがあります。たとえば、定期券代として通勤手当を受け取っている従業員が、実際には自転車で通勤している場合、不正受給と判断される可能性があります。
就業規則には通勤手当の支給方法や金額についてのルールを記載し、規則に従うよう周知しましょう。
通勤手当の決め方
通勤手当の金額は、通勤距離や手段によって決まります。自転車通勤の場合は、通勤距離に応じた手当を支給する方法が一般的です。
たとえば、片道5kmの通勤距離に対して1kmあたり100円を支給したり、5kmまでは月額2,000円と定めたりします。会社によっては2km未満の場合、手当を支給しない場合もあります。
自転車通勤を希望する従業員には、手当の支給条件を明確に伝え、適切な手続きを案内することが重要です。
関連記事:労働基準法による通勤手当の決め方?距離の測り方や支給金額を解説
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
エンゲージメント向上につながる福利厚生16選
多くの企業で優秀な人材の確保と定着が課題となっており、福利厚生の見直しを図るケースが増えてきています。
本資料では、福利厚生の基礎知識に加え、従業員のエンゲージメント向上に役立つユニークな福利厚生を紹介します。
令和に選ばれる福利厚生とは
本資料では、令和に選ばれている福利厚生制度とその理由を解説しております。
今1番選ばれている福利厚生制度が知りたいという方は必見です!
福利厚生 就業規則 記載例(一般的な就業規則付き)
福利厚生に関する就業規則の記載例資料です。 本資料には、一般的な就業規則も付属しております。
ダウンロード後、貴社の就業規則作成や見直しの参考としてご活用ください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
自転車通勤を認める場合のポイント
自転車通勤を導入する際は、安全面やルールの整備が欠かせません。明確な規則を定めることで、従業員が安心して通勤できる環境を整えられます。
本章では、自転車通勤を認める場合のポイントを解説します。
関連記事:通勤とは?定義や交通費の計算方法
自転車通勤規則を作成する
自転車通勤を認める場合、事前にルールを作成することが大切です。従業員の安全を守るため、具体的な条件を決めましょう。
自転車通勤規則には、自転車の整備状態や保険加入の義務などを記載するのが一般的です。たとえば、多くの企業では、自転車通勤者に対して自転車保険の加入を義務付けています。また、ヘルメットの着用を義務付けることで、事故時のリスクを軽減できます。
さらに、自転車通勤規則を作成する際には、各都道府県の自転車に関する条例も確認し、違反がないように注意が必要です。
自転車通勤を導入する際は、ルールを明確に定め、従業員に周知することが大切です。
ルール違反のペナルティを定める
ルールを守らない場合の対応も、事前に決めておく必要があります。
とくに、安全に関わる違反には厳しく対処しましょう。自転車保険に未加入だったり、ヘルメットを着用しなかったりするケースは、安全に直結するため注意が必要です。
違反があった際には、まずは口頭で注意を行い、改善されない場合は書面で警告を行うことが一般的です。重大な違反が続く場合は、自転車通勤を禁止することも検討します。ただし、過度に厳しいペナルティは避け、安全確保のために適切な対応を決めることが大切です。
通勤経路を確認する
自転車通勤を認める場合、事故発生時の対応や通勤災害の適用範囲を明確にするため、従業員の通勤経路の確認が必要です。
労災保険では、合理的な通勤経路を利用している場合、通勤中の事故が「通勤災害」として認められます。しかし、途中で買い物など私用のために経路を外れた場合は適用されません。
自転車通勤を申請する際に、自宅から職場までの経路を届け出るルールを設けるとよいでしょう。地図上で実際の通勤経路を確認し、安全な経路であることを確認することが大切です。また、季節や天候による経路変更の可能性も考慮に入れておくとよいでしょう。
通勤手当の基本ルール
通勤手当は、法律で決まっているわけではなく、それぞれの会社が独自のルールを定めています。通勤手当の仕組みを理解し、適切な対応を行いましょう。
通勤手当の支給は会社の義務ではない
通勤手当は、法律で支給が義務付けられているわけではありません。支給するかどうかは会社によって異なりますが、通勤手当を支給する会社が一般的です。
支給の条件や金額は、定期代を全額支給する会社もあれば、距離に応じて上限を設ける会社などさまざまです。従業員に適切な周知を行うため、社内規定を明確にしておきましょう。
また、正社員だけでなく契約社員やアルバイトにも通勤手当を支給するかどうか、社内でルールを統一し、従業員にわかりやすく伝えることが大切です。
通勤手当は非課税になる
通勤手当は、一定の金額まで所得税がかかりません。従業員にとって、給与として受け取るよりも通勤手当を支給されたほうが税金面でのメリットがあります。
自転車通勤の場合、通勤距離に応じて国税庁が定めた非課税限度額があります。たとえば、通勤距離が2km以上10km未満なら月額4,200円まで、10km以上15km未満なら月額7,100円まで非課税となり、これらの金額を超えた分は課税対象です。
また、マイカー通勤の場合もガソリン代の補助が認められることがありますが、非課税対象となる範囲には上限があるため注意が必要です。会社は従業員の通勤距離を正確に把握し、適切な金額で通勤手当を支給しましょう。
参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
関連記事:交通費は社会保険の課税対象に含まれる?
代替交通手段への対応
天候や出勤時間の都合で、普段と異なる交通手段を使う場合があります。雨の日に自転車からバスに変更したり、混雑を避けるために電車から自転車に切り替えたりするケースです。
会社によって、代替交通手段の費用を別途支給したり、通勤手当の計算方法を変更したりと、対応はさまざまです。事前申請を条件にしている場合や、定期代ではなく出社した日数分だけ交通費を支給する方式を採用する企業もあります。働き方の多様化に対応するため、柔軟な制度を導入することも検討しましょう。
従業員が安心して通勤できるよう、代替した場合の交通費支給や申請手続きについて明確に定めておくことが重要です。
たまに自転車通勤することで発生するリスク
普段と異なる通勤手段を利用すると、会社の規則に違反したり、予期せぬ問題が発生したりする可能性があります。とくに、申請なしの自転車通勤では、交通費の不正受給や労災保険の対象外となるリスクがあります。
また、未申請の交通手段を利用することで、万が一の事故発生時に会社の対応が遅れる可能性もあるでしょう。とくに、勤務中の急な外出や直行直帰の場合、通常の通勤ルートとは異なる移動が発生しやすいため、事前の申請ルールを明確に定めることが重要です。
交通費の不正受給とみなされる可能性がある
会社に届け出た通勤手段と異なる方法で通勤する場合、交通費を不正に受け取っていると判断される場合があります。たとえば、電車通勤の申請をして定期代を支給されているにもかかわらず、毎日自転車で通勤する場合があげられます。
不正受給を防ぐには、通勤手段の変更時の申請方法を明確に定め、就業規則に懲戒処分の規定を設けるとよいでしょう。また、通勤手当の支給を管理するために、申請内容と実際の通勤方法が一致しているかを確認する必要があります。
通勤費の管理には、ICカードの履歴確認や、GPSを活用した出退勤管理システムを導入する企業もあります。適切な通勤手当を支給するには、異なる通勤手段を利用する場合の申請ルールを決め、従業員に周知することが大切です。
労災が適用されない可能性がある
申請した通勤経路と異なるルートを通ると、事故に遭った場合、労災保険が適用されないことがあります。労災保険では、通常の通勤経路を正しく利用していれば、通勤中の事故が補償されます。
会社は申請された通勤経路を把握し、実際の通勤方法と合っているか確認することが大切です。電車通勤を申請している従業員が、自転車で通勤して事故に遭った場合、届出経路を逸脱したと判断され、労災が適用されないケースがあります。また、直行直帰の場合、通常の通勤ルートとは異なる移動が発生しやすいため、事前の申請ルールを明確に定めることが重要です。
万が一の事故に備え、会社は従業員の通勤方法を事前に把握し、適切なルールを定めておくことが必要です。
自転車で通勤する場合のよくある質問
自転車通勤に関してのよくある質問に回答します。
電車で通うための通勤手当を受けながら自転車通勤は可能ですか?
会社に届け出た通勤手段と異なる方法で通勤すると、通勤手当の不正受給とみなされる可能性があります。会社の規定によっては、手当の返還や懲戒処分が必要になるケースもあります。
事前に会社で規則を定め、全従業員に周知することが大切です。
自転車と電車を併用する場合の通勤手当はどうなりますか?
自転車と電車を併用する場合、多くの会社では両方の交通費を合算して通勤手当を計算します。
一般的には、自転車で駅まで移動する距離に応じた手当と、電車の運賃を合算して支給されます。ただし、会社によってはどちらか一方の費用しか支給されないこともあるでしょう。
自転車と電車両方の交通費を支給する場合は、通勤手当には非課税限度額があるため、上限にも注意してください。
自転車で2km未満の場合、通勤手当はいくらですか?
片道2km未満の自転車通勤では、支給されても課税対象になります。そのため、2km未満の通勤の場合、通勤手当が支給されないケースがあります。
たとえば、片道1.5kmの自転車通勤の場合、手当を支給する会社もありますが、その場合は給与と同じ扱いになり、所得税が課されるのです。従業員にとっては手当を受け取るメリットが少なくなる可能性があるため、注意が必要です。
たまに自転車通勤する場合はまずは会社の規則を確認しよう
会社が把握せずに通勤手段を変更すると、不正受給とみなされたり、事故に遭った際に労災保険が適用されなかったりするリスクがあります。
また、通勤手段の申請や通勤手当の支給条件は会社ごとに異なり、対応もさまざまです。
従業員の安全を守り、適切な手続きを行うために、会社は就業規則や通勤手当のルールを明確に定めることが大切です。また、従業員への周知も徹底しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
給与所得控除とは?所得控除との違いや計算方法をわかりやすく解説
給与所得控除とは、会社員や公務員などの給与所得者が、収入を得るために必要な経費を概算で差し引く制度のことです。所得税の計算において、年収からこの控除を差し引くことで所得が確定し、最…
詳しくみる給与計算の業務フローは?毎月の流れから年間スケジュールまで徹底解説
給与計算とは、従業員の勤怠情報に基づき、基本給や各種手当、控除額を正確に算出して給与額を確定し、支払うまでの一連の流れを指します。給与計算の業務フローでは、労働基準法や税法などの専…
詳しくみる給与明細とは?記載項目から計算式、発行の注意点までわかりやすく解説
毎月の給与支給日に従業員へ渡す「給与明細書(給与明細)」。 ルーチン業務として発行している方も多いと思いますが、「法律上の発行義務はあるのか」「Web明細にする際のルールは?」とい…
詳しくみる賞与明細とは?無料テンプレート・作成方法|決算賞与明細とは?
一般的に賞与(ボーナス)は、年2回、夏と冬に支給され、毎月の給与明細とは別に賞与明細が発行されます。なかには普段から「給与明細はほとんど見ない。振込額を確認するだけ」という人も少な…
詳しくみる60歳以降の再雇用、給与の目安は?決め方や下がる理由、違法となる場合を解説
60歳以降も働き続ける再雇用制度を利用する方が増えていますが、多くの人が気にするのは、再雇用後の給与ではないでしょうか。定年前よりも減額されることが一般的ですが、どのくらい下がるの…
詳しくみる給与計算の認定試験「給与計算実務能力検定試験」とは?難易度や勉強方法などを解説
給与計算の実務スキルを客観的に証明したいと考えたとき、多くの実務者が目標とするのが「給与計算実務能力検定試験」です。この資格は、給与計算の専門知識と実務能力を社会的な基準で証明する…
詳しくみる
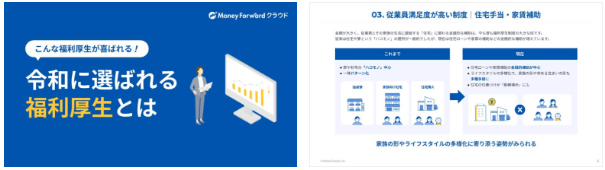
.jpg)
