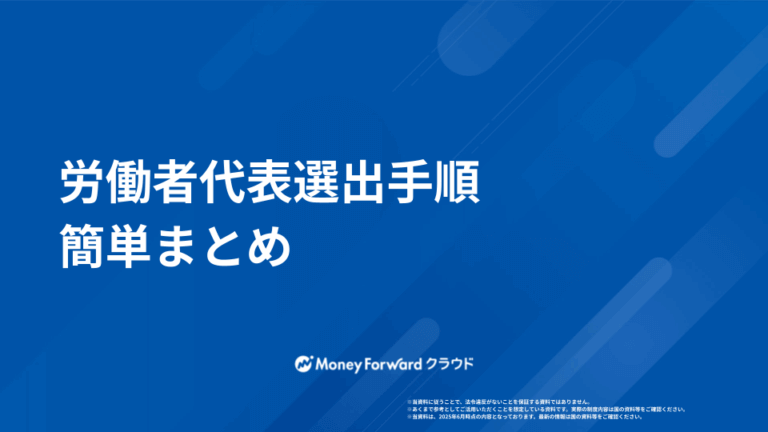- 更新日 : 2025年11月19日
労働者代表とは?選出方法や任期、注意点についても徹底解説
労働者代表とは、企業内で労働者を代表し、意見をまとめる役割がある人物です。選出方法や任期は法律で定められていないものの、適切な選出が求められます。選出や任期の設定にあたっては、ルールや注意点についての理解が重要です。
本記事では、選出方法や任期、注意点などをわかりやすく解説します。
目次
労働者代表は36協定における労働者の代表者のこと
労働者代表とは、事業場に在籍する労働者の過半数を代表する者です。とくに、労働組合がない場合、労働者代表が労働者の意見を集約し、36協定の協議に参加する重要な役割があります。
なお、36協定は法定労働時間の1日8時間、週40時間を超える時間外労働や休日労働を実施する際に、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者代表と企業が締結する協定です。
そのため、労働組合がない企業では、労働者から適切な方法で代表者を選ぶ必要があります。
36協定については、以下の記事をあわせてご覧ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項
労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。
本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド
雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。
本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。
労働者代表と労働組合の違い
労働者代表は、事業場の労働者過半数を代表する労働者個人で、労働者の意見をまとめて提言する者です。
一方、労働組合は組合員により構成されている団体であり、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」が認められ、会社と対等に交渉できます。各権利の意味合いは以下のとおりです。
- 団結権:労働者と使用者が対等な立場で話し合うために、労働組合を作る、または加入する権利
- 団体交渉権:労働組合が使用者と労働条件を交渉し、文書により約束を交わせる権利
- 団体行動権:労働条件改善のため、仕事をせずに団体で抗議する権利(ストライキ権)
なお、必ずしも事業場の労働者全員が組合に加入しているわけではなく、加入状況により交渉力が変動する点でも異なります。
労働組合については、以下の記事をご覧ください。
労働組合とは?概要やメリット、存在しない場合の作り方について解説!
労働者代表の任期は定められていない
労働者代表の任期については、法律上とくに定めがありません。実務上、36協定の有効期間が1年であることから、任期を1年とするケースが多い傾向にあります。
しかし、社内規定が整備されていない場合は、案件ごとに過半数代表を選出し、状況に応じた柔軟な対応が必要です。
労働者代表には、法律で決められた任期の制限はありません。そのため、代表の選出方法や任期についても、労働者の意見を踏まえたうえで決めることが重要です。誰が代表になるかは、労働者自身が自主的に決めるべきであり、適切な方法で選出する必要があります。
そのため、任期を労働者側で定めても問題ありません。
労働者代表の役割
労働者代表は、事業場で働く労働者の意見をまとめ、企業との労使協定締結時に労働者側の立場を代弁する重要な役割があります。
具体的には、36協定を締結する際の正式な協定文書の作成に関与したり、就業規則の制定・変更に関する意見をまとめたりするなどです。
また、衛生委員会や安全委員会への委員推薦など、職場環境の改善や労働条件の向上にも貢献します。
労働者代表がその役割を果たすことにより、労働者の権利保護と円滑な労使関係の構築を促進することが期待できます。
労働者代表を選出する3つの要件
労働者代表は、誰でもなれるわけではありません。労働基準法および労働基準法施行規則では、36協定の労働者代表の選出要件として条件が設けられています。以下では、労働者代表を選出する際の3つの要件をそれぞれ紹介します。
1. 労働者の過半数の代表である
労働者代表の選出要件のひとつは、企業で働くすべての労働者の過半数を代表する人物であることです。正社員だけでなく、パートや契約社員などあらゆる雇用形態の労働者が対象となり、労働者の支持により選出される必要があります。派遣社員は雇用元が派遣会社であるため、労働者代表にはなれないので注意しましょう。
選出方法は、挙手や投票、または話し合いなどの民主的な手続きにより行われ、労働者全体の支持が明確に示されることが求められます。
2. 管理監督者でない
労働基準法第41条により、労働者代表は管理監督者または管理の地位にない者でなければいけないと定められています。
管理監督者は、経営者に近い立場で人事や労働条件の決定権を持っており、法定の労働時間や休日の規定が適用されません。
36協定は、企業と労働者が対等な立場で締結する協定です。そのため、使用者に近い管理監督者が代表に選ばれると、公正な交渉ができず、結果として締結された協定自体が無効になる可能性があります。
したがって、労働者代表は管理監督者でない者から選出しましょう。
管理監督者の詳しい情報は、以下の記事をご覧ください。
管理監督者とは?労働基準法における定義やトラブル、取り扱いについて解説!
3. 使用者の意向により選出された人物でない
労働者代表の要件は、使用者の意向により選出された人物でないことです。
労働者代表は、労使協定締結において労働者側の意見を代表する重要な存在ですが、選出方法は必ず民主的な手続きに基づいて行われなければなりません。
企業の代表者が自ら労働者代表を指名して使用者の意向により選出された場合、手続きは不適正となり、締結された協定自体が無効になる可能性があります。
労働基準法施行規則第6条では、労働者代表の選出方法として民主的な手段(挙手や投票など)で選ばれるべきと定められています。そのため、労働者代表を選出する際は、法律を遵守しましょう。
労働者代表を選出するべきシーン
企業が労働者の意見を正式に反映させるためには、労働者代表の選出が重要です。具体的にどのような場面で労働者代表を選出すべきかは、事前に確認しておく必要があります。以下では、労働者代表を選出するべきシーンについて解説します。
36協定を締結するとき
36協定を締結するときは、労働者代表を選出する必要があります。
36協定は、法定の1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働を行わせる場合に締結が必要な協定です。36協定を締結する際、労働者側の意思を十分に反映させるために、信頼できる労働者代表の選出が不可欠です。
労働者代表は、企業と労働者間の合意を円滑にし、法定労働時間を超える労働に関する適正な手続きと労働条件の維持に寄与します。
就業規則について意見を聞くとき
就業規則の作成や改訂時には、できるだけ労働者全体の意見を反映させることが望ましいため、労働者代表の選出が必要です。ただし、企業は聴取した意見に必ずしも従う義務はなく、あくまで意見を聞くことが義務付けられています。
また、労働者代表の意見を聞くことは、労働者代表による意見集約の際に労働者が自らの権利や労働環境について理解を深める貴重な機会となり、結果的に職場全体の信頼関係の向上やトラブル防止につながります。
企業側は、労働者代表とのコミュニケーションを重ねながら、労働者の不満がない、もしくは最小限となる就業規則を作成しましょう。
寄宿舎規則を作成または変更するとき
寄宿舎規則の作成や変更にも、労働者代表の意見が必要です。
寄宿舎規則は、労働者が宿泊する寄宿舎内での生活の秩序と自治を守るための重要なルールです。新たに規則を定めたり変更したりする際、労働者の過半数を代表する者の同意が必須となります。
具体的には、起床・就寝時間、外出や外泊のルール、さらに食事に関する事項などが挙げられ、適切な同意書を取得し、所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。
労働者代表が労働者の意見を述べることにより、寄宿舎における労働者の私生活の自由を尊重し、健全な共同生活環境を整えられるでしょう。
労働代表者の選出方法と流れ
労働者代表を選出する際は、まず労働者に選出の必要性を伝え、適切に選出プロセスを説明することが重要です。
その後、選出方法としては挙手や投票、回覧などが用いられます。挙手の場合、全員が集まった場で支持を表明し、候補者を決めます。回覧により、労働者代表選出の目的を記載した文書に署名を求め、同意を得ることも可能です。
立候補者や推薦者を募る際は、一定の期限を設け、後に投票により最終候補を決定します。選出結果は記録として保管し、必要に応じて企業へ提出します。
上記の方法で、労働者の意見を公平に反映しながら労働者代表を選出可能です。
労働者代表の選任における企業の義務
企業は、労働基準法や労使協定の締結に関する規定に基づき、適正な方法で労働者代表を選出する義務があります。以下では、労働者代表を選出する際に企業が遵守すべきことについて解説します。
労働者代表だからといって不利益な扱いをしてはいけない
労働者代表の選任に際して、企業は立場を理由に不利益な取り扱いをしてはいけません。
たとえば、代表であることを根拠に解雇や降格、減給などの不利益な処遇を行うことは、労働基準法や労働契約法に反します。代表者は、職務上の責任や重圧を感じることがあり、場合によっては業務遂行に支障をきたす可能性があります。
そのため、企業は労働者代表が安心して意見を述べられる環境作りに努め、不利益が生じないよう、適切な管理と配慮が必要です。
労働者代表が業務をスムーズに進められるようにする
企業は、労働者代表が業務をスムーズに進められるよう配慮する義務があります。
まず、使用者は労働者代表が円滑に作業できる環境を準備しましょう。具体的には、労働者の意見をまとめやすい情報共有のシステムを提供したり、ミーティングや事務作業が行えるスペースを確保したりします。
また、代表者がサポートを求めた際には、企業は柔軟に対応し、必要な支援を提供することが重要です。労働者代表のサポートを徹底することにより、代表者が効率的に業務を進め、労使間の円滑なコミュニケーションを確保することが期待できます。
労働者代表を選出する際の注意点
労働者代表の選出は、公正かつ適切に行うことが重要です。不適切な方法で選ばれると、後の労使関係に影響を及ぼす可能性があります。選出の際は、法的要件を満たし、労働者全体の意思を反映させることが大切です。
以下では、労働者代表を選出する際の各注意点について解説します。
事業場ごとに決める
労働者代表は、事業場ごとに選出するようにしましょう。事業場とはひとつの事業を行う場所であり、同一の場所にある複数の事業場は、それぞれが独立した事業でなければひとつの事業場とされます。
36協定は、原則として支店や工場などの事業場ごとに締結する必要があります。そのため、労働者代表も同様に事業場ごとの選定が必要です。しかし、規模が小さく、事業場として独立性がない場合、上位組織に含めても問題ありません。
なお、労働環境が異なる場合や上位組織に含めることで労働基準法の運用に支障をきたす場合は、同一事業場でも別事業場として扱われます。たとえば、企業内の診療所や食堂などが該当します。
就業規則の作成や変更時には、各事業場の労働者代表の意見を聴取することが法律で義務付けられており、労使間の適切な対話を通して職場環境の改善や労働条件の整備が可能です。
労働者の声が十分に反映されるように、事業場ごとに労働者代表を選出しましょう。
労働者代表の選出の際の記録を残す
労働者代表を選出する際は、選出日や選出方法、選出結果などを詳細に記録する必要があります。さらに、選出した会議の議事録や回覧・署名した文書を必要に応じて企業に提出する場合もあります。
作成の際は、議事録には労働条件も明記する必要があり、とくに「管理監督者ではない」ことを証明するため、労働者代表の当日以前の職務内容を記録に含めることが重要です。選出の過程を適切に記録しておくことで、誤解や事後のトラブルを防ぎ、透明で公正な選出プロセスを保証できます。
また、議事録は労働者全員に共有することで、労使間の信頼関係を確保します。
不適切な選出は労使協定が無効になる可能性がある
労働者代表の選出が不適切である場合、労使協定が無効になる可能性があります。
企業の意向により代表者が選出されたり、代表者が管理監督者に該当したりする場合は、法的な要件を満たさないため労使協定は無効です。
もし無効と判定されてしまうと、36協定に基づく時間外労働が違法となり、労働基準法に定める罰則が科される可能性があります。さらに、悪質な場合には刑事罰が科されることもあり、企業にとって大きなリスクとなります。
労働者代表は、労使協定締結において労働者の意見を反映するために、労働者の支持により選出し、記録も詳細に残しておきましょう。
社員にお願いして選んではいけない
労働者代表の選出は、社員に個別でお願いして選ぶことは認められません。労働者代表は全労働者の意向によって選出されなければならないため、使用者は代表の選出に介入してはならず、労働者に委ねる必要があります。
もし、社員に個人的にお願いして労働者代表を決めた場合、選出は無効になる可能性があります。
選出の過程で残業を強いると違法な対応とみなされ、企業は労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されるリスクがあるため、十分に注意しなければいけません。
労働者代表になったら労働者代表選任届を提出する
労働者代表を選出した後は、「労働者代表選任届」を作成し、労働者に周知することが重要です。労働者代表選任届を企業に提出すること自体は義務ではありませんが、トラブル回避のためには作成・掲示などによる周知が重要です。
労働者代表について書面を作成・周知することで、誰が労働者代表として選出されたかを明確にし、労働者の理解を得られます。
とくに、労働基準法第36条に基づく「36協定」を締結する際には、労働者代表が適正に選出され、立場が明示されていることが求められます。
労働者代表選任届には、労働者代表の氏名、選任年月日、労務協定の内容などを記載し、適切な方法で社内に提示する、または労働者に配布することが望ましいです。
手続きを適切に行うことで、労働者代表の役割が明確になり、労働者の意思を正しく反映した協定の締結につながります。
労働者代表は適切な方法で選出しよう
労働者代表は、労働者全体の意見を取りまとめる重要な役割を担います。そのため、公正かつ透明性のある方法で選出することが不可欠です。選出手続きは十分労働者に周知し、労働者の信頼を得られる形で進めましょう。
適切に労働者代表を選出することで、労働者が安心して働ける職場環境の基盤を築けます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
入社前健康診断の義務とは?実施しないリスクや費用について解説
新しい従業員を迎えるにあたって、健康診断の義務や費用、どこで受けてもらうべきかなど、不安を感じていませんか? 本記事では、雇入時の健康診断について知っておくべき情報をご紹介します。…
詳しくみる【テンプレ&記入例あり】賞与査定表とは?評価基準や作成目的、主な項目をご紹介!
ボーナスは、会社の業績と個人の実績を総合的に判断し支給額を決定します。ボーナスの支給額を決める際、個人の実績を査定するのに用いられるのが賞与査定表です。査定項目は大きく分けて業務考…
詳しくみる賃貸を法人契約するメリット・デメリットを解説!流れや注意点も紹介
個人ではなく、会社名義で物件を借りるのが法人契約です。法人契約を適切に活用することで、会社の経営基盤を強化できます。 賃貸を法人契約することは、「家賃などを経費として計上できる」「…
詳しくみる新型うつ病とは?うつ病との違いやチェック方法、原因、対策方法
近年、従来のうつ病とは異なる新しいタイプの気分障害「新型うつ病」が注目されています。無気力や無為な日々が続き、社会から離れていく症状が特徴的で、若年層を中心に増加する傾向にあります…
詳しくみる派遣のメリット・デメリットは?働く側・企業側それぞれ解説
人材派遣サービスの利用は、労働者側・雇用側双方にメリットがあります。労働者側にとっては、アルバイトより高時給、サポート体制が整っているなどがメリットです。一方、雇用者側は短時間で人…
詳しくみる雇用契約書とは?法的な必要性や項目、作り方をひな形付きで紹介
雇用契約書とは、企業と労働者の合意を証明し、トラブルを防ぐための重要な書類です。2024年4月からは就業場所や業務の「変更の範囲」の明示が義務化されるなど、最新の法改正への対応が不…
詳しくみる