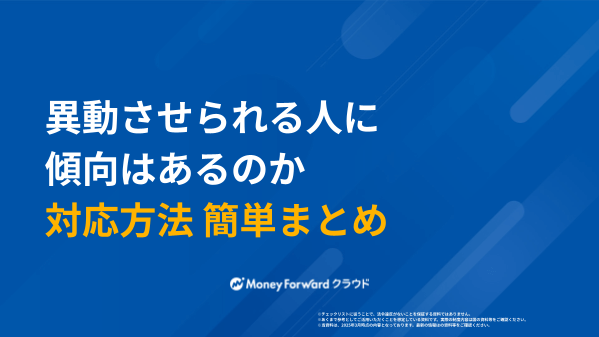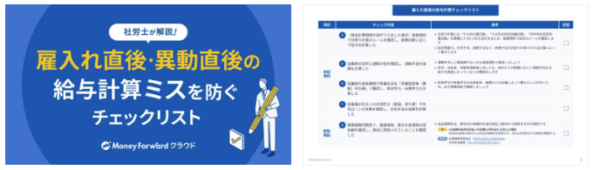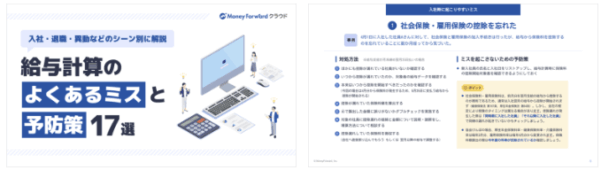- 更新日 : 2025年11月6日
異動させられる人の特徴は?人事異動のからくりを解説
人事異動が多く、なぜ自分だけ異動が多いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。仕事ができないから異動させられたのか、優秀だから抜擢されたのかなど、人事異動の目的を知ることで、今後のキャリアに役立てられます。この記事では、異動させられる人の特徴から、異動させたい部下がいる場合の対応まで、わかりやすく解説します。
人事異動の目的
企業では、さまざまな理由から人事異動が発令されます。ここでは、人事異動が企業や社員にとってどのような意味を持つのかを解説します。
組織全体を最適化するため
人事異動は、組織全体のバランスを考慮しながら行われます。
例えば、新規事業の立ち上げや既存部門の強化などに伴い、必要なスキルや経験を持つ社員を適切な場所に配置するケースがあります。また、部門ごとに必要な人数をコントロールし、人員の不足や過剰を是正する狙いもあります。
経営戦略やビジョンを実現するため
企業の経営戦略によっては、大胆な組織変更や配置転換が必要になり、人事異動が行われる場合もあります。
例えば、経営陣が掲げるビジョンを実現するために、プロジェクトに必要な人材を新規プロジェクトへの参画させるケースがあります。また、部署の改廃や統合により組織改革を推進し、スピード感ある経営を実現しようとするケースもあります。
社員の成長やキャリア形成のため
人事異動は、社員のキャリア形成にも影響を与えます。部署や業務内容が変わることで、自身のスキルや視野を大きく広げる可能性があるためです。
例えば、新しい環境に身を置くことで、今までとは異なる専門知識やスキルを習得できます。また、新たな部署での経験が、社内の課題解決やイノベーションに活かせる柔軟な思考をもたらします。
社員のモチベーション向上のため
人事異動は、社員のモチベーションを高める効果も期待できます。
同じ部署に長く在籍していると、人間関係のマンネリ化や固定観念が生じやすくなります。新しい環境でチャレンジする機会を与えることで、社員の挑戦意欲を喚起し、生産性向上に繋がるのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
雇入れ直後・異動直後の給与計算ミスを防ぐチェックリスト
給与計算にミスがあると、従業員からの信用を失うだけでなく、内容によっては労働基準法違反となる可能性もあります。
本資料では、雇入れ直後・異動直後に焦点を当て、給与計算時のチェックポイントをまとめました。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
この資料では、各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にまとめました。
【異動時も解説!】給与計算のよくあるミスと予防策17選
給与計算で起きやすいミスをシーン別にとりあげ、それぞれの対処方法を具体的なステップに分けて解説します。
ミスを事前に防ぐための予防策も紹介していますので、給与計算の業務フロー見直しにもご活用ください。
異動させられる人の特徴
このように、人事異動は企業の戦略や社員の成長を見据えて行われるのが一般的ですが、「仕事ができないと異動させられるのではないか」という不安を抱える方もいます。ここでは、ネガティブな意味で異動の対象になりやすい人の特徴を見ていきましょう。
企業や上司からの評価が低い社員
企業や上司からの評価が低いと、異動の対象になる場合があります。ただし、評価が低いと言っても、その背景や理由は様々です。例えば、目標を長期間達成できない、または業績への貢献が少ない社員は、今の部署では能力が十分に発揮できないと判断される場合があります。また、周囲とのコミュニケーションが上手くいかずトラブルを起こしたり、社内の人間関係を悪化させてしまう社員も、部署移動の候補になりやすいです。
スキルはあるが環境が合わない社員
仕事のスキルは高いのに、環境が合わずパフォーマンスを発揮できない社員もいます。例えば、配属された部署の業務内容が得意分野と大きく異なり、専門性を活かしきれない場合があります。また、チーム全体の価値観や働き方と大きなギャップがあると、優秀な人材でも成果が出しづらいでしょう。こうした場合に、企業が適性を見極めて、あえて別の部署や業務へ配置転換することがあります。
トラブルの原因となる社員
チームワークを重視する職場では、トラブルの原因になる社員を異動させることがあります。特に、意図的なルール違反や不正を起こすなど、倫理面で問題がある社員は、厳重注意や懲戒を前提とした異動が行われます。また、相手に配慮のない発言が多い、ミスを他責にするなど、周囲から敬遠されるような行動が見られる場合も要注意です。
仕事ができないと異動させられる?
上記の特徴に当てはまる場合、企業の判断で人事異動が検討されることがあります。とはいえ、人事異動は仕事ができない人を切り捨てるためだけに行われるわけではありません。企業としても、問題を抱える社員を異動させれば解決するほど単純な話ではないからです。
また、もし仕事ができないという理由で異動になったとしても、その後の働き方次第ではキャリアにプラスになる可能性も十分あります。部署が変わればメンバーや上司も変わるため、人間関係を一から構築するチャンスと捉え、積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。また、異なる分野の業務に携わることで、自分の強みの再発見できる可能性があります。
優秀でいい人ほどすぐ異動になる?
一方、社内で高く評価されている社員が別の部署へ異動するのを目にしたことはありませんか。ここでは、優秀がゆえに異動の対象になりやすい人の特徴を見ていきましょう。
企業や上司からの評価が高い社員
目標達成や業績向上に貢献する姿勢が際立ち、企業や上司からの評価が高い社員は、新たな部署や重要なプロジェクトへ抜擢されるケースがあります。また、会社として「困りごとを解決してくれるかもしれない」と期待し、立て直しが必要な部署のリーダーに選ばれるケースもあります。難しい部署に送り込むことで、本人にとっては一種の挑戦となり、さらに力を発揮するきっかけになるでしょう。
リーダー候補として期待される社員
将来のリーダー候補を育成するため、いろいろな部署で経験を積ませる場合があります。業務領域や業種が異なる部署を渡り歩くことで、社内全体の動きや課題を広い視点で理解できるようになるからです。また、組織横断的な課題解決力を習得することで、部門連携が必要な場面でもリーダーシップを発揮しやすくなり、経営視点も身につきます。
前向きにキャリアアップを目指す社員
「いい人ほどすぐ異動になる」と言われる背景には、本人の姿勢も関係しています。キャリアアップを念頭に置き、新たな仕事や環境を積極的に受け入れる人は、結果的に社内で評価されやすくなるのです。
異動先でもすぐにチームに溶け込み、成果を出す力が評価されると「また新たな場所で力を発揮してほしい」という話が舞い込むことがあります。また、本人が自ら異動を希望するケースもあり、前向きな挑戦意欲が高い人材ほど部署を移りやすい傾向があります。
異動しない人の特徴
同じ会社に長く勤めても、ずっと異動しない人が存在します。その背景にはどのような特徴や理由があるのでしょうか。
部署に欠かせない専門性を持つ社員
特定の知識やスキルが求められる部署では、人事異動が難しいケースがあります。特に、法務や研究開発、IT系の一部業務など、高度な技術や資格が必要な部署では、人事異動が少ない傾向にあります。また、長年培われた経験やノウハウが重要視され、新人や他部署の人では引き継ぎに相当な時間がかかると判断される場合も、人事異動が少ない傾向にあります。
組織文化や業務内容との相性がいい社員
組織文化や業務内容との相性が極めていい社員も、異動が少ない傾向にあります。上司やチームメンバーとのコミュニケーションが円滑であれば、会社としても配置換えの必要性を感じにくいものです。チームでの役割が明確で、安定した成果を出し続けている場合も、組織側からも異動の検討対象になりにくいです。また、チームをまとめるリーダー的存在として信頼されている場合は、組織の安定やモチベーション維持の観点から、あえて異動しない方向へ調整されることがあります。
自身の健康状態や家族の事情がある社員
自身の健康状態や家族の都合など、特別な理由がある場合は会社として配慮を行うことが多いです。例えば、介護を必要とする家族がいる場合など、単身赴任が困難な状況では、部署異動や転勤が難しいケースがあります。
異動させたい部下がいる場合の対応
異動させたい部下がいる場合は、問題解決のためだけでなく、本人のキャリアや組織全体のメリットを踏まえて判断することが肝心です。丁寧なコミュニケーションと適切なフォローアップを行うことで、当初の目的を果たすと同時に、社員の成長や会社の成果向上にもつなげやすくなります。ここでは、上司や企業が具体的にどのような対応をすべきかを解説します。
人事異動の理由を明確にする
人事異動の理由を、部下の問題行動やパフォーマンス不足とするのではなく、組織の視点と本人の成長機会を見据えて判断することが重要です。そのため、なぜ異動させたいのかという目的を明確にし、単なる左遷のように見えないよう注意する必要があります。また、仕事が上手くいかないのは本人の適性に合っていない可能性もあります。得意分野やキャリア希望をヒアリングし、新たな役割でポテンシャルを発揮できるかを検討することが大切です。さらに、残された部署の業務体制はどうなるのか、異動先の受け入れ準備は整っているかなど、実務面も考慮しましょう。
部下にしっかりと説明する
スムーズな人事異動を行うには、部下に丁寧かつ誠実な説明を行う必要があります。本人と面談を実施し、現状の課題や異動を検討する理由を正直に伝えることが重要です。納得感を持ってもらうためにも、一方的ではなく相手の話に耳を傾けましょう。また「どの部署で、どのような仕事をするのか」「これまでの経験をどう活かせるのか」などを具体的に説明し、今後のキャリア形成をイメージしやすくします。さらに、本人が希望するキャリアプランや得意分野をヒアリングし、折り合いをつけたうえで異動を進めることで、モチベーション低下を防ぐことができます。
引き継ぎや異動後の業務をサポートする
異動が決まったあとも、本人の引き継ぎや新しい業務をサポートする体制が求められます。現在担当している業務の範囲や、引き継ぎ先との業務調整を明確にしておくことで混乱を避けられるでしょう。
異動後も、一定期間後にフォロー面談を実施し、新しい環境での課題や悩みを早期に把握して対処しましょう。異動先の上司や同僚と連携し、業務の進捗をチェックするほか、研修やスキルアップの機会を設けるなど、中長期的な成長支援も大切です。
異動が多い人が無能とは言いきれない
異動が多い人からといって、無能とも優秀とも言いきれません。人事異動は、企業・上司からの評価、スキルと環境がマッチしているか、本人の意欲やキャリアプランなど、さまざまな要因によって決定されるからです。異動の回数や頻度に捉われず、自身のキャリアプランを前向きに向き合ってみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社宅業務を標準化するには?具体的な手順やメリット、代行サービスの活用方法も解説
社宅業務とは、物件探しや契約手続き、家賃管理、入退去の対応、更新・解約といった、社宅に関連する一連の業務の総称です。手続きが煩雑で多岐にわたるため、特定の担当者に業務が集中し、属人…
詳しくみる【早見表】産休はいつからいつまで?期間の計算方法と必要な手続きをわかりやすく解説
産休は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産日の翌日から8週間まで取得可能です。 本記事では、産休期間の計算方法、双子の場合、予定日より早くまたは遅く出産した…
詳しくみる身分証明書とは?種類や従業員証明(社員証)テンプレート、書き方を解説
市区町村役所における公的な手続きや銀行口座の開設、就職時など様々な場面で本人性の確認のために、身分証明書の提示や提出を求められます。その手続きが重要であればあるほど、本人であるか否…
詳しくみる介護離職とは?後悔しない両立方法、企業の取り組み事例、助成金
介護離職とは、家族の介護を理由に仕事を辞めることです。介護離職を防ぐためには、介護休業や介護休暇の制度、勤務先の支援、介護サービスの利用が欠かせません。政府や企業も助成金や柔軟な働…
詳しくみるストレスで異動したい場合の伝え方は?部署異動できない場合の対応も解説
職場でのストレスで部署異動したいと感じる人は少なくありません。しかし、部署異動したいという希望をどのように伝えればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、ストレ…
詳しくみるコワーキングスペースとは?ドロップイン料金・経費・東京での選び方を解説
近年、リモートワークの広がりにより、都内をはじめコワーキングスペースが増えています。コワーキングスペースは、仕事や勉強などの作業を想定してデザインされており、個人事業主やフリーラン…
詳しくみる