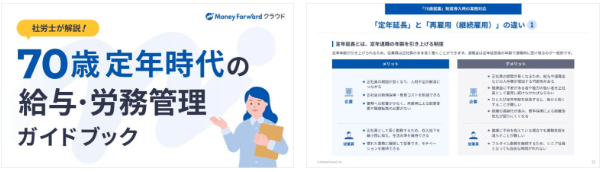- 更新日 : 2025年12月5日
定年後再雇用とは?何歳まで?給与や年金との関係、契約、助成金を解説
定年後再雇用とは、定年を迎えた社員が同一の企業と再び契約し、継続して就労する制度です。再雇用時には勤務形態や職務内容などの労働条件が見直され、給与の減額を伴うことも少なくありません。本記事では、定年後再雇用について、制度の概要や一般的な処遇、年金との関係、再雇用契約の手順や活用できる助成金などを紹介します。
目次
定年後再雇用とは?
定年後再雇用とは、継続雇用制度の一つで、定年に達した従業員が一旦退職し、同じ会社と新たな雇用契約を結ぶ制度です。
何歳から何歳まで
再雇用の期間は会社によって異なりますが、会社は少なくとも65歳まで再雇用可能な制度を整える必要があります。高年齢者雇用安定法により、従業員が希望した場合は、会社はその従業員を65歳まで雇用する義務があるからです。
高年齢者雇用安定法は「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの方法により、65歳までの雇用確保義務を会社に課しています。定年後再雇用は継続雇用制度の1 つです。
同法により、70歳までの就業機会を確保する「努力義務」も定められています。就業機会確保の方法は「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」だけでなく、「70歳までの業務委託契約」や「社会貢献事業に従事できる制度」でもよいとされています。
再就職との違い
再雇用と再就職との違いは「勤務先」です。
再雇用では、定年退職した会社と新たな雇用契約を締結し、定年前と同じ会社で働きます。賃金や雇用形態などの労働条件が変わっても、原則として勤務する会社は変わりません。
一方、再就職では、従業員が自分で勤務先を探し、定年前とは別の会社に就職します。
再就職には、新しい環境で再スタートできるというメリットがある反面、「シニア向けの求人が少ない」「再就職先では、それまでの実績が通用しにくい」などがデメリットです。
勤務延長制度との違い
定年後の継続雇用には、再雇用制度の他に「勤務延長制度」があります。2つの違いは、定年時に退職手続きを取るか否かです。
再雇用制度では、定年退職後に新しく雇用契約を結び直すため、定年を境に、賃金や勤務形態が大きく変わることもあります。
勤務延長制度では、定年を迎えても退職手続きを取らず、従前と同じ条件で雇用が継続されます。そのため雇用形態や賃金、業務内容などは原則として変わりません。
<再雇用制度>
- 一旦定年退職し、退職金を支給した後に再び雇用する制度
- 新たな雇用契約を締結する
- 雇用形態や労働条件は新たに設定される
<勤務延長制度>
- 定年に達しても契約期間を延長し、引き続き雇用が継続される
- 従前の労働条件が継続する
- 退職金は支給されない
つまり、再雇用制度は一旦退職して新たな契約を結ぶのに対し、勤務延長制度は定年を迎えても雇用契約が継続するという違いがあります。
再雇用の場合は、退職金の支給や新たな労働条件の設定が必要になりますが、制度の運用が柔軟にできるメリットがあります。一方、勤務延長は現行の労働条件が継続するため、働き方に変化がない分、安心感があります。
従業員のニーズや企業の状況に合わせて、どちらの制度を採用するかを検討する必要があります。場合によっては、両制度を組み合わせて運用することも可能です。
高年齢者の活躍の場を確保するうえで、企業は最適な制度設計とその適正な運用が求められています。法改正を踏まえ、制度の違いを十分理解したうえで検討を進めることが重要になります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
70歳定年時代の給与・労務管理ガイドブック
高年齢者雇用安定法の改正で「70歳まで働く時代」が到来しています。
本資料では70歳就業制度導入時の実務対応をはじめ、定年延長・再雇用で給与を見直す際のポイント、健康管理・安全衛生管理で配慮すべきことをまとめました。
シニア社員の給与を見直すときにやってはいけない5つのこと
少子高齢化による人口減少が社会問題となっている今、60歳以上の雇用が企業の課題となっています。
本資料ではシニア社員を取り巻く環境変化を説明するとともに、定年延長や再雇用で給与を見直す際の注意点をまとめました。
同一労働同一賃金 対応マニュアル
働き方改革の推進により、正規社員と非正規社員の待遇差解消を目的とする「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
本資料では適切な対応方法を示しながら、非正規社員の給与見直しの手順を解説します。
定年後再雇用の給与や待遇
定年後再雇用の契約内容は、会社や個人によって異なります。ここでは統計データを交えながら、再雇用契約における雇用形態や賃金についてみていきましょう。
再雇用時の雇用形態
再雇用後の雇用形態は、再雇用契約によりさまざまです。再雇用後もフルタイムで働く従業員もいますが、嘱託やパートといった雇用形態に変更される人も少なくありません。また多くの場合、再雇用後は1年更新の有期雇用になります。
独立行政法人労働政策研究・研修機構が2020年に発表した資料によると、60歳代前半における雇用形態は「正社員」「嘱託・契約社員」「パート・アルバイト」「関連会社からの出向等」など多様ですが、そのうち「嘱託・契約社員」を雇用する会社の割合は57.9%にのぼっています。
再雇用時の給与
再雇用時の賃金は、定年前と比べて減少するケースが多くみられます。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の資料によると、61歳の継続雇用者(フルタイム)の賃金は、60歳時に比べ、最も高い水準が89.6%、平均的な水準が78.7%、最も低い水準が70.8%と、おおむね減少していました。
定年後再雇用でも同一労働同一賃金の原則は適用されるため、職務内容などに変化がない場合に賃金だけが大幅に下落したらトラブルになりかねません。
ただし、加齢による体力の低下や年金の受給、退職金の支給などの合理的な理由があれば、ある程度の賃金減少が認められることがあります。
再雇用時のボーナス(賞与)
再雇用後に賞与が支給されるかは、再雇用契約の内容によります。通常の非正規雇用者と同様、賞与支給がなかったり、通常の社員より少額だったりするケースも多いようです。
有給休暇の計算方法
定年後再雇用では雇用契約が刷新されますが、年次有給休暇の算定においては、定年前から雇用が継続しているとみなされます。再雇用時に勤続年数はリセットされることなく、有休残日数も定年退職時に消滅しません。
再雇用日以後に付与される年次有給休暇の日数は、再雇用後の所定労働日数によって決まります。フルタイムからパートタイムになり所定労働日数が減少した場合は、再雇用後の所定労働日数に対応する年次有給休暇が付与されます。
定年後再雇用の仕事内容
再雇用後に従事する仕事の内容は、再雇用契約によって異なります。定年前と同じ仕事をする人もいれば、職務内容が変わることもあります。また仕事の内容が同一でも責任の程度が軽くなるケースは少なくありません。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の資料によると、60歳台前半の継続雇用者の仕事は、以下のような内容となっています。
- 定年前と全く同じ 44.2%
- 定年前と同じ仕事だが責任が軽くなる 38.4%
- 定年前と同じ仕事だが責任が重くなる 0.4%
- 定年前と一部異なる 5.6%
- 定年前と全く異なる 0.5%
上記をみると、定年前と同じ仕事をする継続雇用者が多いことがわかります。ただし、定年前と異なる業種にした場合は問題があるため、注意が必要です。
参考:高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)|独立行政法人労働政策研究・研修機構
定年後再雇用と年金の取り扱い
再雇用後、就労しながら老齢厚生年金を受給する場合、在職老齢年金制度により、年金の一部が支給停止されることがあります。年金が支給停止されるのは、1ヶ月あたりの賃金と老齢厚生年金の合計が50万円を超える場合です。
再雇用契約の所定労働時間や所定労働日数が少なく、厚生年金に加入しない働き方をする場合は、在職老齢年金制度の対象外になるため、この制度による年金支給停止はありません。
定年後に再雇用する手続き、流れ
定年後再雇用には、対象者の意思確認や面談など事前の準備が必要です。また再雇用契約後も社会保険などの手続きを要することがあります。ここでは一般的な再雇用のフローをみていきましょう。
対象者の意思確認
再雇用制度の対象となる定年退職予定者へ、制度の内容と運用方法を事前に通知・説明することが重要です。具体的には以下のようなプロセスを経ます。
(1) 制度概要の通知
定年到達前の一定期間前までに、再雇用制度の概要や対象者の要件などを文書で通知します。対象者全員に制度の存在を周知徹底するためです。
(2) 個別の説明会実施
文書通知後、制度の詳細や再雇用時の就業条件などについて、個別の説明会を開催します。質疑応答の機会も設け、丁寧な説明に努めましょう。
(3) 継続就労の意思確認
説明会後、継続就労の意思を書面で確認します。再雇用を希望する・しない、の意思表示をしてもらいます。
このように、事前に十分な説明と意思確認を行うことが重要です。制度の透明性を確保し、トラブル未然防止にもつながります。
また、就労意思確認時には、健康状態や家族状況など、個別のニーズを把握することも欠かせません。柔軟に対応できる体制づくりが求められます。
再雇用予定者との面談
再雇用を希望する従業員と個別に面談し、再就職後の働き方について本人の希望を聴取するとともに、再雇用後の賃金や雇用形態などについて説明します。後でトラブルが起きないよう、このときよく話し合っておくことが重要です。
(1) 個別面談の実施
再雇用希望者と個別に面談し、スキルや経験、健康状態などを確認します。今後の就業希望や職務適性についても、十分にヒアリングを行います。
(2) 雇用条件の決定
面談内容を踏まえ、担当予定業務や賃金水準、就業時間などの雇用条件を具体的に決定します。公平性や適正な処遇の観点から、一定の基準を設けることが重要です。
(3) 雇用条件の提示
決定した雇用条件について、書面で対象者に提示します。内容を丁寧に説明し、質疑に応じる機会を設けましょう。
(4) 合意形成
対象者と雇用条件について合意に至った場合は、正式に内定通知を行います。条件交渉の結果、合意に至らない場合もあり得るでしょう。
一人ひとりのニーズに合わせて、きめ細かい対応が求められます。公正な評価と処遇を心がけながら、納得性の高い雇用条件を提示することが大切です。
再雇用契約と退職金の支払い
再雇用する従業員と、書面により新しい契約を締結します。また会社の退職金規程に従い、退職金支払準備も進める必要があります。
退職金については、定年到達時に支払う会社もあれば、再雇用終了時に支払う会社もあり、扱いはさまざまです。
(1) 新規雇用手続きの実施
退職後の再雇用となるため、新規雇用と同様の手続きを行います。労働条件通知書の交付、社会保険や雇用保険の手続き、従業員の登録など、法令に則した手続きが求められます。
(2) 労働契約書の作成・締結
合意に至った雇用条件を明記した労働契約書を作成し、再雇用者との間で締結します。有期雇用か無期雇用かについても明記する必要があります。
(3) 賃金・評価制度への反映
賃金規定の改定や賃金テーブルへの再雇用者の位置付けなど、賃金制度上の手続きを行います。また、評価制度についても検討が必要です。
(4) 社内周知と研修の実施
再雇用者の役割や就業場所など、関係部署への周知を徹底します。再雇用者に対しても、就業ルールなどの研修を改めて行います。
再雇用契約書のテンプレート-無料ダウンロード
再雇用契約書を効率的に作成するには、テンプレートを活用すると便利です。
以下より、今すぐ実務で使用できる、テンプレートを無料でダウンロードいただけます。自社に合わせてカスタマイズしながらお役立てください。
社会保険の手続き
再雇用後に所定労働時間が減少し、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の適用範囲外になる場合は、健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続きが必要です。
また定年後の所定労働時間が社会保険の適用範囲でも、再雇用により賃金が低下し社会保険の標準報酬月額が下がる場合は、同日得喪の手続きをします。
同日得喪とは、資格喪失届と資格取得届を同時に提出する手続きです。随時改定や次年度の定時決定を待たず、標準報酬月額を新しい賃金に応じたものにする効果があり、社会保険料の軽減につながります。
定年後再雇用の注意点
再雇用契約における注意点や活用できる給付金や助成金も紹介します。
無期転換ルールに注意する
無期転換ルールとは、有期雇用契約が更新されて通算5年を超えた場合に、従業員からの申し込みにより、期間の定めのない雇用契約に転換できる制度です。
定年後再雇用の場合、1年の有期契約を更新することが一般的ですが、再雇用者にも無期転換ルールは適用されます。
ただし定年後再雇用者については、適切な雇用管理に関する計画(第二種計画認定申請)を都道府県労働局に提出して認定を受けると、無期転換申込権が発生しません。定年後再雇用をする予定がある場合は、あらかじめ第二種計画認定申請をしておくとよいでしょう。
安全や健康に留意する
定年後再雇用では、高年齢従業員の健康や安全に留意する必要があります。若年者に比べ、高年齢者は視力や聴力、筋力などが低下傾向にあり、労働災害を発生しやすいためです。
従業員の健康状態も適切に把握し、状況に応じて勤務時間の短縮や深夜業の制限などの措置を講じる必要もあるでしょう。
雇用形態
再雇用制度における雇用形態は、通常の正社員とは異なり、嘱託社員やパートタイマーなどといった非正規雇用が一般的です。
(1)嘱託社員
定年退職後の社員を企業が直接雇用する有期雇用の形態です。契約社員と称する場合もありますが、法的に明確に区別しているわけではなく、一般的には定年退職後以外のケースで個別の雇用契約に基づき有期雇用するときに使われる名称です。
(2)パートタイマー
短時間労働者として、時給制の雇用形態となります。
雇用形態によって、労働条件や社会保険・退職金の取り扱いが異なります。
契約更新期間
再雇用契約の期間は有期となるため、契約更新の条件や上限期間を明確にしておく必要があります。
(1)契約期間
1年契約が一般的ですが、6ヵ月や2年など企業により異なります。
(2)更新条件
健康状態や業績評価など、更新の要件を明記します。
(3)上限期間
最長で雇用できる期間を設けることが望ましいでしょう。
契約更新の可否が不確定だと、再雇用者の生活設計に影響を与えかねません。明確な基準を設けることが重要です。
給与・賞与
再雇用者の給与水準は、通常の正社員とは異なる設定となります。
(1)給与体系
年俸制や月給制、時給制など、雇用形態に応じた体系を採用します。
(2)給与水準
定年前の賃金カーブから大幅に下げられることが一般的です。
(3)賞与
支給する場合とそうでない場合があります。支給する際は、支給時期や算定基準を明確にします。
給与水準の設定は難しい課題ですが、年齢、役職、職務内容を考慮し、適正な水準を検討する必要があるでしょう。
有給休暇
再雇用者の年次有給休暇は、付与日数など労働基準法に従って適切に行う必要があります。
各種手当
再雇用者に支給する手当については、業務内容や責任の変更に合わせて見直す必要があります。特に以下の手当については、注意が必要です。
(1)通勤手当
再雇用前と同一の職場で勤務する場合は、従前の運用を継続することが一般的です。勤務地変更の際は、新たに算定が必要です。
(2)住宅手当
基本的に従前の支給額を継続するケースが多いようです。ただし、住宅費の変更があれば、それに合わせて支給額を見直すべきでしょう。
(3)役職手当・職能手当
再雇用時に役職や職責が変更になることが一般的です。新しい役職・職能に応じて、支給額を改めて設定する必要があります。
再雇用後の業務内容や責任の変更に合わせ、諸手当の設定を柔軟に見直すことが不可欠です。公平性や従業員のモチベーションの維持にも配慮が求められます。
再雇用時に活用できる給付金・助成金
定年後再雇用などの際に活用可能な給付金や助成金について紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付の一つで、60歳から65歳までの従業員が一定要件を満たした場合に支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金の受給要件は次のとおりです。
- 60歳到達時の賃金と比べ、それ以後の賃金が75%未満に低下したこと
- 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること
- 基本手当や再就職手当を受給していないこと等
高年齢雇用継続基本給付金の受給額は「60歳以後に支払われた賃金×支給率」で計算します。支給率は賃金低下率によって異なり、最大で15%(2025年4月以降、新たに60歳になる場合は10%)です。
高年齢雇用継続基本給付金についての詳細は、ハローワークのサイトをご参照ください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」は、次に該当する場合に受給できる雇用関連助成金です。
- 65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を65歳超まで継続雇用する制度などを整備した
- 制度を整備したときに、一定の経費を支出した等
65歳超雇用継続促進コースの助成額は、整備した制度内容と60歳以上の雇用保険被保険者人数に応じて異なり、最大で160万円です。
65歳超雇用推進助成金についての詳細は、厚生労働省のサイトをご参照ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
この助成金は、高年齢者や障害者など就職が困難な方をハローワークなどから紹介され、継続して雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主を対象にしています。就職困難者の継続的な雇用を支援することを目的としています。
主な支給要件は、次の通りです。
(1)ハローワークや民間の職業紹介事業者等から対象者を紹介され雇い入れること。
(2)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続雇用することが確実と認められること。具体的には、対象者の65歳到達までの継続雇用が見込まれ、かつ2年以上の雇用期間が見込まれること。
(3)その他、雇用関係助成金共通の要件を満たすこと。
対象となる職業紹介機関は、 ハローワーク、地方運輸局(船員として雇う場合) 、適正運営が期待できる有料・無料の職業紹介事業者 (特定地方公共団体、許可業者、届出業者など一定の条件を満たす者)となっています。支給額については、対象労働者の類型と企業規模に応じて金額が異なります。
高年齢者処遇改善促進助成金
この助成金は、60歳から64歳の高年齢労働者の処遇改善を支援するものです。企業が就業規則などで定める賃金規定を改定し、60歳時点の賃金水準から75%以上引き上げた場合に支給されます。高年齢者の公正な待遇の確保を目的としています。
主な支給要件は、次の通りです。
(1)就業規則などで賃金規定を改定し、すべての対象労働者の時給を60歳時点から75%以上増額すること。
(2)賃金規定改定により増額された賃金が支払われた月の前後6ヵ月間を比較し、後の6ヵ月間に高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少していること。
(3)支給申請日時点で改定後の賃金規定を継続して運用していること。
(4)その他、雇用関係助成金共通の要件を満たすこと。
支給額は、事業所の労働者について、賃金規定改定前後での高年齢雇用継続基本給付金の減少額に対し、以下の助成率を乗じた額が支給されます。
– 中小企業以外: 1/2
– 中小企業: 2/3
再雇用制度を導入するメリットは?
再雇用制度を導入することには、企業にとってさまざまなメリットがあります。主なものとして以下の5点が挙げられます。
熟練人材の確保と活用
再雇用により、企業に長年在籍し培った経験やノウハウを有する熟練人材を確保し、継続して活用できます。若手育成の面でも貢献が期待できます。
人材不足への対応
人手不足が深刻化する中、高年齢者を再雇用することで労働力を確保できます。特に、熟練技能職などでは有効な対策となるでしょう。
人件費の抑制
再雇用者は定年前に比べて賃金水準が低くなる傾向にあるため、人件費の抑制につながります。退職金の支給後に契約更新するため、コストメリットになります。
企業価値の向上
多様な人材が活躍できる職場環境が整うことで、企業のイメージアップや優秀な人材確保にもつながり、企業価値の向上が期待できます。
法令遵守と労務リスクの低減
高年齢者就業確保措置への対応が求められる中、再雇用制度の導入は法令遵守にもつながります。また、高年齢者の継続雇用を拒否することによる訴訟リスクを回避できるでしょう。
これらのメリットの一方で、以下のようなデメリットにも留意が必要です。
- 賃金のコスト削減を優先し、処遇が不当に低くなるリスク
- 若手の育成や登用が阻害される恐れ
- 高年齢者に適した業務が確保できないケース
- 労務管理が複雑化する
こうしたデメリットを踏まえつつ、再雇用制度を適切に設計・運用することが重要となります。メリットを最大限に活かしながら、高年齢者が活躍できるダイナミックな職場づくりを推進する必要があるでしょう。
定年後の再雇用制度が導入された背景
65歳までの雇用確保義務ができた背景には、老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げがあります。
以前、老齢厚生年金が60歳から受給できた頃は、会社員が60歳で定年退職しても、生活に支障はありませんでした。
しかし法改正により老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが開始されたため、60歳で定年退職すると無収入の期間が発生し、多くの定年退職者が生活に困窮することが予測されたのです。
それを受け、年金の支給開始年齢まで収入を確保できるよう、高年齢者雇用安定法が改正され、2013年4月から65歳までの雇用確保措置が会社の義務とされました。
雇用確保措置では「定年引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を講じ、就労を希望する従業員に65歳までの雇用を確保する必要があります。定年後再雇用は継続雇用制度の一つで、数多くの会社に導入されています。
2021年度改正で「高年齢者就業確保措置」が追加
2021年4月から、高年齢者雇用安定法が改正され、従来の「高年齢者雇用確保措置」に加え、新たに「高年齢者就業確保措置」が努力義務化されました。どのような違いがあるのか整理してみます。
<従来の高年齢者雇用確保措置>
(1)60歳未満の定年禁止
・定年を定める場合は、60歳以上としなければなりません。
(2)65歳までの雇用確保措置
・65歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、65歳までの雇用継続制度を導入しなければなりません。
この「高年齢者雇用確保措置」に加え、2021年度改正で追加されたのが以下の「高年齢者就業確保措置」です。
<高年齢者就業確保措置>
・次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めるという努力義務が規定されました。
(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
①事業主が自ら実施する社会貢献事業
②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主は、 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、または 継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主とされています。
この改正により、定年退職後の高年齢者の就業機会が大幅に拡充されることが期待されるとともに、高年齢者雇用への取り組みが一層強化されることになります。
再雇用制度を知ってシニア従業員を活用しよう
定年後再雇用とは、定年に達した従業員と新しく雇用契約を締結し、定年退職後も継続雇用する制度です。雇用契約が刷新されることもあり、再雇用では雇用形態・賃金・仕事の内容などが定年前と変更になるケースが多くみられます。
高年齢者雇用安定法により、会社は65歳までの雇用確保措置を講じる義務があり、再雇用制度は有効な措置の一つです。再雇用制度をよく知り、給付金や助成金なども使いながら、シニア従業員を活用してはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
労働者名簿をエクセルで作成するには?無料テンプレートや取扱いの注意点を解説
労働者名簿をエクセルで作成するとき、法的要件を満たす内容にしなければならないことに加え、適切に管理することが求められます。本記事では、労働者名簿をエクセルで管理する際のポイントや必…
詳しくみる労働組合法とは?労働三法の違いやメリット、違反した場合の罰則を解説!
労働者は、雇用する使用者に対して弱い立場に置かれがちです。そのため、労働者を保護するために、労働基準法などの法律が定められています。 当記事では、労働三法のひとつである労働組合法に…
詳しくみるローパフォーマーの社員に退職勧奨するべき?注意点やよくある質問なども解説
企業にとってローパフォーマーの社員の存在は、組織の生産性に関わる課題のひとつです。ローパフォーマーの社員に対して退職勧奨を行うべきなのか、判断に悩む人事担当者も少なくありません。 …
詳しくみる外国人雇用管理士は国家資格?試験概要や外国人労働者雇用に役立つ資格を紹介
外国人雇用管理士は国家資格ではなく、民間資格です。外国人労働者の雇用に関する知識を身につけ、適切な管理を行うための資格として注目されています。 本記事では、外国人雇用管理士の試験概…
詳しくみる在籍証明書とは?必要なケースや記載項目など解説【テンプレート付き】
在籍証明書とは、対象従業員が会社に在籍していることを証明する書面のことです。住宅ローンや賃貸契約だけでなく、保育園の入園申し込みやビザの申請など、用途によって求められる記載項目が異…
詳しくみるなぜ働き方改革にペーパーレス化が必要か?現状や進め方、成功事例を解説
政府は、多様な働き方の実現や不合理な格差の是正等を目指し、働き方改革を推進しています。国や地方公共団体だけでなく民間においても、その流れは波及しており、各社様々な施策を講じています…
詳しくみる