- 更新日 : 2025年12月24日
自律的とは?意味や自立的との違い、自律的に行動するための7つの方法
自律的とは、信条、理念、価値観などに対して自らの規範を作って、それに従って行動することです。 ビジネスにおいて、指示待ちではなく自律的に行動する人材のことを自律型人材と言います。本記事では、自律的の意味や、自立的との違い、自律的に行動するための7つの方法について解説します。
目次
自律的とは?
自律的とは、自らの信条、理念、価値観などの規範やルールを作って、それに従い判断や行動をする状態のことです。自律的に行動できる自律型人材は、自らの意思で考えて能動的に業務を遂行できるのが特徴です。
本項では、自律的の意味や言い換え、自立的や自発的との違いについて解説します。
自律的の言い換え
自律的を言い換えると、以下の言葉になります。
- 自主的
- 自律する
- オートマチック
- 自己統治的な
- 自己制御
どの言葉の意味も、自分で自分を律し制御するさまのことです。自律的と似たような言葉に、「自立的」や「自発的」などがありますが、意味合いが異なります。
自立的、自発的との違い
自律的と自立的、自発的には、以下のような違いがあります。
・自律的と自立的との違い
自立的とは、能力、経済力、身体などに関して、他の助けを受けずに一人で行動することです。
一方、自律的とは、自分が決めた規範やルールに従って、自らの行動をコントロールすることを言います。
・自律的と自発的との違い
自発的とは、自らが進んで物事に取り組んだり、行動したりすることです。他の人からいわれて行動するのではなく、自然に自分から行動します。
一方、自律的とは、自分が決めた規範やルールに沿って行動することです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
従業員の見えない不満や本音を可視化し、従業員エンゲージメントを向上させる方法
従業員エンゲージメントを向上させるためには、従業員の状態把握が重要です。
本資料では、状態把握におけるサーベイの重要性をご紹介いたします。
エンゲージメントサーベイを用いて、離職防止を推進する⽅法
離職防止には従業員エンゲージメントの向上が効果的です。そのために、従業員の状態把握が必要です。
本資料では、従業員の状態を把握する具体的な手段としてマネーフォワード クラウドサーベイをご紹介します。
【テンプレート】育成計画書(エクセル)
従業員の育成計画書の準備は進んでおりますでしょうか。
本資料は、すぐにお使いいただける育成計画書のExcelフォーマットです。ぜひダウンロードいただき、貴社の人材育成にご活用ください。
自律的の例文、使い方
自律的の意味は、指示待ちでなく自分が決めた規範などに従って行動していくことですが、自律的という言葉は以下の例文のように使用します。
- 多くの会社が、自律的に行動する人材を求めています。
- 会社にとって、自律的に学ぶ社員を増やすことは大きな武器になります。
- 仕事を行う上で、自律的に考えることが一番大切です。
会社で自律的に行動しているか判断するには?
会社での行動が自律的であるかは、会社に貢献しているかという観点では重要なことです。本項では、会社で自律的に行動しているか判断するにはどうすればよいかについて解説します。
目標を設定し行動しているか
自律的に行動する自律型人材は、上司の指示待ちではなく自らの考えや意志に従って行動します。そのため、上司から言われなくても自ら目標を設定して、期待されている自分の役割を理解して行動できるのが特徴です。目標を設定し行動しているかどうかで、自律的に行動しているかを判断できます。
問題を発見し解決策を見出しているか
自立型人材は自らが考えることにより問題を発見し、明確化して、解決策を見出す問題解決思考を持っているのが特徴です。上司などから指示されなくても、問題解決のプロセスを進めて解決策を実行する人材は、自律的に行動していると判断してもよいでしょう。
成長志向があるか
自律型人材は、現状に満足せずに常に成長を目指している姿勢を持っているのが特徴です。社内でも新しい知識やスキルを積極的に取得し、成長しようと努力する姿が見られれば、自律的に行動していると判断できます。
自己反省をしているか
自律型人材は、失敗することを恐れずに何事にもチャレンジしていく特徴があるため、実際に失敗することも少なくありません。しかし、きちんと自己反省をすることで、失敗を糧にしながら改善点を見つけ出せる人材は、自律的に行動していると判断してもよいでしょう。
自律的に行動する人材を育成するメリット
自律的に行動する人材を育成することは、会社にとって大きなメリットをもたらします。本項では、自律的に行動する人材を育成するメリットについて解説します。
生産性と効率性が向上する
自律的に行動する人材は、自らの目標を達成するため、効率的に業務を遂行しながら生産性の向上を図ります。このように行動する自律型人材を数多く育成すればするほど、会社全体にとっての業務効率化や生産性向上につながります。
イノベーションを生み出す力が高まる
上司などの指示だけで業務を行っていても、新たなイノベーションを生み出すことはできません。自律的に業務に取り組むことで、たくさんのアイデアや考えが生まれ、会社全体のイノベーションを生み出す力が高まります。
その結果、会社の発展にもつながるため、自律的に行動する人材を数多く育成することは大きなメリットです。
優秀な人材が増える
自律型人材は、指示をしなくても自ら行動するため、上司などの負担が軽減され、その分空いた時間にさらなる人材育成に時間を割くことができます。自律型人材を数多く育成するほど、会社にとって優秀な人材を増やすことが可能です。
自律的に行動する人材育成の7つの方法
自律的に行動する自律型人材を育成するためには、さまざまな方法があります。本項では、自律的に行動する人材を育成する7つの方法について解説します。
自らの判断で行動する機会を設ける
自律型人材は、指示を受けてから行動するのではなく、何をするべきなのかを自分で考えて自ら率先して行動します。自律的に行動する人材を育成するためには、研修や実践の場で指示を待ってから行動するのではなく、自らの判断で行動する機会を設けることが大切です。
目標設定や課題解決の機会を提供する
自ら目標を設定して行動していくことや、課題を明確化して解決策を見出すのも自立型人材の特徴です。そのため、具体的で測定可能な目標を設定する機会を提供すると、課題に対する解決策を自ら考える機会を得られます。
他者を巻き込む力を培う
自律型人材は、周りの社員などの他者を巻き込みながら、目標に向かって物事を進められます。他者を巻き込む力とは、周囲の人と有意義な関係性を築き、積極的な協力を得て成果を出す力のことです。
自立型人材を育成するには、周囲の人と有意義な関係性を築き、他者を巻き込む力を培うことも必要でしょう。
自己表現力やコミュニケーション能力を高める
自立型人材になるためには、指示される前に自発的に行動することが大切ですが、自分の考えや感情などを他者に分かりやすく伝える力を持っていなければなりません。他者に分かりやすく伝えるためには、自己表現力やコミュニケーション能力を高めることが必要です。
リーダーシップを発揮する力を養う
自律的に行動するには、指示を受ける前に自ら率先して行動し、他者を巻き込みまとめていくリーダーシップが必要です。仕事の場でも、チームなどの集団の中で他のメンバーを支援しながら、チームをけん引する機会を与えることで、自律性を高められるでしょう。
自分の行動を調整する力を身につける
自律型人材は、周りに流されることなく自分の意思や意見を持っているのも特徴です。しかし、ビジネスの場では、自分の意志や価値観を大切にしながらも、周囲と調整をはかりながら自ら考え行動しなければなりません。
周りの人に自分の意思や意見を理解してもらうために、自分の行動を調整する力を身につけるよう育成していくことが大切です。
チャレンジする環境づくりを行う
自律型人材であっても、自分の判断による行動すべてが成功するわけではありません。何回もチャレンジして失敗を繰り返すことにより、自律型人材として成長していきます。失敗したことに対して悪い評価をするのではなく、チャレンジしたことに対して評価するような環境を作ることで、自律型人材を育成できるでしょう。
会社にとって自立型人材を増やすことが生き残りの鍵になる
世の中の動きが早く、働き方がどんどん多様化していくこれからの時代において、自律的に行動する自律型人材の重要性はますます高まっていくことが予想されます。
会社にとって時代の変化に対応できる自律型人材をどれだけ育成できるかが、これからの激動の時代を勝ち抜き生き残るための鍵となるでしょう。自律型人材の育成に目を向け、力を入れていくことが、これから会社が発展する上で重要なポイントです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
コンプライアンス意識とは?重視すべき理由や意識向上のポイントを解説
コンプライアンス意識とは、法令を守るだけでなく、社会的責任や倫理観をもって行動する姿勢を指します。 企業ではコンプライアンス意識が欠けると、不祥事や信用失墜などのリスクを招きかねま…
詳しくみるミキワメ適性検査とは?特徴7選と解決する課題、導入メリットとデメリットを紹介
「採用した人材がすぐに辞めてしまう」「配属後のパフォーマンスが安定しない」と悩む人事担当者は多いです。 ミキワメの適性検査は、活躍する人材を可視化するツールです。一般的な性格診断で…
詳しくみるKKDとは?見積りのフレームワークは仕事でどう活用する?
KKDとは「経験・勘・度胸」のことで、日本の製造業で古くから重視されてきた手法です。KKDによる判断は的確で失敗も少ないと評価される一方、論理性や客観性のなさを指摘されることも多く…
詳しくみるEQとは?高い人の特徴や改善方法を解説!
EQとは心の知能指数とも呼ばれ、自分の感情の状態を把握し制御した上で、他者の感情を理解し活かす能力のことです。職場の人間関係構築だけではなく、部下の育成やチームビルディングなど、ビ…
詳しくみるゼネラリストとは?スペシャリストとの違いや育成方法について解説
ゼネラリストとは幅広い知識を持ち、さまざまなことに対応できる能力を持つ人を指します。専門分野を持つスペシャリストが一点集中型とされるのに対し、ゼネラリストはオールラウンド型です。多…
詳しくみる転職の適性検査で落ちる人の特徴は?内容や導入目的、選定ポイントを解説
適性検査は「能力検査」と「性格検査」で構成されており、就職・転職の選考試験で活用される選考プロセスの1つです。適性検査の結果に基づいて、求める人物像にマッチしているかを判断できます…
詳しくみる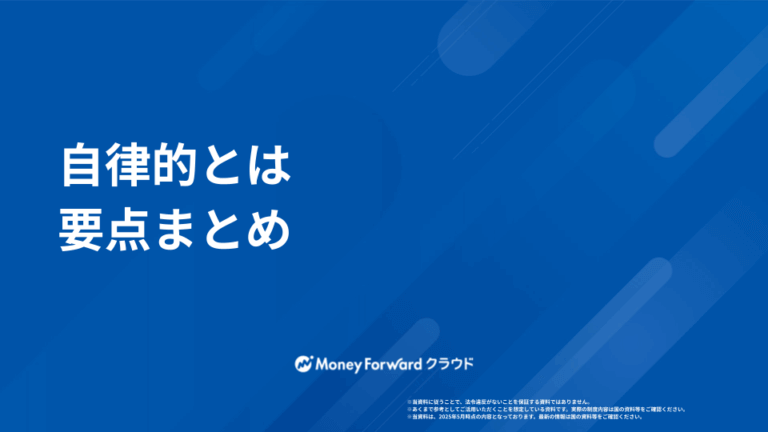



-e1761040031323.png)