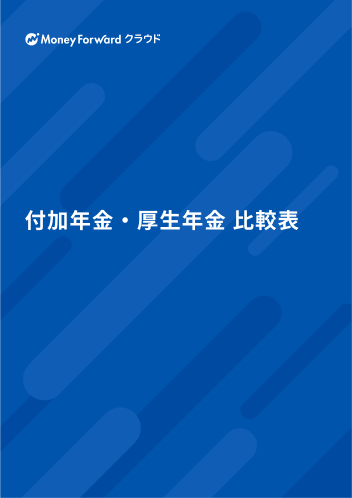- 更新日 : 2025年11月19日
付加年金とは?厚生年金においても活用できる?
付加年金は国民年金第1号被保険者が納付することで、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。月額400円を国民年金保険料と一緒に支払うことで、「200円×付加保険料納付済期間の月数」の付加年金が、老齢基礎年金に上乗せされます。国民年金保険料を支払う第1号被被保険者のみを対象にした制度で、厚生年金加入者は利用できません。
目次
付加年金とは?
付加年金とは国民年金第1号被保険者が、将来受け取る年金額を増やすための制度です。国民年金保険料と一緒に付加保険料を納付することで、付加年金が上乗せされた老齢基礎年金を受け取ることができます。以下のように、国民年金法第87条の2に規定されています。
国民年金法第87条の2
第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐
入社や退職に伴う社会保険の手続きは多岐にわたり、ミスが許されません。特に厚生年金や健康保険は従業員の将来の給付や医療に直結するため、正確な処理が求められます。
手続きの不備でトラブルになる前に、本資料で社会保険・労働保険の正しい手順や必要書類を確認しておきませんか?
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険加入条件 簡単図解 ミニブック
パートやアルバイトの社会保険加入条件を、最新の法令に基づいて正しく判断できていますか?要件の確認漏れは、未加入によるトラブルや遡及徴収のリスクにつながりかねません。
本資料では、複雑な加入条件を視覚的にわかりやすく図解しています。自社の現状チェックや従業員への説明にご活用ください。
付加年金の対象者は?厚生年金でも活用できる?
付加年金の対象者は国民年金第1号被保険者です。国民年金の被保険者は以下のように、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に区分されます。
- 第1号被保険者:自営業者、学生、農業者、無職の人など
- 第2号被保険者:厚生年金加入方者(会社員、公務員など)
- 第3号被保険者:第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されている配偶者
第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者のうち、第1号被保険者のみが国民年金保険料支払い義務を負っています。第1号被保険者が付加年金に加入する場合は、国民年金保険料と付加保険料を一緒に支払うことが求められます。
付加年金に加入できる人
付加年金は国民年金保険料支払い義務を負う、第1号被保険者のみに加入が認められています。また65歳未満の任意加入者も、付加年金保険料を支払うことができます。
付加年金に加入できない人
国民年金第1号被保険者でも、以下の人は付加年金に加入できません。
- 国民年金基金に加入している人
- 国民年金保険料の納付を免除されている人
第2号被保険者は基本的に付加年金を活用できない
3種類の国民年金被保険者のうち、第2号被保険者と第3号被保険者は国民年金保険料の支払い義務を負っていません。第2号被保険者と第3号被保険者が負担すべき国民年金保険料は、厚生年金から拠出されているためです。国民年金保険料を被保険者が自ら支払わなければならないのは第1号被保険者に限られ、第2号被保険者は付加年金を活用することはできません。
付加年金と国民年金基金どっちがお得?
国民年金第1号被保険者は、付加年金を活用することで将来に受け取る年金額を増やすことができます。また第1号被保険者は、国民年金基金の加入によっても老齢時の年金受取額を増やせます。
付加年金のメリット・デメリット
付加年金のメリットは以下のとおりです。
- 負担が少ない
毎月の付加保険料は400円と少額なので、負担が小さいです。
- 負担が少ない
- 効率的に年金額が増やせる
付加年金によって、老齢基礎年金に「200円×付加年金保険料を支払った月」分の金額が上乗せされます。1年分の付加保険料は2年間の年金受給で取り戻せるため、効率的です。
- 効率的に年金額が増やせる
- 繰り下げ受給により割り増しになる
付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下げ受給ができ、割り増しになります。
- 繰り下げ受給により割り増しになる
- 脱退や再加入ができる
付加年金は、それぞれの事情に応じて自由に脱退や再加入ができます。
反対に付加年金のデメリットは以下のとおりです。
- 年金を少ししか増額できない
付加年金による老齢基礎年金の増額は、少額にとどまります。
- 年金を少ししか増額できない
- 繰り上げ受給により減額される
繰り上げ受給をすると、付加年金も老齢基礎年金と同じ割合で減額されます。
国民年金基金のメリット・デメリット
国民年金基金のメリットは以下のとおりです。
- 口数を選べる
掛金上限額(1ヵ月あたり6万8,000円)を超えない範囲で、1口から口数を選べます。
- 口数を選べる
- 将来の年金額を大きく増やすことができる
選ぶ口数によっては、将来受け取る年金額を大きく増やすことができます。
反対に国民年金基金のデメリットは以下のとおりです。
- 脱退や中途解約ができない
口数の増減は自由にできますが、脱退や中途解約はできません。
サラリーマンの場合でも付加年金をさかのぼって支払うことはできる?
付加保険料は、付加年金の加入を申し込んだ月から納付することができます。申し込み前について、さかのぼって付加保険料を支払うことはできません。
厚生年金加入者は付加年金以外の方法で年金受給額を増やそう
付加年金は、将来受け取る年金額を増やすための制度です。毎月400円の付加保険料を支払うことで、老齢基礎年金の受給額に「200円×付加年金保険料を支払った月数」が上乗せされます。少ない負担で確実に、効率よく年金受給額を増やすことができます。
付加年金は国民年金保険料を自ら納付する第1号被保険者を対象にした制度で、厚生年金に加入している第2号被保険者は活用できません。サラリーマンは付加年金以外で年金受給額を増やす方法を考えましょう。
よくある質問
付加年金とは何ですか?
付加保険料を支払うことで、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金でも付加年金の制度を活用できますか?
付加年金を活用できるのは第1号被保険者に限られ、厚生年金加入者は活用できません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の加入条件とは?パートや50人以下企業の場合もあわせて解説
社会保険は、雇用形態にかかわらず、日本の労働者が必ず関わる公的な保険制度です。とくに2024年10月以降、パート・アルバイトの中でも勤務時間が短い短時間労働者を対象とした適用事業所…
詳しくみるパートが社会保険に加入したくないときの働き方は?年収の壁についても解説
パートタイムで働く方が、配偶者の扶養を維持したまま、ご自身の社会保険への加入を避けたいと考えるケースは少なくありません。ただし、2024年10月以降、社会保険の適用範囲は段階的に拡…
詳しくみる過労死とは?定義や症状および防止策を解説
繁忙期や納期の短縮などにより、どうしても長時間労働を行わざるを得ない状況となることもあるでしょう。しかし、長時間の労働は労働者の心身の健康を蝕み、最悪の場合は過労死という痛ましい結…
詳しくみる給料から社会保険料が引かれる額 – 具体例を用いて解説
社会保険料は毎月給与から天引きされるため、いくら引かれているのかを気にする従業員は少ないかもしれません。しかし、企業の人事労務担当者としては、給与から天引きする社会保険料の金額や社…
詳しくみる産休中にもらえる補助金は?出産手当金の支給額・対象者・申請方法を解説
出産は喜ばしいライフイベントですが、産休期間中の収入減や経済的な不安を感じる従業員も少なくありません。会社として従業員をサポートするためにも正しい知識を持つことは大切です。 この記…
詳しくみる社会保険の事業主負担率はいくら?計算式と注意点をわかりやすく解説
企業の経営者や担当者にとって、社会保険料の事業主負担は避けて通れない重要なコストです。「社会保険の事業主負担率は何パーセント?」「給与40万円の従業員だと、会社の負担はいくらになる…
詳しくみる