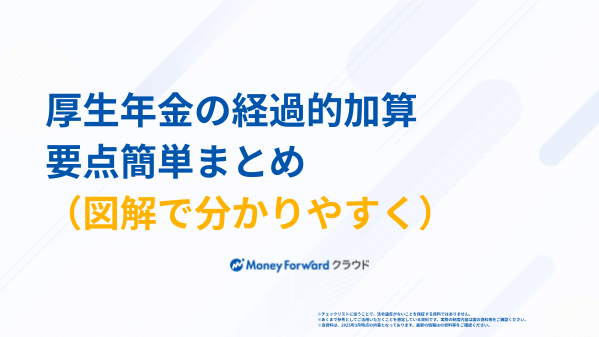- 更新日 : 2025年10月31日
厚生年金における経過的加算とは?計算方法などわかりやすく解説!
長く加入するほど将来もらえる年金額が増えていくのが厚生年金保険ですが、50歳以上の方にハガキで届く「ねんきん定期便」に載っている経過的加算額を見て、経過的加算の意味がわからず疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
今回は、厚生年金保険の経過的加算についてわかりやすく解説するとともに、その計算方法も紹介します。
目次
厚生年金における経過的加算とは?
経過的加算は、20歳未満や60歳以降に厚生年金保険に加入していた場合に、老齢厚生年金に上乗せして支払われる金額です。老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の違いとともに、経過的加算の仕組みについて見ていきましょう。
①老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の違い
国民年金と厚生年金保険は2階建てと聞いたことがある方もいるでしょう。1階部分の国民年金からは、日本に住んでいるすべての方共通の老齢基礎年金(いわゆる国民年金)が支給され、2階部分の会社員や公務員が加入する厚生年金保険からは、報酬に比例して支給される老齢厚生年金が支給されます。この2つは65歳から受け取るのが原則ですが、60歳以降に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれるものがあります。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和61年4月に厚生年金保険の受給開始年齢が65歳に引き上げられた際、経過措置として生年月日に応じて段階的に引き上げるために設けられた制度です。現在の老齢厚生年金との違いを見てみましょう。
- 受給期間
現在の老齢厚生年金:65歳から亡くなるまでの間受給することが可能
特別支給の老齢厚生年金:60歳から65歳までの有期年金となっており、65歳になると受け取る権利がなくなる
- 受給期間
- 主な年金額
現在の老齢厚生年金:加入期間や報酬に応じて金額が計算される「報酬比例部分」特別支給の老齢厚生年金:老齢基礎年金の金額に相当する「定額部分」と「報酬比例部分」の合計金額
②経過的加算とは
65歳になって特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなっても、65歳からは現在の制度に基づく老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることが可能です。しかし、老齢厚生年金の加入期間や加入時期によっては、特別支給の老齢厚生年金の老齢基礎年金相当額である「定額部分」が老齢基礎年金の額よりも多くなることがあります。このような場合に、60歳以前に受給していた「定額部分」の金額を保障するために、65歳以降もその差額を老齢厚生年金に上乗せして支給するのが「経過的加算」です。
国民年金の制度からもらえる老齢基礎年金の金額は、20歳〜60歳までの国民年金や厚生年金保険の納付月数で計算します。しかし、20歳未満や60歳以降に厚生年金保険に加入していたとしても、老齢基礎年金の金額は増えません。
たとえば、22歳〜62歳まで会社員として働いていた場合はどうでしょう。同じ40年働いたとしても国民年金には38年しか加入していないこととなるため、老齢基礎年金は38年分しか計算されません。この場合、60歳〜62歳まで厚生年金保険に加入している期間があるため、「経過的加算」として2年分の老齢基礎年金の金額に相当する額が、厚生年金保険から加算されることになります。
20歳未満や60歳以降の厚生年金保険の加入期間は老齢基礎年金の金額には反映されません。特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の計算による金額と厚生年金保険に加入していた期間における老齢基礎年金との差額、つまり、老齢基礎年金の金額に反映しない「定額部分」による老齢基礎年金相当額が、厚生年金保険から加算される仕組みになっているのです。
また、老齢厚生年金を受け取りながら企業で働く場合には、在職老齢年金の計算の仕組みによって年金額の一部または全部が支給停止になることがあります。在職老齢年金として老齢厚生年金が一部支給停止となったとしても、経過的加算は支給停止の対象にならないことも覚えておきましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
老齢厚生年金および経過的加算の対象となる人
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格である「10年間の受給資格期間」を満たせば、厚生年金保険の加入期間が1ヵ月だったとしても受給することが可能です。受給資格期間には、国民年金、厚生年金保険、共済組合等に加入していた期間のすべてをカウントすることができます。
経過的加算がもらえる人は、厚生年金保険に加入していた人です。したがって、国民年金の加入期間しかない人、つまり、厚生年金保険がもらえない人は、経過的加算の対象にはなりません。なお、経過的加算は厚生年金保険の加入期間のうちの480ヵ月が限度となるため、20歳〜60歳までの40年間、厚生年金保険に加入している場合にも原則として加算はありません。ただし、現状は、老齢基礎年金よりも特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の金額の方が計算方法の違いによって若干多くなるため、その差額が支給されています。
経過的加算の計算方法
経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算による金額と厚生年金保険に加入していた期間における老齢基礎年金との差額から計算します。計算方法は以下のとおりです。
(令和4年度の年金額で各種経過措置による計算率を考慮せずに計算)
定額部分の単価(令和4年度の単価単価)は1,621円となりますので、定額部分は以下のように計算します。
22歳から62歳まで40年間厚生年金保険に加入した場合で、経過的加算額を具体例から計算してみましょう。
- 定額部分:1,621円×480ヵ月=778,080円
- 老齢基礎年金:777,800円×38年×12ヵ月÷480=738,910円
- 経過的加算:778,080円-738,910円=39,170円
このケースでは厚生年金保険の掛け込み期間は40年間ありますが、老齢基礎年金の計算期間は38年しかないため、2年分の老齢基礎年金相当額が経過的加算として厚生年金保険に上乗せされることになります。
参考:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構
経過的加算を受け取るために手続きは必要?
経過的加算を受け取るための特別な手続きはありません。65歳になって老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取る手続きをすれば、経過的加算は自動的に計算されて支給されます。
経過的加算は厚生年金保険を受給しなければ受け取ることができません。「以前厚生年金保険に加入していたことがあるけれども、期間が短くてもらえない」という方もいるのではないでしょうか。しかし、受給資格期間が10年に満たないからといって、あきらめる必要はありません。
受給資格期間の10年には、国民年金、厚生年金保険、共済組合等に加入していた期間のほか、年金額には反映されなくても期間だけ加算できる合算対象期間と呼ばれる期間や、保険料免除期間も含めることができます。70歳以降も厚生年金保険に加入できる高齢任意加入の制度や、国民年金に最長70歳まで加入できる任意加入制度もありますので、受給資格期間が足りない人は年金事務所などで相談することをおすすめします。
参考:70歳以上の方が厚生年金保険に加入(高齢任意加入)するとき|日本年金機構、任意加入制度|日本年金機構
60歳以降も働くことで厚生年金の経過的加算を増やせるケースがある
厚生年金保険の経過的加算は、老齢基礎年金の金額に反映しない老齢基礎年金相当額が、厚生年金保険に上乗せされる金額です。たとえば、大学卒業後、22歳で就職して厚生年金保険に40年加入していないという場合、60歳以降も厚生年金保険に加入すれば、報酬比例部分だけではなく、経過的加算によっても厚生年金保険の年金額を増やすことができます。
近年、多くの企業で定年引上げや継続雇用制度により、65歳、70歳まで働く方が増えています。厚生年金保険は70歳になるまで加入することができ、加入期間が長いほど受け取る年金額が増加する仕組みです。厚生年金保険の加入期間によっては、60歳以降も働くことで年金額を増やせるケースもありますので、今一度、年金定期便などで加入期間の確認をしましょう。
よくある質問
厚生年金における経過的加算とはなんですか?
特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の計算による金額と厚生年金保険に加入していた期間における老齢基礎年金との差額が、厚生年金保険に上乗せされます。この上乗せされた金額を経過的加算といいます。詳しくはこちらをご覧ください。
老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金の違いについて教えてください。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳で失権する有期年金であり、その年金額は老齢基礎年金の金額に相当する定額部分と報酬比例部分の合計額です。老齢厚生年金は亡くなるまで受け取れますが、定額部分はありません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
建設業における労災保険の特徴は?単独有期と一括有期の違いなど
事業主は、労働者を雇用すれば原則として労働保険(労災保険、雇用保険)の適用事業所として加入義務が生じ、所定の手続きを行う必要があります。 一般的な業種の手続きは共通していますが、建…
詳しくみる個人事業主は厚生年金に加入できる?
個人事業主は国民年金に加入するのが一般的です。一方、会社員や公務員などは所属している会社や組織で厚生年金保険に加入します。国民年金よりも手厚い保障を受けられるので、厚生年金保険に加…
詳しくみる雇用保険被保険者証はいつもらえる?タイミングやもらえない・届かない時の対処法を解説
雇用保険被保険者証(雇用保険証)は、転職や給付金申請の際に必要な重要書類ですが、「いつ受け取ったのか記憶にない」「手元に見当たらない」という方が非常に多い書類です。 原則として、こ…
詳しくみる退職者は算定基礎届が必要?対象者・書き方・記入例を紹介
退職者は基本的に算定基礎届の提出は必要ありません。ただし、退職日によっては届出の対象になる場合があり、誤った対応をすると年金事務所から指摘を受ける可能性があります。 本記事では、退…
詳しくみる賞与に雇用保険料はかかる?免除は?退職後や死亡退職の場合
企業に勤めていると、正社員の方はもちろんパート・アルバイトであっても雇用保険料が徴収されます。それでは給与以外で発生した賞与は雇用保険の対象になるのでしょうか。 この記事では雇用保…
詳しくみる【テンプレ付】社会保険料計算のチェックリスト!ミスを防ぐ手順を完全解説
社会保険料の計算は、最新の標準報酬月額と保険料率に基づき行うため、そのミスを防ぐためにチェックリストの活用もおすすめです。社会保険料の計算には、毎月の給与計算だけでなく、算定基礎届…
詳しくみる