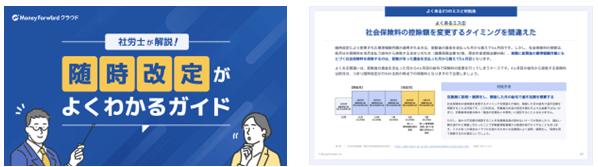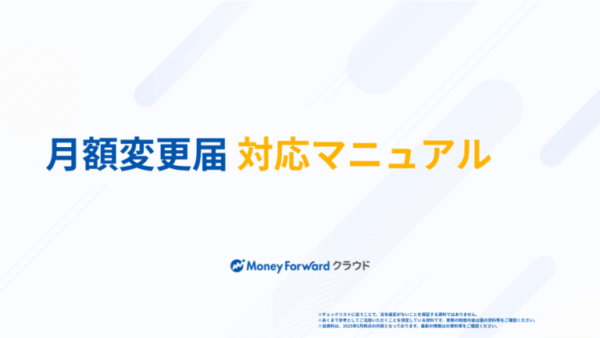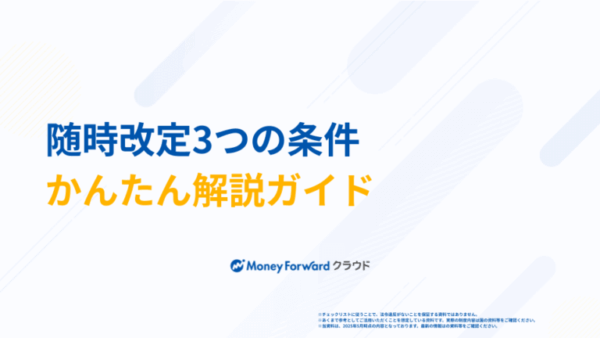- 更新日 : 2025年11月19日
育児休業等終了時報酬月額変更届とは?適用条件や記入方法をわかりやすく解説
育児休業から復帰したあと、思ったより手取りが少ないと感じる方もいるでしょう。これは社会保険料が、育休前の給与をもとに計算されているのが原因です。
育児休業等終了時報酬月額変更届という制度を利用すれば、育休後の実際の給与にあわせて標準報酬月額を見直し、社会保険料の負担を軽減できます。
本記事では、育児休業等終了時報酬月額変更届の概要から適用条件、記入方法をわかりやすく解説します。
目次
育児休業等終了時報酬月額変更届とは?
育児休業等終了時報酬月額変更届は、育児休業(またはこれに準ずる休業)から復帰した従業員の給与が、休業前と比べて変動した場合に、標準報酬月額を適正化するための手続きです。
通常の給与変動時に行う「月額変更届」とは異なり、育休復帰後に特化した特例制度として設けられています。ここでは、届出が必要な理由や月額変更届との違いを解説します。
届出が必要な理由
育休から復帰した従業員は、時短勤務や残業免除などにより、育休前と比べて給与が大幅に減少するケースが少なくありません。
復帰後の社会保険料は育休前の標準報酬月額にもとづいて計算されます。そのため、実際の給与に見合わない高額な保険料が差し引かれてしまう場合があります。これでは、育児と仕事の両立に取り組む従業員の経済的負担が大きくなってしまうでしょう。
そこで育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することで、育休復帰後3ヶ月間の給与平均をもとに標準報酬月額が見直され、4ヶ月目から社会保険料が改定されます。これにより、従業員の負担を軽減し、安心して働き続けられる環境づくりが可能になります。
月額変更届との違い
育児休業等終了時報酬月額変更届と月額変更届(随時改定)は、どちらも社会保険料を見直すための手続きです。しかし、適用条件や対象者が異なります。
| 項目 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 月額変更届(随時改定) |
|---|---|---|
| 対象者 | 育休から復帰した被保険者 | 固定的賃金に変動があった被保険者 |
| 適用条件 | 1等級以上の変動など | 2等級以上の変動など |
| 手続きの必要性 | 任意(希望者のみ) | 必要 |
月額変更届では、2等級以上の変動がなければ社会保険料は変更されません。一方、育児休業等終了時報酬月額変更届は、1等級の変動であっても申請が可能なため、柔軟に対応できる制度です。
以下の記事では、月額変更届について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
随時改定がよくわかるガイド
月額変更届の手続き(随時改定)は、一定の要件を満たす従業員を対象にその都度対応が必要になります。
この資料では、随時改定の基本ルールと手続き方法に加え、よくあるミスの対処方法についても解説します。
月額変更届 対応マニュアル
従業員の報酬が変動した際、「月額変更届」の提出が必要となる場合があります。
本資料は、「月額変更届」に関する対応マニュアルです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きの実務にお役立てください。
随時改定3つの条件 かんたん解説ガイド
社会保険料の標準報酬月額を見直す「随時改定」は、実務上、正確な理解が求められます。
本資料は、「随時改定」の対象となる「3つの条件」について、かんたんに解説したガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社の社会保険手続きにおける実務の参考としてご活用ください。
育児休業等終了時報酬月額変更届の対象となる従業員
育児休業等終了時報酬月額変更届の対象となるのは、下記の条件をすべて満たす従業員です。
- 育児休業を終えて職場に復帰していること
- 復帰後も3歳未満の子どもを養育していること
- 育休前と復帰後の報酬に1等級以上の差があること
- 育休終了日の翌日が属する月以降の3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月で支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上あること
パートタイムなどの短時間就労者(週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の労働者)で、いずれの月も支払基礎日数が17日未満の場合には、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均をもとに標準報酬月額が決定されます。
また、従業員本人がこの届出を希望していることも重要なポイントです。この手続きは義務ではなく任意のため、本人の意向がなければ企業側が一方的に手続きすることはできません。
以下の記事では、時短勤務で給料は減るのかについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
育児休業等終了時報酬月額変更届の対象外となるケース
下記に該当する場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届の対象外となります。
- 復職後の給与が育休前と同じ場合
- 基礎日数が3ヶ月とも17日以下(通常の労働者)の場合
- 等級に変動がない場合
この制度は、随時改定(月額変更届)と異なり、2等級以上の変動や3ヶ月とも基礎日数が17日以上の条件を満たさなくても申請できます。
そのため、報酬に実質的な変化がない場合や、復帰後しばらく欠勤が多いことにより基礎日数を満たさない場合は対象外となります。このようなケースにおいては、その後固定給の変動による随時改定、もしくは次の定時決定まで標準報酬月額は変わりません。
以下の記事では、標準報酬月額について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
育児休業等終了時報酬月額変更届の手続き・提出方法
育児休業等終了時報酬月額変更届は、正しく記入・提出しなければ効果を発揮しません。ここでは、手続きについて解説します。
育児休業等終了時報酬月額変更届の記入方法
まず、日本年金機構のホームページから「育児休業等終了時報酬月額変更届」の様式をダウンロードします。提出は事業主が行う必要があるため、被保険者本人からの申し出を受け、必要事項を記入します。
記入例は、下記のとおりです。
.docx-Google-ドキュメント-docs.google.com_.png)
引用:日本年金機構|記入例
- 実際に提出する日を記入します。
- 事業所整理記号、名称、所在地、事業主氏名、連絡先を記入します。
- 申請者の住所、氏名、連絡先を記入します。
- 申出についてのチェックボックスにチェックを入れ、事業主への提出日付を記入します。
- 被保険者整理番号、マイナンバー、氏名、生年月日を記入します。
- 子の氏名、生年月日、育児休業等終了日を記入します。
- 対象となる3カ月の基礎日数、各月の給与額などを記入します。
- 現在の標準報酬月額と適用月、今回の届出による適用月を記入します。
- 給与の締切日、支払日を記入します。
記入ミスを防ぐためにも、提出前に必ず内容を見直し、必要に応じて記入例と照合しましょう。
育児休業等終了時報酬月額変更届の手続き時期・提出先
育児休業等終了時報酬月額変更届は、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターに提出します。添付書類は原則として不要です。ただし、健康保険組合に加入している場合は、独自の添付書類が必要なケースもあるため確認が必要です。
提出期限については速やかに、となっていますので、育休終了日の翌月から3ヶ月目の給与が支払われたあと、すぐに提出できるよう取り掛かりましょう
提出方法は、電子申請・郵送・窓口申請の3つから選べます。給与計算に影響するため、通常の随時改定(報酬月額変更届)と同様に、給与へ反映されるタイミングに間に合うように、早めに準備しましょう。
届出をしない場合の影響
育児休業等終了時報酬月額変更届は任意の手続きです。しかし、提出しないことで、従業員と企業双方に不利益が生じる可能性があります。
育休から復帰後、短時間勤務や残業制限などで給与が減ったにもかかわらず届出をしないと、育休前の報酬をもと計算された社会保険料を支払うことになり、手取り額が大きく減少します。また、企業側も過剰な保険料を負担することになり、コスト増加につながるでしょう。
適切な手続きを行わなければ、従業員のモチベーション低下や労務トラブルの原因にもなりかねません。そのため、従業員の希望がある場合は速やかに届出を行い、適切な社会保険料の適用を行いましょう。
育児休業等終了時報酬月額変更届が反映されるタイミング
育児休業等終了時報酬月額変更届によって決定された標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後、4ヶ月目から適用されます。育休終了後3ヶ月間の給与平均をもとに、標準報酬月額が決定される仕組みになっているためです。
たとえば、3月30日まで育休を取得し、3月31日から復職した場合は6月分の社会保険料から適用されます。一方、3月31日まで育休を取得し、4月1日から復職した場合は7月分から適用となります。
このように、育休終了日が1日違うだけで、適用開始月が1ヶ月ずれることもあるため注意が必要です。正確な適用時期を把握し、スムーズな手続きを心がけましょう。
育児休業等終了時報酬月額変更届の適用期間
育児休業等終了時報酬月額変更届によって決定された標準報酬月額は、改定時期によって有効期間が異なります。具体的には、下記のとおりです。
- 1~6月に改定された場合:同年の8月まで適用
- 7~12月に改定された場合:翌年の8月まで適用
これらは毎年9月に実施される定時決定(算定基礎届)によって、標準報酬月額が見直される仕組みにもとづくものです。そのため、育休復帰後に改定された標準報酬月額は、その後新たに随時改定に該当しない限り、次の定時決定まで適用されます。
ただし、復職後に昇給などにより給与がプラス変動した場合は、通常の随時改定(月額変更届)の対象となることがあります。給与の変化には注意しておきましょう。
育児休業等終了時報酬月額変更届の注意点
育児休業等終了時報酬月額変更届は、本人・事業主ともに社会保険料の負担を軽減できる点がメリットです。一方で、将来的な給付額に影響が出る可能性もあります。
ここでは、届出を行う前に理解しておきたい注意点を詳しく解説します。
老後にもらえる厚生年金の額が少なくなる可能性
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、復職後の給与額に応じて標準報酬月額が下がり、社会保険料の支払額が減少します。その結果、厚生年金の計算基準となる標準報酬月額も下がってしまうため、老後に受け取れる年金額が減少する可能性があります。
時短勤務や残業の制限によって、復職後の給与が育休前よりも大きく下がっている場合、その影響は長期的に続くと考えられるでしょう。
短期的には社会保険料の負担軽減というメリットがありますが、将来の生活設計にもかかわるため、年金への影響についても十分に理解しておくことが大切です。
以下の記事では、厚生年金保険料について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
養育期間標準報酬月額特例で減額リスクを防ぐ
厚生年金の将来受給額が減ってしまうリスクを防ぐためには、養育期間標準報酬月額特例を活用する方法があります。この制度は、3歳未満の子どもを養育している被保険者が利用できる特例です。
特例では、標準報酬月額が実際には下がっていても、育休前の報酬額をもとに厚生年金の金額が計算されます。そのため、保険料の負担を軽減しながらも、将来の年金額には影響を与えないという仕組みです。
ただし、制度が適用されるのは、3歳未満の子を養育している期間に限られます。特例を受けたい場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届とあわせて、速やかに「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する必要があります。
出産手当金・傷病手当金の額が少なくなる可能性
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出して標準報酬月額が下がると、出産手当金や傷病手当金などの健康保険の給付金額にも影響を与える可能性があります。
出産手当金は、出産のために就労できない期間に支給される給付金で、傷病手当金は病気やケガによる休職時に支給されるものです。いずれも直近1年間の標準報酬月額を平均した額の2/3を基準に金額が計算されるため、標準報酬月額が下がれば、その分給付額も減少します。
厚生年金には養育期間特例がありますが、健康保険の給付に関してはこのような特例制度は存在しません。
今後再び出産や病気による休業の可能性も想定し、届出による影響を十分に理解したうえで、提出を慎重に検討しましょう。
育休復帰する従業員に企業が行うべきこと
育児休業から復帰する従業員が安心して働けるように、企業側は復帰前後のサポート体制を整えておくことが大切です。ここでは、企業が行うべき具体的な対応について解説します。
育休復帰前の準備
育児休業からの復帰をスムーズに進めるには、復帰予定日の1〜2ヶ月前に面談を実施し、勤務時間や業務内容など就労条件を確認しましょう。口頭だけでなく、復職前面談シートなどに記録を残しておくことで、トラブル防止にも役立ちます。
面談で決定した内容は、復帰後に所属する部署や上司にも事前に共有し、チーム内での連携を図ることが大切です。従業員が希望する職場での配慮があるなら、本人の意向を尊重し、周囲への理解を促すことで、安心して職場に戻れる環境づくりができます。
育休復帰後の対応
育休復帰後の従業員の給与が、育休前と比べて減少している場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すれば社会保険料の負担を軽減できることを説明しましょう。届出を行わないと、育休前の報酬にもとづいた高い保険料が差し引かれ、手取りが大きく減少する恐れがあります。
ただし、社会保険料が下がる分、将来の厚生年金が減るリスクもあります。そのため、養育期間標準報酬月額特例申出書の活用もあわせて案内するのが賢明です。特例を申請すれば、年金額は育休前の報酬にもとづいて計算されます。
これら2つの届出は、従業員本人の希望で提出できるため、制度の内容を丁寧に説明し、本人の判断に委ねることが大切です。
また、復帰時には育児休業給付金支給申請書や、育児休業等取得者申出書終了届などの手続きも忘れずに行いましょう。
復帰後のサポート
復職後も、従業員への継続的なサポートを行いましょう。
復帰から1〜2ヶ月後を目安に再度面談を行い、働き方や職場環境についての要望や悩みをヒアリングします。面談結果をもとに、業務内容や勤務体制の調整を行うことで、従業員の負担を軽減できます。
また、子どもの体調不良などで突発的な休みが発生する可能性があるため、急な欠勤にも対応できる体制を整えておくことが望ましいです。さらに、時短勤務制度や在宅勤務、フレックスタイム制度の活用を促進し、育児と仕事の両立を支援するのもおすすめです。
育児中の従業員に配慮した職場環境づくりのために、社内研修や情報共有も積極的に行いましょう。
育児休業等終了時報酬月額変更届を活用して、社会保険料を負担を減らそう
育児休業等終了時報酬月額変更届を活用することで、育休復帰後の給与に応じた社会保険料へと見直しが可能です。この制度によって、従業員の手取り減少を防げます。
届出の仕組みや注意点を正しく理解し、必要な手続きをスムーズに行いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
男性・パパ育休の社会保険料免除の期間は?賞与の場合も解説
育休中の社会保険料免除は、育休開始月から終了日の翌日が属する日の前月まで適用されます。また、2022年10月からは月内14日以上の育休取得でも、その月の保険料が免除されるようになり…
詳しくみる育児休業給付金(育休手当)とは?給付の条件や申請方法を解説
育児休業給付金とは、育児休業を取得したときに国から支給されるお金のことです。休業中の収入が確保されることで、従業員は安心して育児に専念できます。パートや契約社員など、有期雇用社員も…
詳しくみる社会保険の健康保険料はどのくらい?計算方法や標準報酬月額の仕組みを解説
健康保険料や厚生年金保険料がどのように計算されるかは、実務に携わる者として当然備えておくべき基礎知識です。社会保険に関する知識が不足したまま給与計算を行うと、従業員から徴収すべき保…
詳しくみる社会保険の定時決定・随時改定とは?概要や適用条件、重なる場合の対応を解説
定時決定と随時改定は、従業員の給与にもとづいて標準報酬月額を見直すための制度です。しかし、制度の違いや適用条件を正しく理解していないと、手続きの遅れや誤りにつながり、従業員の保険料…
詳しくみる社会保険の加入条件・年齢別一覧!40歳~75歳の手続き方法を解説
社会保険の加入条件や手続きは、年齢によって異なります。介護保険をはじめ、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、「従業員が何歳に達したとき、何をしなければならないかがよくわからない」…
詳しくみる「社会保険」に加入すると会社負担の額は実際いくら?
経営者もサラリーマンも、日本人であれば誰もが切っても切れない社会保険。 しかし、「社会保険とは?」と聞かれても、制度の詳細や具体的な負担金額について説明できる方は多くないでしょう。…
詳しくみる