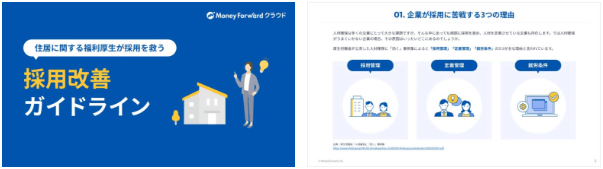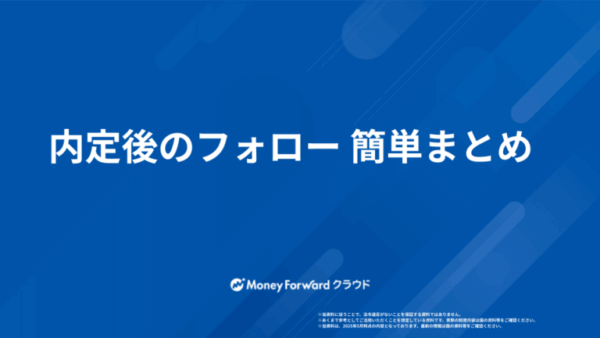- 更新日 : 2025年11月25日
【テンプレ付】採用通知書はいつ届く?内定通知書との違い、書き方を紹介!
採用通知書は、企業が応募者に採用決定を正式に伝えるための書類です。選考過程を経て、企業が採用を決定した場合には、採用通知書が送付されることが一般的です。
内定通知書や労働基準法で義務付けられている労働条件通知書とは役割や法的効力が異なります。これらの違いを理解していないと、後の手続きで認識の齟齬(そご)が生じる原因にもなりかねません。
当記事では、採用通知書の概要や内定通知書との違いなどについて解説します。また、採用通知書の記載事項や便利なテンプレートなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
採用通知書とは?
採用通知書は、企業が応募者に対して「慎重な選考の結果、あなたを採用することに決定しました」という事実を、正式な文書として通知する役割を持ちます。応募者にとっては、選考結果を明確に知るための重要な通知となります。口頭での通知とあわせて、あるいはそれに代わって書面で送付することで、採用の事実を確定させる意味合いがあります。
企業の採用フローでは、書類選考や筆記試験、面接など複数の過程を経たうえで、採用の可否が決定されます。求人への応募者が自社にとって相応しい人材であると判断されれば、晴れて採用となります。
採用通知書はいつ届く?送付のタイミング
採用通知書を送る時期(いつ届くか)に法的な決まりはありません。しかし、最終選考後、企業が採用を決定したら速やかに送付するのが一般的です。 通常、最終面接の結果通知として、1週間から10日以内を目安に発送(またはメール送付)されるケースが多いでしょう。
応募者は他の企業の選考も並行して受けている可能性があり、通知が遅れると、先に連絡があった他社への入社意向が固まってしまうリスクがあります。貴重な人材を確保するためにも、迅速な通知が求められます。
採用通知書に法的効力はある?
採用通知書は法律に規定のあるものではなく、法的効力については、ケースバイケースとなります。応募者の求職への応募に対して、採用通知書が交付されたのであれば、契約の申込みに対する承諾と考えられます。この場合には、両者間で労働契約が成立しており、正当な理由がない限り、契約を解消することはできません。
一方で、内定通知の後に採用通知書が交付されたのであれば、労働契約は内定の時点で成立しており、採用通知書は単なる採用決定の事実を通知する書面に過ぎないことになります。
また、採用内定の意味で採用通知書を交付する場合もあり、実務においては、どのような目的で交付するのかを明確にしなければなりません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
住居に関する福利厚生が採用を救う 採用改善ガイドライン
人材確保は多くの企業にとって大きな課題ですが、そんな中にあっても順調に採用を進め、人材を定着させている企業も存在します。では人材確保がうまくいかない企業の場合、その原因はいったいどこにあるのでしょうか。
3つの原因と、それを解決する福利厚生の具体的な内容まで、採用に役立つ情報を集めた資料をご用意しました。
入社手続きはオンラインで完結できる!
入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?
入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。
内定後のフォロー 簡単まとめ
内定者へのフォローアップは、採用活動における重要なプロセスです。 本資料は「内定後のフォロー」について、簡単におまとめした資料です。
ぜひダウンロードいただき、貴社の取り組みの参考としてご活用ください。
試用期間での本採用見送りにおける、法的リスクと適切な対応
試用期間中や終了時に、企業は従業員を自由に退職させることができるわけではありません。
本資料では、試用期間の基本的な概念と本採用見送りに伴う法的リスク、適切な対応について詳しく解説します。
採用通知書と内定通知書との違い
採用通知書とは別に内定が通知される場合、採用通知書は「採用が決定した事実」を伝える書面になります。これに対し、内定通知書は「労働契約の申込みに対する承諾」にあたります。企業が内定通知を発した時点で労働契約が成立し、法的拘束力が生じる点が両者の大きな違いです。つまり、内定が成立した段階で、すでに労働契約が結ばれていると考えられます。
このように、労働契約の成立に法的効果を持つ内定通知書と、採用決定を知らせる採用通知書では、その法的性質が異なるといえるでしょう。
どちらの書面も採用が決まった応募者に対して送付される任意の書類である点は共通していますが、法的な効力には明確な違いがあるため、混同しないよう注意が必要です。
また、内定の取消しは法律上「解雇」と同様に扱われます。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は「解雇権の濫用」とされ、その取消しは無効となる可能性があります。
なお、採用通知書であっても、文面や条件によっては法的効力を持つと判断される場合があるため、内容には十分な確認が求められます。
採用通知書と労働条件通知書との違い
労働条件通知書は、労働基準法に基づき、企業が労働者に対して明示を義務付けられている「労働条件」を記載した書類です。
労働条件通知書は、労働契約の締結時(通常は入社日までに)に、企業から労働者へ必ず交付(または本人が希望した場合はメールなどの電磁的方法で明示)しなければなりません(労働基準法第15条)。 ここには、賃金、労働時間、休日、就業場所、契約期間など、働くうえでの条件が記載されます。
また、労働条件通知書は労働契約書と一体の書類として作成される場合も多くなっています。このような場合には、「労働契約書 兼 労働条件通知書」などと表記されます。
労働契約締結に際して必要になるという点で、契約締結前の採用決定のみを伝える採用通知書とは異なった書類といえるでしょう。
採用通知書や内定通知書と同時に送付されることも多いですが、法的な義務の有無が決定的な違いです。
採用通知書の書き方は?必須の記載事項と例文
採用通知書の書き方や記載事項にも法的な決まりはありませんが、一般的には以下のような内容を記載します。
- 発行日:書類を作成した日付(和暦または西暦)
- 宛名:応募者の氏名(「様」を付ける)
- 差出人:会社名、代表者名(または採用担当部署名)、住所、電話番号、メールアドレス
- タイトル:「採用通知書」と明確に記載
- 本文(頭語・結語):「拝啓」「敬具」などの一般的なビジネス文書の形式
- 応募への感謝と採用決定の通知:「この度は、弊社の採用選考にご応募いただき、誠にありがとうございました。」といった感謝の言葉に続き、「慎重に選考を重ねました結果、貴殿を採用することに決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。」と採用決定の旨を明記
- 同封書類一覧:入社承諾書、労働条件通知書、添え状など、他に同封した書類があればその一覧
- 提出(返送)が必要な書類と期限:入社承諾書など、応募者に返送してもらう書類がある場合、その旨と提出期限(例:本書類到着後1週間以内)を記載
- 今後の流れ:入社日、入社までの手続き、オリエンテーションの予定など
- 担当者連絡先:本件に関する問い合わせ先(部署名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)
上記のような事項が記載されていれば、文体にも制限はありません。しかし、ビジネス文書であるため、あまり砕けた文体とはしないほうが良いでしょう。そのような採用通知書は、応募者の企業への不信を買うことにもつながりかねません。
採用通知書の作成には、テンプレートの活用も便利でしょう。
採用通知書のテンプレート
採用通知書の作成には、テンプレートの活用も便利です。
以下は、マネーフォワード クラウドが提供する無料で利用可能な採用通知書のテンプレートです。ビジネスで日常的に利用することの多いWordとExcelの形式で提供しているため、どのような企業でも使いやすいテンプレートとなっています。自社に合わせてアレンジしながらご活用ください。
採用通知書の同封書類は?
内定の通知として採用通知書を送付する際は、入社承諾書や雇用契約書(労働契約書)、添え状などの書類が同封されることが一般的です。各書類を簡単な解説とともに紹介します。
入社承諾書・入社誓約書
入社承諾書・入社誓約書は、応募者の入社意志を確認するための書類です。内定承諾書と呼ばれる場合もありますが、書類の目的や内容に大きな違いはありません。採用通知書とは別に送付されることもありますが、双方の手間を省くために同封される場合が多くなっています。
雇用契約書(労働契約書)・労働条件通知書
企業と応募者の間で正式な労働契約を締結するための書類です。 実務上、「労働契約書」と、労働基準法で明示が義務付けられている「労働条件通知書」が一体の書類(例:「労働契約書兼労働条件通知書」)として作成されることもあります。
これらも入社承諾書と同様に、採用通知書に同封されることが一般的です。
身元保証書
採用した本人が会社に損害を与えた場合に備えるための書類です。民法の改正によって、身元保証人が責任を負う上限の金額(極度額)の設定が必要となっており、この定めがない保証契約は無効となります。
添え状(送付状)
添え状(送付状)は、送付する書類の種類や内容、通数などを記載した案内状です。添え状の同封はビジネスにおける一般的なマナーとされています。受け取った側が、同封物を確認しやすくなるため、忘れずに作成し同封しましょう。
返信用封筒
入社承諾書や労働契約書など、応募者に記入・署名捺印のうえで返信してもらう必要がある書類を同封した場合、返信用の封筒も同封します。 返信用封筒にはあらかじめ切手を貼り、返送先の宛名を記入しておくことが望ましい対応です。これにより、応募者の手間が省けるだけでなく、宛名の誤記による郵送トラブルを防ぐことにもつながります。
採用通知書を送付する時の注意点は?
採用通知書の送付方法に決まりはありませんが、確実性とスピードのバランスが重要です。 以前は、重要書類であることから、郵送(配達記録が残る書留や簡易書留)が主流でした。しかし、現在ではスピードを重視し、まずメールで採用決定の旨を通知(PDFを添付)し、後から原本を郵送する方法も増えています。
メールと郵送の併用する
メールと郵送を併用すれば、迅速かつ確実に採用決定を伝えられます。まず採用決定後すぐにメールで採用通知書のPDFファイルなどを送付し、採用決定の旨をいち早く伝えます。これにより、応募者は迅速に結果を知ることができ、他社への意向が固まる前に関係性を構築できます。 その後、入社承諾書や労働条件通知書といった署名・捺印が必要な重要書類の原本を、郵送で送付します。
郵送の場合は書留郵便
採用通知書や同封する労働条件通知書・契約書は、個人情報を含む非常に重要な書類です。郵送する際は、普通郵便ではなく「書留」または「簡易書留」を利用しましょう。 書留郵便は、郵便物の引受けから配達までの過程が記録され、万が一の紛失時には損害賠償が適用されます。また、応募者本人へ対面で手渡されるため、他の郵便物に紛れて見落とされるリスクを防げます。普通郵便では、配達の記録が残らず、「届かない」「受け取っていない」といったトラブルの原因になりかねません。
メールのみの送付も可能
採用通知書をメールで送付することもひとつの方法です。採用通知書や関連書類をPDF化し、メールで送付する企業も増えています。 ただし、メールで送付する場合には、確実に相手に届くように迷惑メールとされないような対策(件名の工夫など)を施しましょう。また、応募者に対してメールで送付する旨を事前に伝えておくことも、見落としを防ぐために必要です。添付ファイルにはパスワードを設定するなど、セキュリティ面にも配慮してください。
ハローワーク(公共職業安定所)経由の場合
ハローワーク(公共職業安定所)の紹介を通じて応募者を採用した場合、応募者本人への通知とは別に、ハローワークへの報告義務が発生します。 企業は、ハローワークに対して所定の「採用結果通知書(採否通知書)」を提出(またはハローワークのシステム上で連絡)しなければなりません。これは、ハローワークが求職者の就職状況を把握し、失業給付などの行政サービスを適切に管理するために必要です。 応募者本人への採用通知書の送付は、このハローワークへの報告とは別個に、通常どおり行います。
採用通知書がない、もらえない時の応募者・企業側の対処法
「採用の連絡は口頭であったものの、採用通知書が届かない」「そもそも採用通知書は発行しなくてもよいのか」といった疑問は、応募者側・企業側双方で生じがちです。ここでは、採用通知書がない場合の法的な扱いと、それぞれの立場で取るべき対処法を解説します。
応募者側:「採用通知書がない」のは違法?
採用通知書の発行は法律上の義務ではないため、採用通知書が「ない」こと自体は違法ではありません。口頭で採用を伝え、通知書の発行を省略する企業もあります。 ただし、労働契約を結ぶ際の「労働条件通知書」の交付は法律で義務付けられています。採用通知書がなくても、労働条件を明記した書面(または電子データ)は必ず受け取る必要があります。
応募者側:「採用通知書のもらい方」は?
採用の連絡(例:電話)はあったものの、採用通知書が送られてこない場合、まずは企業の採用担当者にメールや電話で、選考結果の通知と今後の手続きについて問い合わせましょう。 「先日お電話で採用のご連絡をいただきました件ですが、今後の手続きについて、書面(またはメール)でも詳細をいただけますでしょうか」と丁寧に確認します。
あわせて、労働条件通知書の発行予定も確認しておくと入社までの流れが明確になります。
企業側:「採用通知書は不要」と判断するリスク
企業が口頭連絡のみで採用通知書の発行を省略すると、応募者に不安を与えるうえ、「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。
採用の事実や入社日、給与などの重要条件は、認識の齟齬(そご)を防ぐためにも、必ずメールや書面など「記録に残る形」で通知することが賢明です。
採用通知書を正しく理解し円滑な入社手続きを
採用通知書は、応募者に採用決定を伝える通知です。送付する目的やタイミングによって、法的効力の有無は様々ですが、応募者の信頼を獲得し、入社意欲を高めるために、速やかかつ正確に発行すべき文書と言えるでしょう。
特に、法的な拘束力が生じる「内定通知書」や、交付義務のある「労働条件通知書」との違いを社内で明確に区別し、混同しないよう運用します。送付時期や同封書類にも配慮し、必要に応じてテンプレート(雛形)も活用しながら、応募者が安心して次のステップに進めるよう、丁寧な実務を心がけましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
採用管理とは?業務内容からExcelでの管理やシステム(ATS)の選び方
採用管理とは、企業の成長に必要な人材を確保するため、候補者の募集から選考、内定、入社までの一連のプロセスを計画し、効率的・戦略的に実行・最適化する活動全般を指します。優れた採用管理…
詳しくみる心理的安全性が高い職場とは?メリット・特徴・作り方をわかりやすく解説
職場で安心して発言できる雰囲気は、業務効率やチームの成果に大きな影響を与えます。そこで注目されているのが「心理的安全性」です。これは、発言や提案が否定されたり評価に響いたりすること…
詳しくみる短期離職は人生終わりと言われる理由は?面接で後悔しないポイントを20代・30代向けに解説
短期離職してしまうと「もう自分の人生は終わりだ…」と不安に感じる人は少なくありません。 たしかに、入社後すぐの退職は転職活動で不利になるなどネガティブな影響もあります。しかし、短期…
詳しくみる中堅社員のモチベーション低下を防ぐには?キャリア研修と役割の与え方を解説
「中堅社員のモチベーション低下をどうにかしたい」とお考えではありませんか。その解決の鍵は「キャリア研修」と「役割の与え方」の見直しにあります。企業の成長に欠かせない中堅社員が、再び…
詳しくみる入社式とは?内容や開催時期および準備することを解説!【テンプレート付き】
入社式は新入社員を歓迎し、新たな職場でのスタートを祝福する特別な式典です。この重要なイベントの成功には、準備と計画が欠かせません。本記事では、入社式の内容や開催時期、参加者と企業の…
詳しくみる従業員のストレスカウンセリング:受けるサインと相談先・費用・企業対応
ストレスは従業員誰にでも起こるものですが、その影響を放置すると心身の健康を大きく損ない、組織全体の生産性低下や休職・離職につながることになりかねません。ストレスが原因で従業員の業務…
詳しくみる