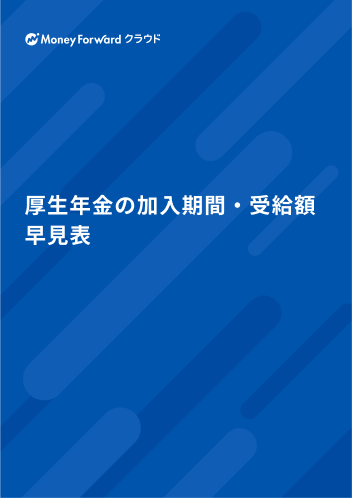- 更新日 : 2025年10月31日
厚生年金の受給に必要な加入期間 – 10年未満の場合はどうなる?
日本の公的年金制度は2段階です。会社勤めで厚生年金保険に加入していた方は、国民年金の制度で受け取れる老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金が上乗せされます。
国民年金の支給額が年間約78万円のため、厚生年金がいくらもらえるか気になる方も多いでしょう。今回は、厚生年金の受給に必要な加入期間や受取れる金額について解説します。
目次
厚生年金の受給に必要な加入期間は10年
日本は「国民皆年金」制度を導入しています。したがって、すべての国民は原則として「国民年金」に加入します。40年間保険料を納付した場合、満額の年間約78万円が「老齢基礎年金」として支給されます。受給開始年齢は、原則65歳からです。
しかし、「老後に必要な貯蓄は2,000万円」といった話が話題になったように、老齢基礎年金だけでは十分ではないと感じる方も多いでしょう。
日本の年金制度は3階建てになっており、1階部分は国民年金の制度から支給される老齢基礎年金です。会社員や公務員等が加入する厚生年金保険の制度(2015年10月から公務員なども加入)から支給される老齢厚生年金は、2階部分にあたります。
2階建ての公的年金制度の仕組みに加え、さらに3階部分には確定給付企業年金や確定拠出年金、厚生年金基金などの企業独自で加入する年金があります。そのほかiDeCoや民間の保険会社で加入した個人年金などの個人の意思で加入する年金を加えると、4階建ての方もいるのではないでしょうか。
会社勤めをしていた方は、老後に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取るのが一般的な年金の形です。そのため、転職などで無職の期間があったり、勤め人から独立したりといった理由で、厚生年金保険の加入期間が短い方は、「厚生年金はもらえないかもしれない」と不安になるかもしれません。
65歳から支給される老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格である「10年間の受給資格期間」があれば、厚生年金保険の加入期間が1カ月でも受給できます。会社員や公務員等が加入する厚生年金保険には、国民年金と厚生年金の加入期間の両方が含まれますので、会社員であった期間が10年に満たないからといって、老齢厚生年金の受給ができなくなるわけではありません。
【年金の受給イメージ】
| 年金の種類 | 第1号被保険者 (自営業等) | 第2号被保険者 (会社員/公務員等) | 第3号被保険者 (被扶養配偶者) |
|---|---|---|---|
| 1階: 国民年金 | 老齢基礎年金: 年間約78万円(満額) | ||
| 2階: 厚生年金保険・共済組合 | ー | 老齢厚生年金: 収入と加入期間による | ー |
| 3階: 確定給付企業年金等 | 個人型確定拠出年金 | 企業型確定拠出年金 確定給付企業年金等 | ー |
- 国民年金の受給資格期間が10年以上
- 国民年金の受給資格を満たしていれば、厚生年金保険の加入期間応じて上乗せ
なお、以前は受給資格期間は最低25年とされていました。2017年8月より社会保険改革が行われ、年金を受給するのに必要な加入期間が25年から10年へと引き下げられています。
参考:必要な資格期間が25年から10年に短縮されました|日本年金機構
受給の条件である「受給資格期間」に含まれるもの
受給資格期間には、保険料を納付した期間に合わせ、以下のような免除期間も含むことができます。
- 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
- 厚生年金保険(船員保険も含む)、共済組合などの公的年金制度の加入期間
- 合算対象期間
合算対象期間とは、「カラ期間」と呼ばれるもので、過去に国民年金に加入していない場合でも、受給資格期間に含むことができる期間をいいます。具体的には、以下の期間が該当します。
- 昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間
- 昭平成3年3月以前に学生だった期間
- 昭海外に住んでいた期間
- 昭脱退手当金の支給対象となった期間
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
算定基礎届の手続き完全ガイド
算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。
手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。
社会保険・労働保険の実務完全ガイド
これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。
本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。
健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック
健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。
年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。
社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選
社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。
本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。
厚生年金への加入期間が10年未満の場合はどうなる?
会社員の期間が短く、厚生年金保険に加入していた期間が10年未満でも、前述のように国民年金の加入期間と合わせて10年を超えていれば、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受け取れます。
しかし、すべての加入期間を合わせても、保険料を納付した期間が10年に満たず、年金がもらえないのではと不安になる方もいるかもしれません。その場合は、受給資格期間に含められる期間があるかどうか、以下を参考に確認してみましょう。
免除期間やカラ期間も計算する
受給資格期間には、上述のように保険料を納付した期間だけではなく、免除期間や合算対象期間(カラ期間)も含むことができます。たとえば、大学生等は20歳から社会人になるまで、免除申請をする方もいます。また、海外に居住していた期間も含むことができます。保険料を免除してもらっていた期間や、合算対象期間になる期間に心当たりがないかもよく思い出し、対象となる期間があればすべて合算して、10年という受給資格期間を満たすのか、もう一度確認してみましょう。
過去にさかのぼって保険料を納付する
あともう少しにも関わらず、受給資格期間が足りないという方は、過去にさかのぼって保険料を納付することで、受給資格を満たすことができる場合もあります。過去2年間であれば支払い忘れた国民保険の保険料を納付することが可能です。
なお、過去には特例として「10年後納制度」及び「5年後納制度」が実施されていましたが、前者は2015年、後者は2018年をもって終了しています。
60歳以上から加入期間を増やす
国民年金や厚生年金保険は、原則として20歳から60歳の間に加入するものですが、未納や未加入などで受給資格期間が満たない方は、本人の申し出により60歳以上でも保険料を納めることができる制度があります。
国民年金の任意加入制度
60歳以上65歳未満の方が対象です。申し出により、国民年金の保険料を納付し、受給資格期間を増やすことができます。なお、制度の利用には「老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない」「申し出時点で厚生年金保険に加入していない」などの条件があります。
65歳まで任意加入してもなお、65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、1965年4月1日以前生まれの方であれば、受給資格期間を満たすまで任意加入が可能です。
厚生年金保険の高齢任意加入制度
会社員でも原則として70歳になると加入資格を喪失します。しかし、70歳になっても受給資格期間が10年に満たない方は、在職中であれば申し出により期間を満たすまで厚生年金保険に加入することが可能です。ただし、この場合、勤務先の同意が得られないと保険料が労使折半とならず、全額自己負担となることに注意しましょう。
厚生年金の注意点
国民年金から支給される老齢基礎年金の計算方法はシンプルです。40年間納付して満額で年間約78万円(令和4年の満額777,800円)。保険料の納付期間が短くなれば、それに比例して年金額も減少します。仮に、保険料納付期間が10年(120カ月)とすれば、年金額は年間19.4万円となります。
一方、厚生年金は、保険料を納付した期間にこれまでの収入額を乗じて年金額を算出します。受給資格期間が10年あれば、厚生年金保険の加入期間が1カ月でも老齢厚生年金が支給されます。しかし、金額は納めた保険料に応じたものになるため、厚生年金保険の加入期間が15年や20年と短い場合は、受け取れる年金額が少なくなります。また、独身か加給年金の対象者となる配偶者や子供がいるかによっても年金額は変動します。
老後に受け取る年金額をシミュレーションする際には、受給資格期間を満たしたかどうか以外に、自身が保険料を納付した期間と、老齢厚生年金の計算方法を踏まえて考える必要があります。
厚生年金の支払い期間が10年、15年や20年と短い場合
老齢厚生年金の受給金額は、以下の式で算出されます。
このとき、年金額のおおもとになるのは「報酬比例部分の年金額」です。これは、給与等の報酬をもとにした「平均標準報酬月額」や「平均標準報酬額」に既定の式を当てはめて計算します。原則となる老齢厚生年金の計算式からシミュレーションしてみましょう。
2003年3月以前
2003年3月以後
たとえば、月額の報酬が30万円前後の会社員で平均標準報酬月額を「30万円」とした条件(2003年3月以後に社会人になったと仮定)で、納付期間ごとに老齢厚生年金の受給額を算出してみましょう。
| 厚生年金保険の納付期間 | 老齢厚生年金の支給額 |
|---|---|
| 10年(120カ月) | 197,316円(月額16,443円) |
| 15年(180カ月) | 295,974円(月額24,664円) |
| 20年(240カ月) | 394,632円(月額32,886円) |
老齢厚生年金は、加入期間の収入額が大きく、納付した期間が長いほど受給金額も大きくなることがわかるでしょう。
配偶者がいる場合は厚生年金の受給金額が変わる?
厚生年金保険に加入している方が、一定の条件を満たした場合、老齢厚生年金の受給金額が上乗せになります。これを、加給年金額といいます。
加給年金額の対象となるのは、厚生年金保険(または共済組合等)の被保険者の期間が原則として合計で20年以上ある方です。本人が65歳に到達した時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分が受給できる年齢に達した時点)において、生計を維持している配偶者や一定の条件を満たす子供がいる場合に、年金額が加算されます。
配偶者は、65歳未満であることが条件です。上乗せされる老齢厚生年金は年額223,800円(令和4年時点)となっています。さらに、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、33,100円から165,100円の特別加算も加わります。
加給年金額は、「配偶者が65歳に達した場合」「配偶者の被保険者期間が原則20年以上ある老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を有する場合」「障害年金を受けている間」は、支給が停止されます。また、本人の加給年金額の停止後、一定の条件を満たした場合には、配偶者の老齢基礎年金額に加算がつく振替加算があります。
受給資格期間が10年あれば厚生年金は受取れる
国民年金と厚生年金保険の加入期間が10年以上であれば、老後に老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方を受け取ることが可能です。もし10年に満たない場合でも、任意加入制度を活用することによって、年金を受け取れるようにする方法があります。
受給資格期間には、保険料を納付した期間だけでなく、免除期間や合算対象期間なども含まれますので、自身の期間がどれくらいあるかを確認し、老後の年金をシミュレーションしてみるのがいいでしょう。
よくある質問
厚生年金の受給に必要な加入期間は何年ですか?
受給資格期間10年という、老齢基礎年金の受給条件を満たしていれば、厚生年金保険の制度で支払われる「老齢厚生年金」を受け取れます。受給資格期間には保険料を納付した期間のほか、免除期間なども含まれます。詳しくはこちらをご覧ください。
厚生年金保険の加入期間が10年未満の場合、厚生年金は受給できませんか?
国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせて10年以上で、老齢厚生年金の受給資格を満たすことになります。また、10年に満たない場合でも、60歳以降に任意加入制度を利用して加入資格を満たすことが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
厚生年金の関連記事
新着記事
役員社宅を賢く経費にする方法は?節税メリットから賃料計算まで徹底解説
Point役員社宅の経費化とは? 役員社宅は、賃料相当額を正しく計算・徴収すれば合法的に経費化でき、大きな節税効果があります。 会社負担の家賃は損金算入可能 賃料相当額の計算が必須…
詳しくみる組織開発とは?人材開発との違いや代表的な手法、成功に導くプロセスを徹底解説
Point組織開発とは、組織全体の関係性と機能を高める取り組み。 組織開発は、人と人の相互作用を改善し、変化に強い組織をつくるプロセスです。 関係性と対話に焦点 個人でなく組織全体…
詳しくみるキャリアパス面談で何を話すべきか?理想の将来を描き自己成長につなげるための完全ガイド
Pointキャリアパス面談とは、将来像を言語化し成長戦略を描く対話です。 キャリアパス面談は、理想の将来と市場価値向上を実現するための戦略設計の場です。 将来像と現状の差を明確化 …
詳しくみるストレスチェック結果の提供同意書とは?取得のタイミングや注意点を徹底解説
Pointストレスチェック結果の提供同意書とは、結果を事業者へ共有するための法定手続きです。 ストレスチェック結果は、本人の明示的同意がなければ会社は取得できません。 事前同意は無…
詳しくみるストレスチェックの方法とは?実施手順から事後措置までの実務を徹底解説
Pointストレスチェック方法とは、労働者の心理的負担を測定し、職場改善につなげる制度。 ストレスチェックは、正しい手順と事後措置まで実施して初めて有効です。 年1回以上の実施が原…
詳しくみるストレスチェック報告書の提出期限や書き方は?労働基準監督署への報告義務と作成手順を解説
Pointストレスチェック報告書とは、実施結果を労働基準監督署へ報告する法定書類です。 ストレスチェック報告書は、常時50名以上の事業場が年1回実施後、遅滞なく提出します。 対象は…
詳しくみる