- 更新日 : 2025年11月19日
退職時の有給買取は拒否できる?検討した方が良い場合や計算方法を解説
労働基準法上、有給買取は禁止されていますが、退職時の有給買取は特に禁止されていません。
そこで本記事では、人事担当者やビジネスパーソンが知りたい退職時の有給買取に関する疑問を解消するため、下記の内容を詳しく解説します。
- 有給買取を検討すべき状況
- 有給買取の具体的な計算方法
- 有給買取と有給消化との比較
- 従業員が有給買取を拒否された場合の対処法
退職時の有給買取を正しく理解し、適切な選択をするためにぜひ参考にしてください。
目次
退職時の有給買取は拒否できる?
従業員から退職時に有給買取を希望された場合、会社が拒否しても違法とまではいえません。しかし、買取拒否によって従業員とのトラブルの発生も想定されるでしょう。
そのため、会社は労働者が退職日までに有給休暇を消化できるよう配慮する義務があります。
ただし、有給買取を希望された場合、会社は残りの有給休暇日数を把握し、退職日までの期間で消化可能かどうかを検討する必要があります。
有給消化が難しいときに、有給買取という選択肢を検討します。
例外として退職時の有給買取は適法
原則として、有給休暇の買取は法律で禁止されています。
これは、有給休暇が労働者の心身のリフレッシュを目的としており、金銭で代替するのを避けるためです。
しかし、退職時の有給買取は、例外として適法とされています。
これは、退職によって有給休暇を取得する機会が失われるため、その補償として金銭で清算するのが合理的と判断されるためです。
具体的には、退職日が確定しており、残りの有給休暇日数を消化するのが物理的に不可能である場合、会社は労働者と合意のうえで、未消化の有給休暇を買い取れます。
この場合、買取金額は、通常の賃金と同様に計算します。
ただし、会社が就業規則等で有給買取に関する規定を設けている場合は、その規定に従って処理しましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド5選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
労働時間管理の基本ルール【社労士解説】
多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。
労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。
有給休暇管理の基本ルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
年次有給休暇管理帳(ワード)
従業員の年次有給休暇の管理は、適切に行えていますでしょうか。
本資料は、すぐにご利用いただけるWord形式の年次有給休暇管理帳です。ぜひダウンロードいただき、従業員の適切な休暇管理にご活用ください。
休日・休暇の基本ルール
休日・休暇の管理は労務管理の中でも重要な業務です。本資料では、法令に準拠した基本のルールをはじめ、よくあるトラブルと対処法について紹介します。
休日・休暇管理に関する就業規則のチェックリスト付き。
時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール
年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。
本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。
退職時の有給買取を検討した方が良いケース
退職時の有給買取は、必ずしも全てのケースで推奨されるわけではありませんが、特定の状況においては検討する価値があります。
退職時の有給買取を検討した方が良いケースは、下記の通りです。
- 会社が退職の推奨をしている
- 退職直前で有給消化が難しい
- 引き継ぎが不十分になる
- 退職が定年や契約満了による場合
次項で、それぞれのケースについて詳しく解説します。
会社が退職の推奨をしている
従業員に対し退職勧奨を行っている場合、有給買取を検討する価値があります。
会社都合による退職の場合、通常よりも手厚い退職条件が提示されることがあり、その中に有給買取が含まれているケースも少なくありません。
会社が退職を推奨する背景には、業績不振による人員削減や事業の縮小など、さまざまな理由が考えられます。
このような状況下では、従業員は今後の生活設計に不安を感じる場合もあるでしょう。
しかし、企業が有給休暇の買取を実施することで、従業員の退職後の生活費の一部に充ててもらうことができます。
会社側にとっても、円満な退職手続きを進めるうえで、有給買取は有効な手段となり得ます。
退職直前で有給消化が難しい
退職日が目前に迫っており、残りの有給休暇を消化する時間がない場合も、有給買取を検討すべきです。
有給休暇は労働者の権利ですが、退職日を過ぎると権利が消滅してしまいます。
たとえば、退職日までの期間が短く、業務の引き継ぎなどで休暇を取得する余裕がない場合や、まとまった休暇を取得すると業務に支障が出る可能性がある場合などが該当します。
このような状況では、有給休暇を消化する代わりに企業側で買い取り、金銭的な補償が受けられるようにしましょう。
引き継ぎが不十分になる
退職前に十分な引き継ぎ期間を確保できない場合も、有給買取を検討する理由となります。
業務の引き継ぎは、後任者へのスムーズな業務移行のために重要です。
たとえば、後任者の決定が遅れたり、引き継ぎに必要な資料の準備が間に合わなかったりする場合、有給休暇を取得すると引き継ぎ作業に支障が出る可能性があります。
このような状況では、有給休暇を買い取り、退職する従業員には引き継ぎ作業に専念してもらうことで、会社への責任を果たすとともに、後任者も安心して業務に取り組めるでしょう。
退職が定年や契約満了による場合
定年退職や契約満了による退職の場合も、有給買取を検討する価値があります。
これらの場合、退職日は事前に確定しており、計画的に有給休暇の消化が可能です。
しかし、長年の勤務に対する慰労の意味合いや、退職後の生活設計の支援として、会社が有給買取を行う場合があります。
退職時の有給買取の計算方法
退職時の有給買取の計算方法は、通常の有給休暇を取得した場合の賃金計算方法と基本的に同じです。
具体的には、下記のいずれかの方法で計算します。
どの方式を用いるかは、就業規則等で定められている場合、それに従いましょう。
定めがない場合は、労働者に有利な方法で計算するのが一般的です。
それぞれの計算方法の詳細は、「有給休暇の買取ができるパターンと計算方法を解説」をご覧ください。
退職所得の受給に関する申告書が必要
退職に伴い有給休暇の買取が行われた場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要となる場合があります。
これは、税務署に対して、退職によって得た所得(この場合は有給買取による金銭)を申告するための書類です。
退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、源泉徴収される所得税額が正確に計算できるため、過不足なく納税できます。
具体的には、退職手当等を含む退職所得の金額を計算し、必要な控除額を差し引いたうえで所得税額を算出します。
もし申告書を提出しない場合、本来よりも多くの所得税が源泉徴収される可能性があるため注意が必要です。
退職時の有給休暇は退職所得として処理
退職時に買い取られた有給休暇は、給与所得ではなく「退職所得」として処理します。
これは、退職によって初めて発生する所得であり、在職中の労働の対価として支払われる給与とは性質が異なります。
退職所得として扱えば、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
具体的には、退職所得控除という制度があり、一定額まで所得税が控除されます。
これにより、給与所得として扱う場合よりも、税負担が軽減します。
退職時の有給買取は、税務処理によるトラブルを避けるためにも、税制上の取り扱いを理解しておきましょう。
有給消化と有給買取はどちらが得なのか
有給休暇は従業員に「取得してもらう」のが大前提であるため、可能な限り有給消化をすすめていきましょう。
ただし、退職直前など、物理的に有給消化が難しい場合には、有給買取を検討します。
有給消化のメリットは、休暇をして心身のリフレッシュを図れることです。
具体的には、退職後の新たな生活に向けて準備期間を設けたり、旅行などでリフレッシュしたりできます。
一方、有給買取は、金銭的な補償を得られるメリットがありますが、休暇を取得する機会を失います。
従業員が退職時の有給買取を拒否された際の対処法
従業員が退職時の有給買取を拒否された際の対処法は、下記の通りです。
- 退職日を有給消化後とする
- 退職に応じない
次項で、それぞれの対処法について詳しく解説します。
退職日を有給消化後とする
会社が有給買取を拒否した場合は、退職日を有給休暇の消化後に変更する旨を会社に伝えましょう。
有給休暇は労働者の権利であり、会社は原則として有給休暇の取得を拒否することはできません。
具体的には、退職日までの期間に未消化の有給休暇日数を含める形で退職日を調整すれば、実質的に有給休暇を消化できます。
たとえば、退職日まで残り10日間の有給休暇がある場合、退職日を10日後に変更すれば、給与を受け取りながら休暇を取得できます。
退職に応じない
会社から退職勧奨を受けており、有給買取を拒否された場合、従業員は退職に応じないという選択肢を取ることも可能です。
退職勧奨は、会社から従業員に対して退職を促す行為であり、法的な強制力はありません。
したがって、従業員は退職勧奨に応じるかどうかを自由に選択できます。
もし、会社側が強引に退職を迫るような場合は、労働基準監督署などへの相談も検討しましょう。
有給休暇の買取を拒否されたことと併せて、不当な扱いを受けている可能性がある場合は、専門機関に相談すれば、適切なアドバイスや支援を受けられます。
退職時の有給買取を正しく理解し、適切な選択をしよう!
退職時の有給買取は、従業員と企業双方にとって重要な問題です。
企業側としては、労働基準法に則り、従業員の権利を尊重しつつ、円滑な退職手続きを進める必要があります。
本記事では、退職時の有給買取に関する法的な側面、検討すべきケース、計算方法などを解説しました。
これらの情報を踏まえ、企業は有給買取に関する社内規定を明確化し、従業員への周知徹底を行いましょう。
また、個々の状況に応じて、従業員と十分にコミュニケーションを取り、双方にとって納得のいく形で柔軟に退職手続きを進めましょう。
とはいえ、有給買取は例外的な措置であるため、基本的には有給消化を推奨する姿勢が大切です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年末調整における給与所得金額の計算方法は?計算ツールや早見表も
年末調整においては、所得税の過不足がないか調整するために給与所得の申告が必要です。また、給与所得金額を計算する際は収入金額から給与所得控除額を差し引く必要があります。 本記事では、…
詳しくみる有給と残業の相殺は違法?原則と例外、悩んだ場合の対処法をわかりやすく解説
有給休暇を取得した日や週に残業をした従業員がいる場合、正しい残業時間の計算方法を理解していないと余分に残業代を支給することになります。また、残業時間が長いことを理由に相当分の有給休…
詳しくみる【各種ひな形付】育休中の給与は?賞与(ボーナス)やもらえるお金を解説
育休・産休期間中はほとんどの場合、給与が支払われません。この記事では、収入減を補うために支給される「育児休業給付金」について、給与の何割程度が支給されるのか、支給期間はいつまでかと…
詳しくみるアルバイト・パートの給与計算方法は?確認事項と注意点を解説
アルバイトやパートの給与計算は、就業規則・給与規程・タイムカードなどの勤務管理書類を確認しながら進めます。時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた際は、アルバイト・パートに対しても社…
詳しくみる残業代にも所得税はかかる?仕組みと計算方法をわかりやすく解説
残業代の所得税に関する取り扱いは複雑で、とくに残業代の計算や未払い分の処理においては、適正な税務対応が求められます。 本記事では、残業代が所得税の課税対象となる仕組みや具体的な計算…
詳しくみる香川県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も
香川県でビジネスを展開する企業にとって、給与計算は従業員の満足度と企業の信頼性を左右する重要な業務です。しかし、税務や社会保険の複雑な手続きを自社で管理するのは大きな負担となります…
詳しくみる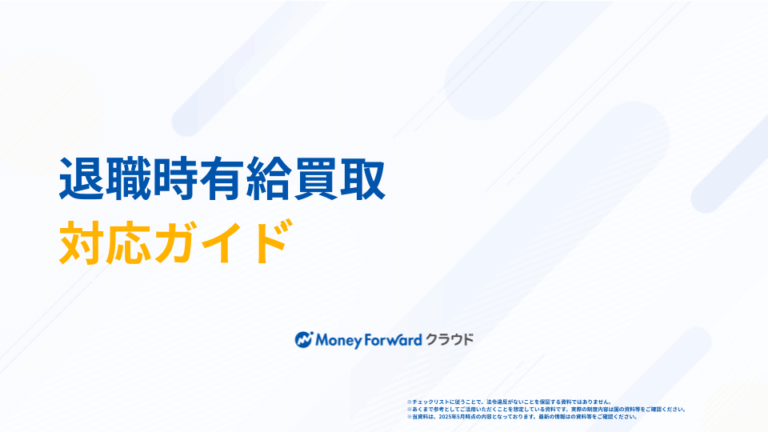


-e1761054979433.png)

