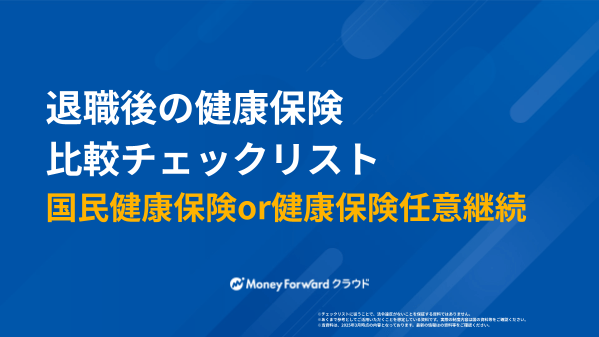- 更新日 : 2025年3月3日
退職後の健康保険 – 国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較
国民皆保険制度を採用している日本では、会社を退職したら、なんらかの公的保険に加入しなければいけません。退職後は国民健康保険に加入することもできますが、会社の健康保険を継続する選択肢もあります。
ここでは、国民健康保険と健康保険任意継続制度の違いをまとめるとともに、任意継続制度で必要な会社側の手続きについても解説します。
目次
国民健康保険について
日本の健康保険制度は「国民皆保険」が原則のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく必ず公的医療保険制度に加入しなければなりません。国民健康保険については、外国籍の方であっても、在留期間が3ヵ月以上の場合には加入が義務付けられてます。
会社員以外の自営業者やフリーランスの働き方をする方、無職の方が加入する一般的な医療保険制度は、市区町村によって運営される「国民健康保険」です。国民健康保険は、加入者の病気や怪我、出産時の一時金や、死亡時の葬祭費などが支給されます。すでに会社の健康保険に加入している方や、75歳以上の方、生活保護受給者などは、国民健康保険に加入する必要はありません。
- 会社等の健康保険、健康保険組合、公務員や私立学校の共済組合に加入している方とその扶養家族(任意継続含む)
- 船員保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
- 生活保護を受給している方
会社に在職中は健康保険に加入していた方でも、退職と同時に資格を喪失すれば、切り替え手続きを行い国民健康保険に加入しなければいけません。
ただし、健康保険の任意継続の手続きをした場合や、配偶者などの被扶養者になる場合は、退職日の翌日付でその手続きを行えば、国民健康保険に加入する必要はなくなります。
健康保険任意継続制度について
健康保険任意継続制度とは、退職者が必要な手続きを行うことで、退職後2年を上限として会社の健康保険に引き続き加入できる制度のことです。
任意継続被保険者は、任意継続中もこれまでと同様の給付を受けることができます。また扶養に入っていた家族も、引き続き扶養者として健康保険の加入が可能です。ただし、出産手当金や傷病手当金などの一部の給付は受けることができません。また、任意継続保険の手続きをしたとしても、保険料の滞納が1日でもあれば資格を失う点に注意が必要です。
任意保険継続の保険料は、会社との折半ではなく全額自己負担です。それでも、場合によっては国民健康保険よりは保険料が抑えられるケースがあります。
国民健康保険は、前年度の所得をもとに保険料を算出します。そのため、退職時の年の給与所得が高い場合は、翌年の国民健康保険の保険料が跳ね上がることとなり、退職後の家計を圧迫することになりかねません。任意継続被保険者の場合、退職時の標準報酬月額を基準としますが、一定の上限額が定められているため、所得額によっては任意継続を選択するほうが保険料を安く抑えられることがあります。
任意継続被保険者となってから2年間を経過すると被保険者の資格を喪失しますので、被保険者は保険証を返納し、国民健康保険への加入手続きが必要です。なお、任意継続被保険者となったとしても、再就職した場合には任意継続被保険者の資格を喪失し、会社の加入する健康保険や健康保険組合の被保険者となります。
国民健康保険と健康保険任意継続制度のメリットデメリット比較表
| 国民健康保険 | 健康保険任意継続制度 | |
|---|---|---|
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
国民健康保険と健康保険任意継続制度を比較すると、所得や扶養家族の状態によって、メリット・デメリットが変動します。国民健康保険は前年度の所得をもとに計算されるため、退職の年の保険料が高額になる可能性がありますが、その後は所得に応じた金額となります。一方、健康保険任意継続制度では退職の2年間はどれだけ所得が減少しようと、保険料に影響はありません。
また、扶養者がいるかどうかも重要な要素になるでしょう。健康保険任意継続制度に保険料の会社負担分はありませんが、保険料が変わることなく扶養者も引き続き健康保険に加入できます。したがって、扶養者の数が多いほど任意継続を選択したほうがメリットが大きくなることがあります。
保険料の会社負担分がなくなる点をデメリットに感じるかもしれませんが、そもそも国民健康保険はすべて自己負担であり、扶養家族がいるとその数に応じて保険料が増えていくことになります。任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するかを判断する場合には、扶養家族の有無、前年度の収入、再就職の見込みなどをトータルで考えて検討するのがポイントです。そのため、2年間の計画をある程度立てたうえで、健康保険任意継続制度を選択するのがいいでしょう。
ケーススタディ:退職後の健康保険はどちらを選ぶべきか?
退職後の健康保険選択は個々の状況によって最適解が異なります。以下、典型的なケース別に国保と任意継続のどちらが適しているかを検討するシナリオを紹介します。
以下のケーススタディからも分かるように、退職後の健康保険選択は世帯構成と収入見通しによって最適解が変わります。
人事担当者は退職者からヒアリングを行い、上記シナリオを参考にしながら最適な制度を提案すると良いでしょう。
※(免責)下記はあくまで参考程度としていただき、個別の状況を基にご決定ください。
ケース1:扶養家族(配偶者・子)がいる場合
⇒ 任意継続が有利なケースが多い。
扶養されていた配偶者やお子様がいる退職者の場合、任意継続を選ぶことで退職後も一つの保険料で家族全員がカバーされます。仮に在職中の標準報酬月額が高く保険料も高額でも、家族について追加負担が発生しない点は大きなメリットです。
一方国保に切り替えると、配偶者や子供もそれぞれ国保に加入することになり、世帯人数分の均等割額が加算され保険料総額が膨らみます。
特に退職前の収入が高かった場合、初年度は国保保険料が家族合算で大幅に高くなる傾向があります。
例えば夫婦と子1人扶養のケースでは、任意継続なら本人の年額約36万円程度で済むところ、国保では世帯年収と3人分の均等割から計算され50万円超となる可能性もあります(自治体により異なる)。扶養家族の収入が少なく国保加入時に減免措置が受けられる場合もありますが、一般的には扶養家族がいる場合は任意継続の方がトータルの保険料負担を抑えやすいと言えます。ただし、任意継続は2年で終了するため、その後は改めて国保へ加入する手続きを念頭に置いておきましょう。
ケース2:単身者・扶養家族がいない場合
⇒ 収入見通しによって判断。
一人暮らしなど退職者本人のみが加入対象の場合、退職後の収入状況によって選択が分かれます。退職後すぐに再就職の予定がない、あるいは年金・蓄えで生活し当面収入がない場合、国保への切り替えを選ぶ方が2年目以降の保険料負担が軽くなる可能性があります。初年度こそ前年所得に基づく国保保険料の負担がありますが、翌年度以降は所得ゼロ(または減少)に応じて保険料も大きく下がり、任意継続を2年間続けるより総額で安くなるケースが多いです。
特に退職時の標準報酬が高かった人ほど、退職後収入が無ければ国保2年目からの保険料減少メリットが大きくなります。
一方、退職後も一定の収入(例えば高額の企業年金や不動産収入等)が見込まれる場合は、国保では翌年もその所得に応じた保険料を課されるため、任意継続を利用して2年間保険料を固定した方が有利になることもあります。
例えば退職後に年金収入が多い60代前半の方などは、その年金に対しても国保保険料がかかる点に注意が必要です。単身の場合は扶養家族に左右されないぶん、退職前後の所得水準の差と2年以内の再就職予定が判断材料となります。
ケース3:配偶者の健康保険の被扶養者になれる場合
⇒ 被扶養者になるのが最も経済的。
質問の主旨からは外れますが重要な選択肢として、退職者に収入がなく、かつ配偶者などご家族が勤務先の健康保険に加入している場合は、その扶養家族(被扶養者)に入ることが可能です。
被扶養者となれば保険料の本人負担はありません(家族の保険料も増えません)ので、国保・任意継続と比べて最も負担が少ない方法です。一般に被扶養者として認められるには退職者本人の年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)等の条件があります。
退職後しばらく収入が途絶える見込みであれば、この条件を満たせる可能性が高いため、まず扶養に入れるか検討します。ただし注意点として、被扶養者となる手続きは扶養に入れるご家族の勤務先で行う必要があります。会社によっては退職日の翌日から扶養に入るために健康保険資格喪失証明書の提出を求める場合があります。
人事担当者は退職者に対し、この証明書の発行を案内しスムーズな扶養手続きができるようサポートしましょう。
被扶養者となれれば国保や任意継続より有利ですが、仮に収入要件を満たさない場合には上述の国保と任意継続の比較検討に戻ります。
健康保険任意継続制度の手続き
健康保険任意継続制度の加入には、以下の条件を満たす必要があります。
- 資格喪失日の前日(退職日)までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
退職から20日が経過してしまうと、健康保険任意継続制度の手続きが行えません。退職前に、健康保険任意継続制度に必要な書類や保険料を比較し、ご自身にとって良い選択肢を検討しておくといいでしょう。
任意継続の保険料や必要となる手続きについては、以下の記事をご参照ください。
国民健康保険への切り替えの手続き方法
健康保険任意継続制度の手続きを行わないまま退職した場合、通常、退職日の翌日から健康保険の資格を喪失します。退職の翌日から新しい会社に就職するのであれば、とくに切り替えは必要ありませんが、再就職先が決まっていないなど社会保険に未加入の状態が1日でもあれば、国民健康保険への切り替え手続きが必要です。
- 手続き場所:住所のある場所の市役所の窓口
- いつまでに:退職した日から2週間以内
- 必要な書類:健康保険等資格喪失証明書(会社が発行した資格喪失日がわかる書類)、本人確認書類、マイナンバーカード等
詳しい手続きについては、住んでいる場所の近隣の市役所窓口でご確認いただけます。保険料についても、源泉徴収票など前年の収入が確認できるものがあれば概算額を試算することができます。市区町村のサイトに自動計算できるツールがある場合も多いので、事前に保険料を計算しておくことをおすすめします。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書のテンプレート(無料)
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
国民皆保険制度における健康保険継続の必要性
国民皆保険制度を原則としている日本においては、1日のあきもなく何らかの健康保険に入っていなければなりません。国民健康保険と健康保険任意継続制度のメリットとデメリットを比較したうえで、ご自身に合った選択を選びましょう。
よくある質問
国民健康保険は全員入らないといけないの?
日本の健康保険制度は「国民皆保険」が原則のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく必ず公的医療保険制度に加入しなくてはいけません。詳しくはこちらをご覧ください。詳しくはこちらをご覧ください。
健康保険任意継続制度の適用期間は?
喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険や健康保険組合への加入を、退職後2年に限り継続することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険のデメリットは?
傷病手当金や出産手当金が支給されないことです。前年の所得が高いと保険料が高額になる可能性があることや、扶養家族が多いほど世帯全体の保険料が高額になることもあげられます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会保険の厚生年金とは
社会保険に含まれる厚生年金保険はその名のとおり「保険」の意味をもちます。社会保険は主に会社員が保険の加入者(被保険者)となり、万が一の場合には被保険者やその家族を対象に年金の給付が行われます。 注意していただきたい点ですが、「社会保険」とい…
詳しくみる引越し時のマイナ保険証の住所変更はどうする?手続きの流れや必要書類を解説
マイナ保険証とは、「マイナンバーカードの健康保険証利用」の略称です。マイナンバーカードを事前に登録することで、健康保険証として病院受付で利用できます。 政府はマイナ保険証への移行を段階的に進めており、2024年12月2日以降は原則として新た…
詳しくみる雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道やもらうタイミングを紹介
退職した時や雇用保険の加入要件を満たさない労働契約に変更になった際に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」という書類を受け取りますが、この書類は何に使うか知っていますか。 名称からわかるかもしれませんが、雇用保険の加入者がその資格を喪失した…
詳しくみる社会保険(公的保険)と民間保険の違いとは?
保険には、国などが運営する社会保険と民間保険があります。いずれも保険事故が発生したときに備え、多くの人が集団を作り、個人経済のリスクを分散しようとする保険方式による点は共通しています。 では、社会保険と民間保険の違いは何でしょうか。 本稿で…
詳しくみる副業すると社会保険料が増える?社会保険加入時に注意すべきポイントを解説!
働き方改革が推進され、多様な働き方の一つとして副業・兼業のダブルワークを認める企業が増えています。「自身の能力を一つの企業にとらわれず幅広く発揮したい」という想いから前向きに検討している方もいるのではないでしょうか。 今回は、副業・兼業に関…
詳しくみる健康保険の年齢は何歳まで?70歳以上を雇用する場合の手続きを解説
健康保険は、労働者が医療機関を受診する際に必要となる制度です。年齢によって扱いが変わるため、労働者を雇用する際には注意しなければなりません。手続きに誤りがあれば、一旦治療費を全額自己負担しなければならない場合もあります。今回は70歳以上の健…
詳しくみる