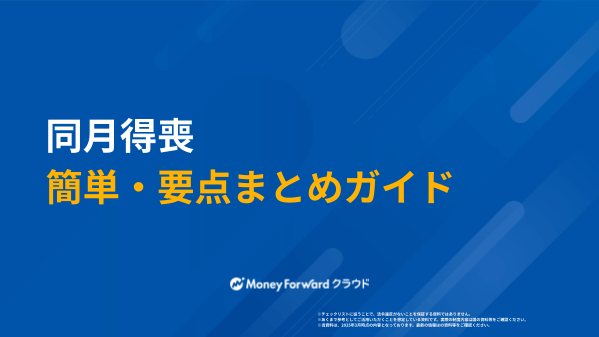- 更新日 : 2025年12月11日
同月得喪における社会保険料を解説!厚生年金や健康保険の保険料はどうなる?
会社は、要件を満たした人を社会保険に加入させます。会社は社員に長く働いてもらいたいのですが、実際は1ヵ月未満など、短期間で退職する人も出てきます。その際に社会保険の同月得喪が生じる場合があります。
今回は、社会保険の同月得喪の定義や概要と、同月得喪が生じた場合に厚生年金や健康保険の保険料がどうなるのかについて解説します。
目次
同月得喪とは
社会保険の同月得喪とは、同月内に社会保険の資格取得日と資格喪失日があることを言います。
ただし、あくまで同じ月内で資格取得日と資格喪失日が発生することが前提です。例えば、退職日が月末である場合は、資格喪失日は翌月1日になってしまうため、同月得喪は成立しないことに注意してください。
同日得喪との違い
「同月得喪」と似たような言葉に「同日得喪」があります。同日得喪とは、60歳以上で退職し、退職後に1日の空白もあけることなく継続して再雇用される場合に雇用関係が一度中断したとして資格喪失と資格取得を行う手続きです。
同月得喪は同月内での資格取得・喪失の手続きですが、同日得喪は同日での資格喪失・取得という違いがあります。
同月得喪が発生するケース
同月得喪が発生するケースとして、例えば、12月1日に入社し社会保険の資格を取得したけれども、12月20日に退職し資格を喪失した場合が挙げられます。この場合、被保険者資格を取得した月に資格を喪失していますので、同月得喪が生じていることになります。
これが、例えば、上記と同じ12月1日に社会保険の資格を取得し、12月31日に退職して資格を喪失した場合には、入社日、退職日は同じ12月ですが、資格取得日、資格喪失日で見ますと、月をまたぐ形になるため同月得喪にはならないのです。
同月得喪が生じた場合の厚生年金保険料
厚生年金保険の資格取得月と同月に資格喪失した際、すなわち、同月得喪が生じた場合は厚生年金保険料の納付が必要になります。
厚生年金保険料の被保険者負担分は退職の際の給与から控除され、会社が被保険者負担分と会社負担分を併せた厚生年金保険料を翌月末までに日本年金機構に納付することとなります。
ただし、同月得喪が生じた場合でも、月末時点で別の年金の被保険者になっていた場合には例外があります。
厚生年金保険料について資格喪失者が同月内に別の年金の被保険者となったとき
同月得喪が生じた人が、同じ月に厚生年金保険の資格、もしくは第2号被保険者を除く国民年金の資格取得があった場合はどのように処理するのでしょうか?
先に厚生年金保険の資格を喪失した会社では、その人が同月末までに別の年金の被保険者になるかどうかがわからないため、資格を喪失した会社の分の厚生年金保険料を徴収します。
その後、その人に、同じ月に厚生年金保険の資格、もしくは第2号被保険者を除く国民年金の資格取得があった場合、その制度に合わせた保険料を納付します。
この場合、年金事務所の手続きを経て先に喪失した会社に厚生年金保険料が還付されますので、本人負担分は会社から被保険者に還付されることになるのです。
これは、保険料の二重払いをしないようにするためです。
同月得喪が生じた場合の健康保険料
健康保険料に関しては、厚生年金保険料と違って同月得喪の場合でもその月の健康保険料の納付が必要になります。健康保険料の納付が必要になるというところが厚生年金保険料と異なりますので注意してください。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の無料テンプレート
以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。
同月得喪について再確認しておきましょう
社会保険の同月得喪が生じる場合のケースと同月得喪が生じた場合の厚生年金保険料、健康保険料の取り扱いについて見てきました。あまり取り扱うことがないと思われるケースですので、知らない方もいるかもしれません。
同じような場合にどのように対応すればよいのか、また、該当するケースが生じた場合に社員に正確な説明ができるように再度確認しておきましょう。
よくある質問
同月得喪とはなんですか?
同月得喪とは、同月内に社会保険の資格取得日(入社日)と資格喪失日(退職日の翌日)があることを言います。ただし、資格喪失日は退職日の翌日となってしまうため、退職日が月末の場合は同月得喪は成立しません。詳しくはこちらをご覧ください。
同月得喪と同日得喪の違いについて教えてください。
同月得喪は同じ月内で資格取得・喪失が生じる手続きですが、同日得喪は60歳以上で退職し、退職後に1日の空白もあけることなく継続して再雇用する際に資格喪失・取得を同日に行う手続きのことを言います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
医療費の限度額とは
重症の病気やけがによる長期入院や療養が必要となった場合、自己負担すべき医療費が高額になってしまいます。そのため、個人の負担を軽くできるように、健康保険には「高額療養費制度」が設けられています。 この制度を利用すると、高額な医療費を支払った場…
詳しくみる算定基礎届はいつ届く?提出期限や書類の書き方、訂正方法も解説
「算定基礎届」は、標準報酬月額を決定するために年に一度提出が必要な書類です。この書類は毎年6月中旬以降に日本年金機構から事業主宛に送付されます。 本記事では、算定基礎届が届く時期や対象者について解説します。詳しい書き方や訂正方法、提出期限に…
詳しくみる退職後も出産手当金がもらえる?要件と手続きについて解説!
出産手当金は被保険者が出産のために休職し、その間に給与を得られなかった場合に支給される給付金です。 このお金は、在職中の休業であれば受け取ることができますが、受け取る前後において退職した場合はどうなるのでしょうか? この出産手当金は退職する…
詳しくみる社会保険の加入要件
社会保険は、国や地方公共団体などによって運営がなされており、国民皆保険体制のもと、一定要件を満たした会社や個人は加入する義務があります。 社会保険の加入要件には、例外的なものまで含めるとじつにさまざまな種類があります。 国民年金の加入要件 …
詳しくみる求職者給付とは?受給条件やメリットを解説!
失業すると雇用保険から失業等給付を受けることができます。基本手当は一般的に失業手当と呼ばれる給付で、労働者が雇用保険に加入していたときの給料から計算される基本手当日額が、加入期間に応じた一定の日数分、受け取れます。コロナの影響で失業した場合…
詳しくみる厚生年金が引かれすぎてる?確認方法を解説!
厚生年金保険料は毎月給与から天引きされるため、月いくら払うのかを意識していないかもしれません。保険料は労使折半で、負担割合は5割です。収入が増えていないのに保険料が高くなった場合は、正しく折半されていない可能性があります。この記事では保険料…
詳しくみる