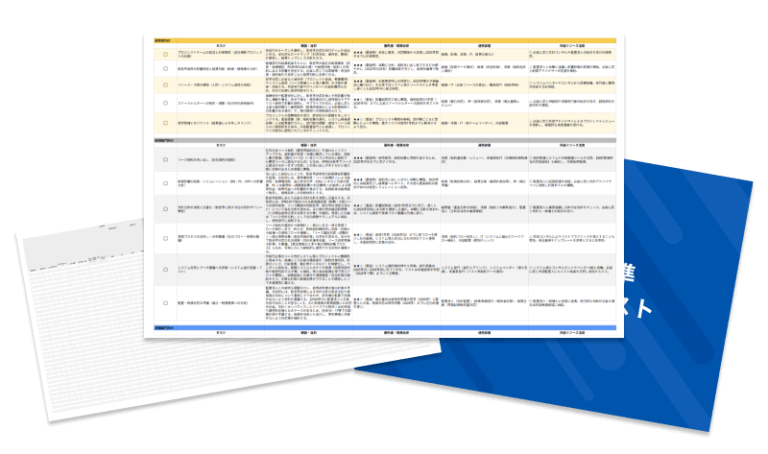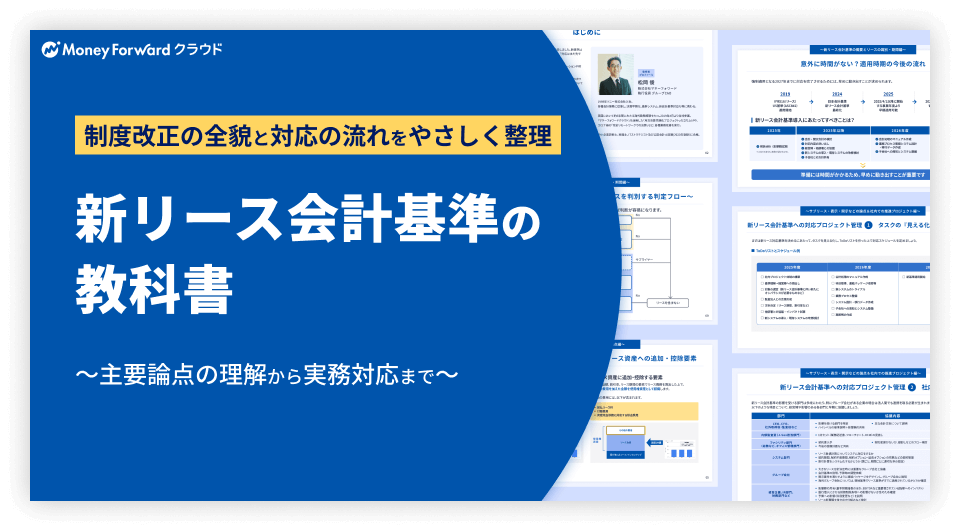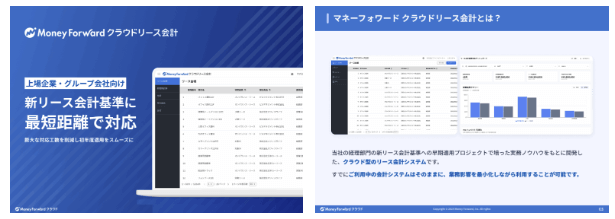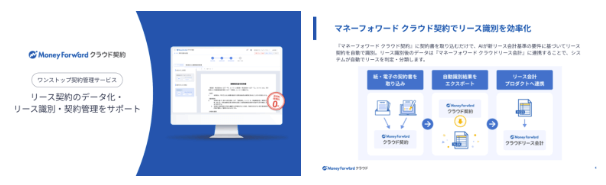- 更新日 : 2026年1月21日
有利子負債とは?勘定科目やリース債務との関係性を解説!
有利子負債とは、貸借対照表に計上される負債のうち、利息の支払いを伴うものを表します。
有利子負債の代表例としては、金融機関からの借入金や資金調達のために発行する社債などが挙げられます。
ここでは、有利子負債の概要や無利子負債との違い、有利子負債を活用した財務分析の方法、リース債務との関係性などについて解説します。
目次
利子負債とは?
企業が事業活動を行うためには、設備投資や運転資金などのまとまった資金が必要になります。これらの資金を調達する方法のひとつが「負債(借入)」です。
負債には、大きく分けて利息が発生する「有利子負債」と利息が発生しない「無利子負債」の2種類があります。金融機関からの融資などに代表される有利子負債の概要や勘定科目について確認しましょう。
有利子負債と無利子負債
貸借対照表に表示される負債は、利息の有無によって「有利子負債」と「無利子負債」の2つに分けられます。
- 有利子負債
有利子負債とは、利息を付けて返済する義務のある負債を指します。具体的には、金融機関からの借入金や社債などが該当し、元本部分に加えて利息も支払うことで必要な資金を調達します。企業は有利子負債を活用することで、自己資金(自己資本)の範囲を超えた大きな事業展開が可能になる半面、利息負担や元本返済のリスクを抱えることになります。 - 無利子負債
無利子負債とは、利息の支払いを伴わない負債を指し、買掛金や未払費用、支払手形などが代表例です。たとえば、商品を仕入れた際の買掛金や、月末締めで翌月支払う未払金などは、代金支払いまでにタイムラグはあるものの、一般的に金利負担は生じません。無利子負債は、金利負担がないことから資金繰りや損益状況を改善する効果はあります。しかし、債権者側のメリットも少ないため、資金調達としては活用しにくいと言えるでしょう。
このように、有利子負債は資金調達コストがかかるものの、外部から大きな資金を取り込む手段として重視される傾向にあります。企業規模を拡大し、投資リターンが利息を上回ることが期待できるような事業であれば、有利子負債の活用は有効な選択肢と考えられます。
有利子負債の代表例
企業が一般的に利用する有利子負債としては、次のようなものが挙げられます。
- 金融機関からの借入金
運転資金の補填や設備投資、大規模プロジェクトの資金など、事業資金として金融機関から融資を受ける場合には、その借入金が有利子負債となります。なお、会計上はその返済期日が決算日の翌日から1年以内である場合には「短期借入金」、返済期日が1年を超える場合には「長期借入金」として貸借対照表に表示します。 - 社債
社債とは、企業が直接投資家から資金を募る形で発行する債券のことです。社債を発行した場合には、満期日まで利息を支払い、償還日には元本を返済する必要があります。金融機関の仲介を経ずに市場から資金を調達できるのがメリットですが、社債を発行するには信用格付けや開示情報の整備など、手続き上のハードルが高い側面もあります。 - コマーシャルペーパー
短期の社債に類似する形態で、企業が短期的な資金需要を賄うために発行します。金利については、償還期間や信用リスクに応じて変動することが一般的です。
これらは企業が日々のオペレーションや投資活動を行ううえで欠かせない金融手段であり、企業規模や資金需要に応じて使い分けが可能です。いずれの方法においても、利息を含めた返済リスクを適切に管理するための財務戦略が求められます。
有利子負債の勘定科目
会計上、有利子負債は貸借対照表における「負債の部」に計上されます。具体的な勘定科目としては、以下のいずれかを用いるケースが一般的です。
- 短期借入金
金融機関などからの借入金のうち、決算日の翌日から起算して、1年以内に返済期日が到来する金額を「短期借入金」として流動負債に計上します。なお、融資期間が1年超の借入金でも、返済期限が1年以内に到来する金額は、「短期借入金」や「1年以内返済長期借入金」などの勘定科目を用いて、流動負債として表示します。 - 長期借入金
金融機関などからの借入金のうち、決算日の翌日から起算して、返済期日が1年を超える金額を「長期借入金」として固定負債に計上します。 - 社債
企業が投資家から資金調達を行うために発行した有価証券のことです。発行形態や条件によって、普通社債や新株予約権付社債などの種類に分かれます。なお、社債の中には、「ゼロクーポン債」のように無利子負債に該当する債券も含まれます。 - リース債務
リース取引によって固定資産を賃借する場合にも、リース料とともに利息相当額を支払うことになります。したがって、負債として計上される「リース債務」についても有利子負債の一部とみなされる場合があります。
財務諸表を読み解く際には、これらの勘定科目に含まれる有利子負債を集計し、企業のキャッシュフロー管理や財務分析などに活用することが重要です。
増資との違い
企業活動においては、「有利子負債(融資や社債発行など)による調達」と「株式発行(増資)」が代表的な資金調達手段として挙げられます。
ただし、有利子負債による資金調達と株式発行による増資では、それぞれ性質が異なるため、以下の違いを正しく理解したうえで、最適な調達方法を検討しましょう。
- 有利子負債
増資のような株式発行が不要であるため、第三者が経営に参画することなく、必要な資金を調達できます。また、調達した資金を活用して収益を拡大した場合でも、配当などの支払いは不要です。その一方で、経営が低迷した場合でも、元本の返済義務と利息支払いが必須となるため、資金繰りの悪化を招くリスクも高まります。 - 株式発行による増資
増資によって集めた資金は資本金となり、負債のような返済義務がないため、仮に経営状況が悪化した場合でも返済による負担は生じません。ただし、株式数が増えることで既存株主の持ち株比率が希薄化することや、利益が出た場合は配当金支払いによる負担が増加する可能性も考えられます。
一般には、株主資本コストより借入金利のほうが低いケースが多いため、レバレッジ効果を狙って有利子負債を積極的に活用する企業も珍しくありません。ただし、過度に有利子負債を増やすことは財務リスクの増大にもつながるため、適切なバランスを維持することが重要です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準の教科書
新リース会計基準を理解するにはこの資料!
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
有利子負債を用いた財務分析
有利子負債は、企業の財務戦略や投資効率、経営の安定性を測るうえで欠かせない重要な指標です。
有利子負債を上手に使うことで、企業は持続的な成長を目指せる一方、事業環境の変化や金利上昇リスクなどを考慮せずに過剰な借入を行うと、返済負担が重くのしかかり、経営破綻に陥る可能性もあります。
そのため、企業内部でも自社の有利子負債の動きをモニタリングして、財務状況の健全性を注視することが大切です。
有利子負債は「健全性」を図る重要な指標
企業の財務健全性や安定性を評価する際には、「有利子負債の水準」が主要なチェック項目のひとつとなります。なぜなら、利息の負担や返済義務に直結する負債額が大きいほど、事業活動が不調に陥った際のリスクが高まるためです。
有利子負債を使った代表的な指標としては、「有利子負債比率」や「EBITDA有利子負債倍率」などが挙げられます。また、M&Aなどにおいては、「純有利子負債」を算出し、リスク分析や企業価値の算定に活用するケースも多いです。
これらの指標を組み合わせ、利益またはキャッシュフローに対する負債返済能力や、自己資本とのバランスを総合的に検証することで、企業の財務健全性を評価します。
企業によっては、投資家や金融機関へこれらの指標に関する改善策を示すことで、自社の信用力向上を図るケースも少なくありません。
有利子負債比率
有利子負債比率とは、自己資本に対して有利子負債が占める割合を示す指標であり、以下の算式によって計算します。
この指標では、自己資本(純資産)に対してどの程度の有利子負債を抱えているかを示すため、財務レバレッジの大きさを測る尺度と言えます。
有利子負債比率が大きいほど、自己資本に対して有利子負債が大きいことを意味するため、比率が小さいほど企業の安全性が高いと判断されます。
有利子負債比率は、一般的に100%未満であることが望ましいとされています。しかし、業種や企業規模などによる資本構造の違いもあるため、同業種の平均値や競合他社との比較で評価することが望ましいと言えるでしょう。
EBITDA有利子負債倍率
EBITDA有利子負債倍率とは、企業の負債返済能力を測る指標であり、以下の算式によって求めることが可能です。
分母となる「EBITDA」はキャッシュ創出能力を大まかに捉えられる数値であるため、上記の算式によって、本業によるキャッシュフローに対し、何倍の有利子負債を保有しているかを表します。
すなわち、この数値が低いほど、本業としての事業活動を通じて負債を返済できる能力が高いとみなされます。
一般的には7〜10倍程度が望ましいとされていますが、短期的な利益変動や減価償却費の大きさによって数値が変わりやすいという側面もあるため、継続的にモニタリングすることが重要です。
純有利子負債(ネット・デッド)とは?
単に有利子負債の金額だけを見るのではなく、企業が手元に保有する現預金や短期有価証券など、すぐに返済に回せるキャッシュを差し引いた実質的な有利子負債を「純有利子負債(Net Debt)」といいます。
たとえば、多額の有利子負債が計上されている場合でも、現金預金が潤沢にある場合には、正味の負債額は縮小し、実質的な返済リスクは低いと判断されるケースもあるでしょう。
有利子負債とリース債務の関係性
企業活動では、必要な機械や設備を「リース取引」によって調達するケースも多いです。
近年の会計基準の変化により、リース取引のオンバランス処理が進んでおり、「リース債務」を財務分析上どのように扱うかが重要な論点となっています。
有利子負債とリース債務の関係性を整理し、財務分析や経営判断に役立てましょう。
リース取引における会計処理
リース取引には、大きく分けて「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類があります。
- ファイナンス・リース
資産の貸し手がリース商品を購入し、借り手に貸し付ける取引形態のことです。実質的に資産の売買と変わらないリース取引であるため、借り手はリース物件を貸借対照表に「リース資産」として資産計上し、対応する負債(元本部分)を「リース債務」として計上します。毎月支払うリース料は、元本返済部分と利息相当分に分割して会計処理されるため、利息負担が発生する構造となります。 - オペレーティング・リース
貸し手が保有する資産を借り手がレンタルする取引形態のことです。リース資産を借りているだけの契約であり、期間満了後は返却する必要があるため、貸借対照表には計上せず、賃貸借取引として処理を行います。したがって、オペレーティング・リースとしてリース料を支払った場合には、支払額をそのまま「リース料(費用)」として計上します。なお、2027年4月1日以後の事業年度にて強制適用される「新リース会計基準」では、オペレーティング・リースについても、賃貸借取引ではなくオンバランス化が求められます。
リース債務は有利子負債に含まれる?
ファイナンス・リースにて負債計上される「リース債務」は、実質的にリース資産に関する購入対価の分割払いであり、利息相当分(支払利息)と合わせてリース料を支払います。
このような背景から、リース取引によって計上された「リース債務」は、有利子負債に含まれると解釈されるケースも少なくありません。
ただし、高額な機械装置などをリースで調達する企業では、リース債務も拡大するため、有利子負債比率などの指標に与える影響も大きくなり、企業の実態が過大・過小評価されるリスクもあります。
したがって、リース債務においては、実質的に利息を伴う債務として理解されることが多い一方で、財務分析を行ううえでは「有利子負債に含めるべきかどうか」を慎重に判断することが重要です。
リース債務の計上状況やリース契約の実態を考慮し、企業としての財政状態を適切に分析する方法を検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
【定率法の償却率】旧定率法と250%と200%の違いを徹底解説
平成19年度税制改正によって定率法の償却率が250%に引き上げられ、平成23年度税制改正によって200%に引き下げられました。 税制改正の影響を受けて、定率法による減価償却率がどのように変化していったのかを解説します。 旧定率法による減価償…
詳しくみる車の耐用年数は何年?減価償却費の計算方法や何年落ちがお得なのかも解説
車の減価償却における耐用年数とは、減価償却資産の本来の用途・用法により通常予定される効果が発揮される年数です。車の耐用年数が把握できたら、減価償却費を算出できます。今回は、車の耐用年数は何年なのかについて詳しく解説します。 車の減価償却にお…
詳しくみるバイクの減価償却まとめ – 中古車の耐用年数は新車と異なる
業務にバイクが必要なときは、バイクを購入した費用を経費として計上することが可能です。10万円未満であれば消耗品費の勘定科目を用いて仕訳します。10万円以上のときは資産となるため耐用年数で減価償却することが基本です。 また、青色申告している個…
詳しくみる保険金の圧縮記帳の仕方とは?圧縮するメリット・デメリットや注意すべきポイントを解説
車両事故や機械の故障により保険金を受け取った際は、益金となるため税負担の増加に注意が必要です。税負担が増えると、資金繰りが悪化して経営に支障をおよぼす可能性があります。 保険金を受け取った年度に検討したいのが圧縮記帳です。圧縮記帳をすれば、…
詳しくみるリース取引の会計処理方法は?仕訳や勘定科目のポイントをわかりやすく解説
企業の経理担当者が直面する重要な業務の一つに、リース取引の仕訳があります。リース取引の会計処理は、リースの種類によって用いる勘定科目が大きく異なり、正確な知識が求められます。 この記事では、リースの仕訳の基本から具体的な記帳方法、そして中小…
詳しくみるエアコンの減価償却を解説!業務用・家庭用の耐用年数は?
エアコンは業務用と家庭用で、法定耐用年数が異なります。そのため、減価償却が必要な場合は耐用年数の違いに注意しましょう。本記事は、エアコンの減価償却と計算方法について紹介します。エアコンを減価償却する際の注意点も解説しているので、併せて参考に…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引