- 作成日 : 2022年2月4日
転リース取引とは?会計処理と仕訳の解説
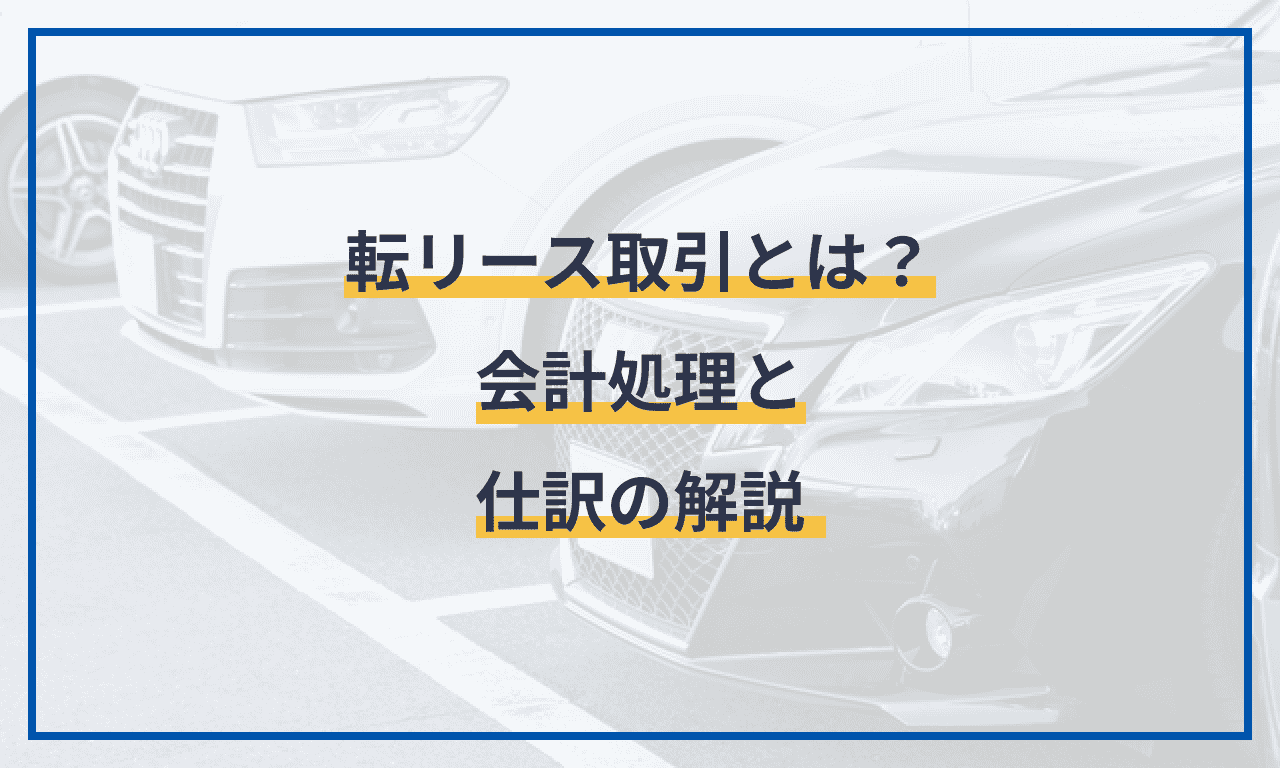
さまざまなビジネスの方法がある中で、転リース取引を行っている事業者は少なくありません。しかし、転リース取引は、通常のリース取引と会計処理が異なります。そこで、転リース取引の概要や会計処理、仕訳について詳しく解説します。
転リース取引とは
転リース取引とは簡単にいうと、リース会社などからリースしている資産を第三者に再度リースする取引のことです。ただし、転リース取引に該当するには、リース会社などと結んだリース契約とおおむね同じ条件で第三者にリースしていることが条件です。転リースを禁じている業者も多いですが、認めているリース会社もあります。
転リース取引は、リースしている資産を第三者にリースする取引のため、以下2つの会計処理が必要です。
- リース会社にリース料を支払うときの会計処理
- 第三者からリース料を受け取るときの会計処理
転リース取引に用いられるリースのほとんどは、所有権移転外ファイナンス・リースのものです。ファイナンス・リースとは、中途解約ができず(ノンキャンセラブル)、リース物件の購入代金や諸費用等を全額リース料として支払う(フルペイアウト)リース取引のことです。
所有権移転外ファイナンス・リースにおける転リース取引の会計処理は、支払ったリース料や受け取ったリース料の全額を、費用や収益に計上しません。支払ったリース料と受け取ったリース料の差額を「転リース料差益」または「転リース差益」などの科目で計上します。
転リース取引の会計処理と仕訳(支払い時)
まずは具体例を挙げて、転リース取引におけるリース会社へのリース料の支払いの仕訳を見ていきましょう。
例)リース会社から車両500,000円を所有権移転外ファイナンス・リースし、毎月リース料10,000円と利息1,000円の合計11,000円を普通預金から支払っている。なお、この車両はA社に転リースしている。
※説明上、毎月のリース料と利息の支払を同額としている。
- リース開始時
- リース料支払時
リース開始時には、利息相当額控除後の金額を「リース投資資産」「リース債務」の勘定科目で処理します。ただし、利息相当額控除前の金額で計上することも可能です。
所有権移転外ファイナンス・リースにおける転リース取引の会計処理は、支払ったリース料や受け取ったリース料を全額、費用や収益に計上しません。そのため、支払利息1,000円については「預り金」で会計処理します。
転リース取引の会計処理と仕訳(受け取り時)
次に、転リース取引における、第三者からのリース料の受け取りの仕訳についても、具体例を挙げて見ていきましょう。
例)上記の車両をA社に転リースした。毎月の受取額は11,500円で、普通預金に入金される
- リース料受取時
リース会社に支払うリース債務相当分を、貸方勘定科目「リース投資資産」勘定で処理します。また、利息部分については、上記の預り金の反対仕訳になります。
転リース取引では、支払ったリース料と受け取ったリース料の差額のみ収益となり、「転リース料差益」または「転リース差益」などの科目で計上します。
転リース取引の会計処理は通常のリース取引の会計処理とは異なる
転リース取引は、通常のリース取引とは異なり、以下の2つの会計処理が必要になります。
- リース会社にリース料を支払うときの会計処理
- 第三者からリース料を受け取るときの会計処理
また、転リース料差益以外の支払利息などの費用や売上高などの収益は計上しないといった違いもあります。損益を正確に把握するためにも、正しい会計処理や仕訳を理解しましょう。
よくある質問
転リース取引とは?
リース会社などからリースしている資産を同じような条件で第三者に再度リースする取引のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
転リース取引の会計処理のポイントは?
売上高や支払利息などの会計処理を行うことがなく、リース料の差額が収益になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。





