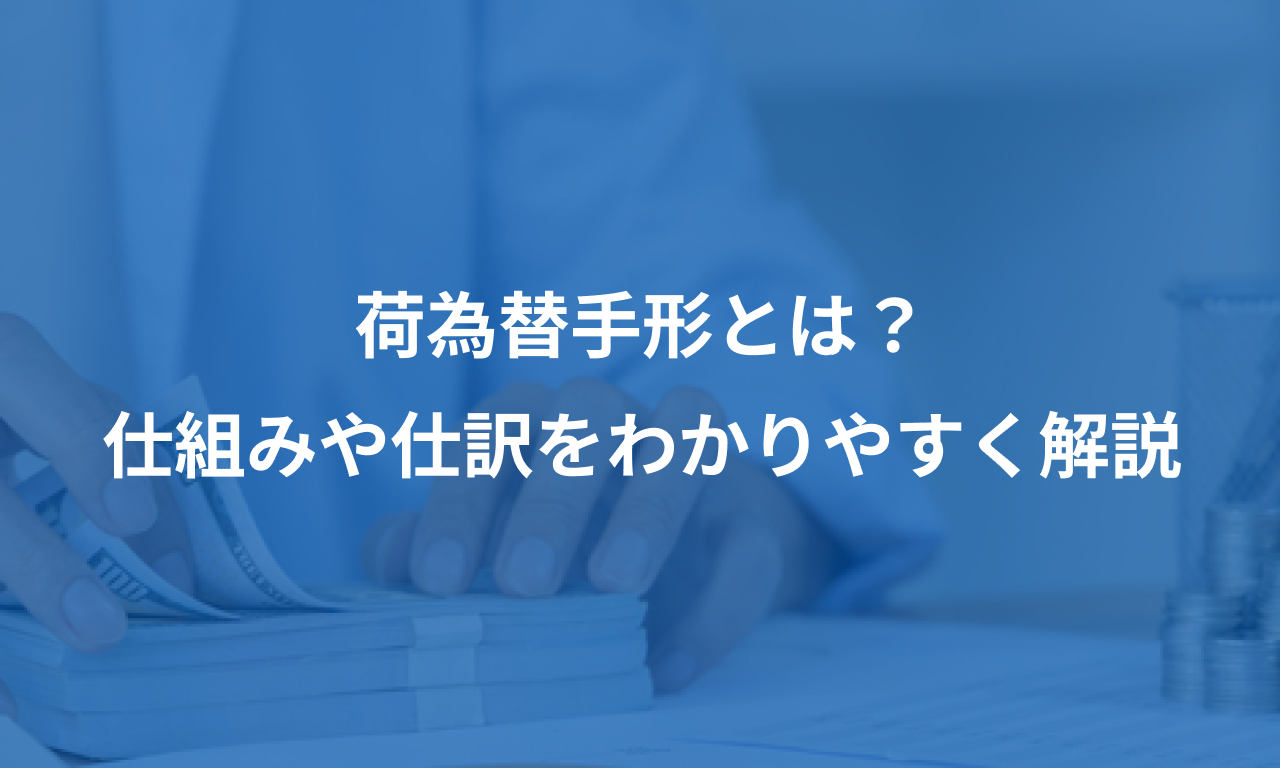- 更新日 : 2024年4月11日
利益率とは?出し方の計算方法や目安の解説

売上高に対する利益の割合を利益率といいます。利益率は、売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率、売上高税引前当期純利益率、売上高当期純利益率の5種類に分類されます。会社がどれだけの利益を出しているのか、会社の収益性を知るための重要な指標です。この記事では利益率の種類や特徴とそれぞれの計算の仕方、利益率の目安について解説していきます。
利益率とは
利益率は、売上高に対する利益の割合を示す指標です。利益率の計算で用いる利益とは、収益の額から費用の額を差し引いた額を指します。
利益率には種類があり、売上高と比較する利益の段階によって、収益分析における意味が異なります。
利益率の種類と計算方法
利益率には、次の5種類があります。
- 売上高総利益率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高税引前当期純利益率
- 売上高当期純利益率
それぞれの意味や計算方法について詳しく見ていきましょう。
売上高総利益率
売上高総利益率とは、以下の計算式により算出した利益率です。
売上高総利益率の計算で用いる売上総利益は、売上高から売上原価(または製造原価)を差し引いた利益額です。粗利ともいわれます。
売上高総利益率でわかるのは、企業のブランド力や競争率の高さです。商品やサービスの利益がどの程度の規模であるか、純粋な営業力を測るのに適しています。ただし、売上総利益は景気の影響を受けやすく、景気が悪いと売上高総利益率が下がる傾向にあるため、景気の動向を考慮に入れた判断をする必要があります。
当期の売上高は5,000万円、仕入高は3,500万円、期首商品棚卸高は500万円、期末商品棚卸高は300万円だった。売上総利益= 5,000万円-(500万円+3,500万円-300万円)※=1,300万円
※売上原価は、期首商品棚卸高+仕入高-期末商品棚卸高で計算
1,300万円÷5,000万円×100=26%(売上高総利益率)
売上高営業利益率
売上高営業利益率は、本業による利益の割合です。売上高総利益率では、売上高と原価の差額である売上総利益を比較対象にしますが、売上高営業利益率ではさらに広い範囲で事業の利益を判断し見ます。
売上高営業利益率は、売上総利益から販売費および一般管理費を差し引いた営業利益を用いて算出します。販売費および一般管理費とは、事業運営上必要な事務所の家賃や地代、事務所の水道光熱費、従業員へ支払う給与や賞与、商品やサービスの販売にかかった広告販売費、取引先とのやり取りに必要な通信費(切手代や電話料など)など、事業に必要な費用を指します。
売上高営業利益率を計算することで、企業の本業からどのくらいの利益が生み出されているのか、すなわち本業の収益力がわかります。
当期の売上高は5,000万円、売上総利益は1,300万円、販売費および一般管理費は1,000万円であった。営業利益= 1,300万円-1,000万円=300万円
300万円÷5,000万円×100=6%(売上高営業利益率)
売上高経常利益率
売上高経常利益率は、売上高に占める経常利益の割合です。経常利益とは、営業利益に、財務活動により発生した損益(本業以外の活動で生じた収益や借入金返済にかかわる利息などの費用)を加えたものになります。突発的に発生するものは含まれず、事業上通常発生する範囲で算出された利益が経常利益です。
売上高経常利益率を計算することで、企業が行う通常の経営活動がどのくらいの利益を生み出しているか、すなわち、通常の経営活動による収益力がわかります。
売上高経常利益率の求め方は以下の通りです。
当期の売上高は5,000万円、営業利益は300万円、営業外収益は100万円、営業外費用は200万円であった。経常利益= 300万円+(100万円-200万円)=200万円
200万円÷5,000万円×100=4%(売上高経常利益率)
売上高税引前当期純利益率
売上高税引前当期純利益率は、売上高に対する税引前当期純利益の割合です。税引前当期純利益は、経常利益から特別損失を差し引き、特別利益を加えた利益額です。税引前とあるように、法人税等を控除する前の利益の額を指しており、その事業年度で売上に対し生み出した利益の規模がわかります。売上高税引前当期純利益率の求め方は以下の通りです。
当期の売上高は5,000万円、経常利益は200万円、特別利益は100万円、特別損失は50万円であった。税引前当期純利益= 200万円+(100万円-50万円)=250万円
250万円÷5,000万円×100=5%(売上高税引前当期純利益率)
売上高当期純利益率
売上高当期純利益率とは、売上高に占める当期純利益の割合です。計算で用いる当期純利益は、税引前当期純利益から法人税等を差し引いた残額を表します。売上高当期純利益率の算出で当該事業年度の最終的な利益率です。以下の計算式によって求めます。
当期の売上高は5,000万円、税引前当期純利益は250万円、法人税等(法人税等調整額含む)は50万円であった。当期純利益= 250万円-50万円=200万円
200万円÷5,000万円×100=4%(当期純利益率)
利益率の目安
公的な調査では、本業における利益や企業の経常的な利益がわかることから、一般的に売上高営業利益率や売上高経常利益率が用いられています。
2021年経済産業省企業活動基本調査(2020年度実績)によると、主要産業の売上高営業利益率は3.2%、売上高経常利益率は5.0%であることがわかりました。
主な業界別では、製造業で売上高営業利益率3.4%、売上高経常利益率6.5%、卸売業で売上高営業利益率2.0%、売上高経常利益率3.4%、小売業で売上高営業利益率2.8%、売上高経常利益率3.1%でした。このように、業界によっても利益率に違いがあることがわかります。
参考:2021年経済産業省企業活動基本調査(2020年度実績)|経済産業省
利益率を把握して経営改善を図ろう
会社の経常状況を把握して適切な経営戦略を立てるには、どの段階でどのくらいの利益が出ているのか利益率を知ることも大切です。
マネーフォワード会計では、仕訳データを登録することで、自動的に売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率、売上高税引前当期純利益率、売上高当期純利益率が集計表に表示されます。手計算でも利益率は把握できますが、マネーフォワード会計を活用すれば、短い時間で確実なデータを算出できます。
よくある質問
利益率とは?
売上高に対する利益の割合を利益率といいます。詳しくはこちらをご覧ください。
利益率の計算方法は?
利益額を売上高で割って求めます。売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益利率、売上高税引前当期純利益率、売上高当期純利益率で対象になる利益が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。