- 更新日 : 2024年3月5日
見積書の保存は2023年の電子帳簿保存法の改正でどう変わる?
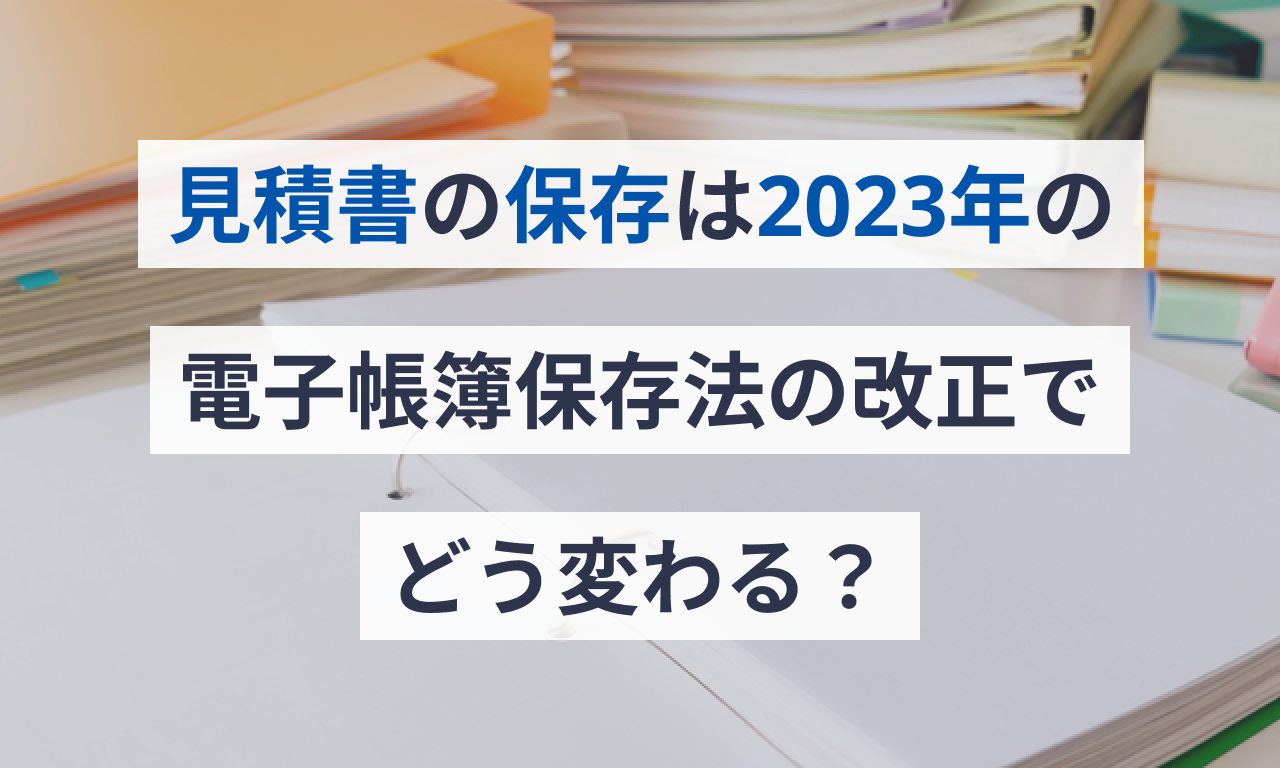
令和4年(2022年)1月1日に施行された電子帳簿保存法の改正により、電子取引データは一定の要件を満たしたうえで、電子データで保存(2023年12月31日までは電子データを印刷して保存することも可)することが義務付けられました。
さらに、令和5年(2023年)度の税制改正によって新たな改正点が加わり、令和6年1月1日以後に行われる電子取引から適用されます。ここでは、2度の改正に伴って定められた見積書の保存方法について解説します。
目次
改正電子帳簿保存法における見積書の対応
令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行されました。電子帳簿保存法の改正により見積書の保存にどのような影響があるのか、見積書の保存方法についてそれぞれ解説していきます。
見積書は改正電子帳簿保存法において保存義務はある?
法人税法によって、帳簿の保存と、取引に関して作成した書類、または受領した書類は、保存義務が定められています。見積書も取引に関する書類に含まれるため、保存が必要です。
電子帳簿保存法では、これまで電子データでの保存義務がなかったものの、改正電子帳簿保存法により電子取引データに限り保存義務が定められることとなりました。電子取引データとは、電子メールやインターネット上のサービスなどを介してやり取りした電子データのことです。
電子データで受け取った見積書、あるいは電子データで送信した見積書の控えは、電子データでの保存が必要です。ただし経過措置として、2023年12月31日までの取引は電子データでやり取りしたものでも印刷して保存することが認められます。
令和5年度の法改正により、上記の経過措置は2023年12月31日を期限に廃止されます。ただし、次の要件をすべて満たす場合は、電子データを保存する際に「改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)」「検索機能の確保の要件」「見読可能装置の備付けの要件」などの保存要件が不要となります(※2024年(令和6年)1月1日以後に行う電子取引について適用されます)。
- 相当の理由があると認められる場合(事前の手続は不要)
- 電子データの出力書面の提示や提出が求められたら、それに応じられるようにしておくこと
- 電子データのダウンロードが求められたら、それに応じられるようにしておくこと
見積書をスキャナ保存するときのタイムスタンプの期限は?
紙で受け取った見積書、紙で発行した見積書控えは、電子帳簿保存法によりスキャナ保存が認められています。しかし、スキャナ保存は、これまでやや厳しい条件が定められていました。
改正電子帳簿保存法ではスキャナ保存の条件が緩和され、タイムスタンプの付与は3営業日以内などの複数の条件から、最長2か月+7営業日以内に期限が統一されています。タイムスタンプをすぐに付与できなかった会社でもスキャナ保存をしやすくなりました。
タイムスタンプ付与の代わりに、時刻証明機能のあるシステムまたは訂正・削除の記録を確認できるクラウド等を使用していれば、タイムスタンプ付与要件に代替することもできます。
見積書のスキャナ保存には一定の不正防止の措置が必要?
これまでの電子帳簿保存法では、スキャナ保存の実行には適正事務処理要件を満たす必要がありました。適正事務処理要件とは、相互けん制、定期的な事務処理の検査、再発防止策の社内規定整備などを定めた事務手続きに関する要件です。
適正事務処理要件が廃止された改正電子帳簿保存法上では、これまで厳格に定められていた一定の不正防止措置を行う必要がなくなりました。改正電子帳簿保存法では、改変できないシステムやクラウドサービスを利用すれば、誰でもスキャナ保存を利用しやすいようになっています。
令和5年度の法改正では、スキャナ保存の要件緩和措置が設けられました(※2024年(令和6年)1月1日以後に行う電子取引について適用)。主な要件緩和措置は、次の3つです。
- 入力者情報の登録不要
- 解像度や階調・大きさのスキャナで読み取った際の情報は保存不要
- 相互関係性を求める書類を重要書類のみに限定
契約に至らない見積書も保存が必要?
電子帳簿保存法などでは、契約に至らなかった見積書の保存について明文化されていません。その後の契約につながっていないことと、実際に取引が行われていないことで会計処理も発生しないことから、契約に至らなかった見積書については保存しなくても問題はありません。
見積書の保存期間は?
法人税法によって、帳簿、取引に関して作成または受領した書類は、確定申告書提出期限の翌日から7年の保存が義務付けられています(青色申告書を提出した事業年度で欠損が生じたときなどは10年の保存が必要です)。
個人事業主においても5年間は見積書を保存しておかなくてはなりません。電子データであるかどうかに関係なく、見積書は一定期間の保存が義務付けられています。
見積書がPDFで届き、請求書が紙で郵送されて来た場合はどうする?
改正電子帳簿保存法により、電子取引データは電子データでの保存が義務付けられました。PDFで送られてきた見積書は、次の要件を満たしたうえでの電子データ保存(PDFやスクリーンショットでの保存も可能)が必要です。
- 改ざん防止の措置(タイムスタンプ付与、履歴の残るシステムでの授受や保存、など)
- 日付、金額、取引先の検索可能性(索引簿作成、規則的なファイル名の設定も可能)
- ディスプレイやプリンターなどの備え付け
紙で送られてきた請求書は、紙の原本をそのまま保存する方法とスキャナ保存による電子データ保存のいずれも認められます。一方、電子データで受領した見積書は、2023年12月31日以降はプリントアウトして保存することは認められません。
原則として保存は電子データで行い、紙で受領した書類のみ紙のままでも認められると覚えておきましょう。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、見積書を含めた国税関係帳簿書類の電子データによる保存を認める法律です。正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
1998年に創設された法律であり、これまでに度々改正が行われ、令和3年度の税制改正でも改正されました。2022年4月1日から、令和3年度の税制改正を反映させた改正後の電子帳簿保存法が施行されています。さらに、令和5年度も法改正が行われ、2024年1月1日以降に行われる電子取引に適用されます。
電子帳簿保存法については、以下の記事より詳細をご覧ください。
改正電子帳簿保存法に適応させて見積書を保存しよう
改正電子帳簿保存法の施行により、特に電子取引データについて大きな変更がありました。2023年12月31日までは電子データをプリントアウトして保存することも認められますが、以降は電子データでの保存が義務付けられます。PDFなどで受け取った見積書も対象になりますので、電子データで保存する際は、電子帳簿保存法の要件を満たしたうえで保存を行いましょう。
よくある質問
見積書は保存する必要がある?
法人税法で原則7年の保存が義務付けられているほか、電子取引データでやり取りした見積書は電子データでの保存が電子帳簿保存法により義務付けられています。詳しくはこちらをご覧ください。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の電子データによる保存を認める法律です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。





