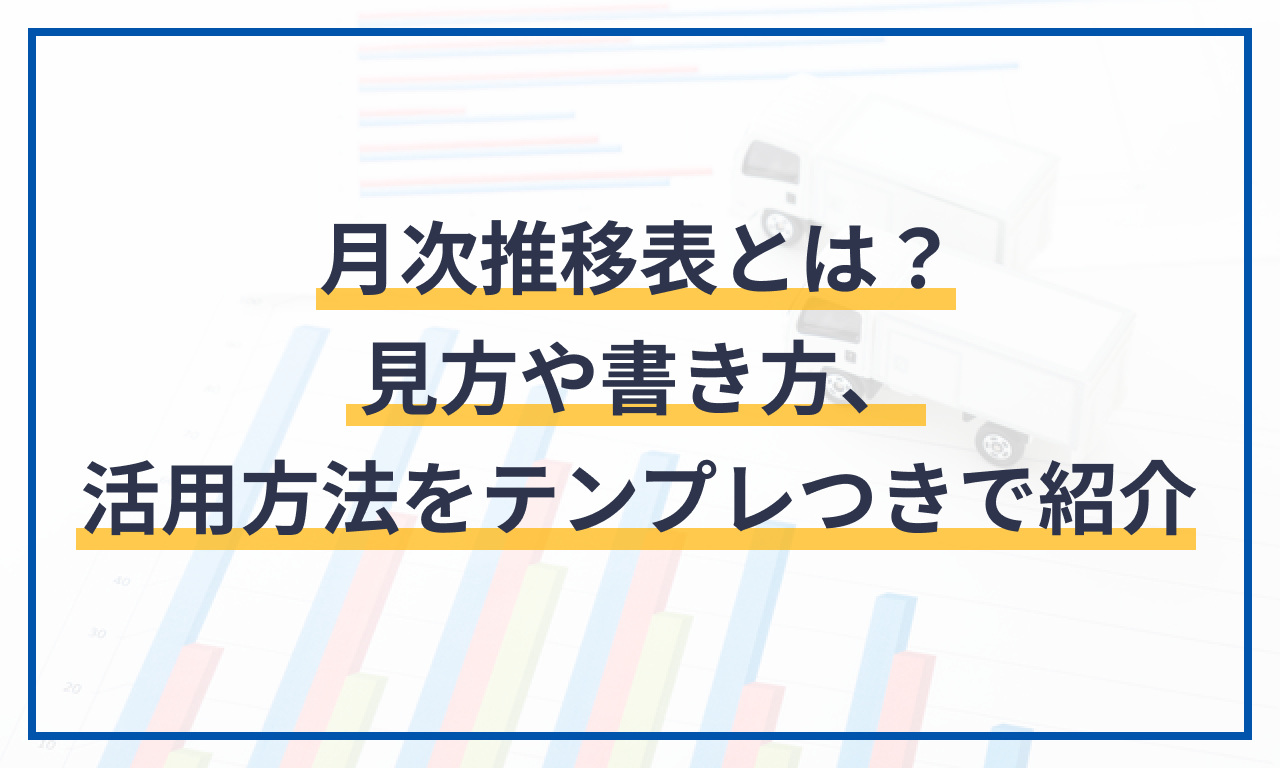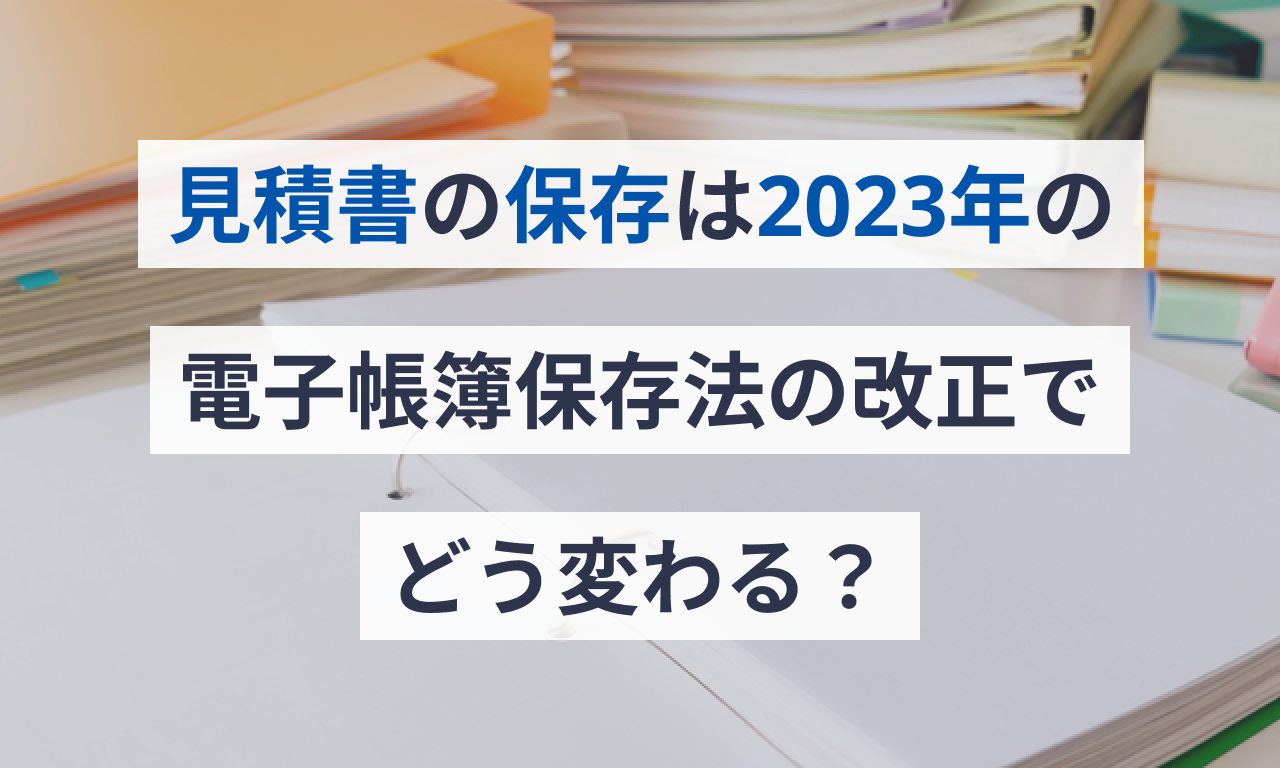- 作成日 : 2021年5月25日
償却資産申告書とは?対象の資産や書き方、固定資産税の納付までわかりやすく解説

土地や建物を所有しているとき、地方自治体から固定資産税が課税されることはよく知られているかと思いますが、これ以外に土地や建物以外の事業用の償却資産がある場合に、固定資産税として償却資産税が賦課されることがあります。償却資産とは何か、この記事では、償却資産の概要や課税対象となる償却資産、償却資産申告書の記入例などを解説していきます。
目次
償却資産申告書とは?
償却資産申告書とは、個人や法人が所有する償却資産について、地方自治体が適切に固定資産税を計算できるよう、所有者自らが償却資産を申告するための書類です。償却資産申告書の記載対象は事業用の償却資産であり、土地や建物については申告書を提出する必要はありません。これは、土地や建物は、登記により不動産の状況を確認できる一方で、償却資産に関しては土地や建物のような登記がないためです。所有者自らが地方自治体に対して償却資産の所有を明らかにする必要があり、そのために「償却資産申告書」が存在しています。
償却資産申告書の提出から納税までの流れ
申告書提出から納税までの流れを簡単に説明します。
1. 償却資産申告書を提出する
1月31日が提出期限です。申告書には、その年の1月1日時点で所有する償却資産を申告します。提出先は、償却資産の所在する市区町村の市役所、東京23区の場合は所在する区の都税事務所です。
2. 課税台帳への登録と公示
申告書の内容、調査の内容から償却資産の価格などが決定され、課税台帳に登録されます。登録後、公示が行われた段階で、所有者は課税台帳の内容を確認できます。登録内容に不服があれば、審査の申し出が可能です。
3. 納税通知書の交付と納付
償却資産税は賦課課税方式です。申告時に納税義務者が支払うのではなく、後日、自治体より納税通知書と納付書が送られてくる形になります。通常は、年4回に分けて支払えるような形で納付書が届くことが多いです。
そもそも償却資産税とは?
償却資産申告書のことについて説明してきましたが、そもそも固定資産税の対象になる償却資産とは何なのでしょう。償却資産の概要と対象となる資産、特例について解説します。
償却資産税は固定資産税の一種
減価償却の対象となる事業用の償却資産を所有している場合、所有者に納税義務が発生します。償却資産税は、固定資産税の一種です。固定資産税は地方税で、固定資産が所在する自治体から課税されます。
償却資産税の対象となる資産は?
償却資産に該当するかは、まず、減価償却対象の事業用の償却資産に該当するか、所得税や法人税の計算上、経費や損金に算入されているまたは類するものかで判断します。例えば、業種別だと以下のような資産が償却資産に該当する可能性が高いです。
[業種別の償却資産の例]
| 一般 | パソコン、コピー機、LAN設備、ルームエアコン、応接セット、看板、屋外広告塔、机や椅子、など |
| 小売業 | 陳列棚、放送設備、室内装飾、など |
| 飲食業 | 冷凍冷蔵庫、厨房用品、カウンター、など |
| 建設業 | 大型特殊自動車、自動車税等の課税対象とならない土木建設車両、など |
| 不動産賃貸業 | 舗装、電気設備、中央監視設備、など |
| ホテル・旅館 | 厨房設備、客室設備、放送設備、駐車場設備、など |
| 理美容業 | 理美容洗面設備、理美容椅子、など |
| 医業 | 手術台、レントゲン装置、手術機器、薬品棚、など |
なお、申告しなければならない事業用の償却資産には、以下のような資産も含まれます。
- 事業用に供されているが建設中のため建設仮勘定で処理されている資産
- 完成しているものの未稼働状態の資産
- 稼働を休止している遊休資産
- 帳簿上にはない簿外資産
- 減価償却が終わり備忘記録のため1円で計上されている資産
会計上は減価償却費として計上されていない資産であっても償却資産申告の対象になることがあります。重要なのは、事業用資産としてすぐに使える状態で所在しているかどうかです。使える状態であれば、償却済みのもの、帳簿上にないものも申告対象になります。このほか、社宅などの福利厚生のための設備も償却資産の対象です。
※償却資産の具体例などは各自治体のホームページなどから確認できます。
一括償却資産の特例
償却資産申告の対象になる資産であっても、一時に損金算入する10万円未満の資産、一括償却資産の特例を使って3年で一括償却した20万円未満の資産は申告の必要がありません。資産を取得したのと同等の効果が得られるファイナンス・リース取引によるリース資産も、20万円未満のものについては申告の対象外となります。
注意したいのは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使った資産は申告の対象になるということです。同特例は、青色申告法人の中小企業等に認められた特例で、取得価額30万円未満の要件を満たした資産は損金にできるというものです。税務上、その年の経費に一括して計上できます。損金算入の特例としては、中小企業等の特例は3年間の一括償却の特例と似ていますが、償却資産申告の有無が異なります。中小企業等の特例では申告の対象外にならないことに注意しましょう。
償却資産申告書の書き方
償却資産申告書には、一般方式と電算処理方式があります。一般方式は、初年度に申告対象の全償却資産を申告し、2年目以降は償却資産の増加や減少についてのみ申告する方法です。償却資産の評価額は自治体側が行うため、申告に必要な内容が簡易的です。一方、電算処理方式は、毎年すべての償却資産を申告し、評価額の計算も事業者側で行う方法になります。償却資産の増減が多くない場合は一般方式が便利ですが、法人などで償却資産の増減の多いケースでは、作成ソフトなどを使い電算処理方式で申告する方が作成は容易な場合もあります。
ここでは、申告2年目以降、一般方式を使って償却資産申告書作成するときの書き方を説明します。(例として東京都主税局の償却資産申告書を使用)
[種類別明細書(増加資産・全資産用)の書き方の例]

種類別明細書(増加資産・全資産用)には、前年中に取得した償却資産の種類や名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、増加事由を記載します。課税標準など、上の緑色の部分は提出後の処理で使われる部分ですので記入しません。申告漏れや増加償却など、特別な理由があれば右端の適用の欄に記入します。
[種類別明細書(減少資産用)の書き方の例]

前年中に売却や除却などで償却資産の減少があれば、種類別明細書(減少資産用)に記入します。記入が必要な項目は、資産コード、資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額などです。
[償却資産申告書]

種類別明細書の内容をもとに、償却資産申告書を作成していきます。特に重要なのは、償却資産の種類別の取得価額の項目です。「前年中に取得したもの」の欄には、各資産種別に所有する償却資産の取得価額の合計を記載します。種類別明細書を使って作成する部分は、「前年中に減少したもの」と「前年中に増加したもの」の部分です。資産種別に合計して、減少額と増加額をそれぞれ記入し、申告書の指示に従って、1月1日時点の所有する償却資産の取得価額の合計を計算します。申告書の8~18番については必要に応じて記入してください。上の画像の緑色の部分は、提出後に処理される部分であるため、提出者側で評価額などを計算する必要はありません。
以上のように、一般方式であれば、取得価額などの償却資産の内容を把握していればその内容を記入するだけ済みます。評価額の計算などが必要な電算処理方式と比べ申告が楽です。
※東京都主税局の申告書をもとに書き方の例をあげましたが、自治体によって償却資産申告書の書式が少し異なる部分もあるため、申告する自治体の申告書を確認ください。
償却資産申告書を提出しないとどうなる?遅れた場合は?
申告すべき償却資産があるにも関わらず、償却資産申告書を提出しなかった場合、地方税法や自治体の条例により、過料(金銭罰)が課されることがあります。提出が遅れた場合については、明確に処罰が定められていないケースもありますが、提出がなかったとみなされることもあります。この場合についても、過料が課される可能性があるため、注意しましょう。
償却資産申告書をきちんと提出しよう
申告すべき償却資産があるにも関わらず、提出を怠った場合ペナルティとして過料が課せられることがあります。自治体から指摘される前に、適切に償却資産の申告を済ませましょう。なお、償却資産申告書に記載の必要がある償却資産の内容は、償却資産の管理ができるソフトを使うと便利です。その都度調べなくても、ソフトの情報をもとに申告書を作成できます。
よくある質問
償却資産申告書とは?
個人や法人が所有する償却資産について、地方自治体が適切に固定資産税を計算できるよう、所有者自らが償却資産を申告するための書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
償却資産税の対象となる資産は?
減価償却対象の事業用の償却資産に該当するか、所得税や法人税の計算上、経費や損金に算入されているまたは類するものかで判断します。詳しくはこちらをご覧ください。
償却資産申告書の書き方は?
償却資産申告書には、一般方式と電算処理方式があります。記載例についてはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。