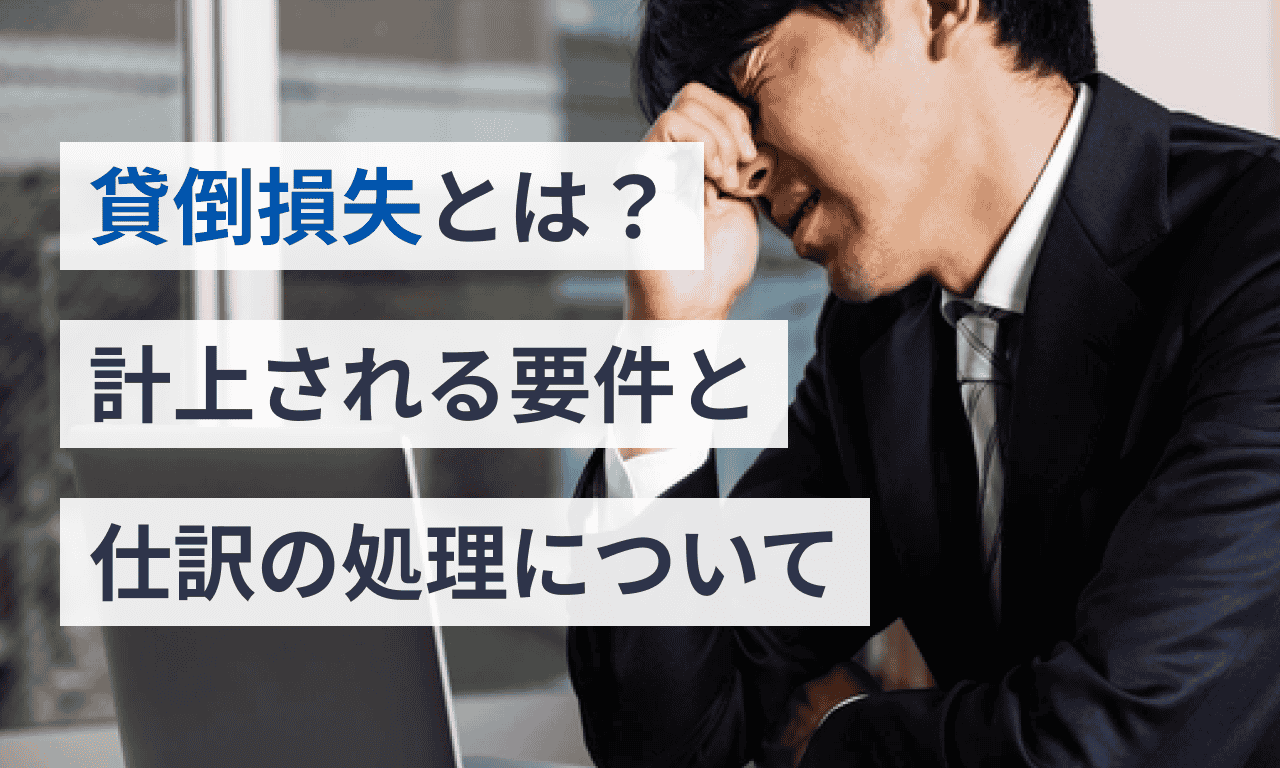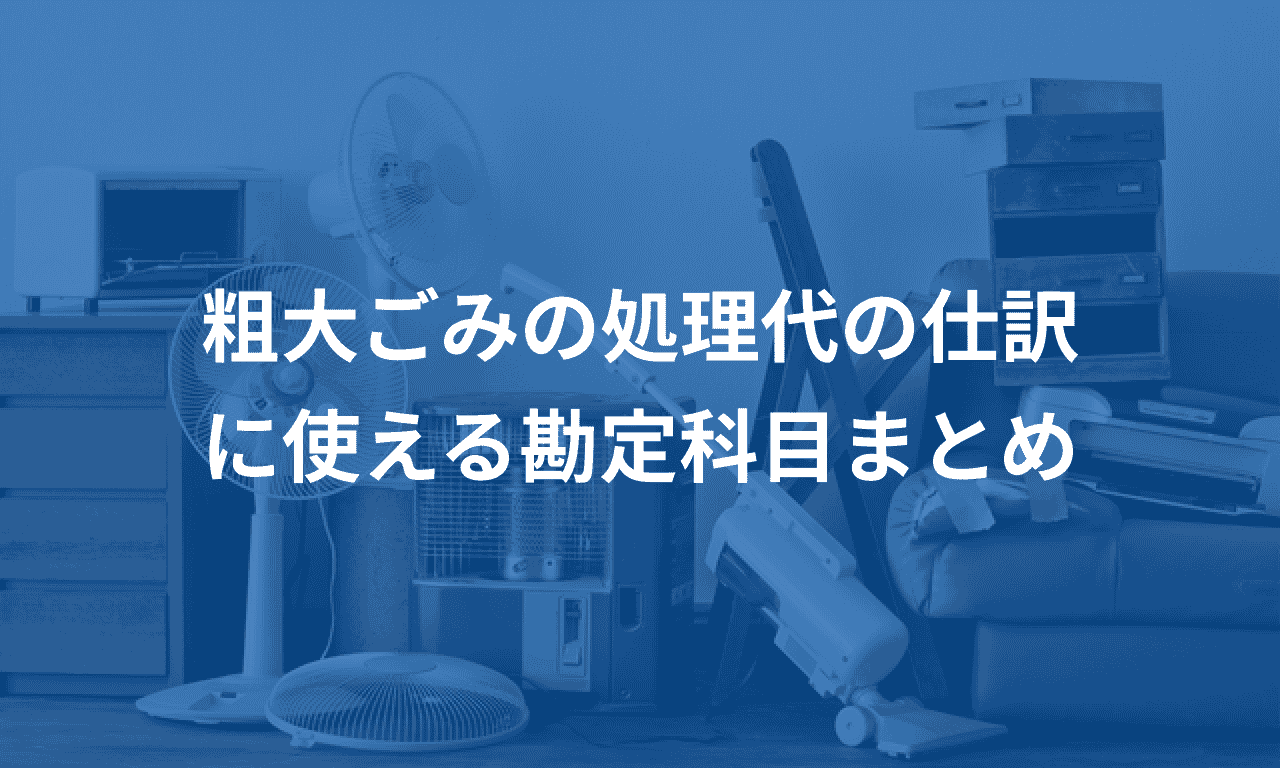- 更新日 : 2021年6月21日
免税事業者は消費税を請求していいのか?
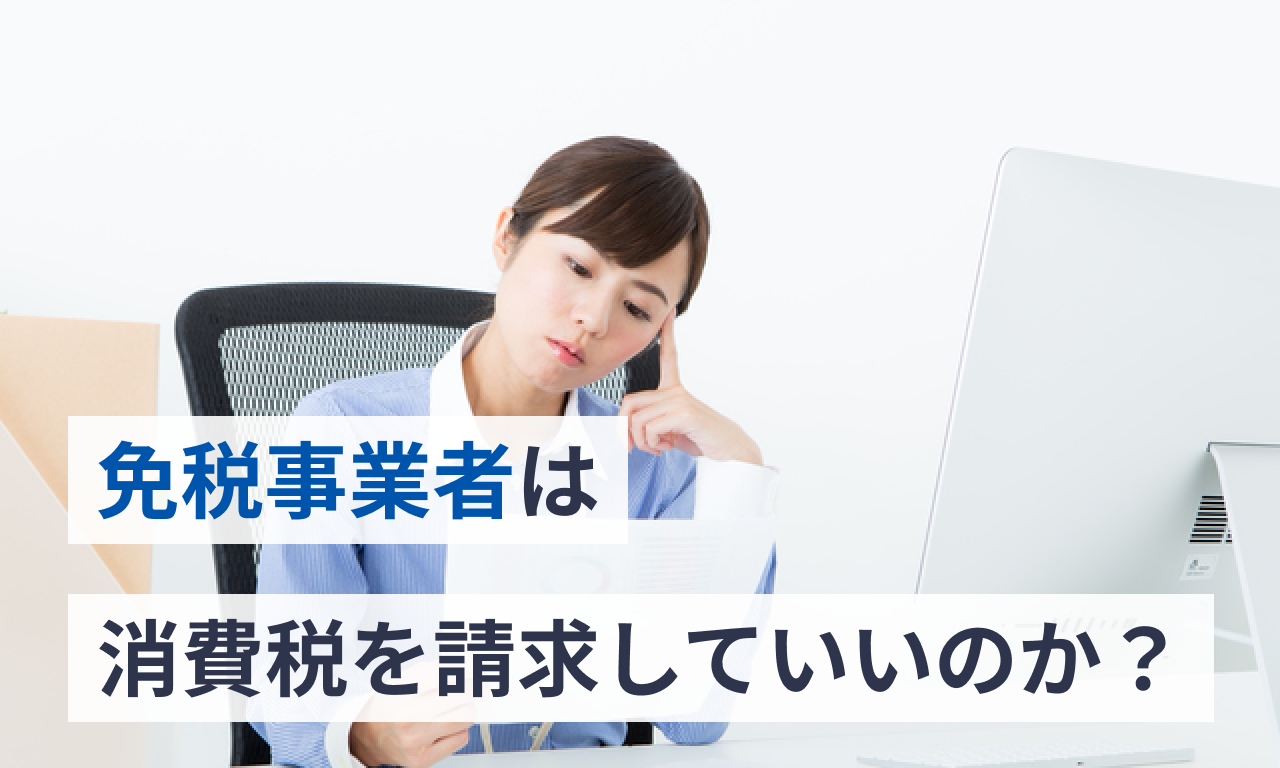
間接税である消費税は、事業者が消費者から預かって納税するものです。ところで、事業者の中には消費税の納税を免除されている免税事業者があります。消費税の納税義務のない免税事業者は、消費税を請求できないのでしょうか?
本記事では、免税事業者における消費税の取り扱いについて説明します。消費税増税後に注意しておきたい点も含めて理解しておきましょう。
目次
免税業者(免税事業者)の条件は?
免税事業者となるためには要件があります。どのような場合に消費税が免除になるのかを知っておきましょう。
消費税のしくみ
消費税は、物やサービスを購入したときにかかる間接税になります。間接税とは、実際に税金を負担する人と納税する人が異なる税金です。
消費税を負担するのは消費者ですが、消費者が直接税務署に納めるわけではありません。物やサービスを販売する事業者が、消費者から消費税を預かって税務署に納税します。
なお、事業者が商品などの仕入れをする際にも、消費税を払っているはずです。そのため、事業者が消費税を納税するときには、消費者から受け取った消費税から仕入先に支払った消費税を差し引きすることができます。これを「仕入額控除」といいます。
消費税の税率
消費税には、国税である消費税と、都道府県税である地方消費税が含まれます。2019年10月1日に消費税率の引き上げと同時に軽減税率制度がスタートし、現在は次の表のような税率となっています。
| 標準税率 | 軽減税率 | |
|---|---|---|
| 消費税率 | 7.8% | 6.24% |
| 地方消費税率 | 2.2% | 1.76% |
| 合計 | 10.0% | 8.0% |
消費税の免税事業者とは?
消費税の免税事業者とは、消費税の納税を免除されている事業者、すなわち納税義務のない事業者です。免税事業者になるかどうかは、基準期間の課税売上高により判定します。
基準期間とは?
基準期間とは、次のとおりです。
・個人事業主の場合・・・その年の前々年
・法人の場合・・・その事業年度の前々事業年度
上記の基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者となります。例えば、個人事業主の2019年の消費税納税義務は、2017年の課税売上高が1,000万円を超えている場合に発生します。
特定期間とは
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば納税義務は免除になりません。特定期間とは、次のとおりです。
・個人事業主の場合・・・その年の前年の1月1日から6月30日までの6カ月間
・法人の場合・・・その事業年度の前事業年度開始日以後6カ月間
新規開業時はどうなる?
新規開業から2年間は基準期間の課税売上高がないため、原則としてその課税期間の納税義務は免除されます。ただし、設立2年目については、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。また、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定することもできます。
なお資本金1,000万円以上の法人に関して、納税義務は免除されないので、設立1期目から消費税を納めなければなりません。
免税業者(免税事業者)の消費税請求について
免税事業者は消費税の納税を免除されているので、「顧客に対して消費税を請求できないのではないか?」と思うこともあるでしょう。免税事業者であっても、消費税を請求することはできます。
免税事業者も消費税を上乗せ請求できる
消費税法や国税庁の通達では、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていません。また、免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ、仕入れ時に払った消費税を自己負担しなければならないことになります。
免税事業者であっても、消費税を請求することに問題はありません。なお、消費税が10%に引き上げになった2019年10月1日より「区分記載請求書保存方式」が導入されているので、請求書では税率8%の品目と税率10%の品目を分けて表示する必要があります。
免税事業者からの仕入額控除が段階的廃止に
消費税率引き上げと軽減税率制度導入に伴って、2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」も開始します。インボイス方式では、事業者は適格請求書(インボイス)に記載された消費税でないと仕入額控除ができません。
インボイス方式では、登録を受けた課税事業者のみがインボイスを発行可能となります。免税事業者が発行した請求書は仕入額控除の対象にならないので、インボイス方式が開始すると、免税事業者から取引先事業者への消費税の請求は実質的に困難になってしまいます。
取引先に消費税を請求できなければ、仕入れの際に支払った消費税を自己負担しなければなりません。また、取引先の事業者側がインボイスを発行できる課税事業者との取引を優先することも考えられ、免税事業者は取引の機会を失ってしまう可能性もあります。
今後は課税売上高1,000万円以下であっても、課税事業者になった方がメリットになるケースが多くなります。インボイス方式は2023年10月以降段階的に導入され、2029年10月以降は免税事業者からの仕入れについて仕入額控除が一切できなくなります。時期を見計らって、課税事業者になるかどうか検討すべきでしょう。
「消費税転嫁対策特別措置法」について
消費税増税時に注意しておきたいのが、取引先による消費税の転嫁拒否といった不当行為です。消費税の転嫁拒否等を取り締まるため、消費税転嫁対策特別措置法が設けられています。
消費税転嫁対策特別措置法は、事業者間取引における消費税の転嫁拒否などを禁止する法律です。正式には「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」という名称になります。
消費税転嫁対策措置法が設けられているのは、2014年4月及び2019年10月の消費税増税時に、増税分の転嫁拒否が横行することが予想されたからです。こうしたことから、消費税転嫁対策特別措置法は、2021年3月までの期間のみ有効な法律となっています。
消費税の転嫁拒否は認められない
消費税転嫁対策特別措置法では、買い手である事業者による消費税の転嫁拒否が禁止されています。
例えば、卸売業者がメーカーから商品を仕入れて小売業者に売る場合、卸売業者はメーカーに消費税込みの価格を支払い、小売業者には消費税込みの価格を請求します。消費税の増税があった場合には、消費税込みの価格が引き上げられるのが当然です。
しかし、買い手は売り手より強い立場なので、売り手に対して「消費税の増税分は値引きして」等の要求をすることが考えられます。このように、消費税の転嫁を阻害して売り手に不利益をもたらす行為は認められません。
消費税転嫁対策特別措置法による禁止行為
消費税転嫁対策特別措置法で禁止されているのは、次のような行為です。
(1)減額
本体価格に消費税を上乗せした額を支払う契約をしていたにもかかわらず、支払う段階になって消費税の全部や一部を減額する行為は認められません。
(2)買いたたき
買いたたきとは、消費税率引き上げ前の税込価格に増税分を上乗せした金額よりも低い対価を定めることです。増税前の税込価格をそのまま据え置きしても、買いたたきとなってしまいます。
(3)商品購入・役務利用または利益提供の要請
消費税率引き上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、特定の商品やサービスを買わせたり、その他の利益供与を要求したりすることも禁止されています。
(4)本体価格での交渉の拒否
消費税抜きの本体価格で交渉したいという申出を拒否することも禁止です。
(5)報復行為
(1)~(4)の行為が行われていることを公正取引委員会などに知らせたことを理由に不利益な取り扱いをすることも認められていません。
消費税の転嫁拒否をするとどうなる?
消費税の転嫁拒否については、公正取引委員会や中小企業庁長官が必要な指導・助言を行います。違反行為が認められた場合には、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表することになっています。
もし消費税の転嫁拒否等に遭った場合には、公正取引委員会や消費生活センターなどの相談窓口に相談しましょう。
よくある質問
消費税の免税事業者とは?
消費税の納税を免除されている事業者、すなわち納税義務のない事業者のことを言います。詳しくはこちらをご覧ください。
免税事業者は顧客に対して消費税を請求できないのでしょうか?
結論から言いますと、請求できます。ただし、表示方法には注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
消費税転嫁対策特別措置法による禁止行為はなんですか?
減額、買いたたき、商品購入・役務利用または利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為などが禁止されています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。