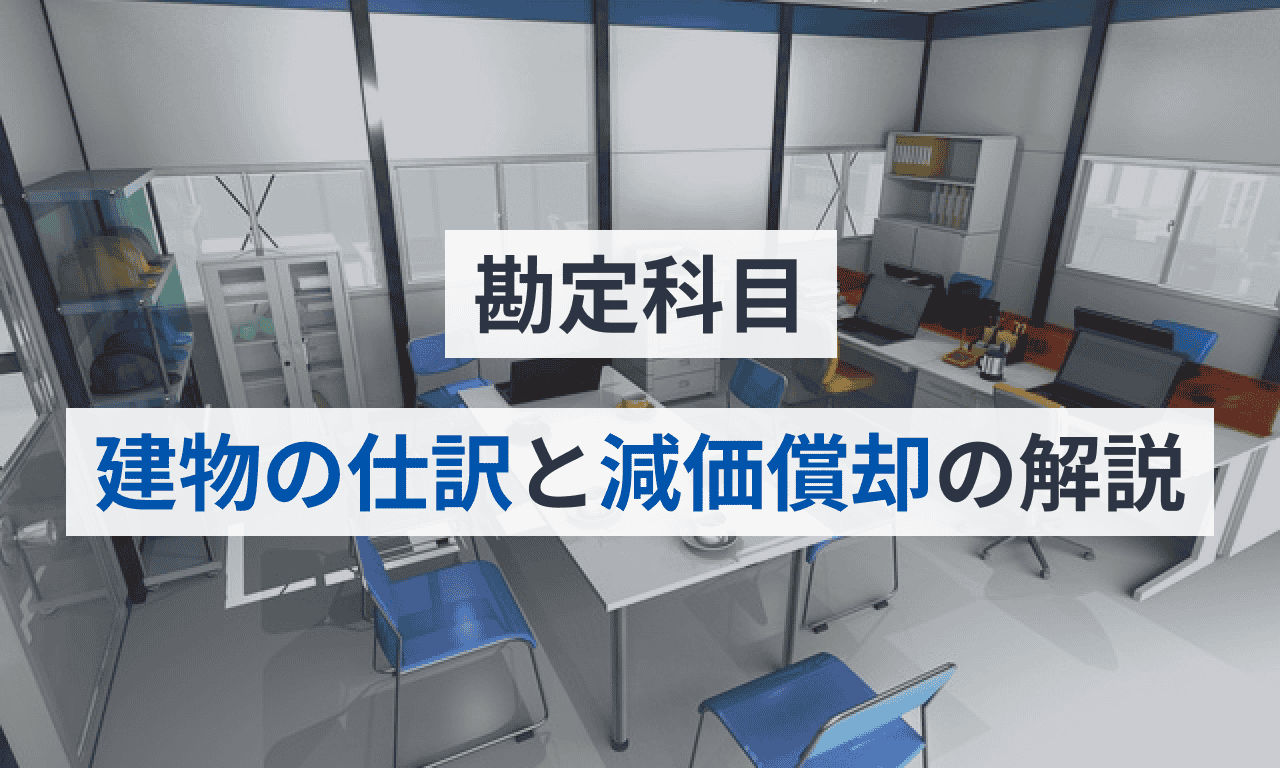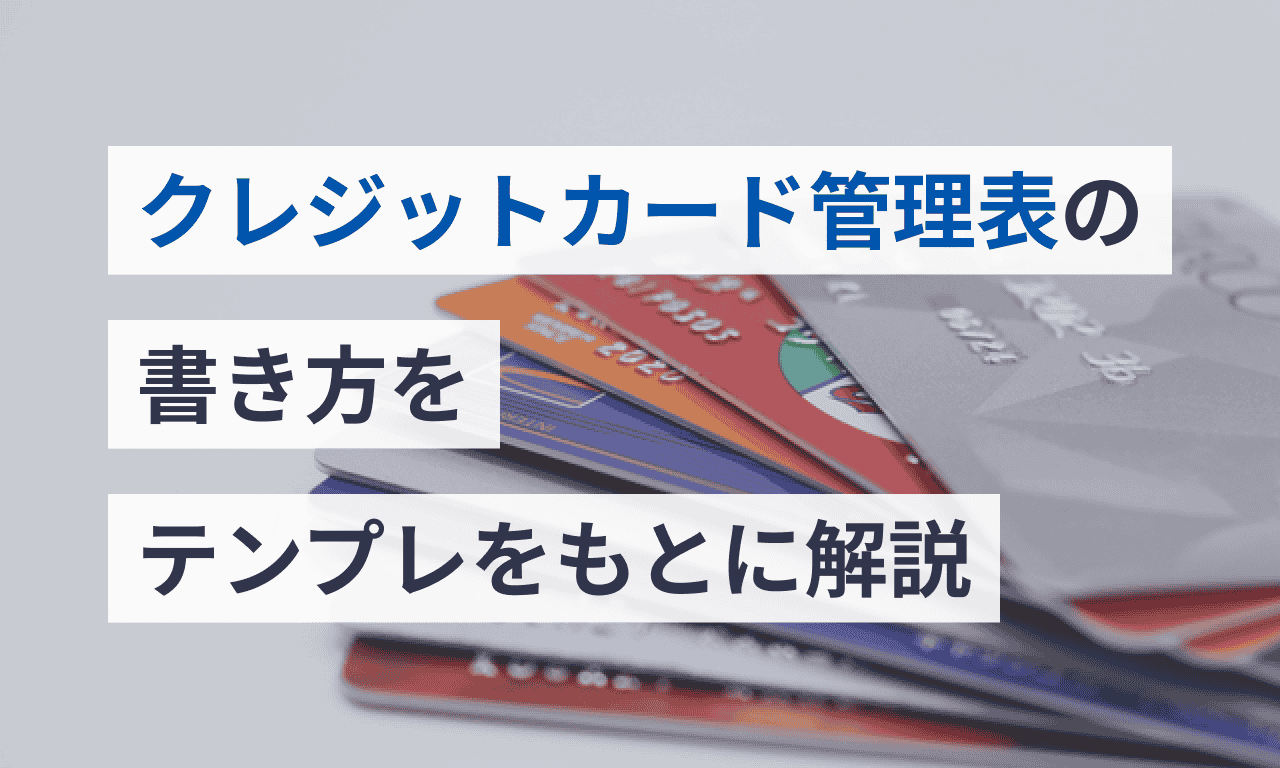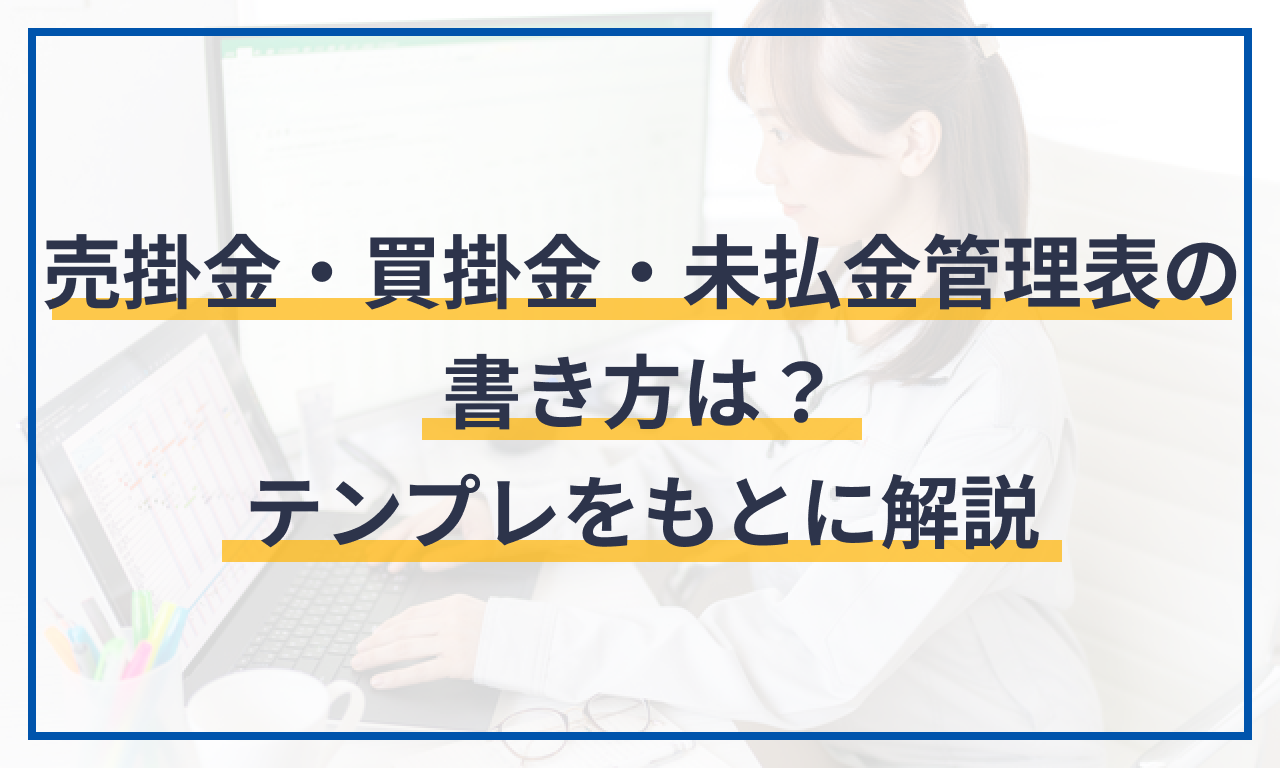- 作成日 : 2022年4月22日
強制評価減とは?わかりやすく解説

強制評価減は取得原価と期末時点での時価に著しい乖離が見られる場合に、強制的に帳簿価額を下落させる会計処理です。それぞれの資産区分に応じて強制評価減を行う要件があるのが特徴です。
今回は強制評価減の概要や条件、例外、減損会計との違いについて解説します。
強制評価減とは
強制評価減とは期末時点での時価に著しい下落が見られるときに強制的に帳簿価額を減額する会計処理です。主に取得原価で評価している場合が多い有価証券において行われます。
「著しい下落」の目安は時価が取得原価と比較して、50%以上落ち込んだときです。
強制評価減の適用条件は、市場価格のある有価証券と市場価格のない有価証券で異なります。市場価格のある有価証券は、シンプルに取得原価と時価を比較して考えます。
時価を貸借対照表に記載し、評価差額は当期の損失として扱わなくてはなりません。例外的に時価に回復の見込みがあるなら、評価減を行わない処理も認められています。
市場価格のない有価証券の場合、財政状態が悪化し、有価証券の実質価額に著しい低下が見られたときに相当の減額を行い、差額を当期の損失として処理しなければなりません。
ただし、回復可能性を示す証拠を提示できるときは、評価減を行わないことが認められます。例えば、子会社や関連会社の場合、事業計画を入手して回復可能性を判断できるなら、減額をしなくてもよい可能性があります。
強制評価減の適用要件と例外
強制評価減が可能な資産は有価証券以外にも棚卸資産や固定資産、繰延資産などが該当します。それぞれの資産において評価減を行う条件が規定されているため、会計処理の方法で迷ったときはこのルールを確認しましょう。
ここでは各資産の区分における強制評価減の適用要件と例外を紹介します。
棚卸資産
棚卸資産の場合、次に該当したときに強制評価減が認められます。
- 著しく陳腐化したこと
- 災害により著しく損傷
- その他特別な事実がある場合
「著しく陳腐化した」とは棚卸資産自体に物質的な欠陥が存在しないにも関わらず、経済的な環境の変化によって価値が著しく減少し、今後の回復が見込まれない場合を指します。具体的には次のようなケースです。
- 売れ残った季節商品において、今後は通常価額では販売できないことが既往の実績や事情に照らし合わせて明らかである場合
- ある商品と用途はおおむね同じであるが、性能や品質等が著しく異なる製品が新たに販売されたことで、元の商品について今後通常の方法で販売することができなくなった場合
有価証券
有価証券において強制評価減が可能となる詳しい条件は次の通りです。
- 特定種類の有価証券について、その価額大きく低下したこと
- 1以外の有価証券について、経営状態が著しく悪化したためその価額が著しく低下したこと
- その他特別な事実がある場合
特定種類の有価証券とは、取扱有価証券、店頭売買有価証券、取引所売買有価証券、その他の価格公表有価証券などを指します。
固定資産
固定資産における強制評価減の適用条件は次の通りです。
- 災害により著しい損傷が見られること
- 1年以上の遊休状態にあること
- 本来の用途に使用できずに他の用途へ用いられたこと
- 所在の場所が著しく変化したこと
- その他特別な事実がある場合
繰延資産
繰延資産における強制評価減の適用条件は次の通りです。
- 他者の有する固定資産を使用するために拠出したものについてはその対象の固定資産について、災害や1年以上の遊休、用途変更、立地条件の変化があったこと
- 1に準じた特別な事実があったこと
例外
原則として金銭債権(例:貸倒引当金)は評価損の対象になりません。また、棚卸資産の価額低下は単に物価変更、建値の変更、過剰生産、等の事情だけでは評価損の対象になりません。
固定資産の場合、価額低下が過度の使用、修理の不十分、償却不足等の事実に基づく場合も評価損の計上は不可能です。
強制評価減と減損の違い
帳簿価額を強制的に切り下げる会計処理には減損会計もありますが、こちらは強制評価減と定義が異なります。
減損会計は土地や機械など保有する固定資産の収益性が低下した結果、その資産に投資した金額を回収できないと見込まれる場合に一定の基準に基づき、資産価値を下落させる会計処理です。
強制評価減では時価と取得原価との差額を損失として計上するのに対し、減損会計の場合将来にわたって回収できないと見込まれる投資額を損失と見なします。
減損会計の対象は有形固定資産や無形固定資産、投資その他の資産などです。上場企業は減損会計が強制適用となり、非上場企業でも会計検査の義務がある大企業も行わなくてはなりません。
強制評価減は期末時点での価値下落を帳簿に反映させる会計処理
強制評価減は期末時点で価値が著しく下落した資産について、その下落分を帳簿価額に反映させる会計処理です。主に有価証券に適用されますが、棚卸資産や固定資産、繰延資産なども対象となる場合があります。
「著しく下落」の目安となるのは、帳簿価額から50%下落した場合です。時価と取得原価との差額は、当期の損失として処理します。
よくある質問
強制評価減とは?
取得原価と期末時点の時価に著しい差が生じている場合に帳簿価額を減額する処理です。詳しくはこちらをご覧ください。
強制評価減と減損の違いは?
強制評価減は取得原価に比べて時価が著しく下落した時に行われるのに対し、減損は投資額を将来的に回収できないと見込まれるときに行う処理です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。