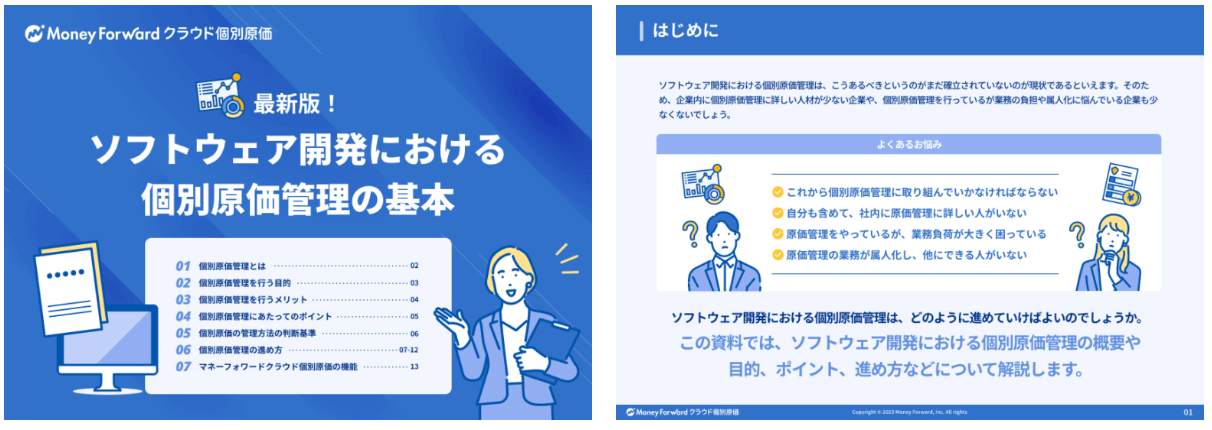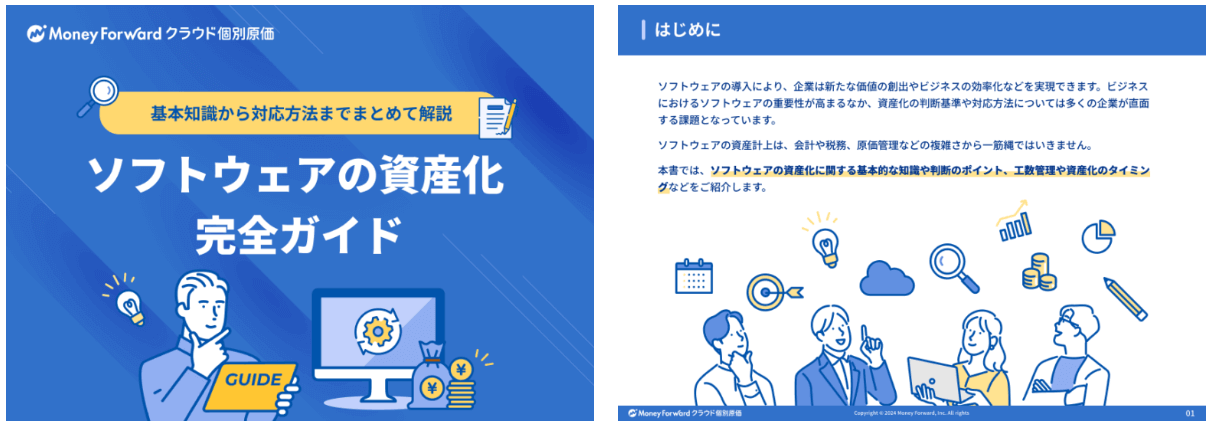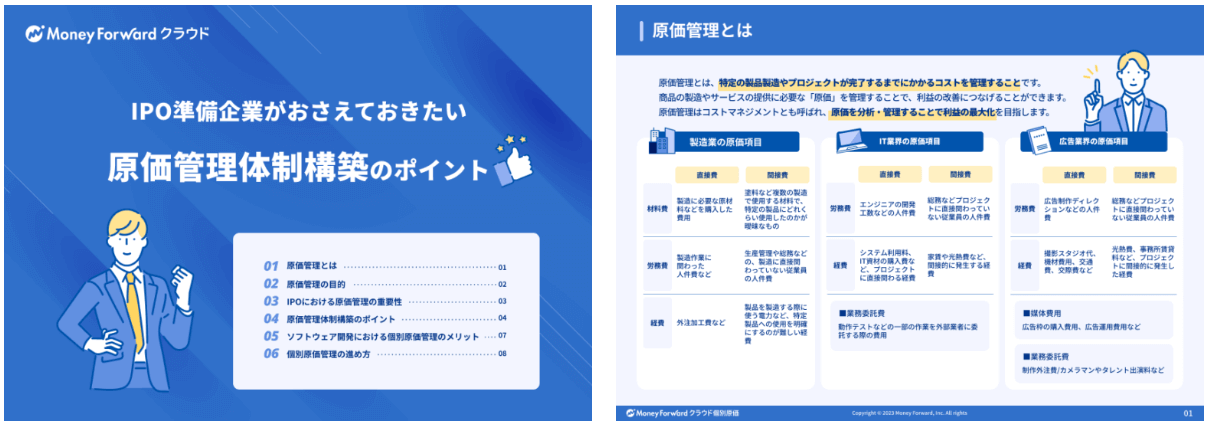- 作成日 : 2025年3月19日
建設業の原価管理とは?基本からメリット、システムの選び方まで解説!
建設業の工事原価管理が大変で改善を考えている経理担当者や経営者は少なくありません。
本記事では、建設業における原価管理の基本から、原価管理するべきメリットや、原価管理システムを導入する必要性を解説します。
建設業の経理担当者や原価管理で利益を上げたいという方はぜひチェックしてみてください。
目次
建設業における原価管理とは?
ASBJ(企業会計基準委員会)が定めた定義によると、原価計算制度における原価とは「経営における一定の給付にかかわらせて、把握された財貨又は用役の消費を、貨幣価値的に表わしたもの」とされます。
具体的には、以下のようにまとめられます。
- 経営過程における価値の消費
- 経営のなかで生み出された一定の給付に転嫁される価値
- 経営目的に関連したもの
- 正常的なもの(災害などによる支出はない)
上記の定義を踏まえると、原価管理は「原価の標準を設定してこれを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを標準と比較して、その差異の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、原価能率を増進する措置を講ずること」と解釈できます。
参照:完成工事未収入金とは?仕訳・勘定科目や、建設業の会計基準の違いも解説
原価の分類
建設業における原価の項目を整理します。
以下の表に建設業における原価の項目を詳しくまとめました。
| 総原価 | 工事原価 | 材料費 | 建設工事に必要な主材料(鉄筋・木材・コンクリートなど)や部品(釘など)の購入や受け入れ |
|---|---|---|---|
| 労務費 | 工事現場で労働する人件費 | ||
| 外注費 | 外部事業者への委託料(一人親方など) | ||
| 経費 | 工事事務所の賃借料・光熱費・材料の運搬や保管の関係費などの細かい諸経費 | ||
| 販売費 | 宣伝広告費・営業担当者の人件費・営業担当者の旅費交通費・接待交際費など | ||
| 一般管理費 | 本社やオフィス、間接部門の水道光熱費・修繕費・通信費・新聞図書費・減価償却費など | ||
| 非原価 | 営業外費用 | 営業活動に無関係な費用(有価証券評価損・支払利息・雑損など) | |
| 特別損失 | 事業活動から発生したものでない臨時の費用(災害損失や固定資産売却損など) | ||
原価は、「総原価」と「非原価」に分けて考えます。
総原価は、製品やサービスの製造から、販売までにかかる費用です。
工事のすべての作業に関わる工事原価や販売に関する販売費、運営において必要な一般管理費の3項目に分類できます。
また、工事原価は、材料費・労務費・外注費・経費の4項目に細分化されます。
建設業・施工管理の5大管理
建設業において「QCDSE」は非常に大切です。
「QCDSE」とは建設業における施工管理の5大管理を指し、下記の頭文字を取って呼ばれます。
それぞれの具体的な内容は以下のとおりです。
| Quality(品質) | 品質・安全面について法令に定められた基準を満たした工事を管理すること |
|---|---|
| Cost(コスト) | 工事に直接携わる人件費や材料費などの費用・原価を管理すること |
| Delivery(工程・工期) | 建設物を工事期間内に工程通りに完成させるように管理すること |
| Safety(安全) | 工事現場で作業員が安全に作業できるように管理すること |
| Environment(環境) | 自然環境・周辺環境・職場環境の3つをまとめた概念 |
材料費や人件費などの原価管理の基本のことで、施工管理においてそれぞれが重要な意味と役割を持ちます。建設業ではいずれもなくてはならない要素です。
自然環境は地盤や土壌・空気汚染などの建設現場の周囲の自然環境に配慮して工事を行うことです。
周辺環境は使用する重機による音・振動・紛塵・排気ガスなどが周辺地域に迷惑をかけないように配慮し対策することを指します。職場環境は作業員が働きやすいように職場環境を整備することです。
原価管理する目的
建設業において原価管理をする目的は、適切な事業計画を遂行するほかに、コストを理解し、必要に応じて削減することです。
このほかにも県や国に提出する「完成工事原価報告書」の作成にも工事原価が必要となります。
一般的な企業では、会社法・法人税法・金融商品取引法などの法律で定められている計算書類や財務諸表の提出が必要です。
しかし、建設業においては計算書類に加えて、建設業法で定められた「完成工事原価報告書」の提出もしなければなりません。
「完成工事原価報告書」とは、工事原価を材料費・労務費・外注費・経費に詳細に振り分けた報告書で、年に一度、建設業許可の申請・取得・更新の際に用いられる重要な書類です。
工事原価管理を行うメリット
適切な事業計画を遂行する上で、工事原価管理は重要な意味を持ちます。
具体的には主に3つのメリットがあります。
1.コスト削減
工事原価管理をすることで材料費や労務費、外注費、設備費・光熱費の諸経費など工事に着手する前に各項目において不要なコストを発見できます。
材料費や労務費において適切な数量を事前に把握できれば、余計な材料の仕入れを防ぐことが可能となります。
結果として余計なコストを削減でき、合理的な工事になります。削減できた分は利益となるため、事業拡大への投資に繋げられるでしょう。
2.損益分岐点の把握
工事原価管理で事前に各項目の支出を管理しておけば、どの程度の利益が見込まれるか粗利益が算出できます。
粗利益を算出するということは、利益額や利益率を計算し、予算と実績を比較して損益分岐点(黒字と赤字の境界線)が把握できるということです。
着工後の赤字を回避するために、想定外の支出を早い段階で発見し、黒字の施工につなげられるように対策もできるため、リスク管理にもつながります。
3.将来的な事業判断
工事原価管理を続けることで、工事における利益が明確になるデータを収集・集約できます。
過去のデータから分析し、将来的に利益の少ない事業や工事を事前に撤退できるなど、経営判断の重要な材料や基準になりえます。
毎度、予算と実績を比較し、利益の最大化を常時見込めて、利益を確保するメリットがあります。
工事原価管理を行うデメリット
工事原価管理のメリットに反して、デメリットが4つ挙げられます。工事原価管理が難しいと言われる理由や、建設業ならではの悩みにも直結しています。
工事原価管理は勘定項目が一般的な企業と比べて複雑で、売上を計上するタイミングが難しいと言われます。
さらに、項目ごとの線引きも曖昧で労務費と外注費という人件費における振り分けの判断に悩む企業も少なくありません。
また、費用の構成が複雑で、経理処理に時間と労力がかかってしまい、結果経理担当者の負担増となってしまう例があります。
1.自社に合ったシステムを選ばないと計算方法が複雑化する
自社に合ったシステムを選ばないと、計算方法が複雑化してしまいます。
建設業における会計・経理処理は一般企業と比べて複雑で特殊です。そのため、工事原価管理システムを導入する企業も多いですが、導入システムを選ぶにも難航する場合があります。
企業や事業内容によって求めるサービスにも差異があるため十分に検討して選ばないといけません。
自社に合わないシステムを導入してしまうと計算方法がより複雑化する恐れがあります。
2.特殊な勘定科目を用いる必要がある
工事原価管理の勘定科目は一般企業とちがい、特殊な勘定科目を用います。そのため複雑で難しいと言われます。
完成工事原価報告書は、国土交通省が定める「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類」に従って作成しなければいけません。
建設業会計で用いる勘定科目は以下が挙げられます。
| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 完成工事高 | 工事が完了したときに得る収益、売上高 |
| 完成工事原価 | 工事原価(材料費・労務費・外注費・経費) |
| 完成工事総利益 | 完成工事高から完成工事原価を差し引いた粗利益 |
| 未成工事支出金 | 完成前の工事で発生した費用、仕掛品 |
| 完成工事未収入金 | 工事が完了済みで翌期に入金予定のお金、売掛金 |
| 未成工事受入金 | 工事が完成し、引き渡す前に発注者から受領した場合に発生するお金、前受金 |
| 工事未払金 | 工事費の中の未払いのお金、買掛金 |
一般企業とちがう点では、建設業会計という建設業独自の経理処理を行わなければいけない点も指摘されます。
細かく勘定科目を分類する必要があり、相当の知識も求められる場合があります。
3.外注費を原価要素に加える必要がある
建設業の原価管理では、外注費を原価要素に加える必要があります。
一般的な会計では、「材料費」「労務費」「経費」の3つの要素で構成されますが、建設業においては「外注費」も含む4つで構成されます。
外注費は外部の企業や個人事業主へ支払われる委託料を指します。建設業では一人親方などの個人への発注や応援も珍しくありません。
「労務費」は契約社員のように、一定の雇用期間が決められている工事作業員・従業員の人件費を指します。
建設業の原価は工事現場ごとに管理され、原価計算の際にも「個別原価計算」に基づいて「現場別原価計算」を使用します。
4.売上・原価を計上するタイミングが特殊である
国税庁から発表され、2021年4月から導入された「収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)」によると、企業が契約内容を履行した時点で、取引先が支払う対価の額で売上計上する取り決めになりました。
この影響で、事業の売上に対しての認識と財務諸表に新しい基準で記入する必要があります。中小企業は任意になりますが、大企業と上場企業が適用対象です。
一方、未上場の中小企業は、従来通りの「工事進行基準」と「工事完成基準」という建設業ならではの計上方法で行う必要があります。
「工事進行基準」とは、工事の完成が期を跨ぐ場合における工事の進捗に合わせて売上原価を分割して計上する方法をいい、「工事完成基準」とは、工事が完成し、引き渡した時点で売上原価を認識する方法をいいます。
「工事完成基準」では完成していない工事で発生した支出分を未成工事支出金として計上する必要があります。
このように、同じ工事であっても、採用する基準によって計上時期は様々であり、売上・原価を計上するタイミングが難しいと言われる由縁となっています。
5.経理業務の負担が大きい
工事原価管理は専門用語が多用されるうえ、一般会計とは別で処理・管理しなくてはいけない点も経理業務の負担を増やしている原因です。
一般的な経理知識よりも専門的なスキルが求められることもマイナスな影響があるといえるでしょう。
さらに、建設業者にとっては毎年の建設業許可の取得と更新にも大きく影響するため、正確な原価管理が必要です。
しかし、各現場でエクセルで原価管理をしてしまうと、それらのデータを経理が集約し、完成工事原価報告書を作成する際に、ヒューマンエラーを起こす可能性を高めてしまいます。
ほかにも工事台帳の作成に時間がかかる、工事ごとの粗利や原価が把握しづらい、複数人での管理が難しいなど建設業者の経理処理には多くの課題が残ります。
だからこそ原価管理システムの導入がおすすめです。
工事原価管理システムを選ぶときのポイント
経理処理の負担を減らし、正確で効率的な管理をするなら工事原価管理システムの導入がおすすめです。
導入する場合の3つのポイントについて解説していきます。
導入する目的を明確にする
システムの導入目的は事前に明確にしておきましょう。
建設業向けの工事原価管理システムは多様で、サービス・機能・特徴など搭載内容はさまざまです。
搭載内容が必要とする経理業務範囲を網羅できるのかを判断する必要があります。
クラウド型かオンプレミス型かで選ぶ
工事原価管理システムの提供形態は「クラウド・SaaS型」や「オンプレミス型」、「パッケージ型」など多種多様です。
それぞれに特徴があるので自社に合った型を選択しましょう。
工事原価管理システムの提供形態の例を参照してください。
| クラウド型 | 導入準備が簡単で費用も抑えられるうえ、サーバーを自社に設置する必要がない |
|---|---|
| オンプレミス型 | 初期費用は高くなるが、柔軟なカスタマイズ性によって現場の要望に応えやすい |
| パッケージ型 | コストを抑えられる |
このようにさまざまな特色があるため自社に合うサービスを活用しましょう。
サポート体制があるかで選ぶ
初めて導入する場合にはサポート体制が付属していると安心です。
サポートの内容もさまざまで、導入前のデータ整備や現場の改善に着目した運用設計のサポートなど特色があります。
現場での運用が複雑になっている場合や、エクセルで管理しているために手間と負担がかかっている状態の企業におすすめです。
建設業の原価管理は管理システムで効率化しよう!
建設業における原価管理は、他業種と異なり複雑な管理が求められます。
しかし、正確に管理することで黒字経営を保持できるほか、将来的な経営判断にも役立ちます。効率的で従業員の負担軽減のためにも自社に合った工事原価管理システムの導入が必要でしょう。
マネーフォワードでは原価管理が早く正確に管理できるシステムがあります。お悩みの経営者や計襟担当者の方はぜひご検討ください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
茨城で経理代行サービスを依頼するには?費用・依頼先や対応範囲を解説
茨城県で経理代行サービスをお探しですか?この記事では、茨城県で経理代行サービスを利用する際の料金相場やメリット、対応範囲、自社に最適なサービスの選び方などを解説します。後継者問題や…
詳しくみるIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」とは
IFRS S1号は、サステナビリティ関連財務情報の開示に関する事項を定めた国際会計基準です。企業が持続可能性に関するリスクや機会を財務報告に適切に反映することで、投資家やステークホ…
詳しくみる「税理士が何も提案しない」当然の理由 上手に付き合うコツは?
社長と話をしていると、「うちの税理士は何も提案してくれない……」という不満を聞くことがあります。こう聞くと「怠慢な税理士がいるんだなぁ」と思う方もいるかしれませんが、本当にそう言え…
詳しくみる関連当事者とは?主な範囲からわかりやすく解説
業績を伸ばすために、取引先を拡大したいと考える会社は多いでしょう。しかし、取引先を選ぶ際は、相手が「関連当事者」ではないかを確認する必要があります。 今回は、会社の業績や利益に大き…
詳しくみる北九州市で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
北九州市(福岡県)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対…
詳しくみる懇親会の稟議書の書き方は?テンプレートや例文でポイントが分かる!
懇親会の稟議書は、新入社員の歓迎会や忘年会などの開催に際し、上長の承認を得るために作成します。目的や開催のメリットを明確にし、わかりやすい文章で書くことが大切です。 本記事では、懇…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引