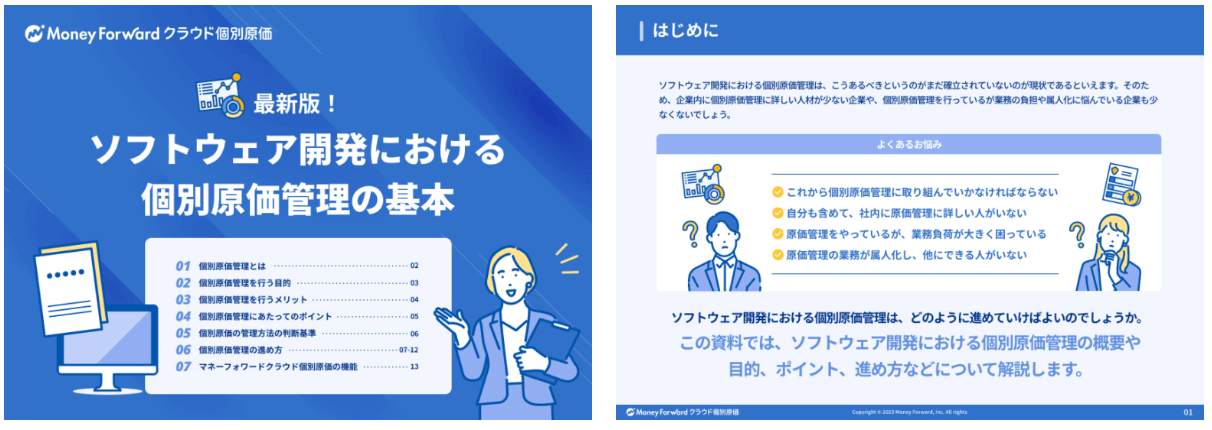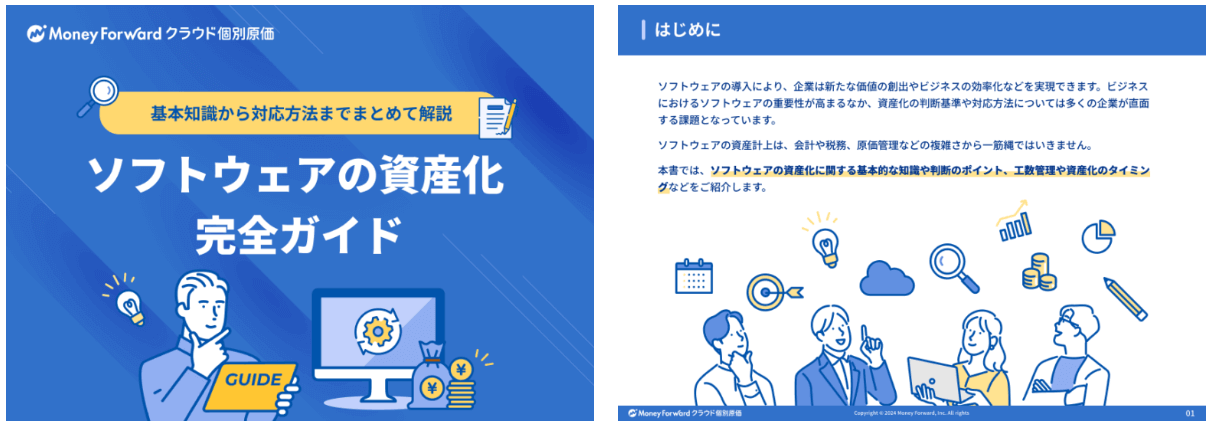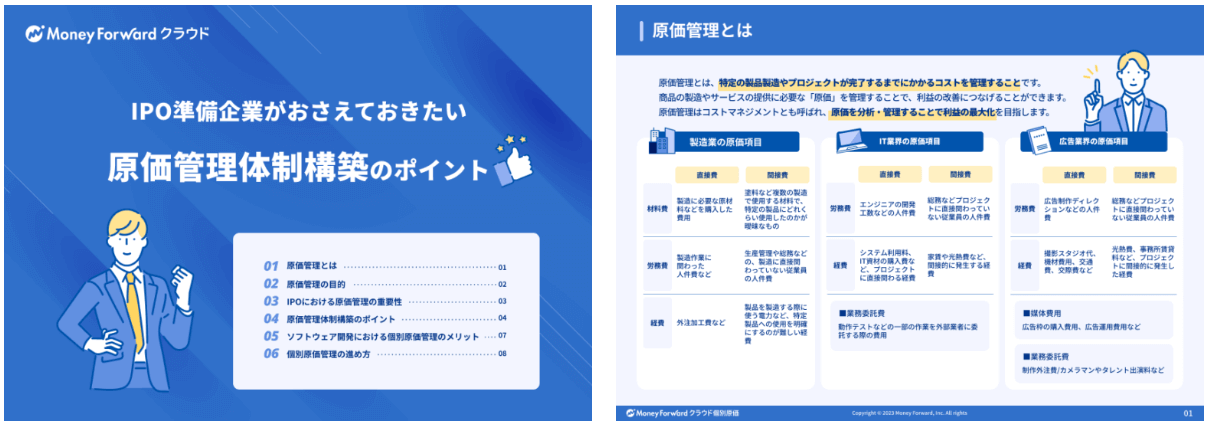- 更新日 : 2025年2月20日
ソフトウェア仮勘定の会計処理方法や消費税の取り扱いを解説
ソフトウェア仮勘定とは、長期にわたるソフトウェア開発プロジェクトにおいて、制作に関する費用を計上するための勘定項目です。関連費用をソフトウェア仮勘定として計上することで、会計や税務をより正確に行うことができます。
本記事では、ソフトウェア仮勘定の概要や会計処理方法をはじめ、消費税の取り扱いや建設仮勘定との違いなどについて解説します。
目次
ソフトウェア仮勘定とは
「ソフトウェア仮勘定」とは、ソフトウェア制作に関する費用を計上するための勘定科目です。
ソフトウェア仮勘定で計上した費用は、ソフトウェア完成時に「ソフトウェア」という勘定科目に振り替えます。ソフトウェアは完成・稼働するまでは業務には使えず資産としても計上できないため、「ソフトウェア仮勘定」として計上することで、会計上の正確性を保つことができます。
なお、ソフトウェア開発は長期間に及ぶケースも多く、大規模プロジェクトなどでは年単位の時間を要する場合もあります。このような場合も、ソフトウェア仮勘定を用いて開発にかかった費用を繰り延べておけば、完成後の減価償却で「費用」と「収益」を期間対応させることができます。
さらに税務上の費用認識タイミングも調整できるため、結果として消費税などの計算を正確に行えます。
ソフトウェア仮勘定については、次の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
ソフトウェア仮勘定の会計処理方法
ソフトウェアは「受注制作」か、あるいは「市場販売目的」かによって、次の3種類に分類されます。
- 受注制作
- 市場販売目的
- 自社利用
なお、工程によって「ソフトウェア仮勘定」に計上できるかが異なる点には注意が必要です。
本章ではソフトウェアの分類別に会計処理方法を解説します。
受注制作のソフトウェア
受注制作の場合、ソフトウェアの制作に関するコストは「仕掛品」として計上するため「ソフトウェア仮勘定」は用いません。
なお、受注制作の場合は、制作に関する進捗の確実性により「工事進行基準」と「工事完成基準」のいずれかの会計処理を行う必要があります。
市場販売目的のソフトウェア
市場販売目的の場合は、開発工程によって「研究開発費」と「ソフトウェア仮勘定」という勘定科目を使い分ける必要があります。
企画から設計、開発を経て最初の製品マスター(Ver.0)が完成するまでの費用は「研究開発費」に計上します。その後、Ver.0の製品に対して実施する機能追加や、改良後に制作される製品マスター(Ver.1)が完成するまでの費用は「ソフトウェア仮勘定」として計上可能です。
「製品マスター(Ver.1)」の制作時に発生した費用の仕訳は下記のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| ソフトウェア仮勘定 | 500,000 | 人件費 | 300,000 |
| 外注費 | 150,000 | ||
| 経費 | 50,000 |
その後「製品マスター(Ver.1)」が完成したタイミングで下記の仕訳を行い、ソフトウェア仮勘定をソフトウェアに振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| ソフトウェア | 500,000 | ソフトウェア仮勘定 | 500,000 |
自社利用のソフトウェア
自社利用の場合、収益獲得や費用削減が確実と認められるまでは「研究開発費」、認められた後は「ソフトウェア仮勘定」として計上します。
例えば、基本設計完了時点で将来の収益獲得あるいは費用削減が確実と認められ、予算が承認された場合は次の仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| ソフトウェア仮勘定 | 500,000 | 人件費 | 300,000 |
| 外注費 | 150,000 | ||
| 経費 | 50,000 |
その後、ソフトウェアが完成した時点で下記の仕訳を行い、ソフトウェア仮勘定をソフトウェアに振り替えましょう。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| ソフトウェア | 500,000 | ソフトウェア仮勘定 | 500,000 |
ソフトウェア仮勘定に関する消費税の取り扱い
本章では、ソフトウェア仮勘定に関する消費税の取り扱いについて解説します。
消費税法における仕入税額控除の基本原則
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納税額を算出する際、仕入れや経費に対して外部に支払った消費税を売上にかかる消費税から差し引くことができる制度です。
仕入税額控除を行うには、外部への支払いを行った取引が消費税のかかる取引(課税仕入れ)である必要があります。なお課税仕入れには、材料費・広告宣伝費・水道光熱費・通信費など、多岐にわたる費用が該当します。
一方で給与・賞与・退職金など、自社の役員や従業員に支払う人件費は非課税です。また健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などは消費税の対象外です。ただし、人材派遣費用は外注費として扱われるため、仕入税額控除の対象となります。
ソフトウェア仮勘定に対する消費税の計上時期と注意点
ソフトウェア制作中の費用(材料費、労務費、経費など)をソフトウェア仮勘定に計上する際、どのように消費税を処理すればよいのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
ソフトウェア仮勘定に計上する費用にかかる消費税は、各取引が発生したタイミングで「仮払消費税」として処理するため、個々の取引ごとに判断する必要があります。
主な費用科目に対する仕入税額控除の適用可否は次のとおりです。
| 科目 | 消費税の処理 |
| 材料費 | ソフトウェア制作時に利用した消耗品の購入は課税仕入れに該当し、仕入税額控除が適用される。 |
| 労務費 | 社内の人件費は基本的に非課税であり、仕入税額控除の対象にはならない。 |
| 経費 | 以下の取引は主に課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。
|
仕入税額控除を適用するためには、精緻な帳簿記載と請求書などの保存が必要です。また、ソフトウェア仮勘定に計上する際は、各費用の性質を正確に把握し、適切な税務処理を行うことが重要になります。
なお、税法は改正される可能性があるため、最新の情報を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
ソフトウェア仮勘定と建設仮勘定との比較
ソフトウェア仮勘定と類似の勘定科目として、「建設仮勘定」があります。
建設仮勘定は、建物や構築物、製作中の機械など、建設中の固定資産に支払われた費用を、該当する固定資産が完成するまで一時的に計上するための勘定科目です。
ソフトウェア仮勘定と建設仮勘定は、どちらも長期にわたるプロジェクトの費用を暫定的に計上するための勘定科目という共通点があります。
ただし、消費税の仕入税額控除のタイミングについて、建設仮勘定の場合は建設工事が長期にわたるため、工事の目的物がすべて完成し引き渡された時点で課税仕入れとして処理する方法も認められています。(消費税法基本通達11-3-6)
また、将来の資産計上時における償却方法について、ソフトウェア仮勘定は無形固定資産として振り替え、比較的短期間(3年または5年)で償却されます。一方で建設仮勘定は有形固定資産に振り替えますが、建物や設備によっては長期間にわたって償却が続くのが特徴です。そのため、税務への影響を長いスパンで考慮する必要があります。
両勘定科目の特性と税務処理の違いを踏まえ、資産計上時の計画と実務対応をしっかりと進めることが重要です。
まとめ
本記事では、ソフトウェア仮勘定の会計処理方法や消費税の取り扱いをはじめ、建設仮勘定との比較などについて解説しました。
ソフトウェア開発は完成までに数年間という歳月を要することも珍しくありません。その開発期間に発生する費用は、特定の条件を満たせばソフトウェア仮勘定に計上可能です。ただし、費用科目によって仕入税額控除の適用可否が異なる点には注意しましょう。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
最新版!ソフトウェア開発における個別原価管理の基本
ソフトウェア開発における個別原価管理にお悩みではありませんか?
ソフトウェア開発における個別原価管理の基本から、その目的やメリット、具体的な進め方までを詳しく解説します。
ソフトウェアの資産化完全ガイド
ソフトウェアの資産計上は、会計や税務、原価管理などの複雑さから難易度が高く、うまく進められていない企業も多いのではないでしょうか?
ソフトウェアの資産化に関する基本的な知識や判断のポイント、工数管理や資産化のタイミングなどを解説します。
IPO準備企業におすすめ!原価管理体制構築のポイント
個別原価管理は、IPOに必要とされるあらゆる経営管理体制の構築・運用と密接に関連しており、非常に重要です。
これから原価管理をはじめる企業向けに、体制構築のポイントや進め方を解説します。
マネーフォワード クラウド個別原価 サービス資料
IT開発・プロジェクト型ビジネスのための個別原価管理システムをお探しではありませんか?
マネーフォワード クラウド個別原価は、個別原価計算はもちろん、プロジェクト申請・工数入力・資産振替・レポート作成までの一連の業務をワンストップでサポートします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
静岡で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
静岡県で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中…
詳しくみるIFRS(国際会計基準)とJGAAP(日本会計基準)の違いは?具体例でわかりやすく解説
IFRSとJGAAPの違いは、企業の財務報告における売上や貸借対照表の表示方法などが挙げられます。この記事では、収益認識や営業利益などの具体例を交えながら、IFRSとJGAAPの違…
詳しくみる会計ソフトのセキュリティが心配…クラウド型とインストール型の安全性を徹底解説!
ほとんどの企業では、利便性の高さなどから会計ソフトを導入していることと思います。これまでは、パソコンにインストールして使用するインストール型、あるいは表計算ソフト(Excel)を使…
詳しくみる【これは軽減税率?】会議室までサンドイッチ配達。消費税8%と10%の分かれ道は「給仕」
2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…
詳しくみる北海道で記帳代行を依頼するなら?相談先や具体的な業務内容、料金相場を解説
北海道の事業者が記帳代行サービスを利用したいと考えている場合、税理士事務所や会計事務所に相談すると良いでしょう。記帳代行サービスの対応範囲は、会計ソフトへの入力や仕訳の起票、各種帳…
詳しくみる売上原価率とは?計算式や平均、高い場合の改善方法を解説
売上原価率は、売上に直接要した仕入コストや製造コストの割合を示す指標です。この記事では、売上原価率の計算方法や売上原価率を把握することでわかることや、業界別の平均値、売上原価率が高…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引