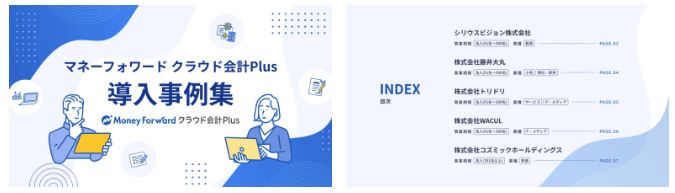- 更新日 : 2025年4月23日
会計ソフトを導入しても税理士は不要にならない、その理由を解説
この記事では「確定申告が不安で税理士に依頼するかどうか悩んでいる方」、「税理士費用が高いと感じている方」に向け、会計ソフトを使えば税理士は不要になるかどうかを説明していきます。
目次
帳簿から申告までの業務
日本国内で事業を行っている個人事業主または法人であれば、簿記(帳簿付け)と確定申告を行う必要があります。
まずは、税理士に頼む前にそもそもどんな業務があるかを把握しましょう。
自分ができる業務は自分で行うことで、税理士費用を節約することにつながります。
業務は大きく分けると以下の4つになります。
それぞれ、1つずつ説明していきます。
簿記(仕訳・決算書作成・その他の必要書類の整理)
経理や伝票処理など呼び方はさまざまですが、この項目では「簿記」として説明していきます。
簿記は仕訳と決算書作成です。
初めて簿記をする方や簿記の知識がない方は、多少の勉強と慣れが必要になるかもしれません。ただし、慣れてしまえば仕訳の大半は「入力作業」か「会計ソフトで自動仕訳」のどちらかで済んでしまう業務がほとんどです。
また、決算書作成は日常の仕訳を勘定科目ごとに集計し、決算書としてまとめる作業です。
したがって、表計算ソフトなどを使って自分で集計する、または会計ソフトですでに集計されているものを加工する業務になります。
ただし、決算整理仕訳については、未収・未払計上、減価償却費や棚卸資産の計算など特殊なものもあります。正しく計算しないと決算書の金額が間違ったものとなってしまいますので、気を付けましょう。
また、仕訳の根拠になる書類(レシートや請求書など)を整理する必要がでてきます。
電子保存の手続きをしない限りは紙で整理し保管することになります。
年末調整
年末調整は従業員に給与を支払っている個人事業主、または法人が行う業務です。
簡単にいうと、従業員に対する年間の給与支払額から所得税等の計算を行います。
確定申告
簿記(仕訳と決算書作成)が終わった後に、確定申告書を作成し申告・納付する業務です。
具体的には、申告書の形式に従って決算書の数値を入力して所得の計算を行い、各種所得控除や税額控除が適用できるかどうかを調べることになります。
申告書は、確定申告の相談窓口や国税庁HPから作成するか、申告書作成機能のある会計ソフトで作成します。
今後の税金上の判断
自身の売上や所得、税法改正などによって変わる業務です。
業種、取引内容、売上などさまざまな要因で節税につながったり、損をしたりすることがあります。
そのため、自分で勉強する、または調べることが大切です。
どうしても解決できない場合は、近くの税務署へ相談するか税理士を頼ることになります。
税理士がいるメリット・デメリット
注意点として、税理士にお願いするメリット・デメリットはご自身の目的、業種や効率などによってさまざまです。この記事では一般的なメリット・デメリットを紹介していきます。
税理士がいるメリット
税理士がいるメリットは以下になります。
- 正しい納税と安心感
税金計算のプロに任せるため、税金で損をしないという安心感があります。 - めんどうな業務を代行してくれる
コストはかかりますが、簿記や申告書作成にかかる時間を減らすことができます。 - 困った時に頼れる
税務調査や今後の税金上の判断など、困った場合の相談相手になってくれます。
メリットをまとめると、簿記・申告書作成に対する多少の勉強時間、業務時間を少なくできると共に、税金に対する不安を軽減できること、といえます。
税理士がいるデメリット
税理士がいるデメリットは以下になります。
- 税理士費用がかかる
税理士も仕事として行っているので、当然無料というわけにはいきません。
上記で述べた業務のうち、どこまでを依頼するかで費用が変わってきます。 - コミュニケーションが必要
簿記・申告書作成ではさまざまな判断が求められることがあり、場合によっては税理士と密にコミュニケーションを取る必要があります。
デメリットをまとめると、金額が高い安いは別として費用がかかり、税理士とのコミュニケーションが発生すること、といえます。
税理士とコミュニケーションを取るために、簿記・税金の多少の知識が必要になります。
税理士に頼んだ方がいいの?
税理士に頼んだ方がいいかどうかは、ご自身の状況や業種、事業規模によって変わります。
そこでこの項目では、税理士に頼むかどうか考えるべきポイントを説明していきます。
自分の知識量と作業時間
簿記・申告書作成の知識と、それに対してどれぐらいの作業時間を使えるかが大切なポイントです。
まず、知識に関しては簿記3級程度の知識があれば十分です。知識がない場合でも1カ月程度コツコツと勉強することで対応できます。ただし建設業や製造業の場合は、原価計算の知識が必要になることもあります。
勉強してもどうしても解決できない場合は、税務署に問い合わせるか、確定申告相談コーナーで解決することができます。
次に、作業時間に関しては事業規模や年商によって変わりますが、小規模な個人事業主の場合は、年間で3日前後が参考になります。 (※知識や手段によって異なります)
簿記に時間がかかり本業を圧迫してしまう場合は、会計ソフトを使うか、もしくは税理士に頼むことが選択肢になります。
税理士費用
冒頭で、業務には以下の4つがあることを説明しました。
- 簿記(仕訳・決算書作成)
- 年末調整
- 確定申告
- 今後の税金上の判断
上記の業務と税理士費用の対応をまとめると以下になります。
※下記の表は、個人事業主を想定した表で、費用は事業規模によって異なる場合があります。また、法人の場合も税理士費用は事業規模によってさまざまです。
| 業務 | 税理士の訪問回数 | 費用 |
|---|---|---|
| 簿記(仕訳・決算書作成) | 月1回または 3カ月程度に1回 | 月15,000円前後 |
| 年末調整 | 年1回 | 従業員1名2,000円前後 |
| 確定申告 | 年1回 | 70,000円前後 |
| 今後の税金上の判断 | その都度 | 内容によって異なる |
税理士に頼まない場合は、上記表の業務すべてを自分で行うことになります。そのサポートとして会計ソフトを使うことや、確定申告相談コーナーを使うことも選択肢になります。
また、税理士に頼むとしても、なるべく安く済ませたい場合は「上記の業務の一部だけお願いする」「時間の観点からどうしても税理士に代行してほしい時だけお願いする」ようにしましょう。
クラウド型会計ソフトで何ができる?できないことは?
自分で表計算ソフトなどを使用して簿記・申告書作成を行うよりもクラウド型会計ソフトを使用すれば、効率化することができます。
以下では、クラウド型会計ソフトで「できること」と「できないこと」を説明していきます。
クラウド型会計ソフトでできること
ある程度の簿記の知識とソフトに慣れる必要がありますが、クラウド型会計ソフトでは簿記・申告書作成、さらに年末調整まで行うことができ、作業効率がアップします。
また、表計算ソフトなどを使うよりもクラウド型会計ソフトを使う方が入力・集計の手間が軽減されます。
さらに、クラウド型会計ソフトの中には、ネットバンキングやネット上のクレジットカード明細と連携する機能があり、データを取り込んで自動仕訳が可能です。
自動仕訳機能で入力作業は大幅に減少します。
ただし、自動仕訳機能を使う前提としてネットバンキングの準備や勘定科目を整理しておくことが必要です。
クラウド型会計ソフトでできないこと
具体的には、納税義務の判断や各届出が必要かどうかなどの判断は自分で行うことになります。その際には、自分の状況や所得など、さまざまなことを調べる必要があります。
クラウド型会計ソフトでは「経営判断」や「税金の判断」などの判断をソフトが代わりに判断することはできません。しかし、クラウド型会計ソフトでは売上レポートや試算表などを簡単に作ることができ、経営判断に役立つ機能が付いています。
役立つレポートなどで見やすく比較することができますが、最終的には自分で調べ、勉強した上で判断することになります。
まとめ
最後に、「税理士は不要かどうか」の結論は、自分の状況や予算、作業時間によってさまざまです。
簿記・税金の勉強は多少必要になりますが、クラウド型会計ソフトを使いこなし、正しく確定申告書を使うのであれば基本的作成できれば、基本的にに税理士は不要です。
ただし、「作業量が多すぎる」「専門的すぎてわからない」などの特別な事情がある場合は、税理士に頼みましょう。
>>簿記知識がなくても大丈夫?会計ソフトで作業効率アップするコツ
>>一人で決算を行うための基礎知識と注意点
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
マネーフォワード クラウド会計Plus導入事例
マネーフォワード クラウド会計Plusは多くの成長企業にご導入いただいています。
本資料では、選定過程や導入効果など導入企業様の声をまとめました。導入に成功した企業について知りたい!という方におすすめです。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
青色申告1から簡単ガイド
個人事業主で会計ソフトをお探しの方におすすめです!
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
自分で法人決算!決算書の作り方ガイド
会計ソフトにご興味がある、1人法人の方や、中小企業の経理の方におすすめなのがこちらのガイドです。
本書では、各決算書の概要や具体的な作り方をわかりやすく解説しています。 また、作成した決算書の提出先や「マネーフォワード クラウド会計」で簡単に作成する流れも紹介しています。
よくある質問
帳簿から申告までの業務にはどんなものがある?
大きくわけて、簿記(仕訳・決算書作成)、 年末調整、確定申告、今後の税金上の判断の4つがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
税理士に依頼するメリットは?
簿記・申告書作成に対する多少の勉強時間、業務時間を少なくできると共に、税金に対する不安を軽減できることが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
税理士に依頼するデメリットは?
コストがかかることや、税理士とのコミュニケーションが発生すること、またそのために簿記・税金の知識が多少必要になることが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引