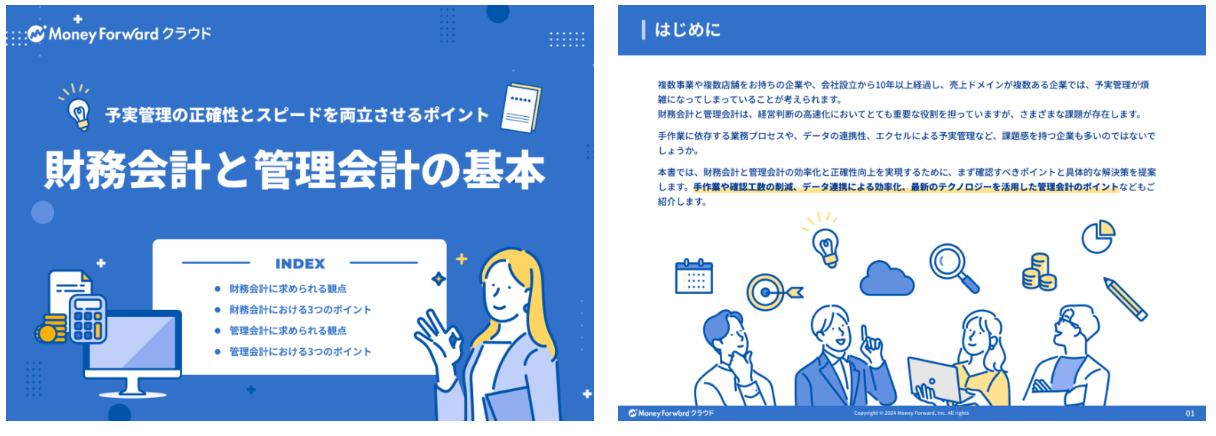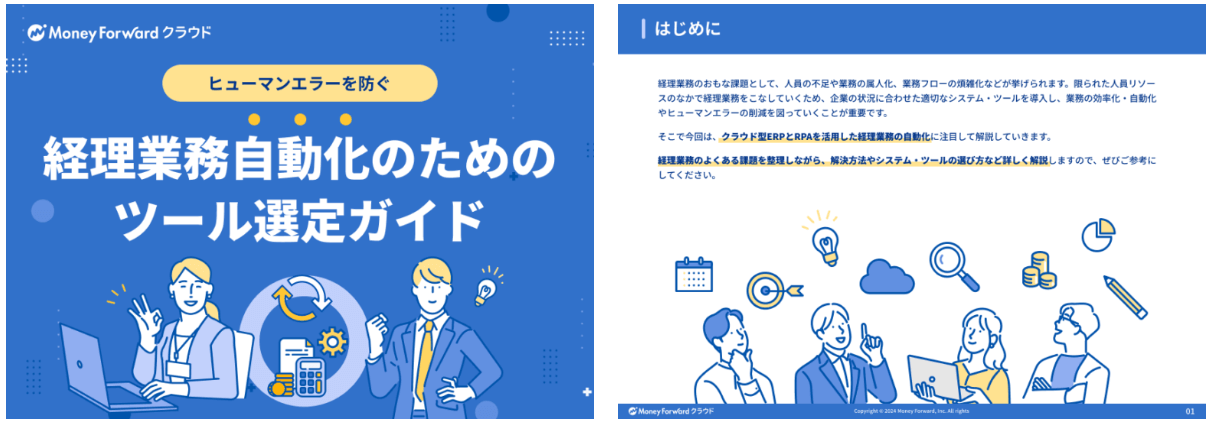- 更新日 : 2025年9月4日
IFRS(国際会計基準)とJGAAP(日本会計基準)の違いは?具体例でわかりやすく解説
IFRSとJGAAPの違いは、企業の財務報告における売上や貸借対照表の表示方法などが挙げられます。この記事では、収益認識や営業利益などの具体例を交えながら、IFRSとJGAAPの違いをわかりやすく解説します。
目次
IFRS(国際会計基準)とは
IFRS(International Financial Reporting Standards:国際会計基準)とは、国際的に統一された会計基準を指します。企業の財務状態や経営成績を、世界共通のルールでわかりやすく報告することを目的としており、IASB(国際会計基準審議会)が策定・公表しています。
世界中の投資家への情報公開を円滑にするため、多くの国や地域で導入が進められています。日本でも任意適用が認められており、上場企業を中心に導入事例が増加傾向にあります。
JGAAP(日本会計基準)とは
JGAAP(Japanese Generally Accepted Accounting Principles:日本会計基準)とは、日本国内で適用される会計基準の総称です。企業会計原則や企業会計基準など、複数の指針や法令によって構成されており、主に金融庁や企業会計基準委員会(ASBJ)などが整備を行っています。
日本特有の慣習や法体系に合わせて設計されており、国内企業にとっては馴染みのある会計処理を行いやすい点が特徴です。
IFRSとJGAAPの基本的な違い
IFRSとJGAAPの最大の違いは、国際標準を重視するか、日本国内の商慣行や法令に合わせるかという点にあります。さらに、会計処理における「原則主義」と「細則主義」の考え方も大きく異なります。
原則主義と細則主義の違い
IFRSは広範な原則のもとで企業が実質的に重要と考える情報を開示する「原則主義」を採用しています。例えば、売上や損益計算の基準が包括的に示され、具体的な判断は企業に委ねられることが多いです。
一方、JGAAPは詳細な会計処理手続きの規定に基づく「細則主義」が採用されており、処理がわかりやすい反面、柔軟性に欠ける場合もあります。企業の状況に合わせてどちらを選ぶかは、経営方針やステークホルダーのニーズによって異なります。
IFRSとJGAAPの会計処理の違い
IFRSとJGAAPでは、具体的な会計処理や表示方法も異なります。ここでは、収益認識や営業利益の算定方法など、主要な項目ごとに違いを整理してご説明します。
収益認識基準(売上計上基準)の違い
IFRSでは、原則として「顧客との契約から得られる履行義務を満たした時点」で収益を認識します。そのため、成果物の引き渡しやサービス提供の進捗度などを総合的に判断することが求められます。
一方、日本の場合も収益認識会計基準が既に適用されており、完成基準や部分完成基準というものはありません。現在は期間がごく短い工事契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識します。一方、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる場合は、その進捗度に基づき、収益を一定の期間にわたり認識するのが原則です。
なお、一定の期間にわたり充足される履行義務について、進捗度を合理的に見積もることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができるときまで、原価回収基準により処理されます。
営業利益の違い
IFRSでは、営業利益(Operating Profit)という科目が必ずしも規定されていません。代わりに、「営業活動に伴う損益」といった概念的な開示が中心で、実際に「営業利益」を財務諸表に表示するかは各企業の判断に任されるケースが多いです。
一方、JGAAPでは損益計算書において「営業利益」という区分が明確に定義されており、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を差し引いた指標として一般的に用いられています。
減損処理の違い
IFRSでは、将来キャッシュ・フローの回収可能性を定期的に評価し、資産の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合には減損を計上します。また、減損が認識された資産の回収可能価額が回復した場合には、一定の条件下で減損損失を戻し入れ(リバーサル)できる仕組みがあります。
一方、JGAAPでは一度減損を認識した資産の減損損失を戻し入れすることが禁止されているため、IFRSに比べて回復可能性が反映されにくいという特徴があります。
リース会計の違い
IFRS(IFRS第16号)では、原則としてリース契約の資産と負債をすべて貸借対照表に計上します。
一方、JGAAPではファイナンス・リース取引は資産計上が求められますが、オペレーティング・リースに該当する取引では賃貸借取引として処理するのが一般的です。このように、リース取引の認識基準が異なるので、貸借対照表と損益計算書の数値にも影響が出ます。
ヘッジ会計の違い
IFRSでは、ヘッジ手段とヘッジ対象を明確に特定し、ヘッジ効果が高いことを証明できれば、ヘッジ会計を適用できます。さらに、デリバティブ取引の評価や開示に関する要件が細かく定められています。
一方、JGAAPでも同様の考え方があるものの、IFRSに比べると詳細な測定や開示を求めるルールが一部異なり、例えば繰延ヘッジ処理の要件や特例処理など、日本特有の規定が存在します。
税効果会計の違い
IFRSでは、繰延税金資産・負債を認識する際に、将来的な課税所得を見込みやすい企業ほど繰延税金資産を大きく計上できる傾向にあります。
JGAAPでも基本的な考え方は同様ですが、評価性引当額の計上基準がより厳格で、過去の損益実績などから回収可能性を慎重に判断するケースが多いです。そのため、IFRSとJGAAP間で繰延税金の計上額に差が生じる可能性があります。
M&Aの違い
IFRSでは、企業結合において「取得法(Purchase Method)」を基本とし、買収した資産・負債を公正価値で測定します。のれんの償却は行わず、定期的に減損テストを実施する方針をとります。
一方、JGAAPではのれんを定額で償却することが一般的で、IFRSとはのれんの計上期間や償却・減損のタイミングに差が生じやすいです。この違いにより、M&A後の財務諸表上の利益計上タイミングや資産評価が変わります。
IFRSとJGAAPの財務諸表の違い
IFRSとJGAAPでは、財務諸表の構成や科目名、表示順序などが異なります。特に貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表に差が見られます。
貸借対照表の違い
IFRSの貸借対照表では、流動資産・固定資産などの分類や表示順序が各企業の判断により柔軟に行われる場合があります。一方、JGAAPでは「流動」「固定」の区分が明確に示され、昔から決まったレイアウトに沿って表示されることが一般的です。
また、IFRSでは再評価モデルの適用によって資産を時価評価する選択肢がある一方、JGAAPでは基本的に原価モデルを採用するため、同じ資産でも帳簿価額に差異が出ることがあります。
損益計算書の違い
IFRSでは「包括利益計算書」として、純利益に含まれない損益項目(その他の包括利益)も同時に表示します。一方、JGAAPでは損益計算書と包括利益計算書を別々に作成するなど、企業ごとに若干の違いがあります。
また、IFRSでは「営業利益」が必須科目ではないのに対し、JGAAPでは損益計算書上において営業利益が明示されるのが一般的です。
キャッシュ・フロー計算書の違い
IFRSでは、キャッシュ・フローを営業活動・投資活動・財務活動の3区分に分けて計上する点はJGAAPと同様ですが、利息や配当金の受払の分類が異なるケースが多いです。
例えば、利息の支払を営業活動とみなすか、財務活動とみなすかはIFRSでは選択可能な場合もありますが、JGAAPでは原則営業活動に含めるといった規定があります。この違いにより、営業CFなどの金額に差が出ることがあります。
連結財務諸表の違い
IFRSの連結基準は「実質支配基準」を重視し、実際に支配力を及ぼすかどうかによって連結範囲を決定し、子会社と認められる会社はすべて連結対象となります。一方、JGAAPでは「過半数所有基準」が中心で、形式的に議決権の過半数を保有している企業を子会社として連結する手法が一般的です。
そのため、持分法適用会社との境界線がやや異なり、連結範囲がIFRSとJGAAPで変わる場合があります。
JGAAPからIFRSに変更するメリット
JGAAPからIFRSへ移行すると、海外投資家向けの財務報告を統一できるなど、国際ビジネスに有利なメリットが生まれます。以下では代表的なメリットを紹介します。
海外向けに財務情報を統一できる
IFRSは世界共通の会計言語ともいわれ、多くの国際企業が採用しています。したがって、JGAAPからIFRSに切り替えることで、自社の財務諸表を海外の投資家や取引先に対してわかりやすく提示できます。
海外子会社や関連会社との取引調整も容易になり、管理会計や連結決算プロセスの効率化につながるケースも多いです。結果として、グローバルでの信用度や透明性を高める効果が期待できます。
海外投資家から資金調達しやすくなる
IFRSを導入すると、海外の株式市場や投資家とのコミュニケーションがとりやすくなります。投資家はIFRSを前提に企業の業績を比較検討することが多く、財務情報が国際的に整合性のある形式で開示されている企業を評価しやすいからです。
特に、海外からの大型投資や債券発行などを検討している企業にとって、IFRSの採用は資金調達力を強化する一つの手段となり得ます。
M&Aや海外展開がしやすくなる
IFRSを採用していると、海外企業とのM&Aや合弁事業などを行う際に、財務諸表の比較や統合がスムーズです。買収先企業がIFRSベースで決算を行っている場合、のれんや資産負債の評価を統一的に行えるため、シナジー創出やリスク評価を正確に行いやすくなります。また、海外市場への上場や事業拡大時にも、IFRSに準拠した財務報告書を提示することで、国際的な信用度を高めることが可能です。
JGAAPからIFRSに変更するデメリット
一方で、JGAAPからIFRSへ移行することで、会計処理の見直しやシステム対応など、大きな負担が伴う可能性があります。以下で代表的なデメリットを確認しましょう。
日本の会計基準から変更する手間がかかる
IFRSでは、原則主義をベースとした柔軟な会計処理が求められます。そのため、会計の規則を再整理し、企業内で適切な会計方針を策定・導入しなければなりません。
さらに、会計担当者への研修や経理フローの変更も必要です。大規模な企業ほど移行プロジェクトが大掛かりになるため、時間とコストをしっかり確保する必要があります。
会計ソフトをIFRSに対応する必要がある
経理業務で使用する会計ソフトやERPシステムをIFRSに対応させるためには、システム改修やバージョンアップが避けられません。リース会計や減損会計など、IFRS特有の処理を自動化する機能が必要になることも多いです。
システム上の対応だけでなく、実運用においては入力項目の増加や作業フローの変更も考えられるため、事前のテストや導入サポートの確保が重要となります。
JGAAPからIFRSに変更するのがおすすめの企業
すべての企業がIFRSへ移行する必要はありません。しかし、特にグローバル展開や海外投資家からの資金調達を重視する企業にとっては、IFRS導入のデメリットよりもメリットのほうが大きくなる場合があります。
上場企業・グローバル企業
海外市場との取引が多い上場企業や、世界各国に子会社を持つグローバル企業は、IFRSに切り替えることで一貫した会計基準を採用できます。結果として、連結決算プロセスがシンプルになり、複数地域にわたる子会社や関係会社との報告書類を統合しやすくなるメリットがあります。
また、海外投資家に対して国際的に認知された財務報告を行える点で、信用力の向上が期待できます。
M&Aや海外進出を考えている企業
M&Aを通じて事業拡大を目指す企業や、新たに海外進出を検討している企業にとって、IFRSは財務情報の国際基準として役立ちます。買収先や合弁先がIFRSを導入している場合は、決算の集約やデューデリジェンスでの比較が容易になるため、スムーズにプロジェクトを進めることができるでしょう。
海外拠点の設立や現地法人の管理面でも、国際的な基準に合わせた会計処理がメリットを生むケースがあります。
IFRSとJGAAPを使いこなして経営に役立てよう
IFRSとJGAAPはそれぞれ特徴や適用範囲が異なるため、自社の経営戦略や事業展開に応じて最適な会計基準を選ぶことが大切です。グローバル化や海外投資家からの資金調達が急務であればIFRSを採用する意味は大きい反面、国内中心の中小企業などにとってはJGAAPのままでも十分に対応できる場合があります。
どちらの基準を適用するにしても、経営やステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に進めるために、最新の会計トレンドを常に把握し、自社の方針に合わせた活用を心がけましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
「管理会計を効率よく正確にできるようになりたい」とお悩みではないですか?
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説します。
経理業務自動化のためのツール選定ガイド
「ツールをうまく活用して、経理業務におけるヒューマンエラーを削減したい」とお悩みではないですか?
経理業務のよくある課題を整理しながら、クラウド型ERPとRPAを活用した経理業務の自動化について詳しく解説します。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みではないですか?
中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
業務効率化と内部統制の強化を実現!
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けのクラウド型会計ソフトです。データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務を効率化すると同時に、仕訳承認・権限管理機能で内部統制にも対応します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
国際会計基準(IFRS)の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引