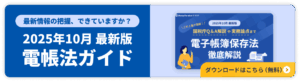- 更新日 : 2025年2月20日
経理の無駄な作業を削減する3つの方法!課題や進め方を解説
経理の無駄な作業を削減する方法として、エクセルやクラウド会計ソフトの導入、アウトソーシングの活用が効果的です。作業時間の短縮や手入力によるミスを削減し、業務効率化が期待できます。ツールや外部リソースを上手に活用することで、日々の負担を軽減し、業務の正確性も向上させましょう。本記事では、よくある経理の無駄な作業や、無駄な作業を効率化する具体的な方法などを解説します。
よくある経理の無駄な作業
経理の仕事には、時間やリソースを無駄にし、業務効率を低下させる作業が存在します。本章では、よくある無駄な作業と問題点について解説します。
少額現金・小口現金の管理
小口現金とは、切手代や消耗品代、交通費など、日々の細かい経費精算に備えて用意しておく現金のことです。従業員から個別で不定期的に経費精算を依頼されるケースでは、経理担当者の負担が大きくなります。
少額現金・小口現金の管理には以下のような問題点が挙げられます。
- 盗難や不正のリスク:現金管理には常に盗難や不正のリスクが伴い、定期的なチェックや精査が必要になり、時間コストを増やす要因となる。
手作業による請求書などの帳票入力
請求書や伝票などの帳票を手作業で入力する作業は、多くの時間を割かれる日常業務です。
手作業による帳票の入力作業には、以下のような問題点が挙げられます。
- 確認作業の負担:入力後にミスがないかを確認する必要があり、多くの時間が割かれる
- 入力ミスのリスク:金額や日付の誤入力など、手作業による単純なミスが起こり、修正するための時間がかかる
とくに、企業に経理担当者が1人だけである「1人経理」の場合、ダブルチェックを正確に行うのが困難です。手入力による入力ミスに気が付かず、最終的な決算処理や税務申告に大きな影響を及ぼす可能性も考えられます。
転記などの二重作業
経理業務では、同じデータを複数のシステムや帳簿に転記する「二重作業」が頻繁に発生します。たとえば、請求書のデータを会計システムに入力した後、別の管理システムにも同じデータを入力するようなケースです。
転記などの二重作業には、以下のような問題点が挙げられます。
- 時間の浪費:同じデータを複数回手入力することで、無駄な時間が発生する
- ミスのリスク:入力作業を複数回行うことで、データの不一致や入力ミスのリスクが高まり、修正に多くの時間を要する
紙ベースによる押印、承認作業
紙ベースで書類を管理している企業では、請求書や経費精算書などの承認に押印が必要なケースがあります。
紙での承認作業には以下のような問題点が挙げられます。
- 書類の受け渡しと保管:従業員間で書類を受け渡す手間や時間がかかる上に、保管スペースが必要になる
- 押印待ち:承認者が不在の場合、押印ができず、業務が滞ることがある
郵送による書類のやり取り
書類の郵送は、時間やコストが大幅にかかる業務です。
郵送作業には以下のような工程があります。
- 書類の印刷と押印
- 送付状の作成
- あて名書き
- 郵送手続き
郵便局への移動時間や郵便局での手続きも、経理担当者の時間を浪費する大きな問題として挙げられるでしょう。加えて、郵送費用や封筒、用紙など、物理的なコストも発生します。
書類の整理や保管
紙の書類を物理的に整理し保管する作業は、経理担当者の時間を消費する業務です。
書類の整理や保管をする作業には、以下のような問題点が挙げられます。
- 書類探しに時間がかかる:大量の書類の中から必要な書類を見つける時間がかかる
- 書類の整理:帳票ごとや取引先ごとなど、帳票類を整理したり、ファイリングしたりする作業に時間がかかり、メイン業務の妨げになる可能性がある
財務データの集計やレポートの作成
財務データを分析・集計し、損益計算書や貸借対照表などの財務レポートを作成する作業は、企業の経営状態を把握する重要な業務です。しかし、手作業で行う場合、作業効率が悪く、手間と時間が大幅にかかります。
また、多くの数値を入力し分析するため、入力ミスや計算式の誤りが生じるリスクも高まります。集計結果が正確でない場合、再度データを見直す必要が生じ、さらに時間を浪費することになるでしょう。
経理の業務効率化で直面する課題
経理業務の効率化を進める過程で、さまざまな課題が発生することも少なくありません。
本章では、経理の業務効率化を図る上での課題について詳しく解説します。
古い慣習が残っている
企業によっては、古い慣習や手続きが根強く残り、経理業務の効率化が難航することがあります。たとえば、紙ベースの書類や押印文化が強く残っている場合、デジタル化や自動化がスムーズに進まないことがあります。また、従業員は、長年の経験で確立された現行のやり方に安心感を抱いていることも少なくありません。
自社に残っている慣習を見直し、必要ない業務はカットすることが重要です。効率化しても問題のない業務と、現状のやり方が良い業務を明確にすることが重要です。
従業員や取引先から反発される
新しいシステム導入や業務フローの変更に伴い、従業員や取引先からの反発が大きな課題となるケースがあります。従来のやり方に慣れている従業員は、新しい仕組みへの適応にストレスを感じたり、負担が増えたと感じることがあるためです。また、取引先が従来のフォーマットや契約方式を希望する場合、新しいプロセスを導入するのが難しくなることもあります。
業務効率化を円滑に進めるには、事前に十分な説明を行い、従業員や取引先に新しい業務形態のメリットを理解してもらうことが重要です。
従業員の育成が必要になる
経理業務の効率化のため、新しい技術やソフトウェアを活用するには、従業員のスキルアップが必要です。とくに、ITスキルに不安を感じている従業員にとっては、新しいシステムや自動化ツールの使用に対する抵抗感がある場合も多いため、丁寧な教育を行いましょう。
従業員への適切な教育を提供し、実践的なスキルを身につけてもらうことで、効率化の効果を最大限に発揮できるでしょう。ただし、トレーニングの実施には時間とコストがかかるため、計画的な準備と実行が必要です。
経理の無駄な作業を効率化する際のポイント
経理業務の無駄な作業を効率化するためには、現状の業務フローを見直し、優先的に改善すべき箇所を明確にすることが重要です。
本章では、具体的なポイントを順に解説します。
現状の業務フローを把握する
効率化を進める1つめのステップは、業務フローの把握です。どのような手順で業務が進行しているのか、各担当者がどの作業をどのように行っているのかを確認し、業務の全体像を可視化します。導入しているシステムやツールの利用状況も併せて確認しましょう。
たとえば、請求書処理の場合、受領から支払いまでのフローを洗い出し、どこで手作業や重複作業が発生しているかを確認します。とくに、ミスが起きやすい部分や時間がかかる作業は重要な見直しポイントです。また、担当者へのヒアリングを通じて、属人化している業務を明確にし、改善の余地がある業務を見つけ出します。
経理業務の効率化を成功させるためには、現状のネックになっている部分を正確に把握することが重要です。
作業にかかっている時間を把握する
2つめのステップでは、各作業にどれだけの時間がかかっているかを具体的に把握しましょう。たとえば、帳票入力や請求書発行、転記作業などの各タスクが、どの程度の時間を消費しているかを数値で確認します。「請求書の入力・発行に1日2時間」「経費精算に週3時間」など、具体的な時間を計測することで、非効率な作業がどこにあるのかを見極められます。
さらに、日常的な定期業務と、年次や不定期に発生する業務を区別して把握することも重要です。
時間を把握することで、もっとも時間を費やしている業務や、頻繁に行われている非効率な作業を特定し、効率化の優先順位をつけやすくなります。
どの業務から効率化すべきか検討する
3つめのステップでは、効率化の優先順位を決めます。効率化の効果が大きい業務から着手することで、リソースを最大限に活用し、短期間で大きな改善を実現できます。
優先的に効率化すべき業務には、以下のような特徴があります。
- 手作業が多い業務
- ミスが発生しやすい業務
- 単純な反復作業
たとえば、紙ベースの書類管理や手作業でのデータ入力は、デジタル化や自動化によって大幅に効率化できる上に、入力ミスや書類紛失のリスクも軽減されるでしょう。とくに、ミスや作業負担が大きい業務を優先することで、従業員の負担軽減や、業務の質向上にもつながります。
経理の無駄な作業を効率化する3つの方法
エクセルなどのツールで効率化する
手軽に導入できる効率化ツールとして、エクセルやスプレッドシートを活用できます。
たとえば、計算式や関数を活用すれば、帳票の自動集計やデータの整理がスムーズに行える上に、手作業によるミスのリスクを削減可能です。また、マクロ機能を使用すれば、定型業務を自動化し、作業時間を大幅に短縮できるでしょう。ただし、エクセルやスプレッドシートの基礎知識が必要なため、経理担当者の教育が必要です。
アウトソーシングを活用する
経理業務の効率化を進めるためには、アウトソーシングの活用が効果的です。たとえば、給与計算や税務申告、決算業務などをアウトソーシングすることで、社内のリソースを重要な業務に集中させられます。
専門的な知識をもつ委託業者に任せることで、ミスや業務遅延のリスクも減少します。また、業務の標準化や自動化などにも長けているため、効率化の面でも大きなメリットが期待できるでしょう。
クラウド会計ソフトを導入する
クラウド会計ソフトで効率化できる業務として、以下のような一例が挙げられます。
- 伝票入力(仕訳入力)
- 支払管理
- 会計レポートの出力
- 決算書の作成
- 帳票出力
など
時間のかかる業務を効率化できる上、クラウド上でデータを管理するため、時間や場所に縛られることなく、リアルタイムでアクセスできるのが大きなメリットです。さらに、データのバックアップも自動的に行われるため、情報漏洩やデータ紛失のリスクも軽減されます。
クラウド会計ソフトを導入することで、経理業務の自動化やペーパーレス化、データ管理の強化など、効率化に大きな影響を与えるでしょう。
経理の無駄な業務の削減には自動化・ペーパーレス化が鍵!
経理業務の無駄を削減し、効率化を図るには、自社の業務フローを把握し、適切なツールを導入することが大切です。エクセルの活用やアウトソーシング、クラウド会計ソフトなどを上手にとり入れ、効率化を進めましょう。
とくに、クラウド会計ソフトは、手作業によるミスや時間の浪費を減らし、経理業務の自動化とペーパーレス化を実現する便利なツールです。また、リアルタイムでデータにアクセスできるため、在宅ワークにも対応できます。経理業務の効率化を目指すなら、クラウド会計ソフトの導入をぜひ、検討してみてください。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新着記事
法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の種類を体系的に整理し、それぞれの税率や計算の仕組み、さらには…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率を知ることです。 本記事では、会社の規模による法人税率の違い…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引