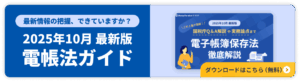- 更新日 : 2024年8月8日
ポイントの勘定科目は?買手と売手でケース別に解説
ポイントを使った物品を購入した場合やポイント分を値引きして物品を仕訳する際、どの勘定科目を使えばいいのか迷う方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ポイントを利用した・利用された際の勘定科目や仕訳について買手・売手、双方の立場から解説します。また、新収益認識基準導入で仕訳がどう変わるかについても紹介します。
目次
買手がポイントを取得・利用した際の勘定科目と仕訳例は?
まずは、買手側としてポイントをもらった場合、そして利用した場合の勘定科目について紹介します。
ポイントを取得した場合
買手側としてポイントを付与された時点では仕訳は行いません。ポイントを付与されたからといっても、まだ何か商品を得たり、サービスを受けたりしたわけではないからです。仕訳はポイントを利用したタイミングで発生します。
ポイントを利用した場合
ポイントを利用すると、仕訳処理の必要が生じます。ポイントの利用には以下の3つの考え方がありますので、いずれかの勘定科目を選択して仕訳を行います。
なお、どの仕訳方法を選択しても、利益や課税金額は変わりません。
■ポイントを「仕入値引」として処理する
ポイントを仕入額に対する値引きとして処理する場合、以下の仕訳を行います。
【例】仕入30,000円への支払いに対し500円分のポイントを充当し、残額を現金で支払った。ポイントは仕入値引として処理を行う。
■ポイントを「収入」として処理する
ポイントを収入として処理する場合、以下の仕訳を行います。
【例】仕入30,000円への支払いに対し500円分のポイントを充当し、残額を現金で支払った。使用したポイントは雑収入として処理を行う。
■現金の支払い額を基準に処理する
ポイントを会計処理上の収益・費用として扱わず、実際に発生した金銭の授受を基準とする場合、以下の仕訳を行います。
【例】仕入30,000円への支払いに対し500円分のポイントを充当し、残額を現金で支払った。
売手がポイントを付与した・利用された際の勘定科目と仕訳例は?
売手側として買手にポイントを付与した場合、そして利用された場合の勘定科目について見ていきましょう。
ポイントを付与した場合
買手側と同様にポイントを付与した時点では仕訳を行わないため、勘定科目について考える必要はありません。付与したポイントが利用されるかが、付与時点では不明なためです。
サービスとしてのポイントの付与額を把握しておく必要はありますが、会計処理は不要ですので、帳簿には売上が生じた事実のみ仕訳を行いましょう。
ポイントが利用された場合
ポイントが利用されたら仕訳を行います。以下2つの考え方のうちのどちらかを選択して仕訳してください。
ポイントを値引きととらえるか、販促のための費用ととらえるかは事業者によって異なります。どのように扱うかを事前に考えておきましょう。
■ポイント分を「売上値引」として処理する
利用されたポイントを売上に対する値引きとしてとらえる場合には、以下の仕訳を行います。
【例】売上30,000円対し500円分のポイントの利用を受け、残額を現金で受け取った。利用されたポイントは売上に対する値引分として処理する。
■ポイント分を「販売促進費」として処理する
利用されたポイントを販売促進費として考える場合には、以下の仕訳を行います。
【例】売上30,000円対し500円分のポイントの利用を受け、残額を現金で受け取った。利用されたポイントは販売促進費として処理する。
新収益認識基準導入におけるポイントの仕訳
2021年4月より、一部の企業(上場企業、会社法上の大会社等公認会計士監査対象会社など)においては「収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)」が適用されています。どのようなものかを内容を見てみましょう。
収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)とはどのような基準?
収益認識に関する会計基準(以下「新収益認識基準」)とは、売上の認識と財務諸表への反映方法について定めた基準です。
日本国内における従来の売上計上基準は「実現主義」を用いるよう定められていました。しかし、IFRS(国際財務報告基準)や米国会計基準ではすでに収益認識基準を用いるよう明確に定められており、日本も米国や欧州等に追従する形で同じ基準の適用を目指した改正が行われました。
新収益認識基準が適用される会社
現時点で新収益認識基準が適用されるのは、資本金5億円以上もしくは負債200億円以上の会社法上の「大会社」および上場会社、また今後上場を予定している会社が対象となります。現在日本にある大会社以外の会社や個人事業主は対象外です。
新収益認識基準での仕訳とは?
新収益認識基準が適用されると仕訳の方法も変わります。今までは売手としてポイントを付与した場合、ポイントを使用するまではポイント分を仕訳する必要がありませんでした。しかし、新収益認識基準ではポイントを付与した時点で仕訳をしないといけません。
では、1万円の物品を現金で販売し、1,000円分のポイントを付与する場合の仕訳を見てみましょう。詳細は以下の通りです。
- 自社が発行するポイントの付与を想定しています。
- 消費税は考慮しないものとします。
- 過去の実績から、付与したポイントの使用率は80%とします。
1.使用率に基づき付与ポイントを仕訳
まずは、付与しているポイントに使用率をかけます。
1,000円×80%=800円のため、ポイントの独立販売価格が800円と算出されます。この独立販売価格は、将来値引きされるであろう金額として考えられます。
2.取引価格の配分
次に取引価格の配分を行います。
商品購入時に自社ポイントを使用されたものと仮定して取引価格へポイントを配分します。
商品への配分は1万円×1万円/(1万円+800)=約9,259円≒9,260円
自社ポイントの配分は1万円×800/(1万円+800)=約740円
3.ポイントを加味した仕訳
物品の販売金額は収益となりますが、まだ使われていないポイントは販売時には収益となりません。よって「契約負債」という勘定科目が使われ仕訳されます。
4.付与ポイントが使用された際の収益認識
この取引で付与したポイントが使われた場合の仕訳は以下の通りです。付与したポイントの消費にともない収益が認識されたと考えられ、売上に振り分けられます。
以上が、売手としてポイントを付与した場合、そしてポイントを利用された場合の仕訳です。大会社以外の会社、個人事業主への新収益認識基準適用時期は未定ですが、将来に備え今のうちから頭に入れておくと良いでしょう。
現時点では大会社以外のポイント付与時の仕訳は不要!
従来の会計制度では、ポイントに関する仕訳はポイントの付与または利用されたときに限られています。会計上では付与したポイントを認識せず、実際に付与されたポイントや発行したポイントの利用が発生した際に仕訳を行います。認識の仕方によって使用する勘定科目が異なりますので、自社の基準にあった勘定科目を選択しましょう。
一方、2021年4月から大会社や上場企業・上場予定会社を対象に適用され始めた新収益認識基準では、ポイントを付与した時点で仕訳を行う必要があります。現在は一部の企業のみに適用されている基準ですが、将来的には適用範囲が広がることが予想されます。いつ適用されても対応できるよう、どのような制度なのかだけでも確認しておくと良いでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
よくある質問
ポイント支払いをした場合の買手側の勘定科目は?
ポイントを値引きとする場合は「仕入値引」、収入とする場合は「雑収入」、現金支払い額として処理する場合は「現金」となります。詳しくはこちらをご覧ください。
ポイントで支払われた際の売手側の勘定科目は?
「売上値引」「販売促進費」いずれかで処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
勘定科目 収益の関連記事
新着記事
法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の種類を体系的に整理し、それぞれの税率や計算の仕組み、さらには…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率を知ることです。 本記事では、会社の規模による法人税率の違い…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引