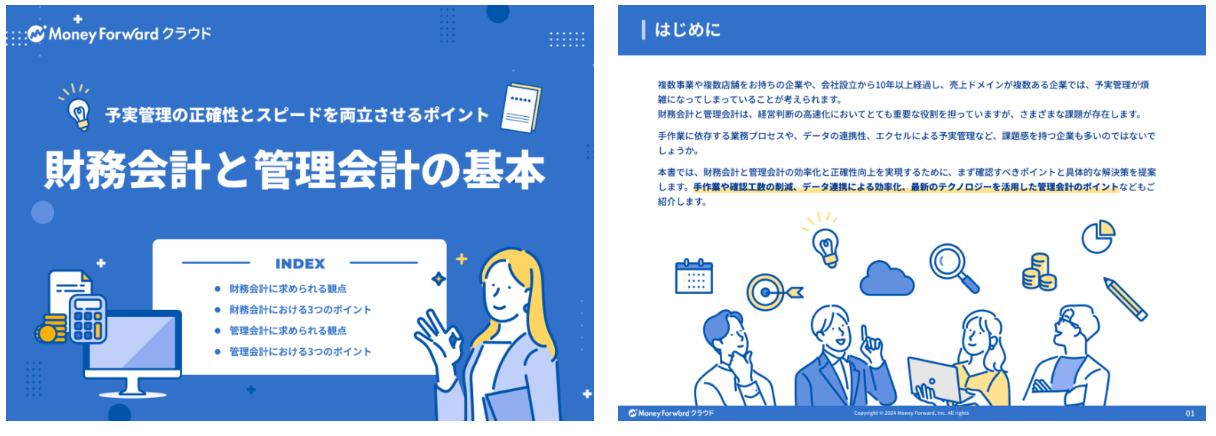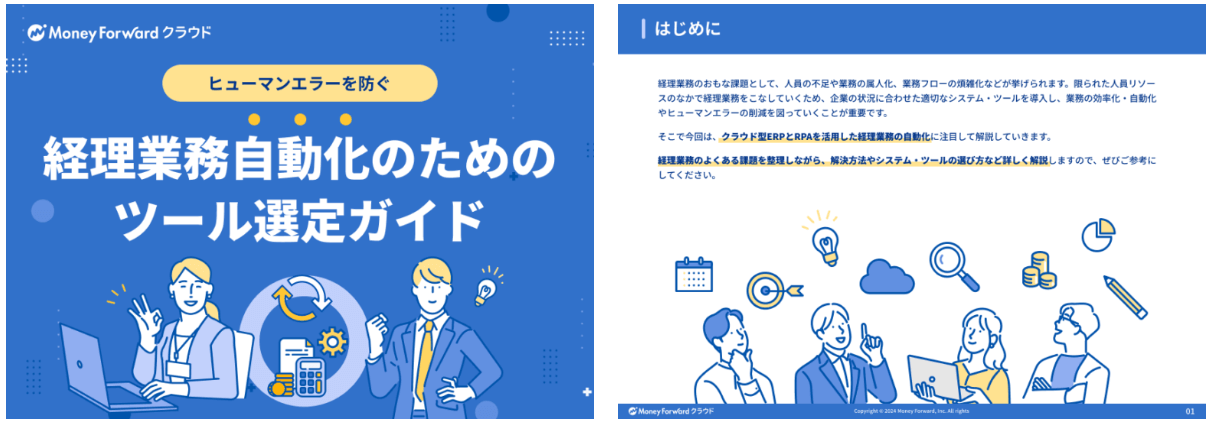- 更新日 : 2026年1月27日
新収益認識基準とは?適用範囲や導入時の注意点を解説
収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)が2021年4月から適用されるようになりました。原則として全ての企業が対象となっていますが、中小企業に関しては、従来通りの会計処理を継続してもよいとされています。この記事では、新収益認識基準の内容と適用範囲・対象、導入にあたっての注意点を解説します。
目次
新収益認識基準とは
はじめに、収益認識基準の定義をおさらいした上で、新収益認識基準の意味や適用時期、従来の収益認識基準との違いを解説します。
収益認識基準のおさらい
収益認識基準とは、「どのように売上を認識し、認識したものをどのように財務諸表に反映させるか(どのような会計処理を行うか)」に関する基準を意味します。つまり、「どの時点で売上を何円計上するのか」を定めたルールです。
新収益認識基準の意味
新収益認識基準は、2021年4月から開始される会計年度より、上場企業や上場予定会社、大会社に強制適用となった新たな収益認識基準です。
新収益認識基準における最大の特徴は、売上計上に5つのステップを経る点です。具体的には、「契約の識別」、「履行義務の識別」、「取引価格の算定」、「履行義務への取引価格の配分」、「収益の認識」の5ステップです。各ステップで行う業務は、後ほどくわしく解説します。
いつから適用される?
国税庁の「『収益認識に関する会計基準』への対応について」によれば、新収益認識基準は以下の時期から早期適用することが認められていました。
- 2018年4月1日以後に始まる事業年度
- 2018年12月31日以後に終わる事業年度
上記の時期から適用していない場合でも、前述の通り上場企業や大会社などは2021年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となっています。
従来の収益認識基準との違い
従来の収益認識基準と新収益認識基準の違いは以下のとおりです。
| 従来の収益認識基準 | 新収益認識基準 | |
|---|---|---|
| 売上の計上タイミング | 出荷基準、引渡基準、検収基準の3つがあり、企業によって採用基準が異なる | 履行義務が充足されたタイミング |
| 会計処理の具体例 ※年をまたいで履行義務が生じる場合 | 取引が成立したタイミングでまとめて計上 | 当期と翌期に収益を分けて認識・計上 |
簡単にいうと、比較的自由に選べた売上の計上タイミングについて、「履行義務が充足されたタイミング」に一本化されました。またタイミングだけではなく、金額に関しても、履行義務に応じて取引金額を区分することが求められるようになっています。
タイミングや金額の具体的な認識ステップについては、後ほど詳しく説明します。
※参考サイト:国税庁「『収益認識に関する会計基準』への対応について」
新収益認識基準の導入背景
ここからは、新収益認識基準の導入の背景を解説していきます。従来の日本では、前述のとおり収益認識の包括的な基準が定められていませんでした。定められていたのは「実現主義」の原則に従うということだけです。
「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」
(企業会計原則 – 第二、三)
収益の認識には、大きく分けて「現金主義」「発生主義」「実現主義」の3つの考え方があります。
- 現金主義:現金を受け取った時点で収益を認識し、収益・費用を計上する考え方
- 発生主義:取引が発生した時点で収益を認識し、収益・費用を計上する考え方
- 実現主義:商品やサービスの提供が行われ、現金や売掛金・受取手形などを受け取った時点で収益を認識し、収益・費用を計上する考え方
上述の通り、従来の日本では、収益認識を実現主義で行うことは定められていました。しかし実現主義には、より厳密な基準である「出荷基準」「引渡基準」「検収基準」の3つがあります。そのため、企業によって採用する基準が異なっていたのです。
企業の事業内容が多様で複雑になっている近年、企業によって収益認識が異なることになる実現主義だけでは、混乱を招く可能性が出てきました。
また、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が共同で、収益認識に関する包括的な会計基準を開発するという出来事もありました。そこで、日本の収益認識基準も、国際的な会計基準に合わせて統一することとなったのです。
新収益認識基準の5つのステップ
新収益認識基準では、売上は5つのステップを経て検討した金額とタイミングにより計上されます。この5つのステップについて解説します。
ステップ1:契約の識別
最初に、商品やサービスの提供について、顧客とどのような契約をしたのかを確認します。ここで契約とは、正式な書面で取り交わされたものに限りません。口約束や取引慣行なども当てはまります。
ステップ2:履行義務の識別
次に、その契約の内容を顧客に対する「履行義務」に分解します。この履行義務は、これまでの日本の会計基準にはなかった、新収益認識基準で初めて登場する概念です。
例えば、契約の内容が「商品を販売し、その保守サービスを行う」というものだったとしましょう。その場合には、履行義務は「商品の販売」と「保守サービス」の2つになります。契約内容を一体のものと見るのでなく、個別の履行義務に分解するのが新収益認識基準の特徴です。
ステップ3:取引価格の算定
契約の内容を確認し、履行義務に分解できたら、次に契約全体の取引価格を算定します。ここで注意が必要なのは、ポイントやクーポンを顧客に提供する場合です。
従来の会計基準では、ポイントやクーポンの有無にかかわらず、商品を販売すればその売上の全額を計上できました。しかし、新収益認識基準では、ポイントやクーポンの提供額を差し引かなければなりません。
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
契約全体の取引価格を算定したら、次にステップ2で識別した履行義務のそれぞれに、取引価格を配分します。
上の例で「商品販売と保守サービス」の取引価格が2万円だったとしましょう。それを、商品販売で1万円、保守サービスで1万円のように、履行義務ごとに価格設定するのです。このように新収益認識基準では、契約内容も取引価格も履行義務ごとに分解するのがポイントとなっています。
ステップ5:収益の認識
ここまでで、ようやく収益の認識ができる準備が整いました。収益は、契約に含まれるそれぞれの履行義務が果たされた時点で認識されます。
ここでも上の「商品販売と保守サービス」の例を取り上げてみましょう。まず商品販売は、商品が顧客に引き渡されれば履行義務が果たされます。そのため、収益は商品の引き渡しをもって認識されることになります。
それに対して保守サービスは、一定の契約期間にわたって継続しながら、徐々に履行義務を果たしていくことになります。簡単のため、保守サービスが当期初めから翌期末までの2年間だったとしましょう。その場合には、保守サービス料1万円は、当期で5,000円、翌期で5,000円のように、期間を分けて計上します。
新収益認識基準の適用対象となる会社の範囲
はじめに、新収益認識基準の適用対象が一目でわかる表を紹介します。概要のみを知りたい方はこちらをご参照ください。
| 強制適用 | |
| 任意適用(対象外) |
国税庁の「『収益認識に関する会計基準』への対応について」には、中小企業(監査対象法人以外)においては、今後も企業会計原則に基づいた会計処理も認められると記載されています。
監査対象法人とは、監査法人による監査が義務となる法人です。具体的な対象は、日本公認会計士協会の「金融商品取引法監査」および「会社法監査」によると以下のとおりです。
- 上場企業
- 上場準備会社
- 大会社(資本金5億円以上または負債金額200億円以上)
- 指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社
上記より、上場予定がない中小企業以外は、新収益認識基準が強制適用となります。現時点で上場していない場合でも、上場準備を進めている場合には強制適用となる点に注意が必要です。
また、上場会社や上場準備会社には、原則として子会社や関連会社が含まれる点にも注意を要します。理由としては、企業会計基準委員会の「連結財務諸表に関する会計基準」第17項にて、連結会社間においては会計基準を統一するようにと定められているためです。
※参考サイト:
日本公認会計士協会「金融商品取引法監査」
日本公認会計士協会「会社法監査」
企業会計基準委員会「連結財務諸表に関する会計基準」
新収益認識基準に影響される取引や業種
新収益認識基準は、顧客と締結した契約から発生する収益の会計処理・開示に適用されます。国税庁の「『収益認識に関する会計基準』への対応について」をもとに、新収益認識基準の影響を受ける主な取引・業種の具体例を解説します。
長期間にわたってサービスを提供する義務がある取引
事業年度をまたいで履行義務が一定期間で充足される取引が該当します。
たとえば、3年間にわたって同じサービスを提供する場合、契約時点で代金を受領しても、収益は各年(正確には月々)に分割して計上します。また、取引内容によっては進捗度に基づいて収益を計上する必要があります。
影響を受ける業種と想定される取引としては、主に下記があります。
- 建設業:建築工事
- IT業:ソフトウェア開発、保守サービス
- コンサルティング業:経営コンサルティングのサービス
商品とサービスをセットで販売する取引
1つの契約に複数の履行義務が含まれるケースです。たとえば、商品の売買契約に保守サービスの提供が含まれる場合、「商品販売」と「保守サービス」に分けて、収益計上のタイミングや金額を別々に考える必要があります。タイミングを例にすると、商品販売の部分は収益を受け取った時点で計上可能ですが、保守サービスの部分は実際にサービスを行うタイミングで都度計上する必要があります。
1つの契約に複数の履行義務が含まれるケースは多々あるため、ITや製造業などの幅広い業種に影響が及ぶと考えられます。
代理人取引
代理人取引とは、他の当事者が顧客に対する商品販売に関与している取引です。代理人取引では、自社が自ら商品を提供している(本人である)か、自社は他の当事者が商品を提供することを手配している(代理人である)かによって、認識する収益の金額が変わってきます。
本人である場合には、対価の総額を収益として認識します。一方で代理人である場合には、報酬または手数料の金額のみを収益として認識します。
影響を受ける業種と想定される取引としては、主に下記があります。
- IT業:ECサイトの運営
- 百貨店:テナント貸し
- 小売店:消化仕入
その他
上記以外の取引として、主に以下のものが新収益認識基準の影響を受けます。
| 取引の概要 | 会計処理 | 影響を受ける主な業種 |
|---|---|---|
| ポイントの付与が発生する取引 | ポイントが使われたタイミングで収益を認識する | 小売業、飲食店業など |
| キャッシュバック、値引き、リベート等 | 原則、キャッシュバック等の金額分を取引価格から減額する | 製造業、卸売業、小売業、IT業など |
新収益認識基準の適用外となる取引
ただし、以下の取引に関しては適用されません。
- 「金融商品会計基準」の範囲に含まれる取引
- 「リース会計基準」の範囲に含まれる取引
- 保険法による定義を満たす保険取引
- 同業他社との交換取引
- 金融商品の組成や取得で受け取る手数料
- 「不動産流動化実務指針」の対象となる不動産の譲渡
以上のケースに新収益認識基準が適用されないのは、他の会計基準や法令が優先される、または「顧客との契約から生じる収益」ではないと見なされることが理由です。
なお、上場企業・大企業以外の中小企業(監査対象法人以外の企業)については、新収益認識基準を適用せず、これまで通り企業会計原則にのっとった会計処理を行ってもよいとされています。
新収益認識基準導入時の注意点
新収益認識基準を導入する際の注意点は、以下の通りです。
現状を把握する
新収益認識基準の導入にあたっては、まず自社の商品・サービスの契約内容を精査し、履行義務を整理しましょう。何がどのように変更になるのか、しっかりと把握することが重要です。
対象を絞り込む
新収益認識基準は、必ずしも全ての取引に適用する必要はありません。グループ内に複数の会社がある場合、あるいは会社内に複数の商流がある場合には、各部門の負担なども考慮しながら重要度の高い取引を絞り込み、優先的に導入しましょう。
システムへの影響を分析する
新収益認識基準の導入で、各種システムの変更が必要となってくる場合があります。例えば、売上の計上額と顧客への請求額が異なってくる場合などには、会計システムの変更が必要となるでしょう。導入によりどのようなシステム変更を行わなければならないのか、問題点やリスクを洗い出すことが大切です。
契約への影響を検討する
新収益認識基準の導入で契約内容の変更が必要となるケースもあります。契約内容への影響もしっかり検討しておきましょう。
複雑な新収益認識基準に対応できるツールを導入する
新収益認識基準では複雑な会計処理を求められるため、対応可能な会計システムやERPツールの導入が重要です。
この基準に準拠した会計システムやERPツールの導入により、収益認識をはじめとした会計処理のミスを防ぎやすくなります。
また、新収益認識基準への対応に伴う経理担当者の負担軽減にもつながります。
財務会計の業務にERPを導入するメリットは、以下の記事で詳しく解説しています。
影響を洗い出して新収益認識基準を導入しよう
新収益認識基準とは、売上をどのように認識し、どのタイミングで財務諸表に反映するかについての統一的な基準です。契約内容を履行義務に分解し、履行義務が果たされた時点で売上を計上していくことになります。
新収益認識基準の導入は、変更による混乱が起きないよう、システムや契約への影響を洗い出し、場合によっては適用対象を絞り込んで進めていきましょう。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
「管理会計を効率よく正確にできるようになりたい」とお悩みではないですか?
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説します。
経理業務自動化のためのツール選定ガイド
「ツールをうまく活用して、経理業務におけるヒューマンエラーを削減したい」とお悩みではないですか?
経理業務のよくある課題を整理しながら、クラウド型ERPとRPAを活用した経理業務の自動化について詳しく解説します。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みではないですか?
中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
業務効率化と内部統制の強化を実現!
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けのクラウド型会計ソフトです。データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務を効率化すると同時に、仕訳承認・権限管理機能で内部統制にも対応します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
「税理士が何も提案しない」当然の理由 上手に付き合うコツは?
社長と話をしていると、「うちの税理士は何も提案してくれない……」という不満を聞くことがあります。こう聞くと「怠慢な税理士がいるんだなぁ」と思う方もいるかしれませんが、本当にそう言え…
詳しくみる広島で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
広島県で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中…
詳しくみる固定資産除却損とは?
固定資産除却損とは、会社の事業において、不要となり廃棄処分した有形固定資産を、除却することによって発生した損失のことである。 固定資産除却損は、バランスシートに計上されている、使用…
詳しくみる掛け払いとは?後払いとの違い、始め方とリスクについて解説
掛け払い(ツケ払い)とは、先に商品やサービスを提供し、請求書送付後まとめて支払いを受ける方法を指します。取引相手が法人中心(BtoB)である点が、後払いとの違いです。 本記事では、…
詳しくみる製造間接費配賦差異とは?求め方や仕訳(借方・貸方)をわかりやすく解説
製品の原価を正確に把握するためには、製造にかかる間接費の扱い方が重要です。特に、事前に見積もった費用と実際にかかった費用のズレである製造間接費配賦差異は、企業のコスト管理や経営判断…
詳しくみる支払明細書とは?意味や書き方、領収書・請求書との違い、無料テンプレートも
支払明細書というと、クレジットカードを使用した際などに発行されるものが思い浮かぶのではないでしょうか。しかし、会社同士の取引でも支払明細書を発行することがあり、さらには領収書や請求…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引