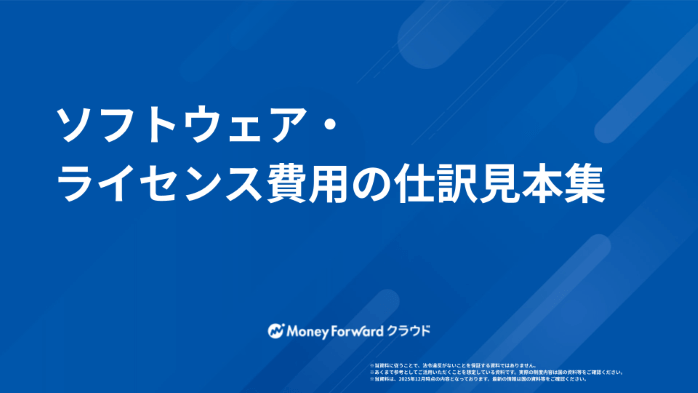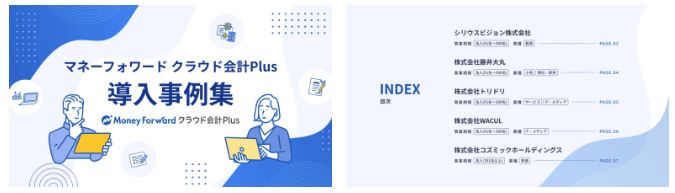- 更新日 : 2026年1月8日
会計ソフトやライセンスを購入した場合の勘定科目と仕訳例
会計ソフトやライセンスの購入費、月額のシステム使用料を仕訳する際、その勘定科目の種類や扱いはソフトのタイプが「インストール型(パッケージ型)」か「クラウド型」かで変化します。
ケース次第では経費計上ではなく「無形固定資産として資産計上」する必要があるため、財務状態を正しく把握・記録するためにも基本知識は押さえておきましょう。
当記事では会計ソフトを購入した場合の勘定科目の扱いと仕訳例を解説します。
目次
会計ソフトやシステム使用料の勘定科目はどうすればいい?
まずは会計ソフトを購入した場合に、システム使用料やその支払いに関係する勘定科目の扱いについて、インストール型とクラウド型に分けて解説します。
会計ソフトの勘定科目に明確なルールは存在しない
「会計ソフトの購入・利用料金はどの勘定科目にすればよいか」ですが、実は明確なルールが存在しません。というよりも、すべての勘定科目に関して「この代金はこのように分類しなさい」という法的な指示はありません。
つまり、どの勘定科目に分類するかは事業主の裁量次第で決まります。極端なことをいえば、すべての費用を雑費として計上することも可能です。
ただし何も考えずに決めてしまうと、財政状態が正確に把握できなかったり、銀行や税務署に財務情報を開示するときに不信感を持たれたりなどのデメリットが大きくなります。
なにより、固定資産など「資産として計上すべきもの」を経費計上するなどの仕訳に関しては、完全な間違いです。正確な財務・税務状態が記録できず、正しい決算書や確定申告書の作成が不可能になります。
以下5つの「勘定科目のグループ」から外れないような分類が必要です。
- 資産:企業などが支配している経済的資源
- 負債:企業などが支配している経済的資源の放棄や引き渡しの義務があるもの
- 純資産:資産から負債を差し引いた額
- 収益:取引に対して受け取った、あるいは受け取りが確定した金額
- 費用:取引に対して発生した、また支払った額
など
一度勘定科目の振り分けに関するルールを決めた場合は、後の記帳はすべてそのルールに従いましょう。もし途中で勘定科目を変えてしまうと、継続した経営状態の把握が難しくなります。
なにより、万が一税務調査が入ったときに「この事業所は勘定科目がコロコロと変わっているから、不正な経費を計上していないだろうか」と、調査官に悪い印象を与える可能性が高いです。もし自社内でルールを決める際は、国税庁の「帳簿の記帳の仕方」を参考にしてください。ちなみに、青色申告決算書に追加できる勘定科目は6個までです。
一般的には「消耗品費」か「通信費」
会計ソフトにかかる費用の勘定科目は、一般的に「消耗品費」か「通信費」のどちらかに分けられます。
- 通信費:会社経営で必要な電話代や郵便代金などの通信にかかる費用
- 消耗品費:消耗性があるものや使用可能年数1年未満かつ10万円未満の備品の費用
詳しくは後述しますが、PCにインストールするタイプの「インストール型会計ソフト」は消耗品費、クラウド環境を利用したタイプの「クラウド型会計ソフト」は通信費として仕訳を行うケースが多いです。
会計ソフトは減価償却の対象
10万円以上かつインストール型の会計ソフトは「無形固定資産」として資産計上するため、減価償却の対象になります。
なぜ資産計上になるかというと、会計ソフトを始めとするソフトウェアは「時間経過によって情報の価値・鮮度が落ちていく=価額が落ちる」という考えがあるためです。
ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額及び耐用年数は次のとおりです。
(引用:国税庁|ソフトウェアの取得価額と耐用年数)
10万円以上で業務用に導入した会計ソフトは、ソフトウェアを無形固定資産として計上する条件である「自社利用目的かつ収益獲得や費用削減が認められること」と、減価償却資産の条件である「1年以上の使用と10万円以上の取得価額」に当てはまります。
対してクラウド型会計ソフトの場合は、資産計上にはなりません。
サービス本体の保有元は提供会社であり、「自社が本体を取得したわけではない=資産が増えていない」という関係性になるためです(会計ソフト以外のクラウドサービスのすべてがそうというわけではない)。
インストール型会計ソフトの勘定科目
ここからは、インストール型会計ソフトの一般的な勘定科目の仕訳について解説します。
インストール型の会計ソフトは、購入費が10万円未満か以上かで扱いが変わります。正しい記帳を行うためにも、概要を理解しておきましょう。
インストール型は「消耗品費」になる
インストール型会計ソフトの勘定科目は「消耗品費」とするのが一般的です。
店頭で購入する場合も、インターネットを通じてダウンロードする場合も、どちらも消耗品費として費用計上します。
取得価額には、インストール時に必要なカスタマイズ料や環境設定にかかる人件費も含むため注意しましょう。
もし合計額が10万円以上となった場合は、無形固定資産の「ソフトウェア」として仕訳するのが一般的です。
10万円以上の場合は資産計上が必要
前述のとおり、10万円以上のインストール型会計ソフトは無形固定資産として計上します。減価償却処理も必要です。
ただし次の特例を使用することで、全額を損金算入できたり3年間に分けて計上できたりします。
1つめは少額減価償却資産の特例(中小企業の特例)です。
中小企業者等が取得価額30万円以下の減価償却資産を2022年3月31日までに取得した場合、その金額を全額損金へ算入できます。つまりその全額の経費計上が認めらます。
ただし、その適用を受ける事業年度において経費計上が認められるのは、取得価額の合計額が300万円が限度となります。
適用条件は次のとおりです。
2つめは一括償却資産の損金算入です。
これは法人・個人事業主が10万円以上20万円未満の減価償却資産を均等償却し、3年間損金として参入できる制度です。
たとえば18万円で購入した場合は、概算で大体6万円×3年間で計上できます。書類提出などの特別な条件はないものの、一括償却資産として勘定科目に含めたり確定申告時に損金にした分を調整したりする作業が必要です。
インストール型会計ソフトの費用の仕訳方法
ここからは、インストール型会計ソフトの費用の仕訳方法を解説します。10万円以上のパターンと10万円未満のパターンのそれぞれを見ていきましょう。
10万円以上のパターン
10万円以上のインストール型会計ソフトの仕訳方法は、「通常の場合」と「特例を適用した場合」の2パターンに分かれます。
まずは特例を使わず、通常の無形固定資産として計上する場合の仕訳パターンです。
<通常の無形固定資産として計上>
続いて仕訳した年度末に減価償却した金額を記帳していきます。
事業用に導入した会計ソフトの耐用年数5年であるため、使用する減価償却費は280,000円×0.2=56,000円としました(取得価額×定額法の償却率)。
次に30万円以下で購入した会計ソフトに対し、少額減価償却資産の特例を当てはまる場合の仕訳方法を見ていきます。
<少額減価償却資産の特例を適用した場合>
先ほどと同じ金額でもすべて損金算入できるため、全額を消耗品費として経費計上します。減価償却も不要です。年度末の仕訳は発生しません。
最後に10万円以上20万円未満の会計ソフトで一括償却資産として計上したパターンを見ていきます。
<一括償却資産の損金算入を適用した場合>
上記のように、会計ソフトの購入費を一括償却資産として仕訳します。年度末は一括償却資産の損金算入によって、通常の5年ではなく3年で減価償却を行います。
使用する数値は180,000円×0.334(3年の償却率)=60,120円です。
10万円未満のパターン
10万円未満のインストール型会計ソフトの場合は、すべて消耗品費として経費計上を行います。
<10万円未満のインストール型会計ソフトの仕訳の場合>
特別な手順もないため、他の勘定科目と同じように仕訳を進めていきましょう。
クラウド型会計ソフトの勘定科目
インストール型会計ソフトに反して、クラウド型会計ソフトの勘定科目の仕訳は複雑ではありません。詳細を見ていきましょう。
クラウド型は「通信費」になる
インストール型と違い、クラウド型会計ソフトは「モノの購入代金」というより「インターネット環境の使用料」という形式に近くなります。「無形固定資産(ソフトウェア)を購入した」という扱いにはなりません。
そのため仕訳のときは、通信費として経費計上することが一般的です。
この考え方は、日本公認会計士協会の「研究開発費及びソフトウェアの会計ソフトに関する実務指針」に基づいています。
支払いはすべて経費として全額計上する
クラウド型会計ソフトにかかる支払いは全額経費として計上します。
大手がリリースする会計ソフトのほとんどは、サービスやサポートの費用を月額プラン(年額プラン)としてまとめているため、月割の通信費として毎月計上するケースが多くなるはずです。
クラウド型会計ソフトの費用の仕訳方法
クラウド型会計ソフトの仕訳は、支払い時に通信費として記帳するのみです。
サポートを受けた場合の勘定科目
会計ソフトを購入した際には、実務にかかわるサービスの利用料金以外にも「サポートを受けた際に発生する料金」があります。このサポートにかかる支払いに関する勘定科目も、前述までと同じように明確な決まりはありません。
ただし会計ソフトの購入から導入・環境構築までのサポートがセットになっている場合や、月額料金にサポート費用が含まれている場合は、消耗品費や通信費、ソフトウェアなどの勘定科目に含めて計上しましょう。
会計ソフトの勘定科目を適切に処理して節税につなげよう!
会計ソフトの勘定科目は、購入した会計ソフトが「インストール型」か「クラウド型」で考え方が違います。一般的にはインストール型が消耗品費、クラウド型が通信費です。
インストール型会計ソフトの場合は、購入金額が10万円未満か以上かで経費になるか資産になるかが変わるので注意しましょう。対してクラウド型会計ソフトは全額が経費計上できます。
とはいえ、法や規則で勘定科目が決まっているわけではありません。ときには臨機応変に対応しつつ、あなたや税務署にとって明確な勘定科目となるよう設定しておきましょう。
企業規模別!会計システム選び方ガイド
マネーフォワード クラウドでは、中堅企業とIPO準備企業向けに、それぞれ会計システムの選び方ガイドをご用意しています。ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
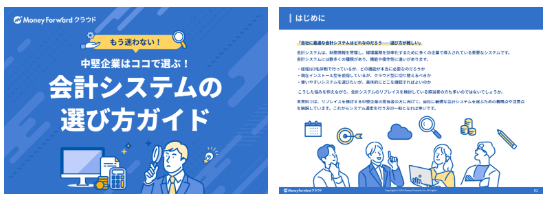 「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本書では、中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
IPO準備企業のための会計ソフト選び方ガイド
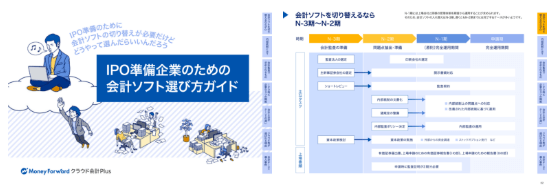 IPOに向けて会計ソフトを見直したいが、いつ・どのようなポイントで選べばよいか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
IPOに向けて会計ソフトを見直したいが、いつ・どのようなポイントで選べばよいか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
本資料では、上場準備の流れに沿って、効果的な内部統制の構築と会計監査に効率的に対応するために必要な機能を解説します。
会計ソフトの仕訳と似たような解説記事はこちら
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
マネーフォワード クラウド会計Plus導入事例
マネーフォワード クラウド会計Plusは多くの成長企業にご導入いただいています。
本資料では、選定過程や導入効果など導入企業様の声をまとめました。導入に成功した企業について知りたい!という方におすすめです。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
青色申告1から簡単ガイド
個人事業主で会計ソフトをお探しの方におすすめです!
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
自分で法人決算!決算書の作り方ガイド
会計ソフトにご興味がある、1人法人の方や、中小企業の経理の方におすすめなのがこちらのガイドです。
本書では、各決算書の概要や具体的な作り方をわかりやすく解説しています。 また、作成した決算書の提出先や「マネーフォワード クラウド会計」で簡単に作成する流れも紹介しています。
よくある質問
会計ソフト(確定申告ソフト)の勘定科目はどうすればいい?
一般的に消耗品費か通信費のいずれかに分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
インストール型会計ソフトの勘定科目は?
消耗品費とするのが一般的ですが、10万円以上の場合は資産計上が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
クラウド型会計ソフトの勘定科目は?
通信費となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
会計ソフトの関連記事
勘定科目 通信費の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引