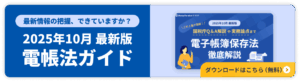- 作成日 : 2025年10月6日
法人に税務調査が入る確率は?入りやすい会社の特徴と対応方法を解説
会社を経営していると気になるのが税務調査です。
すべての法人が毎年調査されるわけではないものの、一定の割合で税務署から調査の対象に選ばれる場合があります。
実際に調査が来るのは全体の数%程度である一方、業種や規模によって入りやすい会社とそうでない会社があるのも事実です。
突然の調査に慌てないためには、確率の目安を知るだけでなく、調査の種類や流れ、必要書類、当日にチェックされやすい項目を理解しておく姿勢が大切です。
本記事では、法人に税務調査が入る確率から調査の流れ、対象になりやすい特徴、そして税務調査が実施される際の具体的な対応方法までをわかりやすく解説します。
目次
法人に税務調査が入る確率はどのくらい?
法人に税務調査が入る確率は、実際にはごく一部の法人に限られます。
令和5年度のデータによると、法人税の申告件数は約317万6千件、そのうち調査を受けたのは約5万9千件でした。
税務調査を受けた法人の割合はおよそ1.9%で、全体の数%程度しか調査がおこなわれていない状況です。
つまり、税務調査はすべての法人に必ずおこなわれるわけではなく、対象となるのはごく一部に限られます。
しかし、どの法人でも選ばれる可能性があるため、いつ調査の対象になっても慌てないよう、普段から準備を整えておく意識が大切です。
とくに業種や事業規模、売上の動きによっては、税務調査に選ばれやすい場合もあります。
経営者としては「自分の会社は大丈夫」と油断せず、帳簿や領収書を日頃から整理しておくように心掛けましょう。
正しく申告し、基本的な整理ができていれば、突然の税務調査にも落ち着いて対応できます。
法人に対しておこなう税務調査の種類
法人に入る税務調査には主に2つの種類があります。
基本的には「任意調査」が中心で、悪質な脱税が疑われる場合には「強制調査」がおこなわれる場合があります。
事前に、それぞれの特徴を理解しておくと安心です。
任意調査
任意調査は、税務調査で多くの会社が受ける一般的な調査方法です。
まず税務署から電話で連絡があり、対象となる期間や調査の目的、必要な書類などが伝えられ、会社側と日程を調整します。
調査官は帳簿や領収書、請求書、通帳などを丁寧に確認し、社長や経理担当者に対して取引内容や経費の裏付けなど、調査内容に応じた質問をします。
調査は通常1日から数日程度で終わり、内容に問題がなければ申告どおりと判断され、基本的に特別な対応は求められません。
書類を普段から整理しておき、数字の根拠を説明できれば、任意調査は落ち着いて対応できます。
強制調査
強制調査は、ニュースなどで取り上げられる「マルサ」が実施する調査にあたります。
強制調査になるケースは、脱税の疑いが強く、証拠を隠したり処分したりする恐れがある場合などです。
任意調査と異なり、事前の通知は一切なく、裁判所の令状を持った調査官が突然会社に押し入り、早朝から一斉に調査を始めるのが特徴です。
帳簿や現金、パソコンのデータなども細かく確認され、関係者への聞き取り調査もおこなわれるケースがあります。
対象となるのはごく一部の悪質な事例であり、通常の会社経営をしていれば強制調査を受けることはまずありません。
ほとんどの法人にとっては、日常的におこなわれる任意調査が中心です。
法人に対しておこなう税務調査の流れ
法人に対する税務調査は、通常は事前の通知から結果の通知まで一定の流れがあります。
流れとしては、大きく分けると「事前通知・日程調整」「必要書類の準備」「調査当日」「調査後」の4段階に整理できます。
それぞれの段階で確認される内容や対応のポイントを理解しておき、落ち着いて対応しましょう。
事前通知・日程調整
法人への税務調査は、税務署からの事前通知で始まり、対象年度や確認内容、準備すべき資料が伝えられます。
その後、会社と税務署の間で訪問日を調整し、通常は1〜2週間以上の余裕をもって日程が決まります。
余裕を持ったスケジュール調整は会社に備える時間を与える意味合いもあり、調査官が効率的に調査を進めるためにも欠かせない手順です。
しかし、税務署から連絡を受けた後に慌てて準備すると不備が出やすい場合もあるため、帳簿や証憑を日頃から整理しておくのが安心です。
また、事前通知は調査の流れを理解する良い機会でもあるため、必要書類の確認や顧問税理士への相談を早めに進めておきましょう。
必要書類の準備
税務調査に臨む際には、法律で定められた保存義務に基づき、7年間分の帳簿や証憑を整えて提示できる状態にしておく必要があります。
代表的な資料には、決算書や法人税・消費税の申告書控え、仕訳帳などの申告関連書類があります。
あわせて、請求書や領収書、銀行通帳、現金出納帳といった売上・経費関連の書類も必須です。
さらに、給与台帳や源泉徴収簿といった人件費資料、棚卸表などの在庫関連資料も確認対象です。
調査官は数字の整合性や裏付けを重視するため、必要書類を取引ごとや日付順に整理し、金額や内容が一目でわかる状態にしておきましょう。
税務調査当日
調査当日は、税務署の調査官が会社を訪問し、帳簿や証憑をもとに申告内容の正確性を確認します。
社長や経理担当者に「この取引の根拠は何か」「この経費は業務に関連しているか」といった具体的な説明を求められた場合は、速やかに対応しましょう。
帳簿や領収書だけでなく、通帳や契約書、現金残高、在庫の実地確認まで調べられる場合があります。
とくに注目されるのは、売上の計上漏れや不適切な経費処理の有無です。
質問に対して曖昧に答えると余計に疑念を招く恐れがあるため、数字の根拠を整理しておきましょう。
普段から帳簿や証憑を整えておけば、調査当日も落ち着いて対応でき、不要なトラブルを避けやすくなります。
税務調査後
調査が終了すると、税務署から結果が通知されます。
問題がなければ是認通知が交付され、「申告内容が正しかった」と認められて調査終了です。
一方、計上漏れや経費処理の誤りが見つかった場合には、修正申告をおこない、追加の税金を納める必要があります。
さらに、売上隠しなど意図的な不正が確認された場合は、重加算税のような厳しいペナルティが課されるケースもあります。
調査結果は単なる指摘にとどまらず、会社の内部管理体制や税務リスクの改善点を示す指針です。
そのため、不安があれば顧問税理士に相談し、指摘事項を整理して次年度以降の申告に反映しましょう。
調査を単なる負担と捉えず、経営改善の機会として活かす姿勢が求められます。
税務調査が入りやすい法人の特徴5つ
税務調査はすべての法人に同じ確率で入るわけではなく、業種や規模、経営状況によって対象になりやすい会社があります。
ここでは、とくに調査に入りやすいとされる法人の特徴を5つに整理し、それぞれの背景や注意点を解説します。
自社が当てはまるかどうかを確認し、早めに備えておきましょう。
① 事業規模が大きい
売上や従業員数が多い法人は、税務調査の対象に選ばれやすい傾向があります。
背景としては、取引金額が大きくなるほど、申告に誤りがあった際の税額への影響も大きくなるため、国として税務リスクが高いと判断されやすい点が挙げられます。
大企業はもちろん、急速に成長している中小企業も注意が必要です。
とくに、売上規模が数億円を超える水準に達すると、取引の複雑さや経費処理の多さから、申告内容の確認をおこなう目的で調査が入る可能性が高まります。
事業規模が拡大すると経理体制が追いつかず、管理の不備が生じやすい点も背景にあります。
そのため、会社の規模が大きくなった段階で、経理担当者の増員や会計ソフトの活用・見直し、顧問税理士のサポート強化など、内部管理の整備を進めておきましょう。
② 税務調査に入られやすい業種である
税務調査対象になりやすい業種の場合、調査の確率は高まります。
代表的なのは、飲食業や小売業のように現金取引が多い業種です。
現金は記録が残りにくく、売上の一部を申告から外してしまう不正がおこなわれやすい背景から、税務署も重点的に注視します。
また、建設業や不動産業も取引金額が大きく、契約の途中で報酬を受け取ったり、工事がまだ終わっていない段階で費用が発生したりするなど複雑な処理が多い業種です。
税務調査対象になりやすい業種は国税庁の内部方針で「重点調査業種」と位置付けられる場合もあり、定期的に調査対象に選ばれるケースが目立ちます。
事業をおこなう側としては、業種特有の会計処理を理解し、誤りが起きやすいポイントを把握しておきましょう。
顧問税理士のサポートを受けながら、業種特性に即した帳簿管理を徹底する意識が求められます。
③ 売上や利益が大きく伸びている
急激に業績が伸びている法人も、税務調査に選ばれやすい特徴があります。
前年まで赤字や横ばいだったのに、ある年から急に売上や利益が大きく伸びた場合、申告内容の正確性について調査がおこなわれる場合があります。
とくに新規事業を始めたばかりの会社や、急成長分野で事業を展開している会社は注意が必要です。
業績が急拡大すると、経理体制が追いつかず記帳の誤りが発生したり、節税対策が不十分で申告漏れを疑われたりするリスクも高まります。
実際には適正に申告していても、調査官は「確認目的」で訪問するケースも少なくありません。
売上が伸びている時期こそ、会計処理を正しくおこない、数字の根拠をすぐに示せる状態を整えておく必要があります。
④ 不正や誤りを指摘されたことがある
過去に修正申告をおこなった経験がある法人は、税務署から「再チェックの必要がある」と判断されやすくなります。
一度指摘を受けた会社は、「帳簿管理や会計処理に不安がある」と見られるため、数年後に再び調査がおこなわれるケースも珍しくありません。
小さな計算ミスや処理の誤りでも、頻繁に発生していると「管理体制に問題がある」と評価され、継続的に注視される可能性が高まります。
そのため、指摘を受けた場合は単に修正申告をして終わりにするのではなく、原因を分析し、改善策を講じる姿勢が求められます。
たとえば、仕訳入力の二重チェック体制を整えたり、経理担当者の教育を強化したりする施策も効果的でしょう。
税務署に対して「改善済みである」と示す姿勢が、再調査への備えとなります。
⑤ 開業後3年以上経過している
新設法人は設立からしばらくの間は税務調査の対象にならない場合が多い一方で、設立後3〜5年が経過すると税務調査が入るケースがあります。
比較的新しい法人においては、税務署は「一度は確認しておこう」という意図で調査をおこなう場合があります。
また、法人が安定した経営基盤を築き、適正な申告ができているかを確かめる意味合いもあり、とくに「初回調査」は丁寧に実施される傾向です。
開業直後は調査が無いからと安心するのではなく、数年後には調査を受ける可能性がある前提で準備を整えておきましょう。
帳簿の付け方や経費処理の仕組みが不十分だと、初回調査で大きな指摘を受けかねません。
創業期から正しい会計処理を身につけ、税理士と連携しながら経理体制を固めておけば、将来的にも安心です。
法人に税務調査が入った際の対応方法
法人に税務調査が入った場合、焦らず冷静に対応することが大切です。
とくに必要書類の準備や申告内容の整理、専門家への相談は、調査を円滑に進めるうえで欠かせません。
ここでは、実際に調査を受けたときに押さえておきたい3つの対応ポイントを解説します。
必要書類を準備する
税務調査では、まず資料の提示を求められます。
申告書や決算書、総勘定元帳や仕訳帳といった基本的な帳簿類はもちろん、領収書や請求書、伝票など日常の取引を裏付ける証憑も対象です。
必要書類は日付順や金額ごとに整理しておくと、調査官から求められた際にすぐ提示でき、やり取りもスムーズです。
また、現金出納帳や銀行通帳はとくに重点的に確認されやすいため、残高や記帳内容の一致を普段から確認しておきましょう。
さらに調査官は机や金庫、店舗の棚など、実際の現場を確認する場合もあります。
書類だけでなく、保管状況や在庫の管理体制まで見られる可能性があるため、事務所や店舗を整理整頓しておきましょう。
申告内容や事実関係を事前に整理する
税務調査では、調査官から申告内容の根拠を問われる場面が多くあります。
「この売上はどの取引先との契約に基づくのか」「この経費はどの業務に関連するのか」といった質問に対し、根拠を明確に答えられないと不要な疑念を招きかねません。
そのため、数字の裏付けをあらかじめ整理し、説明できる状態にしておく取り組みが重要です。
不安な点があれば事前にメモを作り、想定される質問に備えておくのも有効です。
調査は事実確認を目的としているため、誤魔化そうとする姿勢は逆効果になります。
誠実に説明しつつ、数字の正当性を裏付ける資料を準備しておけば、調査官の信頼を得やすく、調査を円滑に進められます。
税理士に相談する
顧問税理士がいる場合は、税務調査の連絡を受けた時点で早めに相談しましょう。
税理士は調査の立ち会いができるため、経営者や経理担当者が答えにくい専門的な質問に対応可能です。
また、回答の仕方や資料の出し方についても事前に助言を受けられるため、余計なトラブルを避けやすくなります。
税務署とのやり取りに不慣れな経営者が一人で対応すると、思わぬ言い回しが誤解を招くケースもあります。
その点、税理士が同席していれば、適切にフォローしてくれるため安心です。
顧問税理士がいない場合でも、スポットで調査立ち会いを依頼できる場合もあるので、専門家のフォローを受け、調査全体を落ち着いて乗り切りましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
墨田区で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
墨田区(東京都)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな負担となりがちです…
詳しくみるペーパーレス化とは?導入方法のポイントやメリットを解説
近年は多くの企業でペーパーレス化の動きが加速しています。そもそもペーパーレス化がどういったものなのか、その意味や目的を理解していない方も多いでしょう。 そこで、本記事ではペーパーレス化の概要を解説するとともに、導入する効果やメリット、今後の…
詳しくみるものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金を活用しよう!
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」という制度があるのをご存じでしょうか。革新的なものづくりやサービスを創出するための補助金です。今回は、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金制度の内容について見ていきましょう。 事業…
詳しくみる中小企業・零細企業が会計ソフトを比較するための13のポイント
従業員が増え、会計処理も増加すると、いよいよExcelや紙ベースでは管理が難しくなってきます。経理業務効率化のため会計ソフトの導入を考えている中小企業もあるでしょう。 しかし、会計ソフトは、その種類が豊富なため、いざ導入するとなったとき、ど…
詳しくみる2026年版-会計ソフトとは?代表ソフト一覧!法人・個人別の選び方のコツ
この記事では、代表的な会計ソフト(経理ソフト)や、会計ソフトの種類、主な機能、初心者向けの使い方などを解説します。 会計ソフト探しでよくある疑問・悩み 【法人の方】貸借対照表や損益計算書などの決算書も作成したい 【個人事業主・副業の方】確定…
詳しくみる雑損失とは?いくらまで計上できる?仕訳や消費税区分まで解説
営業外費用のうち、他の勘定科目のいずれにも該当しない費用や損失を処理するときに、雑損失の勘定科目が使われることがあります。そもそも、雑損失はどのような性質の勘定科目なのでしょうか。この記事では、雑損失の例や仕訳例、消費税区分や雑費との違い、…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引