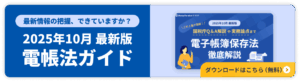- 作成日 : 2025年10月6日
税務調査の反面調査とは?事例・対応の流れと回避方法を解説
税務調査の中でも「反面調査」と呼ばれる調査は、取引先や銀行など第三者にまで調査が及ぶケースです。
突然おこなわれる場合もあり、取引先に迷惑をかけたり、信用低下につながる可能性があるため、とくに注意が必要です。
反面調査はすべての税務調査でおこなわれるわけではないものの、実施されれば精神的な負担も大きくなります。
本記事では、反面調査とは何か、どのような場合におこなわれるのか、さらに実際に調査を受けたときの対応や回避のための備えについて、わかりやすく解説していきます。
目次
税務調査の反面調査とは
税務調査の中でも「反面調査」とは、納税者本人ではなく、取引先や顧客、銀行、不動産会社など第三者に対しておこなわれる調査を指します。
通常の税務調査で帳簿や領収書を直接確認したり、本人から説明を受けたりするだけでは取引の実態が判断できない場合に、第三者へ確認が及びます。
反面調査はすべての調査でおこなわれるわけではなく、例外的に実施される調査です。
ただし一度実施されると、取引先に「自分との取引が疑われているのではないか」と不安を与えたり、場合によっては信用低下につながるリスクがあります。
また、反面調査は事前に通知される場合もある一方で、法律上は必ずしも通知義務があるわけではありません。
そのため、税務署が突然取引先を訪問するケースもあり、納税者にとっても取引先にとっても大きな心理的負担になりやすいのが実情です。
したがって、日頃から帳簿や証拠書類を整理し、誤解を招かないようにしておく取り組みが、反面調査を防ぐための最善の備えといえます。
反面調査がおこなわれる事例
反面調査は、すべての税務調査で実施するわけではありません。
どんなときに反面調査がおこなわれやすいのかを知っておけば、日頃の準備や対応にも役立ちます。
ここでは代表的な事例を3つにしぼって紹介します。
税務調査で資料が不十分だった場合
反面調査が実施される典型的なケースは、必要な資料が不十分な場合です。
たとえば、帳簿や領収書を紛失・破棄してしまい証拠が残っていない場合や、保存はしていても不備が多く、取引の裏付けとして不十分な場合などが挙げられます。
本人の説明に客観的な裏付けがないと、調査官は「事実関係を確認する必要がある」と判断し、取引先や金融機関に直接確認する流れになりやすくなります。
また、必要書類を提出しなかったり、質問への回答を避けるなど非協力的な態度をとった場合も同様です。
つまり、資料の管理や誠実な対応は、反面調査を防ぐための重要なポイントといえます。
申告内容に矛盾や不自然さがある場合
申告された内容に矛盾や不自然さが見られると、税務署は「本当に正しいのか」を確認するために反面調査をおこなう場合があります。
たとえば、実際には存在しない架空の経費や仕入れを帳簿に計上すると、数字上は支出が増えて利益が減ったように見えるものの、実態が伴わないため虚偽の申告と判断されます。
また、売上や仕入の金額が、取引先が把握している数字と大きく食い違っている場合や、本人の説明に一貫性がなく供述内容に矛盾がある場合も同様です。
申告内容が不自然な場合、税務署が取引先や関係者に直接問い合わせをおこない、事実確認を進めます。
所得隠しや脱税の疑いがある場合
所得を意図的に隠したり、税金を免れるための不自然な取引が見られる場合には、反面調査が実施されやすくなります。
たとえば、資金の流れが複雑な取引や、親族や関連会社を経由して売上を分散させるような不透明な方法は所得隠しや脱税が疑われます。
また、高額な現金取引や、説明のつかない入金・出金が見つかった場合も、疑いを招く原因です。
前年と比べて急に所得が大幅に減っている場合も、売上の一部を隠しているのではないかと疑われやすい例のひとつです。
通常の経営活動では説明できない不自然な点があると、税務署は取引先など第三者へ確認せざるを得なくなります。
反面調査対応のポイント5つ
反面調査に直面した際は、その場の対応の仕方ひとつで税務署の印象が変わり、調査の長さや今後の信用にも影響します。
適切な準備と誠実な態度を見せれば、疑念が解消されて調査が早く終わったり、取引先に不必要な迷惑をかけずに済んだりといったメリットにつながります。
ここでは、実際に反面調査がおこなわれる場合に押さえておきたい5つの具体的な対応ポイントを確認しておきましょう。
① 顧問税理士に立ち会いを依頼する
反面調査を含む税務調査を受ける際には、まず顧問税理士へ速やかに連絡し、できる限り立ち会いを依頼しましょう。
税理士は税法や調査対応の専門知識を持っているため、調査官とのやり取りをスムーズに進められます。
税理士が同席していれば、経営者がうまく説明できなかった部分や、言葉の選び方で誤解を招きそうな場面でも、その都度フォロー可能です。
税務署側も、専門家の関与がある点で安心感を持って調査を進められるため、無用な疑念を抱かれにくくなる可能性があります。
結果として不利な発言を避けつつ、公平な調査環境を整えられるため、税理士の立ち会いは大きな安心材料のひとつといえます。
税理士との関わりがない場合は、早めに契約しておきましょう。
② 取引内容を正しく説明する
調査にあたっては、取引の経緯や背景を正しく説明する姿勢が求められるため、請求書や契約書、振込明細などの証拠書類をあらかじめ整理しておく準備が大切です。
調査時に記憶だけで話すと、細部が曖昧になり「本当に正しいのか」と疑われやすくなります。
さらに、取引先や社内関係者にも事前に調査の内容を共有しておけば、回答に食い違いが生じるリスクを下げられます。
少しでも矛盾した説明が出ると「虚偽の可能性がある」と判断され、反面調査に発展するケースも珍しくありません。
短期的にはごまかしでしのげても、後から証拠が出ればかえって重い指摘につながるため、正しい事実を整理して伝える姿勢が、調査を早期に終わらせるカギです。
調査当日の説明に不安がある場合は、税理士へ相談して話し方を準備しておくと安心です。
③ 資料を事前準備して提示できるようにする
調査では帳簿や領収書、契約書などの証憑を求められるため、資料をすぐに提示できるよう、日頃からファイルや会計ソフトで整理しておきましょう。
調査の際は、求められた資料だけを出す意識も大切なポイントです。
関連のない書類まで提出してしまうと、調査官が余計な疑問を持ち、別の部分まで調査が広がるおそれがあります。
逆に、必要な資料を隠したり渋ったりすると「何か不正があるのでは」と判断されやすくなり、反面調査につながりやすくなります。
普段から資料をデジタル化しておき、急な調査にも落ち着いて対応しましょう。
④ 誠実に対応する姿勢を見せる
調査官が「事実を隠しているのでは」と感じると、調査が長引き、取引先にも迷惑が及ぶ可能性があるため、反面調査では誠実な姿勢を意識しましょう。
質問に正直に答え、必要な資料を丁寧に提示すれば、調査官から協力的であると評価され、調査が早期に終わる可能性があります。
加えて、誤りが見つかった場合に速やかに修正申告をおこなえば、正直に向き合っている姿勢として信頼につながります。
注意すべきは、取引先に対し虚偽や隠ぺいの協力を求めると、取引先が罰則を受ける可能性がある点です。
もともと税務調査を受けている会社が虚偽申告や隠ぺいをしていれば、重加算税や追徴課税といった処分を科されるおそれもあります。
税務署側に誠実さを示す意識が信用維持とトラブル回避の両方につながります。
⑤ 調査の内容を記録に残す
調査官とのやり取りや、提出した資料の内容は必ず記録に残しましょう。
記録がないと、後日「そんな説明は受けていない」「その資料は出していない」といった食い違いが起きやすくなります。
やり取りを日時ごとに記録し、提出資料の控えを残しておく取り組みは、後日のトラブル防止に有効です。
さらに、調査時の記録を税理士や反面調査が入った取引先と共有すれば、状況の把握や対応方針の調整もスムーズにおこなえます。
とくに反面調査は第三者を巻き込むため、関係者への説明責任を果たす意味でも記録が重要です。
可能であればデジタルで時系列に整理しておくと、必要なときにすぐ確認できます。
調査が長引いたり再度問い合わせが来た場合にも、記録があれば安心して対応できます。
反面調査を回避する方法
反面調査は取引先や銀行など第三者にまで影響が及ぶため、できれば避けたいものです。
普段から正しく準備・対応しておけば、反面調査に発展するリスクを下げられます。
ここでは、実務で役立つ3つの具体的な方法を紹介します。
会計データを保存期間に従って保管する
反面調査を避けるためには、まず帳簿や請求書、領収書などの会計データを正しく保管しておく取り組みが欠かせません。
法律では原則7年間の保存が義務づけられており、少なくとも直近3~5年分は必須です。
保存が不十分で証拠が揃わないと、取引先にまで確認が及ぶ可能性が高まります。
逆に、データが整っていれば税務署も第三者に確認をする必要がなく、その場で調査を終えられるケースもあります。
紙の資料だけでなく、通帳やレシート、電子データなども含めてきちんと保管しておきましょう。
普段から資料を整理し、提出を求められたときにすぐ提示できるようにしておけば、反面調査のリスクを大幅に下げられます。
税務調査で誠実に協力する
税務調査に誠実に協力する姿勢は、反面調査を回避する大きなポイントのひとつです。
調査官からの質問に正直に答え、必要な資料を丁寧に提示すれば「協力的」と評価され、調査が早期に終わる可能性も高まります。
逆に、曖昧な返答や虚偽の説明をしたり、書類の提示を拒んだりすると、調査官は疑念を深め、取引先や金融機関にまで確認が及ぶおそれがあります。
普段から不自然な取引を避け、判断に迷う部分は必ず専門家に相談する習慣があると安心です。
正直かつ前向きに対応する姿勢が、最終的には自社を守る一番の近道です。
税務調査の段階で顧問税理士に同席を依頼する
税務調査が入ったときには、早い段階で顧問税理士に同席を依頼しましょう。
専門知識を持つ税理士が調査に立ち会うと、税務署とのやり取りがスムーズになり、誤解や不要な疑義を避けられます。
税理士は資料の整備や説明の仕方をサポートしてくれるため、調査の進行が短縮される可能性があります。
調査官に対して「適切に対応している会社」という印象を与えられるのも大きなメリットです。
さらに、税務調査の現場での発言や対応はすべて記録に残されるため、専門家が間に入ると不用意な発言によるリスクも減らせます。
普段から顧問税理士と信頼関係を築いておき、いざというときにすぐ同席を依頼できる体制を整えておく取り組みは、反面調査を回避する有効な手段のひとつといえます。
反面調査のよくある質問
反面調査は一般的な税務調査に比べると耳慣れないため、多くの人が調査内容や必要な対応について疑問を持ちます。
ここでは、とくに問い合わせや不安の声が多い3つの質問について、わかりやすく解説します。
反面調査の有無は取引先に知られてしまう?
反面調査は、調査対象者本人ではなく、取引先や銀行、不動産会社などの第三者に直接確認が入る仕組みです。
そのため、対象となった取引先には必ず反面調査の事実が伝わり、秘密のまま進むことはありません。
取引先からすると「なぜ自社に調査が来たのか」と不安や迷惑に感じる可能性があり、信頼関係に影響を与えるリスクがあります。
さらに、もし申告内容に不自然な点があれば高い確率で発覚するため、信用低下につながる可能性も否定できません。
リスクを避けるために、日頃から帳簿や領収書を正しく管理し、説明できる状態を維持しておきましょう。
適切な管理を続けていれば、反面調査に発展するリスクを大幅に下げられます。
反面調査は拒否できる?
反面調査は、国税当局に認められた「質問検査権」に基づいて実施されるため、基本的に拒否できません。
調査に応じない場合、納税者本人だけでなく取引先に対しても、より厳しい調査や処分につながる可能性があります。
ただし、正当な理由があるときは、調査日を延期してもらうなどの柔軟な対応を依頼できる場合があります。
重要なのは、調査自体を無理に拒もうとせず、誠実に協力する姿勢を見せる意識です。
誠実さを示せば調査が早期に終わり、反面調査の範囲を広げずに済むケースも少なくありません。
反面調査は個人事業主も対象になる?
反面調査は法人だけでなく、個人事業主も対象です。
事業の規模が小さいからといって免れるわけではなく、帳簿や領収書の不備、申告内容の不自然さが見られれば調査の対象になる可能性があります。
たとえば売上の一部を除外していたり、経費の裏付け資料が揃っていなかったりすれば、税務署は取引先へ確認しに行くケースがあります。
小規模な個人事業主の場合、取引先との関係が限られている場合も多く、反面調査がおこなわれると信頼関係に大きな影響を与えかねません。
規模の大小にかかわらず、誠実な申告と証拠の管理が反面調査を回避する一番の備えといえます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
税務調査の関連記事
新着記事
法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の種類を体系的に整理し、それぞれの税率や計算の仕組み、さらには…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率を知ることです。 本記事では、会社の規模による法人税率の違い…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引