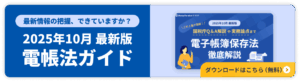- 作成日 : 2025年10月6日
税務調査の結果は遅い?通知までの流れ・期間と対処法を解説
税務調査を受けたあと、「なかなか結果が届かないけれど大丈夫なのか」と不安になる方は多いでしょう。
税務調査は、調査官が帳簿や契約書を確認し、審査を経て結果通知が出されるため、その場では結論は出ません。
法人の場合は通常1週間〜3か月以内に通知されるケースが多く、取引内容が複雑な場合や不備が多い場合は半年以上かかる可能性もあります。
本記事では、税務調査の流れや結果が遅れる理由、そして調査を長期化させないためのポイントを分かりやすく解説します。
目次
税務調査の結果が通知されるのは遅い?
税務調査とは、国税局や税務署が申告内容に誤りがないかを確認するための調査です。
調査官が帳簿や契約書をチェックし、必要に応じて経営者や経理担当者へ質問をおこないます。
税務調査が終了しても、結果がその場で伝えられるわけではなく、調査官が部内で精査をおこなったあと、正式に通知する流れです。
一般的には1週間から3か月程度が目安とされ、取引内容が複雑で確認事項が多い場合や、書類の不備が目立つ場合にはさらに時間が延びるケースもあります。
結果通知までに半年以上かかる例もあるため、「思ったより遅い」と感じても、まずは想定範囲内だと理解しておけば安心につながります。
調査にかかる時間
税務調査は「事前の通知」から「当日の調査」「結果の通知」まで、段階を経て進められます。
それぞれに準備や確認の時間が必要で、調査が終わってもすぐに結論が出るわけではありません。
流れを知っておくと、結果通知までに時間がかかる理由を理解しやすくなります。
税務調査を通知される
税務調査は、まず税務署からの事前通知によって始まり、実施日が具体的に伝えられます。
何日前に連絡が来るかは法律で明確に定められていないものの、多くの場合は1週間前後の猶予が設けられます。
通知を受けたら帳簿や契約書、領収書など調査で必要な資料を揃えておきましょう。
準備に数日から1週間ほどかかるのが通常である一方で、日ごろから整理整頓をしておけば短期間で対応可能です。
帳簿や領収書が整理されていないと調査直前に確認作業が増え、調査官の確認にも時間がかかりやすくなります。
普段から正しく整理・保管しておく取り組みが、調査をスムーズに進める大切なポイントです。
税務調査を受ける
指定された当日には、税務署の調査官が会社や事務所を訪問し、帳簿や領収書、契約書などの確認をおこないます。
また、経営者や経理担当者に対して取引内容や経費の処理についてのヒアリングが実施されます。
個人事業主の場合は1日程度で終了するケースが多く、法人の場合は2〜3日間にわたるのが一般的です。
さらに、多店舗展開している会社や、取引が多岐にわたる場合は、より多くの確認が必要となり、日数が追加される場合もあります。
内容がシンプルな事業であれば短期間で済む一方、複雑な取引や関連会社が多い場合は長引くのが通常です。
そのため、当日のスケジュールは余裕をもって確保しておく必要があります。
結果を通知される
調査が終わると、調査官は持ち帰った資料やヒアリングの内容を整理し、税務署内で上司の承認を得たうえで、正式な結果通知を作成します。
結果は当日すぐに伝えられるわけではなく、通常は1週間から3か月程度かかるのが一般的です。
とくに法人の場合、確認する書類や取引の件数が多いため、時間を要するケースが少なくありません。
また、書類の不備が多い、複雑な取引が多い、関連会社や取引先にも調査が及ぶといった要因があると、さらに長期化する可能性があります。
中には3か月を超えるケースもあるため、通知が遅れても慌てる必要はありません。
あらかじめ通知までの期間を把握しておけば、精神的にも余裕を持って対応できます。
【結果別】税務調査に対する対処法
税務調査が終わると、最終的に「結果通知」が届きます。
内容は大きく3種類に分かれており、それぞれで納税者の対応も異なります。
正しく申告できていた場合は追加の対応は不要で、誤りや不正があった場合には申告のやり直しや税務署による処分が必要です。
ここでは3つのパターンを整理して解説します。
申告が認められる
税務調査の結果、帳簿や申告内容に誤りがなく「正しく処理されている」と判断されるケースを「申告是認」といいます。
申告是認の場合は、追加で税金を納める必要も、申告書を修正する必要もありません。
通知を受けた時点で調査は終了し、納税者側での対応は不要です。
最も安心できる結果であり、普段から適切に記帳や申告をしていれば、申告是認で終わる可能性が高いといえます。
なお、是認とされるかどうかは調査官の確認内容や証拠資料の整備状況によるため、日常的に帳簿や領収書をきちんと整理しておきましょう。
修正申告をおこなう
税務調査の過程で、記帳漏れや計算間違いなどの誤りが見つかった場合、納税者が自主的に修正申告書を提出します。
不足分の税金を納める手続きを「修正申告」と言い、誤りの大きさに関わらず、自ら提出するのが特徴です。
長期間誤りを放置していた場合には、延滞税や加算税が上乗せされるケースがあるので要注意です。
悪質と判断された場合には重加算税が課される可能性があります。
調査官に指摘を受けた時点で速やかに対応し、不要な負担を減らしましょう。
更正処分を受ける
調査の結果、誤りがあるにもかかわらず納税者が修正申告をおこなわない場合や、明らかな不正が発覚した場合には、税務署が職権で課税額を決定します。
税務署が課税額を決定するケースを「更正処分」といい、通知によって正式に納税額が示されます。
更正処分が下されると、本来納めるべき税金に加えて延滞税や加算税が課されるのが通常です。
さらに、架空経費の計上や売上隠しなど、悪質と判断される行為については重加算税の対象です。
更正処分が納税者にとって大きな負担である場合や、結果に不服がある場合は「審査請求」や「再調査請求」といった不服申立ての手続きをおこなえます。
税務調査の結果が遅くなるケース4つ
書類や回答の不備、取引の複雑さ、不正の疑いなどがあると確認作業に時間がかかり、半年以上かかる場合があります。
ここでは税務調査の結果が遅くなるケースについて、代表例をご紹介します。
結果が遅れると資金繰りの見通しや経営判断にも影響するため、原因を理解しておきましょう。
① 書類の不備が多い
帳簿の記載漏れや計算ミス、領収書や契約書の不足といった書類の不備は、調査を長引かせる代表的な原因です。
本来であればすぐに確認できるはずの内容も、資料が揃っていなければ追加で提出を求められ、やり取りに時間がかかります。
普段から帳簿整理や書類の保管をきちんとおこなっていないと、調査官が内容を精査するのに余計な時間を要し、結果的に結果通知が大幅に遅れる可能性があります。
とくに法人の場合は資料の種類や量が多いため、整理が不十分だと確認作業がさらに難航しがちです。
場合によっては再提出や税理士への確認を求められ、通知が数か月先延ばしになる場合もあります。
② ヒアリングの回答が不十分である
調査におけるヒアリングにおいて、会社側の回答があいまいだったり、説明が不十分であったりすると、税務調査に時間がかかります。
ヒアリングの回答が不十分な場合、内容の整合性を確かめるために再度ヒアリングを求められる可能性もあります。
また、納税者が非協力的な態度を取った場合も調査が長引く要因なので、注意しましょう。
もし不安がある場合は税理士を同席させると、回答の補足や正確性を担保できるため安心です。
③ 取引規模や内容が複雑である
大規模な法人や多業種にわたる事業を営んでいる場合、調査対象の取引数が膨大になり、確認作業に時間がかかります。
さらに無申告の年度が複数ある場合や、グループ会社・関連会社が関わっている場合は、取引の突き合わせや外部調査を要する可能性があります。
取引先が多岐にわたるほど調査官の確認は慎重におこなわれるため、通常よりも長い期間を要するのは避けられません。
場合によっては数か月を超える場合もあり、規模が大きい企業ほど結果通知までの時間が延びる傾向があります。
とくに海外取引や特殊な会計処理がある場合は、追加の専門的な確認が入るためさらに時間がかかる点にも注意が必要です。
④ 不正の疑いがある
脱税や架空経費の計上、売上の隠ぺいといった不正の疑いがある場合、税務署は徹底的な調査をおこないます。
通常の帳簿確認だけではなく、取引先や関係会社への聞き取り、証拠書類の追加収集など、多角的な調査が実施されます。
結果が出るまでに半年から1年程度かかる場合も珍しくありません。
悪質なケースでは刑事告発に発展する可能性もあり、その場合はさらに時間が延びます。
不正が疑われた場合には徹底調査に発展するため、普段から透明性の高い経理処理を徹底しましょう。
とくに法人では、内部統制やガバナンス体制が整っていないと、調査の対象が広がり、長期化する傾向があるので要注意です。
税務調査を長期化させないための対策方法
税務調査の結果通知が遅れるケースは、経営者にとっても大きな心理的ストレスです。
調査そのものを早く終えるのは難しいものの、準備や対応を工夫すれば長期化は防止できます。
ここでは調査をスムーズに進めるための3つのポイントを紹介します。
普段から帳簿・書類整理を徹底する
調査を円滑に進めるためには、日ごろから帳簿や証憑書類をきちんと整理・保管しておく取り組みが基本です。
領収書や契約書、請求書などが散逸していると、調査官に提出を求められた際にすぐに対応できず、確認に時間がかかってしまいます。
とくに法人では資料の量が膨大なため、定期的に整理しておく体制を整えておきましょう。
また、電子帳簿保存法の要件を満たすように電子化を進めると、検索や確認がしやすく効率的です。
調査官から必要な書類を求められた際に迅速に提示できれば、余計な往復や確認作業が減り、調査の長期化防止にも役立ちます。
調査対象資料を事前に準備・点検する
調査の通知を受けたら、指定された帳簿や契約書、領収書などの資料を早めに揃えましょう。
その際、記載内容と実際の取引に矛盾がないかを事前に点検しておくと安心です。
たとえば、売上と入金記録、仕入と支払記録が一致しているか、契約書と請求書の内容が整合しているかなどを確認しておくと、調査官からの追加指摘を減らせます。
事前に税理士へ確認を依頼すれば、専門的な視点でチェックを受けられるため、見落とし防止につながります。
通知を受けてから準備を始めると時間が限られるため、普段から資料の保管や点検の体制を整えておきましょう。
質問には誠実に回答する
調査官からの質問に対しては、正確かつ誠実に答える姿勢が重要です。
あいまいな返答や不十分な説明は、調査官に「追加確認が必要だ」と判断され、再ヒアリングにつながる場合があります。
不明点や判断に迷う部分は無理に答えず、専門家の助言を得ながらスムーズに回答しましょう。
また、緊張して感情的に対応してしまうと調査官との信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
冷静さを保ちながら誠実に答えられれば調査がスムーズに進み、長期化を防ぐ効果が期待できます。
さらに、必要に応じて税理士を同席させると、その場で補足や訂正ができる点で安心です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
税務調査の関連記事
新着記事
法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の種類を体系的に整理し、それぞれの税率や計算の仕組み、さらには…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率を知ることです。 本記事では、会社の規模による法人税率の違い…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引