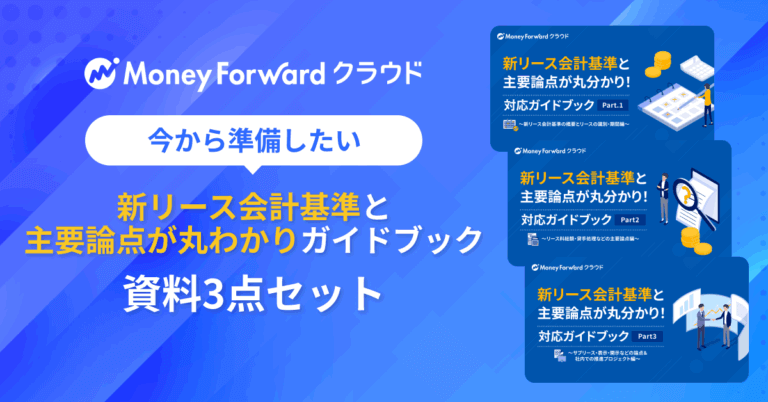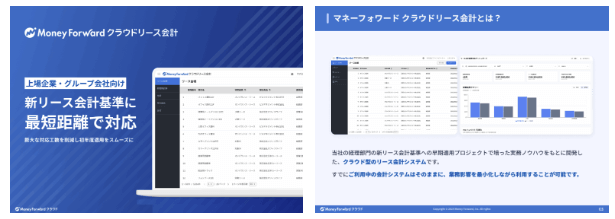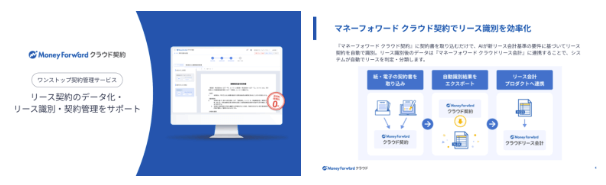- 作成日 : 2025年11月12日
法人向けリースのメリット・デメリットは?リースとどちらが得かを徹底比較!
法人が事業運営でPCや社用車などの設備を導入する際、リース契約は初期投資を抑えられる有効な選択肢です。しかし、そのメリットとデメリットを正確に理解しなければ、かえってコストが増加したり、経営の柔軟性を損なったりする可能性もあります。
この記事では、法人向けリースの基本的な仕組みから、レンタルや購入との違い、具体的なメリット・デメリットを深掘りします。
目次
法人向けリースとは?
法人向けリースとは、企業が希望する設備をリース会社が代わりに購入し、一定期間貸し出す取引を指します。通常は契約期間中に分割で支払う形式が多く、定額払いになる場合もありますが、契約形態や支払方法によって変動型となることもあります。
法人向けリースの仕組み
法人向けリースは、設備を利用したい企業、販売会社(ディーラーなど)、そしてリース会社の三者間で成立します。具体的な流れは、企業が選んだPCや社用車などの設備をリース会社が販売会社から購入し、その企業に貸し出すというものです。利用企業は、その対価として月々のリース料をリース会社に支払います。この仕組みにより、企業はまとまった購入資金を用意する必要がなくなります。
リース・レンタル・購入の違い
リース・レンタル・購入は、契約期間や所有権の有無、対象物件の自由度において明確な違いがあります。特に、契約期間が比較的長く、借主が自由に物件を選べる点がリースの大きな特徴です。
これらの違いを理解することは、自社の事業計画や財務状況に最適な選択をする上で非常に重要です。例えば、ごく短期間だけ使いたい場合はレンタル、長期間にわたり自社の資産として保有したい場合は購入が適しています。
| 項目 | リース | レンタル | 購入(一括・割賦) |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 中長期 | 短期 | なし |
| 所有権 | リース会社 | レンタル会社 | 購入者(割賦完済後) |
| 対象物件 | 企業が自由に選定可能 | レンタル会社の在庫品のみ | 企業が自由に選定可能 |
| 中途解約 | 原則不可 | 可能 | 不可 |
| 保守・修繕義務 | 契約による(通常は借主) | レンタル会社 | 購入者 |
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準丸わかりガイドブック3点セット
本資料は、2025年3月から順次公開した「新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック」のPart.1〜Part.3の3点セットになります。
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
法人がリースを利用するメリットは?
法人がリースを利用する最大のメリットは、多額の初期投資を避けつつ、常に最新の設備を導入できる点です。これにより、手元の資金を他の重要な事業投資に回すことが可能になり、経営の柔軟性が高まります。
メリット1. 初期費用を抑えられる
リースを利用すれば、高額な設備を導入する際に必要なまとまった購入資金が不要になります。手元に残した資金は、運転資金や人材採用、マーケティングといった他の成長分野へ投資することができ、資金繰りの安定化と事業機会の拡大に直結します。特に、事業の立ち上げ期にあるスタートアップやベンチャー企業でも、必要な設備を迅速に揃えることが可能です。
メリット2. コスト管理が簡単になる
リース料は原則として毎月定額であるため、将来にわたるコストの見通しが立てやすくなります。これにより、事業計画や予算策定が非常にスムーズになります。また、多くの場合、リース料は全額を損金として経費計上できるため、会計処理がシンプルになる点も大きな利点です。購入した場合に発生する複雑な減価償却計算や固定資産税(償却資産税)の申告・納付といった手間もかかりません。
メリット3. 常に最新の設備を利用できる
リース契約では、設備の耐用年数に合わせて契約期間を設定することで、契約満了のタイミングで常に最新の機種に入れ替えることが可能です。技術革新の速いIT機器(PC、サーバーなど)や、モデルチェンジの頻繁な車両などは、数年で陳腐化してしまうリスクがありますが、リースならその心配がありません。これにより、企業の生産性や競争力を高く維持することができます。
メリット4. 資産管理の手間を削減できる
リースを利用すれば、資産管理に伴う煩雑な業務から解放されます。設備を購入した場合、固定資産台帳への登録、減価償却計算、固定資産税(償却資産税)の支払い、そして廃棄時の手続きなど、多くの管理業務が発生します。リースであれば、これらの資産管理はすべてリース会社の責任で行われるため、企業の管理部門の負担を大幅に軽減できます。
メリット5. 節税効果が期待できる場合がある
リース料は原則として全額を損金算入できるため、法人税の課税対象となる所得を圧縮する効果があります。また、購入した場合の法定耐用年数よりも短い期間でリース契約を組むことで、実質的に早期の費用化が可能となり、短期的な節税効果が高まるケースもあります。ただし、税務上の判断は契約内容によるため、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
法人がリースを利用するデメリットは?
リースには多くのメリットがある一方で、総支払額が割高になる可能性や、契約の自由度が低いといったデメリットも存在します。
デメリット1. 総支払額は購入より割高になる
リース料の総支払額は、同じ物件を一括購入する場合と比較して割高になるのが一般的です。なぜなら、リース料には物件価格や保険料、固定資産税に加えて、リース会社の利益、金利などが含まれているためです。長期的なコストだけを考えれば、購入した方が経済的であるケースも少なくありません。
デメリット2. 原則として中途解約ができない
リース契約は、契約期間中の継続利用を前提として料金が設定されているため、原則として中途解約は認められていません。万が一、事業計画の変更などで設備が不要になった場合でも、残りの期間のリース料や違約金を一括で支払う必要が生じます。この点は、短期的な利用が想定される場合に大きなリスクとなります。
デメリット3. 所有権がないためカスタマイズや売却ができない
リース物件の所有権はリース会社にあるため、企業が自由に改造、カスタマイズ、売却、譲渡を行うことはできません。特別な仕様が必要な機械や、自社の業務に合わせて機器に手を加えたい場合は、リース契約は不向きと言えるでしょう。
デメリット4. 契約には与信審査が必要となる
リース契約を締結する前には、必ずリース会社による与信審査が行われます。企業の財務状況や事業の安定性などが評価され、審査の結果によっては契約ができない場合や、保証人が必要になるケースもあります。特に設立間もない企業や、財務基盤が弱い企業にとっては、これが一つのハードルとなる可能性があります。
法人向けカーリースならではのメリット・デメリットは?
社用車を導入する際、一般的なリースのメリットに加え、カーリースならではのメリットとデメリットが存在します。
カーリースのメリット
- 車両に関するコストを一本化できる
車両価格だけでなく、登録諸費用、自動車税、重量税、自賠責保険料などがリース料に含まれているため、支払いを一本化でき経理処理が簡素化されます。 - メンテナンスの手間を削減できる
オイル交換や車検などの定期メンテナンス費用もリース料に含める「メンテナンスリース」を選べば、車両管理の手間とコストを大幅に削減でき、常に安全な状態で社用車を利用できます。
カーリースのデメリット
- 走行距離制限がある場合が多い
多くのカーリース契約には、月間や年間の走行距離に上限が設けられています。超過すると追加料金が発生するため、営業などで長距離を走行する企業は注意が必要です。 - 事故時の対応や原状回復義務
事故を起こしてしまった場合の修理費用は、原則として借主の負担となります。また、契約満了時に車両を返却する際は、通常の使用による損耗を超える傷やへこみがある場合、原状回復費用を請求されることがあります。
法人向けリースと購入はどちらが得か?
リースと購入のどちらが得かは、企業の財務状況、設備の使用期間、そして経営戦略によって異なります。一概にどちらが良いとは言えず、それぞれの特性を理解し、自社の状況に合わせて選択することが重要です。
リースがおすすめな企業の特徴
以下のような特徴を持つ企業には、リースの活用が特に推奨されます。
- スタートアップやベンチャー企業:自己資金が限られ、迅速な事業展開が求められる企業にとって、初期投資を抑えられるリースは非常に有効です。資金を設備投資に固定せず、人材獲得や開発などのコア業務に集中させることができます。
- 最新設備を常に導入したいIT企業や製造業:技術の陳腐化が早いPCやサーバーなどを扱うIT企業や、高性能な工作機械が必要な製造業では、リースが適しています。設備の入れ替えが容易なため、競争優位性を保つことにつながります。
- 資金繰りを安定させたい中小企業:定額払い・長期契約を前提としたリースでは、キャッシュ・フロー見通しを立てやすく、資金繰りを安定させる効果が期待できます。
購入がおすすめな企業の特徴
一方で、以下のような場合には購入が適していると言えます。
- 長期間にわたり同じ設備を利用する場合:法定耐用年数を超えて長期間使用する見込みのある設備は、総支払額が安くなる購入の方が経済的です。
- 設備を自由にカスタマイズしたい場合:自社の業務に合わせて特別な改造や設定が必要な設備は、所有権が得られる購入が必須となります。
- 潤沢な自己資金があり、資産を増やしたい企業:財務体力があり、資産として計上したい場合は、購入が適しています。減価償却による長期的な節税も可能です。
法人向けリース契約の種類は?
リース契約は、主に「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類に大別されます。両者は契約の性質や会計処理の方法が異なるため、自社の目的に合った契約形態を選ぶことが重要です。
ファイナンス・リースとは
ファイナンス・リースは、実質的に分割払いで資産を購入するのに近い性質を持つリース取引です。特徴は、契約の中途解約が不可能であることと、利用企業が物件の購入代金と諸費用のほぼ全額を負担するフルペイアウトである点です。
オペレーティング・リースとは
オペレーティング・リースは、ファイナンス・リース以外のすべてのリース取引を指し、レンタルの性質に近い契約です。リース会社が契約満了時の物件価値(残価)をあらかじめ設定し、物件価格から残価を差し引いた金額を基にリース料を算出します。そのため、月々のリース料がファイナンス・リースに比べて安くなる傾向があります。
リース契約の種類による会計処理の違い
リース契約の種類によって、会計上の処理が異なります。特にファイナンス・リースは、原則として資産計上が必要となるため注意が必要です。
- ファイナンス・リース:原則として、売買取引に準じた会計処理が必要です。リース資産とリース債務をそれぞれ固定資産と負債として計上し、減価償却を行います。ただし、中小企業の場合は、一定の要件を満たせば賃貸借処理(支払いリース料を経費として計上する簡便な方法)が認められることもあります。
- オペレーティング・リース:通常の賃貸借取引として扱われ、支払ったリース料を費用として計上するだけで済み、資産計上は不要です。ただし、2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる「新リース会計基準」では、オペレーティング・リースも原則として売買取引に準じた会計処理が必要となりますのでご注意ください。
※会計・税務に関する最終的な判断は、必ず顧問税理士等の専門家にご確認ください。
法人向けリースの契約手続きは?
法人向けリースの契約は、一般的に以下のステップで進められます。事前に流れを把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
- リースしたい物件の選定と見積もり取得
まず、事業に必要なPC、複合機、車両などの設備を販売会社(ディーラー)で選定し、見積もりを取得します。 - リース会社への申し込みと与信審査
物件が決まったら、リース会社に申し込みを行います。その際、企業の決算書などの財務資料を提出し、与信審査を受けます。 - リース契約の締結
審査に通過したら、リース会社と正式にリース契約を締結します。契約内容(リース期間、月額料金、保守の範囲、契約満了時の取り扱いなど)を十分に確認しましょう。 - 物件の納品とリース開始
契約締結後、リース会社が販売会社から物件を購入し、利用企業へ納品します。物件の検収が完了した時点からリース期間がスタートし、リース料の支払いも開始となります。 - 契約満了時の手続き
契約期間が満了すると、事前に定めた契約内容に基づき、「再リース(契約延長)」「物件の返却」「買取(買取オプションがある場合)」のいずれかを選択します。
自社の状況に合わせてリースか購入かを選択しましょう
本記事では、法人がリース契約を利用する際のメリット・デメリット、そしてレンタルや購入との違いについて詳しく解説しました。
リースは、初期投資を抑えて資金繰りを安定させ、常に最新の設備を利用できるという大きな利点があります。一方で、総支払額が割高になることや中途解約ができないといった注意点も存在します。
最終的に重要なのは、自社の事業計画、財務状況、そして対象となる設備の特性を総合的に考慮し、購入やレンタルといった他の選択肢とも比較検討した上で、最も賢明な判断を下すことです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
IFRS第16号「リース」と日本基準の違いをわかりやすく解説
IFRS第16号と現行の日本の会計基準との大きな違いは、企業のリース契約をどのように財務諸表に反映するかという点です。この記事では、IFRS第16号の概要や強制適用の有無、リース判…
詳しくみる外構工事は減価償却できる?素材ごとの耐用年数も解説
事業用で建物の外に塀や舗装を設置する外構工事を注文した場合、費用を減価償却できます。ただし、減価償却費を算出する際に用いる耐用年数は、工事の素材によって異なる点に注意が必要です。 …
詳しくみるホームページの耐用年数と減価償却費計算を解説
ホームページとは、企業・個人などにより設置されたWebサイトを指します。物体として存在するものではないため、会計上の資産としてどのように扱うべきか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう…
詳しくみるパソコンは減価償却できる?計算方法や30万円未満の特例、耐用年数も解説
パソコンの減価償却は、取得価額や用途ごとに処理が異なり、判断に迷うことも多い業務です。特に法定耐用年数や特例の適用条件を誤ると、税務上のリスクが発生する可能性が否定できません。その…
詳しくみるリース取引の会計処理方法は?仕訳や勘定科目のポイントをわかりやすく解説
企業の経理担当者が直面する重要な業務の一つに、リース取引の仕訳があります。リース取引の会計処理は、リースの種類によって用いる勘定科目が大きく異なり、正確な知識が求められます。 この…
詳しくみる隠れリースとは?新リース会計基準で知っておくべきポイント
「隠れリース」とは、契約書上は「リース」という名称ではないものの、その経済的実態が新基準のリースの定義に合致する契約を指します。これには、従来サービス契約や業務委託契約として処理さ…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引