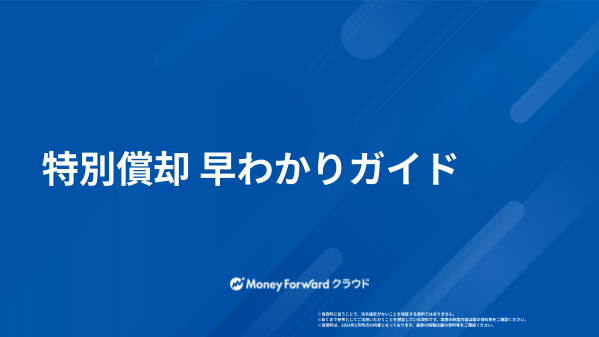- 更新日 : 2026年1月30日
特別償却とは?一括償却との違いや対象設備などの要件をわかりやすく解説
特別償却は、租税特別措置法に基づき一定の要件を満たす設備投資に対して、通常の減価償却とは別枠で費用計上できる優遇制度です。中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制など、多くの中小企業が活用できる制度が複数存在します。
本記事では特別償却と一括償却との違いや、対象設備・要件をわかりやすく解説します。
目次
特別償却とは
特別償却は、租税特別措置法に基づき、一定の要件を満たす固定資産を取得した場合に通常の減価償却費に加えて追加の償却額(特別償却額)を損金として計上できる優遇制度です。たとえば、設備投資の初年度から大きめの減価償却費を計上することが許されるため、早期に投資コストを回収しやすいメリットがあります。
ここでは、特別償却についての基本的な考え方や、類似の制度である即時償却・一括償却・税額控除との違いを整理してみましょう。
そもそも減価償却とは
減価償却とは、固定資産の取得価額を一度に費用計上せず、資産の利用可能期間(耐用年数)にわたって、毎期の費用として計上する会計および税務上の手続きです。建物や機械装置などの設備は時間の経過や使用によって価値が減少していきますが、それを会計上合理的に反映させるために行います。
減価償却の方法には定額法や定率法などがあり、通常は税法(法人税法)や会計基準で定められた耐用年数をもとに、一定の計算ルールで毎期の償却費を算出します。
減価償却の仕組みについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
特別償却と即時償却の違い
特別償却は、取得した資産のうち一定要件を満たすものについて、通常の減価償却費に加えて初年度から一定の割合の特別償却額を計上する制度です。
一方、即時償却は「取得した資産の全額を一度に費用計上する」仕組みです。中小企業経営強化税制や特定の措置で要件を満たす場合に、導入した年に全額を損金に算入できます。
即時償却は初年度にすべて費用化できる点で特別償却よりも短期間に大きな効果を生みますが、必ずしも常に選択できるわけではありません。対象資産や要件が厳しく、制度ごとに細かい制限があるため注意が必要です。
特別償却と一括償却の違い
一括償却は、「取得価額が20万円未満」の減価償却資産を対象とする制度です。一括償却資産として計上した場合、取得年度から3年間にわたって均等に償却を行えます。つまり、一括償却は少額資産向けの簡便的な制度といえます。
それに対して特別償却は、取得価額の制限がありません。取得価額が20万円を超える高額な設備であっても、要件さえ満たしていれば初年度から追加で償却ができる点が一括償却とは異なります。
特別償却が適用される制度一覧
特別償却が適用される主な税制優遇制度としては、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業防災・減災投資促進税制があげられます。いずれも、中小企業が生産性向上や防災対策などの目的で設備投資を行う場合に活用できる制度です。
以下の表に対象希望規模と優遇措置など、主な違いをまとめました。
| 中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 | 中小企業防災・減災投資促進税制 | |
|---|---|---|---|
| 主な対象企業規模 |
|
| |
| 優遇措置 | 30%特別償却または7%税額控除(資本金3,000万円超は特別償却のみ) |
|
|
| 必要計画認定 | 不要 | 経営力向上計画の認定必須 | 事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定必須 |
中小企業投資促進税制における特別償却の要件
中小企業投資促進税制は、中小企業が生産性向上や経営力強化を目的として設備投資を行う際、特別償却や税額控除などの優遇を受けられる制度です。租税特別措置法の規定により、要件を満たした設備を購入・設置した場合、投資初年度に通常の減価償却に加えてさらに特別償却額を計上できます。
中小企業投資促進税制の対象企業
中小企業投資促進税制の対象になるのは、資本金または出資金の額が1億円以下の法人、協同組合(農業協同組合、商店街振興組合など)、あるいは従業員1,000人以下の個人事業主です。また、いずれも青色申告を行っている企業や協同組合等・個人事業主に限られます。
電気業や水道業、銀行業、鉄道業など一部除外されるものがあるものの、農林水産業や建設・建築業、小売業、飲食店業など幅広い業種で活用できます。
中小企業投資促進税制の対象設備
中小企業投資促進税制の対象になる設備は、以下のとおりです。
- 機械装置:1台160万円以上
- 測定工具および検査器具:1台120万円以上、または1台30万円以上で複数合計120万円以上
- 貨物自動車:車両総重量3.5トン以上
- 内航船舶:取得価額の72%が対象
- 一定のソフトウェア:70万円以上(複数合計で70万円以上も可)
中小企業経営強化税制における特別償却の要件
中小企業経営強化税制は、「中小企業等経営強化法」に基づいて経営力向上計画の認定を受けた企業が、生産性向上に資する設備投資を行った場合に特別償却や税額控除を受けられる制度です。こちらは投資促進税制と比べ、対象となる設備の区分がより多様化している点が特徴といえます。
中小企業経営強化税制の対象企業
中小企業経営強化税制の対象になる企業の要件は、中小企業投資促進税制と同じ青色申告を行っている中小企業等です。
さらに、中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき「経営力向上計画」の認定を受けた事業者でなければなりません。この認定は設備の取得前に受ける必要があります。
中小企業経営強化税制の対象設備
中小企業経営強化税制は、設備目的に応じて以下の4種類に分かれます。
- A類型:生産性向上設備
- B類型:収益力強化設備
- C類型:デジタル化設備
- D類型:経営資源集約化設備
対象となる設備は4つの累計で共通ではありますが、適用される詳細な要件はそれぞれ異なります。対象となる設備は、以下のとおりです。
- 機械装置:160万円以上
- 工具:30万円以上
- 器具部品:30万円以上
- 建物附属設備:60万円以上
- ソフトウェア:70万円以上
なお、令和7年度の税制改正において、B類型に限り売上高100億円を目指す企業向けに対象設備に建物が追加されました。
中小企業防災・減災投資促進税制の要件
中小企業防災・減災投資促進税制は、自然災害などのリスクが高まる中、事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業が防災・減災設備を導入した場合に特別償却や税額控除を受けられる制度です。設備投資を通じて災害リスクを低減することを主な目的としています。
中小企業防災・減災投資促進税制の対象企業
令和7年3月31日までに「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業者が対象です。計画の認定には、防災・減災に関する具体的な取り組み内容や、想定リスクに対する対策の明記が求められます。
中小企業防災・減災投資促進税制の対象設備
対象となる設備は、以下のとおりです。
- 機械および装置:100万円以上(自家発電設備、浄水装置、耐震・精神・免震装置など)
- 器具・備品:30万円以上(感染症対策のためサーモグラフィ、自然災害による事業活動への被害を軽減するすべての設備)
- 建物附属設備:60万円以上(自家発電設備、貯水タンク、変圧器、防水シャッターなど)
特別償却と税額控除はどちらを選択すべき?
中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制などでは、特別償却と税額控除のいずれかを選択できる場合があります。税額控除は法人税額から直接差し引く仕組みであり、安定的に利益を計上している企業にとっては効果が大きいといえるでしょう。ただし、法人税額の20%が上限となる制約があります。
一方、特別償却は初年度の償却費を増やして税負担を軽減するため、当期利益が大きい企業や、設備投資により資金繰りが厳しい企業に有効です。さらに赤字の場合でも、翌期以降の損益通算により効果が期待できる点が特別償却の強みといえます。資金繰りに余裕があれば税額控除、そうでなければ特別償却を選ぶといいでしょう。
特別償却が適用される期間はいつまで?
特別償却の適用期限における基本ルールは各制度共通ではありますが、令和7年度経済産業関係税制改正によって一部例外が出ています。
適用期間の基本ルール
原則として、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業防災・減災投資促進税制いずれも令和6年度末(2025年3月末)までが適用期限です。
ただし、令和7年度経済産業関係税制改正によって、中小企業経営強化税制に関してはC類型(デジタル化設備)を除き令和8年度末(2027年3月末)まで適用期間が延長される見込みです。
繰越制度について
青色申告法人が特別償却を適用する際、その期に償却限度額を超えて償却しきれなかった場合は、「特別償却の償却不足額」として翌期以降に繰り越すことが可能です。繰り越しを行う場合は、申告書に必要な明細を記載して提出する必要があります。
初年度で引ききれなかった分の金額を翌期以降に適用できるため、企業の税務戦略の選択肢が広がるでしょう。
個人事業主は特別償却を適用できない?
特別償却は法人だけの制度ではありません。要件を満たせば、個人事業主も適用可能です。
個人事業主の適用要件
従業員数1,000人以下の個人事業主であれば、特別償却が利用できます。ただし、青色申告を行っている必要があります。
必要な手続きと書類
個人事業主の場合は、青色申告決算書「減価償却の計算」の「割増(特別)償却費」の欄に、特別償却額を記入します。
確定申告書提出時には、償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告しましょう。
特別償却を適用する場合の仕訳
特別償却を適用する際の会計処理には、大きく分けて「直接合算方式」と「準備金方式(特別償却準備金を使用する方法)」の2パターンがあります。
以下で、それぞれの仕訳例を紹介します。なお、前提条件は次のとおりです。
- 取得価額:1,000万円の機械装置
- 耐用年数:10年
- 償却方法:定額法
- 通常償却率:10%(1,000万円 x 10% = 100万円)
- 特別償却率:30%(1,000万円 x 30% = 300万円)
直接合算方式
初年度に通常の減価償却費と特別償却費を合算して減価償却費として計上する方法です。決算書上で特別償却額を独立して把握しにくいものの、仕訳がシンプルという利点があります。
初年度の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 400万円 | 減価償却費累計額 | 400万円 | 特別償却費を含む減価償却費 |
準備金方式
初年度の仕訳は、通常の減価償却費を計上し、特別償却額は特別償却準備金として積み立てます。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 100万円 | 減価償却費累計額 | 100万円 | 通常の減価償却費(1年目) |
| 繰越利益剰余金 | 300万円 | 特別償却準備金 | 300万円 | 特別償却準備金 の積立(1年目) |
耐用年数10年の場合、特別償却準備金は84ヶ月(7年)で均等償却します。そのため年度ごとの特別償却準備金の取り崩し額は42.86万円です。
初年度以降の仕訳は、以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特別償却準備金 | 42.86万円 | その他利益剰余金 | 42.86万円 | 特別償却準備金の取崩(2年目以降) |
毎年この仕訳を7年間繰り返し、最終的に準備金残高がゼロになります。
特別償却を適用する場合の注意点
特別償却は節税メリットをもたらす制度ですが、適用するにあたってはいくつかの注意点があります。誤った申告をすると税務リスクが発生するため、事前に要件を正確に把握しておくことが大切です。
最終的な償却総額は変わらない
特別償却を適用しても、資産の耐用年数が終了するまでに償却できる総額は変わりません。あくまで「初期に多くの費用を計上できる」という時期配分の問題です。将来的な償却費がその分だけ減少する、という点を踏まえ、資金繰り計画を立てる必要があります。
適用要件や対象資産の確認
特別償却の適用には、細かい基準があります。投資資産の金額要件や取得時期、用途などをよく確認したうえで判断しましょう。また、同一資産について複数の特別措置を重複適用することは認められない、などの注意点もあります。
さらに、証明書類の不備や提出書類の遅延は否認リスクを高めます。事前に行政庁や税務署の窓口、公式サイトなどで最新情報をチェックし、期限内に必要書類を揃えておきましょう。
特別償却について正しく理解しよう
特別償却は、中小企業の設備投資を後押しするために設計された税制優遇措置です。初年度に多額の減価償却費を計上することで資金繰りを改善しつつ、将来的な事業拡大や防災対策にも活用できるメリットがあります。
一方で、適用要件の確認や書類整備などの手続きが必要であるなどの注意点もあります。適用期限や対象要件を正しく理解し、計画的に制度を活用しましょう。
最後までこの記事をお読みの方に人気のガイド3選
最後に、ここまでこの記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。こちらもすべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
固定資産管理と減価償却の基本
固定資産管理の基本知識や流れ、ソフトウェアやシステム資産の管理と減価償却のポイントなどを解説した分かりやすいガイドです。
基本版の1冊として、多くの経理担当者の方にダウンロードいただいていおります。
経理のための固定資産管理見直しガイド
表計算ソフトでの固定資産管理に限界を感じる企業も多いのではないでしょうか。
経理業務における固定資産管理の見直しを検討している企業向けに、基本的な固定資産管理の業務の流れと、効率的な管理方法を詳しく解説した人気のガイドです。
マネーフォワード クラウド固定資産 サービス資料
マネーフォワード クラウド固定資産は、固定資産に関わる担当者全員がラクになる、複数台帳管理可能なクラウド型固定資産管理システムです。
クラウド上で資産の情報を一括管理できるため、最新の情報がすぐに見つかります。償却資産税申告書や法人税別表十六などの帳票が出力可能で、固定資産管理〜税務申告までを効率化します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
リース資産の減価償却を解説 | 減価償却費の計算から仕訳まで
機械や運搬具など、固定資産の種類によっては購入価格が高額になるものがあります。特に、規模の小さな会社で高額の固定資産を自己資金で取得すると、キャッシュ・フローが悪化することにもなる…
詳しくみる減価償却とは?計算方法、対象となる資産、仕訳、節税の仕組みまで簡単にわかりやすく解説
減価償却は、事業や経理に携わると必ず耳にする重要な会計用語です。高額な資産(パソコン、車、建物など)を購入した際、なぜ一括で経費にできないのか、その費用をどのように処理すればよいの…
詳しくみる減価償却明細書とは?テンプレートを基に書き方や注意点を解説
減価償却明細書とは、企業が保有する資産の減価償却状況を一覧にした帳簿を指します。個々の固定資産の減価償却の流れを記載した固定資産台帳とは別の帳簿です。 減価償却明細書があると「少額…
詳しくみるカーポートの耐用年数と減価償却費計算を解説
カーポートは車を日差しや雨風から守るための設備です。四方を壁で囲んだ施設であるガレージに比べ、屋根と柱だけを設置するカーポートは設置が簡易的であり、設置する場所を問わないメリットが…
詳しくみる少額減価償却資産は償却資産税の対象?計算方法や申告書の書き方も解説
中小企業には、「少額減価償却資産の特例」という減価償却に関する優遇措置が設けられています。ただし、「一括償却資産」と異なり償却資産税の対象となるため、注意が必要です。 本記事では、…
詳しくみる中古車は一括償却できる?減価償却との違いや経費計上のシミュレーションも
中古車は取得価額20万円未満であれば、一括償却資産として3年で経費化が可能です。 本記事では、一括償却制度の概要をはじめ、減価償却との違いや法人・個人事業主を問わず利用可能な要件に…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引