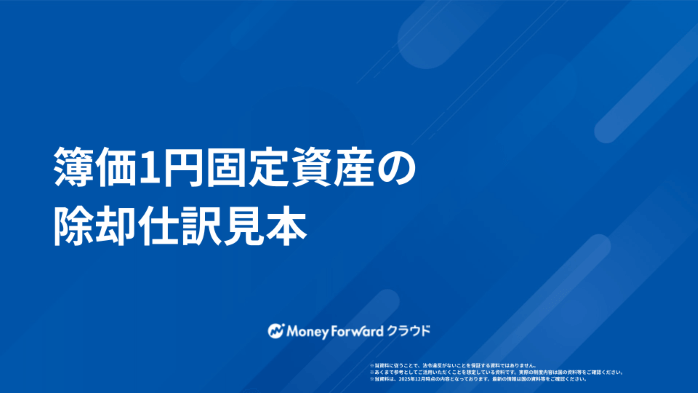- 更新日 : 2026年1月8日
減価償却資産における残存簿価1円とは?残す意味や仕訳、確定申告での書き方も解説
減価償却資産(時間経過とともに価値が減少していく資産)は、税務上の取り扱いに合わせた償却処理によって、残存簿価1円が残ることがあります。これは、減価償却が終了した後もその資産が事業の用に供している(事業で使っている)ことを意味します。
この記事では、減価償却において1円を残す意味、計算方法、除却する場合の経理処理、そして確定申告や税金との関係について詳しく解説します。
目次
減価償却資産の残存簿価1円とは?
残存簿価1円とは、減価償却が終了した後も事業の用に供している減価償却資産の存在を意味します。
そもそも残存簿価とは、法定耐用年数の経過後に残る固定資産の価値のことです。多くの会社では、税法上の取り決めに従った処理として、減価償却が終了している資産を残存簿価1円として残す会計処理を行っています。
残存簿価を1円残す意味は?
残存簿価として1円を残すのは、その資産がまだ存在し、事業で使われていることを帳簿上明らかにするためです。この1円を「備忘価額」と呼びます。
もし償却後に価値を0円にしてしまうと、帳簿上はその資産が存在しないことになり、現物の管理台帳などと不整合が生じる可能性があります。そのため、あえて1円の価値を残すことで、その資産の存在を管理しやすくなります。
残存簿価と残存価額の違いは?
残存価額とは、本来、耐用年数が経過した時点で見込まれる資産の売却可能価額などを指す会計上の見積額です。
税法上、2007年(平成19年)3月31日以前に取得した資産は、原則として取得価額の10%を「残存価額」として残す必要がありました。
しかし、現在の税法(2007年(平成19年)4月1日以降に取得した資産)では、残存価額は実質的に廃止され、0円として減価償却費を計算し、最終年度に備忘価額として1円を残す処理が採用されています。
平成19年度税制改正の影響は?
残存簿価を1円まで償却できる扱いは、2007年(平成19年)4月1日以降に取得した減価償却資産に適用されます。
税法改正により、この日以降に取得した有形の減価償却資産は、残存簿価1円まで償却できるようになりました。それ以前(2007年(平成19年)3月31日以前)に取得した減価償却資産は、原則として残存簿価10%(有形の減価償却資産の場合)を残す必要がありました。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準と主要論点が丸わかり!対応ガイドブック
リース会計基準の変更は、会社全体や財務諸表など影響範囲は想像以上に広いことが想定されます。
本ガイドでは、新旧リース会計基準の概要から、新リース会計基準の対象範囲、リース期間などの基本的ではあるものの重要な論点についてご紹介します。
経理担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ12選
債権管理担当者や経理担当者がChat GPTをどのように活用できるか、主なアイデアを12選まとめた人気のガイドです。
プロンプトと出力内容も掲載しており、コピペで簡単に試すことも可能です。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。
経理担当者向け!Excel関数集 まとめブック
経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。
新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。
会計士監修!簿記の教科書
簿記のキホンについて最低限知っておきたい情報をギュッとまとめた保存版のガイドです。
仕訳例や勘定科目がついており、はじめての方でもイメージをつけながら読むことができるようになっています。
減価償却の計算方法と期末残高は?
残存簿価が1円になるまでには、どのような計算が行われるのでしょうか。法定償却方法による計算を例に、減価償却の計算方法と期末残高の推移を、定額法と定率法に分けて説明します。
定額法の場合
定額法は、耐用年数に応じた定額法の償却率を用いて毎期一定額を減価償却する方法です。
定額法では、耐用年数の最後の事業年度に残存簿価が1円になるよう調整します。具体的には、その年度の計算上の償却費から1円を差し引いた額を、その期の減価償却費とします。
例:2012年(平成24年)4月1日以後取得の減価償却資産で、取得価額100万円、耐用年数5年(定額法の償却率0.200)の減価償却の推移
※期首に取得したものとする。
| 減価償却費 (税法上の償却限度額) | 減価償却累計額 | 期末残高 (残存簿価) | |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,000,000円×0.200×12/12=200,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
| 2年目 | 1,000,000円×0.200×12/12=200,000円 | 400,000円 | 600,000円 |
| 3年目 | 1,000,000円×0.200×12/12=200,000円 | 600,000円 | 400,000円 |
| 4年目 | 1,000,000円×0.200×12/12=200,000円 | 800,000円 | 200,000円 |
| 5年目 | 200,000円-1円=199,999円 | 999,999円 | 1円 |
5年目は、計算上の償却費200,000円から1円を差し引いた199,999円を償却費とすることで、期末残高を1円にします。
定率法の場合
定率法でも、耐用年数の最後の事業年度に残存簿価が1円になります。定額法と同じように、耐用年数の最後で、通常の減価償却費から1円を差し引いた額を減価償却費とし、1円の簿価を残します。
定率法では、「期末残高×定率法」の償却率の額と、「取得価額×保証率」の額を比較します。計算額が保証率を下回らない場合は通常の償却率により減価償却費を求めます。減価償却が「取得価額×保証率」を下回った場合は、「改訂償却率適用開始時の期末残高×改定償却率」による償却が必要です。
例: 2012年(平成24年)4月1日以後取得の減価償却資産で、取得価額100万円、耐用年数5年(200%定率法の償却率0.400、改定償却率0.500、保証率0.10800)の減価償却の推移
※期首に取得したものとする。
| 減価償却費 (税法上の償却限度額) | 減価償却累計額 | 期末残高 (残存簿価) | |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,000,000円×0.400=400,000円 保証額108,000円超 | 400,000円 | 600,000円 |
| 2年目 | 600,000円×0.400=240,000円 保証額108,000円超 | 640,000円 | 360,000円 |
| 3年目 | 360,000円×0.400=144,000円 保証額108,000円超 | 784,000円 | 216,000円 |
| 4年目 | 216,000円×0.400=86,400円 保証額108,000円未満 | 892,000円 | 108,000円 |
| 5年目 | 216,000×0.500=108,000円 → 108,000円-1円=107,999円 | 999,999円 | 1円 |
4年目で計算額(86,400円)が保証額(108,000円)を下回るため、改定償却率(0.500)が適用されます。5年目は、4年目と同じ計算額(108,000円)から1円を差し引いた107,999円を償却費とし、期末残高を1円にします。
参考:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁
確定申告での減価償却費の書き方は?
個人事業主の所得税の確定申告(青色申告)では、「青色申告決算書」の損益計算書に「減価償却費」として年間の合計額を記入します。その内訳として、裏面の「減価償却費の計算」欄に、資産ごとの取得価額、償却方法、耐用年数、当期の償却費などを記載します。
法人税の申告では、「法人税申告書」の別表四で損金算入の調整を行うとともに、別表十六で減価償却費の計算明細を示します。
計算された減価償却費は、税務上、経費(損金)として認められるため、その年の課税所得を減らし、結果として所得税や法人税の負担を軽減する効果があります。
1円になった資産の取り扱いは?
ここでは、「確定申告」と「償却資産税」の2つの側面から、1円になった資産の取り扱いを解説します。
確定申告における取り扱い
残存簿価が1円になった資産は、その年(償却が完了した年)の翌年以降、新たに計上できる減価償却費は0円になります。
ただし、確定申告書の「減価償却費の計算」欄や、社内で管理する「固定資産台帳」には、その資産がまだ事業で使われていることを示すため、残存簿価1円の資産として記載し続ける必要があります。
償却資産税における取り扱い
残存簿価が1円になった資産であっても、それが事業用資産(土地・家屋以外)である場合、地方税である固定資産税(償却資産税)の申告対象には含まれ続けます。
ただし、償却資産税には課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されない「免税点」が設けられています。そのため、1円の資産が数点あるだけですぐに税金が発生するわけではありませんが、申告自体は必要となる点に注意が必要です。
残存簿価1円資産の処分方法と仕訳は?
残存簿価1円の減価償却資産は、事業で使わなくなった(事業の用に供しなくなった)タイミングで「除却」や「売却」といった処分を行います。
ここでは、日々の簿記処理として必要な残存簿価1円の資産を処分する際の仕訳を、会計処理の方法(直接法・間接法)や処分の内容(除却・売却)に分けて見ていきましょう。
除却・廃棄する場合(直接法)
直接法とは、減価償却資産の帳簿価額から直接、減価償却額を差し引く方法です。そのため、除却する場合は、1円の残存簿価を消去するような仕訳が必要です。
借方に「固定資産除却損」などの費用、貸方に除却したい減価償却資産の勘定科目を置き仕訳を行います。
例:取得価額50万円、残存簿価1円の工具器具備品を除却した。なお、減価償却は直接法により行っている。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産除却損 | 1円 | 工具器具備品 | 1円 |
除却・廃棄する場合(間接法)
間接法は、資産科目から直接的に減価償却を行わずに、「減価償却累計額」の科目を利用して、間接的に減価償却を行う方法です。
間接法を適用している場合、資産科目には取得価額、減価償却累計額にはこれまでの減価償却費の累計(残存簿価1円の場合は取得価額-1円の残額)が計上されていることになります。
除却時には、資産科目に計上された「取得価額」と、その資産の「減価償却累計額」を同時に消去する仕訳が必要です。
例:取得価額50万円、残存簿価1円の工具器具備品を除却した。なお、減価償却は間接法により行っている。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 固定資産除却損 | 1円 | 工具器具備品 | 500,000円 |
| 減価償却累計額 | 499,999円 | ||
売却する場合
残存簿価1円の資産を有償で売却した場合、帳簿価額(1円)と売却価額との差額を「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として計上します。
例: 取得価額50万円、残存簿価1円(減価償却累計額499,999円)の工具器具備品を1,000円で売却し、代金は現金で受け取った(間接法)。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,000円 | 工具器具備品 | 500,000円 |
| 減価償却累計額 | 499,999円 | 固定資産売却益 | 999円 |
残存簿価1円はいつまで残す?
残存簿価1円になった資産は、事業で使用している限りいつまでも帳簿上に残し続ける必要があります。
減価償却が済んだ残存簿価1円のものでも、事業でまだ使用している減価償却資産は除却ができません。前述の通り、この残存簿価1円は備忘価額であり、まだ事業で使用している事実を証明する意味があるためです。
そのため、減価償却終了後も事業で使用している資産は除却をせず、残存簿価1円として帳簿上(固定資産台帳)に残しておく必要があります。
この資産を実際に廃棄したり、売却したり、事業での使用を完全に中止したりするタイミングが来たときに、初めて上記で解説した「除却」や「売却」の仕訳を行い、帳簿上から消去します。
少額減価償却資産の特例とは?
減価償却資産の処理には、備忘価額1円を残す方法の他にも、取得価額に応じた特例が存在します。これらは1円まで償却する処理とは異なるため、区別して理解することが重要です。
これらの特例は、備忘価額1円を残す通常の減価償却とは異なり、早期に費用化できる点が特徴です。
参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
残存簿価1円の資産は適切に管理・処分を
残存簿価1円の減価償却資産は、減価償却が終了した後も、事業で使用している事実を示す「備忘価額」としての意味を持ちます。
事業で使っている限りは除却できず 、確定申告や償却資産税の申告においても、その存在を管理し続ける必要があります。
残存簿価1円の減価償却資産を除却するのは、事業で使用しなくなったタイミングです。税法に連動した会計処理として、資産の状況に合わせて適切なタイミングで除却や売却の仕訳を行いましょう。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025/10 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
10年落ちの中古車を減価償却するには?計算方法や耐用年数を解説
中古車を減価償却する場合には、新規登録をした時期から月数を確認して耐用年数を求めることが重要です。また、中古車の価格によっても対応が異なるため、注意が必要です。 本記事では、10年…
詳しくみる楽器の耐用年数と減価償却費計算を解説
楽器は時間の経過とともに価値が減少する減価償却資産であるため、減価償却が必要です。本記事では、楽器の減価償却費の計算方法や仕訳について解説します。耐用年数についても解説しているので…
詳しくみる少額減価償却資産は償却資産税の対象?計算方法や申告書の書き方も解説
中小企業には、「少額減価償却資産の特例」という減価償却に関する優遇措置が設けられています。ただし、「一括償却資産」と異なり償却資産税の対象となるため、注意が必要です。 本記事では、…
詳しくみる耐用年数とは?償却資産別や中古資産の年数、減価償却の計算方法も解説
減価償却費を算出するには、固定資産の「耐用年数」が必要です。しかし、耐用年数は償却資産の種類によって細かく設定されており、建物や車両、工具などそれぞれ異なります。 そのため、確定申…
詳しくみるレバレッジドリースとは?オペレーティングリースの違いとは?
少しの支出で高額な固定資産を運用することができる「レバレッジドリース」という仕組みがあります。かつては航空機にレバレッジドリースの仕組みが利用されたことはよく知られていますが、ここ…
詳しくみる建物の減価償却費の計算方法は?耐用年数や新築・中古の違いなども解説
建物の減価償却とは、建物の取得費用を法定耐用年数に応じて毎年少しずつ費用として計上する仕組みです。正しい計算や処理は、経理業務をスムーズに進める鍵となります。 この記事では、建物の…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引