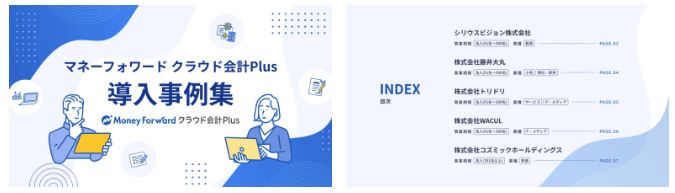- 更新日 : 2025年4月23日
わかりやすくて簡単な会計ソフトを比較する15のポイント
会計ソフトとは、伝票作成や総勘定元帳などの会計処理を効率よく行い、データとして管理するためのソフトウェアです。さまざまな会計ソフトがありますので、自社に合った会計ソフト選びが重要なポイントになります。
わかりやすい操作で、簡単に会計処理を行うためには、会計ソフトのどういった部分を比較すれば良いのでしょうか。この記事では、会計ソフト選びでチェックしたい15のポイントを紹介します。
この記事がよく分かる動画
会計ソフトを比較するポイント
会計ソフトにはさまざまなタイプがあります。いずれも、操作が簡単で直感的に使える会計ソフト、自動化機能などが優れた会計ソフトであれば、大幅な工数削減が可能です。会計ソフトを選ぶ際は、自社の会計処理が効率的に行えるかという点を重視して選ぶようにしましょう。以下の見出しでは、会計ソフトを選択する際に比較したい15のポイントを解説していきます。
1.仕訳を簡単に入力できるか
会計ソフトでの会計処理は、日々の取引を仕訳し、登録する作業がメインになります。仕訳作業が多いため、会計ソフトを選ぶ際は、仕訳を簡単に入力できるかという点に注目してみると良いです。
仕訳を簡単に入力できるかどうかは、入力画面のわかりやすさ、仕訳を簡単に入力できる機能の有無から判断します。
まず、入力画面のわかりやすさです。仕訳入力の画面を開いた際、勘定科目、金額、摘要など、どこに何を入力するか一目でわかりやすい会計ソフトを選ぶと良いです。入力画面は会計ソフトのデモ版などで確認できます。
次に、仕訳を簡単に入力できる機能の有無についてです。会計ソフトには、よく使う仕訳を登録できる仕訳辞書、取り込んだデータを自動で仕訳する機能をもったものもあります。いずれも一から仕訳を作成する必要はなく、データを確認するだけで簡単に仕訳ができます。
2.金融機関とデータ連携が簡単にできるか
会計ソフトの中には、金融機関とデータ連携できる機能をもったものがあります。金融機関とのデータ連携のメリットは、金融機関に足を運んだり、ネットバンキングでその都度データを取得したりしなくても、入出金のデータを自動で取り込めることです。
会計ソフトによっては取り込んだデータの仕訳を自動で提案してくれるものもありますので、自動仕訳まで使用できるものだと、さらに効率化を図ることができます。
会計ソフトを比較する際は、金融機関とのデータ連携ができるかという点はもちろん、連携が簡単にできるかどうかも確認しておきましょう。連携のたびに手間がかかると一苦労ですので、データ連携の初期設定が会計ソフト上ででき、その後も自動でデータを取得してくれるような会計ソフトが便利です。
3.金融機関以外にどのような連携ができるか
会計仕訳を少しでも簡単に済ませたいなら、金融機関以外にもデータ連携ができるか確認しておくと良いです。会計ソフトによっては、金融機関のほか、クレジット、電子マネー、クラウドソーシングサイト、ECサイトなど、さまざまなデータ連携に対応しているものもあります。
データを一から入力すると金額の入力ミスなど人的ミスが発生することもありますので、データ連携で、入出金データを取得できる、連携の充実した会計ソフトがおすすめです。会計ソフトを選ぶ際は、会社で利用しているクレジットカードなどが連携に対応しているかも確認しておきましょう。
4.決算書の作成が簡単にできるか
決算書は、事業の財政状況や経営成績を確認するための重要な資料です。法人税または所得税の確定申告の際のベースの資料としても活用するため、決算書の作成ができるかどうかも会計ソフト選びのポイントになります。
決算書作成まで対応している会計ソフトは多いので、作成が簡単にできるかという点を重点的に見ていくのが良いでしょう。仕訳登録と同時に、自動で決算書にデータを反映してくれるようなソフトが便利です。
年単位ではなく、月単位や四半期単位で決算書を確認したいときは、期間を選択して決算書の作成ができるかもチェックしておきましょう。
5.経営レポートはわかりやすいか
経営レポートは、経営分析などに役立つレポートのことです。財務諸表(決算書)のほか、会計ソフトによってはキャッシュフローや財務指標などさまざまなレポートを自動で作成してくれるものもあります。
経営レポートは、経営者などが経営分析や経営戦略に役立てるものですので、一目でわかりやすいレポートが望ましいです。経営レポートのサンプルやデモ版などを使い、経営レポートの内容はわかりやすいか、よく比較しておきましょう。
6.紙の領収書の読み取りが簡単にできるか
会計ソフトを利用している場合でも、入力ミスによる人的ミスが発生することがあります。ミスを減らすには人が入力する部分を減らすこと、ミスに対処するにはすぐに元のデータを確認できるようにしておくことが重要です。
会計ソフトの中には紙の領収書を読み込んでデータを取得できるもの、領収書のデータを仕訳に紐づけられるものもあります。紙の領収書に対してどこまで対応しているかも確認しておきましょう。
領収書の読み込みは、スマートフォンのカメラ機能でできるなど、専用の機械がなくても簡単にデータを取り込めるものがおすすめです。
7.スマホでもデータが簡単に確認できるか
経営層などが会計データを確認したいとき、経理担当者に連絡して必要なデータを送ってもらうとなると、多少のタイムロスが生まれます。リアルタイムで必要なデータを確認できるようにするためにも、パソコンだけでなく、スマートフォンなどの携帯端末でもデータを確認できる会計ソフトがおすすめです。
特に、個人事業主の場合は、事業主自ら経理処理を担当することも多いです。すき間時間に経理処理ができると便利ですので、スマートフォンからデータを確認できるほか、データ入力までできる会計ソフトだと時間を有効的活用できるでしょう。
8.税理士との情報共有が簡単か
確定申告などの税務を税理士に依頼している企業も多いかと思います。インターネットの発達により、近場の税理士ではなく、遠方の税理士に依頼をする企業も増えました。
税理士とやり取りする際、データ共有のため仕訳データを送付することもありますが、やり取りが複雑だと、その分手間がかかります。
税理士からの助言をすぐにもらいたい場面も発生しますので、税理士とのデータ共有が簡単にできるような会計ソフトが便利です。
9.サポートはあるか
いくら便利な会計ソフトでも、操作方法や機能を理解していないと使いこなせません。必要なときにサポートを受けられるかも、会計ソフト選びでは確認しておきたいところです。
サポートにもさまざまな方法があります。会計ソフトの操作ガイドをホームページ上で簡単に閲覧できるようになっていたり、電話やチャットで問い合わせができたり、サービスごとにサポートの内容は変わります。困ったときに不安が解消できるサポート内容になっているか確認しておきましょう。
会計ソフトの導入に不安がある場合は、導入支援を行っているかもチェックしておきたいところです。
10.見積書や請求書作成システムなどの連携や拡張性はどうか
会計処理に関わるデータは、できるだけ会計ソフトに紐づけすることをおすすめします。データを連携すれば、入力ミスを防げるためです。
見積書や請求書作成システム、あるいは年末調整や法定調書作成も可能な給与計算ソフトなどと連携でき、自動で仕訳を作成してくれるような会計ソフトだとミスを抑制できるでしょう。すでに見積書や請求書作成システムなどを利用している場合は、候補として考えている会計ソフトに連携できるか確認しておくと良いです。
連携以外にも、会計ソフトの機能を拡張することで会計処理以外の機能を利用できるケースもあります。例えば、税務申告は会計と関連性が高いので拡張できると便利です。基本機能になくても、拡張またはシステム連携で、税務申告の機能を利用できる会計ソフトもあります。システム連携と合わせて、会計ソフト自体の拡張性も見ておきましょう。
11.他社会計ソフトからの乗り換えが簡単にできるか
新規で会計ソフトを利用する場合はあまり考慮しなくても良いですが、すでに会計ソフトを利用していて、乗り換えを考えている場合は、乗り換えが簡単にできるかも見ておきましょう。
事業年度の終わりと同時に新しく会計ソフトを取り入れる場合は、古い会計ソフト、新しい会計ソフトで分けて管理もできます。しかし、年度の途中で会計ソフトを乗り換える場合は、年度中のデータを移行しなければなりません。
移行に対応していない会計ソフトだと入力し直さなければならないので、できるだけデータ移行の手間がかからないものがおすすめです。
乗り換えで新しい会計ソフトを探しているなら、まず、現在使用している会計ソフトの移行に対応しているかを確認します。対応している場合は、インポート機能などで簡単にデータを移行できるか見ておきましょう。
12.クラウド型かインストール型か
会計ソフトは、インターネット上で利用できるクラウド型、ソフトウェアを端末にインストールして使用するインストール型に分けられます。
クラウド型は、インターネット環境があれば、さまざまな端末から利用できるのが特徴です。また、クラウド型のほとんどは月額制や年額制を採用していることが多く、バージョンアップで別料金がかかることはありません。会計ソフトにかかるコストを予測できます。
一方のインストール型は、端末にインストールして使うため、基本的に限られた端末で利用することになります。インターネット環境がなくても利用できますが、クラウド型のようにさまざまな端末からアクセスできません。
クラウド型を利用するか、インストール型を利用するかは、自社での会計ソフトの利用形態に合わせて考えると良いです。
13.有料か無料か、プランはわかりやすいか
事業で使用するなら、有料の会計ソフトを使用するのが一般的です。有料の会計ソフトでも、機能を制限して無料プランを設けているものもありますので、取引が少ない場合は無料プランで検討してみるのも良いでしょう。コストを抑えられます。
有料の会計ソフトで比較する際は、料金プランがわかりやすいかどうかも確認しておきましょう。料金プランが不明確なものだと、オプション利用で思わぬコストがかかることもあります。
そのため月額制などシンプルでわかりやすい会計ソフトがおすすめです。オプションで料金が発生する会計ソフトについては、条件が明記されているかよく確認しておきましょう。
14.セキュリティはしっかりしているか
会計情報は、重要な内部情報です。情報が流出しないように、会計ソフトはセキュリティのしっかりしたものを選ぶことをおすすめします。
検討している会計ソフトについてセキュリティに関する説明があれば、どのようなセキュリティ対策が行われているかチェックしておきましょう。例えば、個人情報の適切な保護を認定するプライバシーマークなどが参考になります。
クラウド型を利用する場合は、データが消失してしまわないように、データをバックアップしているかも確認しておきたい部分です。
15.会計知識はどの程度必要そうか
小規模企業や個人事業主では、専任で経理担当を置かないこともあります。すでに会計知識を十分にもっている人が会計ソフトを扱う分には問題ありませんが、会計知識がそこまでない場合は、会計ソフト選びも慎重に進めるべきでしょう。シンプルな機能しかない会計ソフトだと、仕訳や帳票の作成に苦労します。
会計ソフトを取り入れる際は、会計知識がどの程度必要そうか、デモ版などで確認しておくと良いです。会計知識があまりない場合は、仕訳の提案機能、自動仕訳機能、簡易入力機能など、仕訳や操作をサポートしてくれるような機能がある会計ソフトを選ぶと会計処理も楽になります。
マネーフォワード クラウド会計は簿記知識が少なくても使いやすい
会計ソフトを利用するなら、「マネーフォワード クラウド会計」がおすすめです。マネーフォワード クラウド会計は、データ連携機能、AIを利用した自動仕訳機能などが充実していますので、簿記知識が少なくても安心です。充実した機能で、会計処理ができます。
また、簿記知識が少ない人に限らず、簿記知識をもっている人にとっても、マネーフォワード クラウド会計は使いやすい作りになっています。勘定科目や補助科目などカスタマイズできる部分もありますので、特殊な仕訳にも対応しやすく、希望に沿った使い方ができます。
会計ソフトはよく比較してぴったりなものを
コスト面だけなど、一方向で会計ソフトを比較して選ぶと失敗することもあります。この記事でも紹介したように、会計ソフトは多方面から比較して選ぶと良いです。失敗も減りますし、なにより事業や希望に合った会計ソフトを見つけられるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
マネーフォワード クラウド会計Plus導入事例
マネーフォワード クラウド会計Plusは多くの成長企業にご導入いただいています。
本資料では、選定過程や導入効果など導入企業様の声をまとめました。導入に成功した企業について知りたい!という方におすすめです。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
青色申告1から簡単ガイド
個人事業主で会計ソフトをお探しの方におすすめです!
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
自分で法人決算!決算書の作り方ガイド
会計ソフトにご興味がある、1人法人の方や、中小企業の経理の方におすすめなのがこちらのガイドです。
本書では、各決算書の概要や具体的な作り方をわかりやすく解説しています。 また、作成した決算書の提出先や「マネーフォワード クラウド会計」で簡単に作成する流れも紹介しています。
よくある質問
わかりやすくて簡単な会計ソフトを選ぶポイントは?
仕訳を簡単に入力できるか、金融機関とのデータ連携が簡単にできるか、決算書の作成が簡単にできるかなどを見極めると良いでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
会計ソフトの使用に会計知識はどの程度必要?
ソフトによります。会計知識がどの程度必要そうかをデモ版などで事前に確認し、知識があまりない場合は仕訳や操作をサポートしてくれるような機能があるものを選ぶと会計処理も楽になります。詳しくはこちらをご覧ください。
わかりやすくて簡単に使える会計ソフトは?
マネーフォワード クラウド会計はデータ連携機能や自動仕訳機能などが充実しているので、簿記知識が少なくても安心して会計処理ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
会計ソフトの関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引