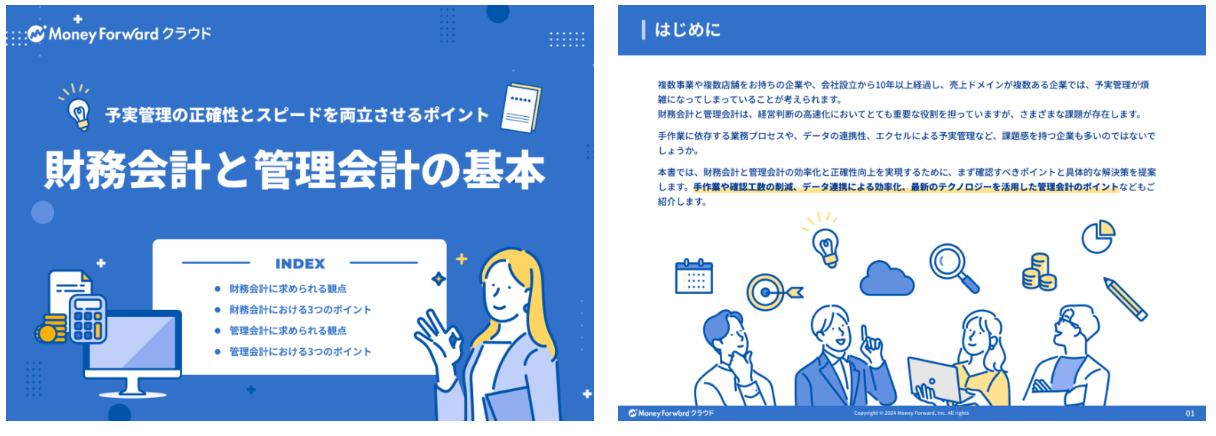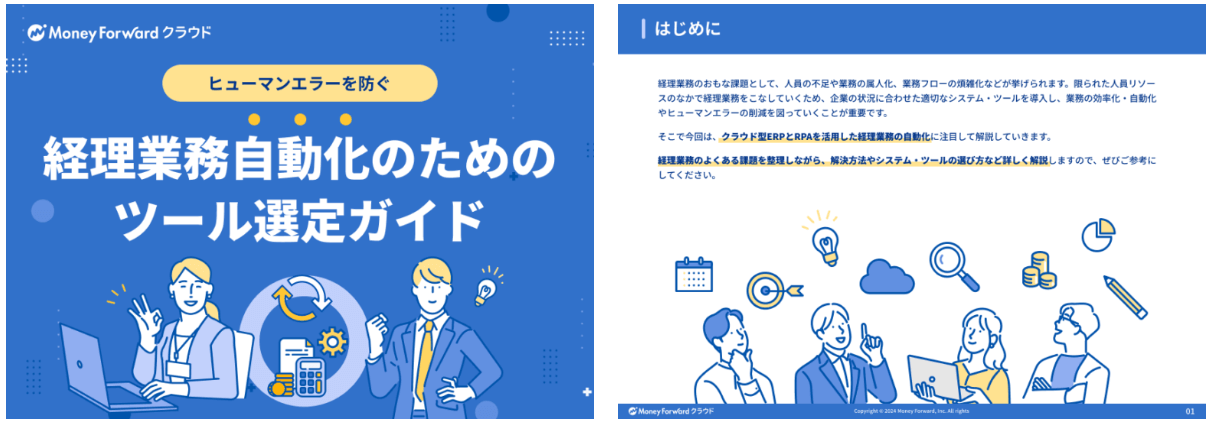- 更新日 : 2025年2月20日
会計監査っていつ何をやる?目的や担当者が準備すべき資料を解説
会計監査は、会社法の要件を満たした大会社が受ける監査のことです。
特に監査を行う人を会計監査人といいます。
では、会計監査はどのようなことを行うのでしょうか。そのために経理担当者はどのような準備が必要になるのでしょうか。
この記事では具体例を交えながら会計監査について分かりやすく解説していきます。
目次
会計監査とは
会計監査とは、会社が作成した財務諸表に対して、公認会計士または監査法人(以下「会計監査人」という)が行う監査のことをいいます。会計監査は財務諸表監査ともいわれます。
会計監査を行うことができるのは、会社に対して利害関係のない第三者の立場である会計監査人のみです。利害関係がある場合は会社に都合の良い意見を出す可能性を排除できないため、会計監査を行うことができません。
会計監査の目的
会計監査の目的は、会社が作成した財務諸表が適正に表示されているかどうかに対して会計監査人が意見を表明することです。会計監査人の意見があることによって、投資家は会社の財務情報を信頼することができます。
さらに、会計監査人の意見は「独立監査人の監査報告書」という様式で意見表明されます。監査報告書は会社が公開する財務情報と共に公開されます。
特に有価証券報告書には必ず監査報告書が含まれています。
会計監査人の意見は以下の4つがあります。
| 意見 | 意味 |
|---|---|
| 無限定適正意見 | 財務諸表を適正に表示している |
| 限定付適正意見 | 財務諸表の一部に誤りがあるが、それ以外は適正に表示している |
| 不適正意見 | 財務諸表を適正に表示していない |
| 意見不表明 | 監査を実施することができず、財務諸表を適正に表示しているかどうか不明の意味 |
会計監査の時期
会計監査の実施時期は、後述する監査の種類によって異なります。
金融商品取引法の監査であれば、会計監査人は少なくとも2カ月に1回以上、会社に訪問することになります。大きな会社であるほど訪問回数は増加します。
また、会社法やその他の法律による監査であれば年に3~4回程度、訪問することが一般的です。
補足として、会計監査人は財務諸表が適正に表示されているかどうかを調査するため、会社が決算を終えた直後に必ず会計監査人が来ることになります。
会計監査の種類
会計監査は、会計監査を義務付ける法律によって以下の3つに大別することができます。
- 金融商品取引法による会計監査
- 会社法による会計監査
- その他の会計監査
上記のように法律で会計監査を分類することができますが、会計監査の目的である財務諸表を適正に表示しているかどうかという点は変わりません。
以下では、それぞれ適用される会社や関連する書類を解説していきます。
金融商品取引法による会計監査
金融商品取引法では、主に上場企業に対して会計監査と内部統制監査の2つを義務付けています。
会計監査では、企業が作成した財務諸表が適正に表示されているかどうかの調査を行います。内部統制監査では、企業が作成した内部統制報告書が適正に表示されているかどうかに対して、会計監査人が調査を行います。
会計監査と内部統制監査は別の監査になりますが、基本的に同一の会計監査人が行います。
会計監査と内部統制監査の監査報告書は、有価証券報告書に添付される形で公開されます。
補足として、金融商品取引法が適用される会社は大規模な会社であるため、以下の会社法による監査も義務付けられます。
会社法による会計監査
会社法による会計監査は、「会社法上の大会社」に該当する場合に義務付けられます。会社法の大会社の条件は、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または同負債の部の合計額が200億円以上である株式会社をいいます。
会社法による会計監査の監査報告書は、会社が公開する財務諸表(会社法では計算書類と附属明細書という)に添付する形で公開されます。
その他の会計監査
その他の会計監査は、金融商品取引法と会社法以外の法律で義務付けられる会計監査です。
具体的には、学校法人や独立行政法人、社会福祉法人などの会計監査があります。
これらの会計監査の内容は、財務諸表の様式とは異なりますが財務諸表を適正に表示しているかどうかを調査することには変わりません。
上記の他に、法律の義務が無くても任意で会計監査を受けることが可能です。
具体的には、企業買収の前に任意で会計監査を受けることがあります。
会計監査の実施内容
以下では、会社法の会計監査を前提として会計監査の実施内容を説明していきます。
会計監査の目的は、財務諸表を適正に表示しているかどうかを調査することです。財務諸表を細分化すると、財務諸表は多数の勘定科目で構成されています。
つまり、会計監査人は勘定科目の金額が妥当であるかどうかを調査することになります。
この調査を前倒しできるものは期中の監査で行い、決算時で対応しなければいけないものは決算時に対応します。
期中の監査の実施内容
期中の監査で行われることは、主に会社の重要な内部統制を会計監査人が調査することです。調査では、従業員への聞き取りや関連する書類の閲覧を行います。
会計監査人はこのような調査を行い、内部統制が有効かどうかを評価することで、財務諸表に間違いが生じにくい体制であるかどうかを確認します。
具体的な例として、人件費を使って説明します。
人件費は従業員の給与や賞与です。従業員が多数いる会社で、会計監査人がすべての従業員の給与・賞与の計算を調査すると膨大な時間がかかってしまいます。
この場合に、会計監査人は給与計算を行う従業員への聞き取りや給与計算ソフトなどを調査し、間違った人件費が計上されない体制であるかどうかを確認します。
決算時の監査の実施内容
決算時に会計監査人が行うのは、決算書や仕訳帳、勘定科目の内訳などを閲覧し、勘定科目と金額が妥当であるかどうかの調査です。調査の方法は勘定科目によって異なります。
具体例として、預金や借入金では、会計監査人が銀行から残高証明書を入手することがあります。
さらに、決算時には会社が公開する財務諸表に間違いが無いかどうかを会計監査人が確認します。具体的には、法律や会計基準の様式に合っているかどうかや、勘定科目が適切かどうかなどを確認します。
その他の監査の実施内容
上記の調査の他に会計監査人の判断よって会社に訪問することがあります。
具体的には、会計監査人が、経営者や監査役との面談や、会社が行う実地棚卸へ立ち会うことなどがあります。
担当者が準備すべき書類
上記では、会計監査人が実施する調査を大まかに説明しました。この調査に対応するように担当者が準備すべき書類を説明していきます。
期中の監査で必要な書類
期中の監査では、主に重要な内部統制に関する資料の提出を会計監査人から求められます。
内部統制に関する資料は大きく分けて2つあります。
まず1つ目は、内部統制の始まりと終わりまでのプロセスを会計監査人が確認するための資料です。例として「仕入と買掛金」で説明します。
仕入に関連する書類は、会社が作成した発注書、取引先から受け取る納品書・請求書があることがほとんどです。これらの資料を元に会計監査人が従業員に対して聞き取りを行い、仕入の始まりから終わり、買掛金の支払までのプロセスを確認します。
2つ目は、会計監査人がランダムに選んだ(サンプリングした)資料があります。
例として「仕入」で説明します。
この場合は、会計監査人が請求書をランダムに数十枚選ぶことがあります。
これに関連して担当者側で対応する納品書や発注書をすべて準備することになります。
上記の他、高額な固定資産を購入した場合や高額な借入を行った場合は、関連する書類の提出を求められることがあります。会計監査人は、財務諸表の大きな金額の間違いに注意しているため、金額が大きい取引・リスクが高い特殊な取引に対して関連する書類の提出を求めることがあります。
期末の監査で必要な書類
期末の監査では、会計監査人に決算書や仕訳帳・勘定科目の内訳を提出します。これ以外の書類は必要に応じて提出することになります。
理由としては勘定科目によって会計監査人の調査方法が異なるためです。
提出する書類の例として2つ説明します。
まず1つ目は、固定資産や仕入などの勘定科目です。
これらの勘定科目には通常、契約書や請求書があるため、金額が大きい場合や会計監査人の判断によって提出が求められることがあります。
2つ目は、貸倒引当金や繰延税金資産などの見積を伴う勘定科目です。
引当金は契約書や請求書が無いことが多く、経理担当者の見積で計上するため、会計監査人は計算の根拠や質問の回答を求めることがあります。この場合は計算の根拠や実績をまとめた表などを提出することになります。
その他の監査で必要な書類
その他の監査の場合は、株主総会議事録や取締役会議事録、稟議書(りんぎしょ)などが求められます。ただし、期中や期末の監査ほど書類は求められないため準備するのは大変ではありません。会計監査人の指示に従って書類を提出しましょう。
会計監査は適正な会計を立証するためのもの
会計監査の目的は、会社が作成した財務諸表に対して会計監査人が意見を表明することです。会計監査人は意見を表明するために、会社の財務諸表がどのように作成されるかを理解し、勘定科目の金額が妥当であるかどうかを立証するための調査を行います。
経理の担当者としては、会計監査人と協力し必要な資料を提出することを心がけましょう。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
財務会計と管理会計の基本
「管理会計を効率よく正確にできるようになりたい」とお悩みではないですか?
財務会計と管理会計の基本を押さえつつ、予実管理の正確性とスピードを両立させるためのポイントと具体的な解決策を詳しく解説します。
経理業務自動化のためのツール選定ガイド
「ツールをうまく活用して、経理業務におけるヒューマンエラーを削減したい」とお悩みではないですか?
経理業務のよくある課題を整理しながら、クラウド型ERPとRPAを活用した経理業務の自動化について詳しく解説します。
中堅企業はココで選ぶ!会計システムの選び方ガイド
「会計システムのリプレイスを検討しているが、種類が多く、どのポイントで比較したらいいかわからない」とお悩みではないですか?
中堅企業に最適な会計システムを選ぶための着眼点や注意点を解説します。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
業務効率化と内部統制の強化を実現!
マネーフォワード クラウド会計Plusは、IPO準備・中堅〜上場企業向けのクラウド型会計ソフトです。データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務を効率化すると同時に、仕訳承認・権限管理機能で内部統制にも対応します。
よくある質問
会計監査とは?
会社が作成した財務諸表に対して、公認会計士または監査法人が行う監査のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
会計監査の種類は?
金融商品取引法による会計監査、会社法による会計監査、その他の会計監査の3つがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
担当者が準備すべき書類は?
期中の監査、決算時の監査、その他の監査で異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
消費税は費用になる?勘定科目や仕訳方法、税率変更時のコストまで解説
日々の取引で発生する消費税について、「最終的に納める消費税は、会社の費用や経費として計上できるのだろうか」と疑問に思ったことはないでしょうか。結論からいうと、消費税は原則として費用…
詳しくみる【これは軽減税率?】「宅配ピザ」と「UberEatsでピザ配達」で消費税は変わる?
2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。 本シリ…
詳しくみる経理のペーパーレス事例7選!実現に向けた課題や進め方、失敗事例も解説
経理におけるペーパーレス化には多くのメリットがあります。しかしながら、実施には多くの課題もあります。 目的意識があいまいなまま物事を進めてもうまく行かないように、ペーパーレス化にお…
詳しくみる神奈川で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
神奈川県で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応は、特に…
詳しくみる自己株式とは?取得・消却のメリットや制限、手続きをわかりやすく解説
上場企業では、比較的頻繁に行われている自己株式の取得や消却ですが、中小企業でも自己株式の取得や消却を行う会社が増えてきました。それは、自己株式の取得や消却にさまざまなメリットがある…
詳しくみる粉飾決算の事例一覧|手口や影響、有名企業から学ぶ防止策まで徹底解説
「粉飾決算」という言葉をニュースなどで耳にしたことはありませんか? これは、企業が意図的に財務諸表を偽り、実際よりも経営状態を良く見せかける不正な会計処理のことです。 この記事では…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引