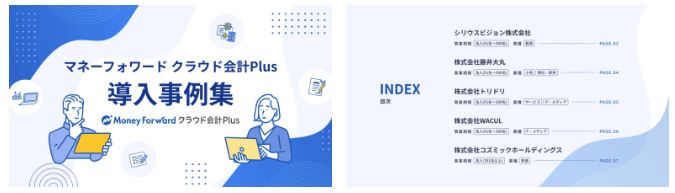- 更新日 : 2026年2月17日
中小企業におすすめ会計ソフトの選び方・種類と比較方法
初めて会計ソフトを導入する場合や、今まで使用していた会計ソフトを更改したい場合、どの会計ソフトを選べばいいのかについて悩んでいませんか?
新たに会計システムの導入を検討する際はまず、自社が必要とする機能をピックアップしつつ、事業規模にあったものを選定します。パッケージ製品やクラウドサービスなど選択肢も豊富です。
目次
会計ソフトとは?
会計ソフトとは、企業の財務内容を数値化するスキルである「簿記」を、パソコンを使って効率的に管理するためのソフトです。
「簿記」では、現金出納帳や売掛帳、仕訳帳、総勘定元帳など、実に様々な帳簿を作成します。これらの帳簿を全て手書きで作成すると、ひとつの仕訳を複数の帳簿に転記処理する必要がありますし、転記漏れや転記ミスなどが発生します。
会計ソフトは、ひとつの仕訳が関連する全ての帳簿に自動連動されますので転記する手間が省けますしミスもなくなります。煩雑な会計処理の効率化には今や欠かせない存在となっています。
会計ソフトの種類とは?
パソコン用会計ソフトの種類は、パッケージ会計ソフト、クラウド、ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)に大別できます。それぞれの特徴について見てみましょう。
| 会計ソフトの種類 | 特徴 |
|---|---|
| パッケージ会計ソフト | パソコンにインストールして使用するタイプ。スタンドアローン(インターネットやサーバーにつながなくても単独で使える)製品と、クライアント・サーバーシステムで、複数のパソコンとデータ共有ができる製品がある。ある程度会計知識を必要とする場合が多い。 |
| クラウド会計サービス | インターネット経由で会計ソフトを利用するサービス。サーバーを自社で用意したり、ソフトウェアをインストールしたりする必要もなく、既存のパソコンやスマホ、タブレットなどからのアクセスが可能。会計知識がなくてもすぐに使い始めることができる。 |
| ERP | 経営上不可欠な業務ソフト(営業、経理、人事など)を統合したソフトウェア。会計ソフトは、数ある業務ソフトのひとつ。各業務ソフトで扱う情報を統合したデータベースで一元管理するため、全社で情報共有がしやすく、業務効率化が可能。大企業向けであったが、中小企業向けのものもある。 |
さらに同じソフト名であってもパッケージ利用とクラウド利用が用意されているシステムもあります。また、パソコンにインストール作業はするけれども、会計データはクラウド上で保管するシステムもあります。この場合はパッケージ型ソフトに分類されます。
パッケージ会計ソフトとクラウド会計ソフトの比較
全業務をシステムに一元化するERPは、導入までの期間や導入費用も企業の利用形態によって変動が大きいです。そこで、ここでは中小企業や個人事業主を想定し、パッケージ会計ソフトとクラウド会計ソフトを比較します。
パッケージ会計ソフトとクラウド会計ソフトの早見・比較表
パッケージ会計ソフトとクラウド会計ソフトの違いを分かり易く早見表にしてみましょう。
| パッケージ会計ソフト | クラウド会計ソフト | |
|---|---|---|
| 価格(初期導入時) | △ 初期費用が必ず発生し、料金も高めになる場合が多い | ◎ 初期費用が安いものが多く、初期費用が無料のものもある |
| セキュリティ | 〇 ネット環境のないパソコンにインストールすれば安全に運用できる | △ データが必ずインターネットを経由するので常にリスクが |
| 作業効率 | ◎ 環境依存する必要がないため動作は安定している | △ 通信速度が遅かったり、サーバーが混雑していたりすると動作が不安定になる |
| 料金 | △ 月額料金は発生しないものが多いが、税制改正などがあった場合には更新パッケージを追加購入しなければならないケースが多い | ◎ 割安な月額料金のものがほとんどであり、税制改正への対応は月額料金に含まれている |
| データの共有 | △ パッケージをインストールしたPCからデータを外部に持ち出す際にはメディアが必要となる | ◎ データがクラウド上にあるので ネット環境さえあればデータ共有が容易にできる |
| データの保全 | △ ハードディスクが破損したらデータも消失するので、作業終了の都度バックアップが必要となる | ◎ データセンターにてバックアップされているので自身でバックアップをとる必要がない |
| バージョンアップ | △ ネット環境がない場合、バージョンアップの時期を自分で判断し、手作業で行わなければならない | ◎ バージョンアップは運営会社が行うので、バージョンアップを気にする必要がない |
| デバイス | △ 使用できるデバイスはパソコンのみ | ◎ ネット環境さえあればパソコンはもちろん、スマホやタブレットでも操作可能(アプリのインストールが必要になる場合がある) |
| OS | △ 会計ソフトが対応するOSを使わなければならない | 〇 使用するOSは問わない (ソフトをインストールするタイプのクラウド型は除く) |
| 利用台数 | 〇 パソコン1台に1ライセンス | 〇 1ライセンスで複数台処理が可能 (ソフトをインストールするタイプのクラウド型は除く) |
パッケージ型とクラウド型のメリット・デメリット
上記の早見表に基づき「パッケージ型会計ソフト」と「クラウド型会計ソフト」のメリット・デメリットについて詳しく解説していきましょう。
【パッケージ会計ソフト】
<メリット>
- 社内回線(イントラネット)での利用なのでセキュリティ面で安心
- ブラウザ画面に比べて、画面の操作性が良い
- メーカーサポートが手厚く、動作不良などへの対応も早い
- インターネット回線に依存せずに運用が可能なので作業効率が良く、主に社内で経理をする方におすすめ
<デメリット>
- サーバー構築、インストールや更新が手間
- サーバーなどハードウェアも合わせて初期パッケージ価格が高くなる傾向にある
- 運用コスト(サーバー運用の人件費やメーカーサポート料金、バージョンアップ費用)がかかる
- サーバークライアントシステムの場合、社外からアクセスできない場合もある
- ネット環境がない場合、税理士とのデータ共有に手間がかかる
【クラウド会計ソフト】
<メリット>
- 入出金取引について金融機関の口座情報との連携で自動仕訳・自動入力が可能
- パッケージ製品に比べ、初期費用が少なくて済む
- サーバーの運用もメンテナンスも不要
- インターネット環境と対応ブラウザ搭載の端末(パソコン、スマホ、タブレット)があればいつでもどこでも使えるので、外出している時間が長い方におすすめ(スマホ・タブレットの場合はアプリのインストールが必要な場合がある)
- 月額料金が安いものが多い
- 税制改正への対応が無料のものが多い
- 経営分析やレポートを最新の情報で作成できる
<デメリット>
- 自動仕訳後の見直しが必要で製品によっては修正に手間がかかる
- 通信環境速度に影響されて動作が遅くストレスになる場合がある
- オンラインでの処理が必須となるため常にネット環境が必要となる
- 月額利用料は毎月かかるため、ユーザー数や利用年数によってはパッケージ製品より高くつく場合がある
- 不正アクセスなどセキュリティが気になる
作成可能な帳簿や使用する勘定科目・補助科目など、ソフトの機能そのものに大きな差はありませんが、総合的に見れば中小企業にとってはクラウド会計ソフトの方が導入しやすいメリットを多く備えています。ただ、パッケージ会計ソフトは、操作性の良さや豊富な機能などクラウド会計ソフトにない魅力もあり、どちらを選ぶかは悩ましいところです。
中小企業が導入するべき会計ソフトの選び方
中小企業が会計ソフトを選定する際に気を付けるべきポイントを紹介します
- 経理担当者のレベルに合っているか
経理の担当者には、複式簿記を理解しているだけの初心者から、経営分析やERPの管理までこなすベテランまで、その実務レベルは様々です。簿記知識が浅い方には多機能のソフトより仕訳入力や伝票入力が簡単なソフトを選択すべきですし、ベテランの方には経理データを資金繰りや融資対策、ワークフローなどと併用できる機能が搭載された複合システムをおすすめします。
- 会社規模に合っているか
上場企業のように支店単位で会計処理を行い、レポート結果を本社で一括して取りまとめグループ損益を計算するような形態であれば、本社や顧問税理士とのデータのやりとりに手間がかかるパッケージ型よりクラウド型の会計ソフトがおすすめです。
- 主に経理処理をする場所がどこか
担当者が社内での作業時間を充分にとれる場合にはパッケージ型でも可能ですが、例えば経理担当者が外回りを兼務している場合など、外出している時間が長いときにはスマホやタブレットでの携帯処理が可能なクラウド型の方が効率よく仕事が進められます。
- どれくらいのコストをかけられるか
パッケージ型は自社独自のカスタマイズがしやすい反面、システム導入の初期費用や更新費用がクラウド型より割高となります。予算があまりかけられずコストを抑えたい場合にはクラウド型がおすすめです。
上場を目指す中小企業におすすめの会計ソフト
では、これから上場を目指す中小企業が会計ソフトを導入する際のおすすめポイントを挙げてみましょう。
株式上場(IPO)するためにはまず、証券取引所における上場審査があります。しかし、IPO準備として審査前に監査法人によるショートレビューを受けなければなりません。また上場審査をクリアするため、決算書は最新の会計基準を適用する必要がありますし、予算組みや事業計画は精度の高いものが求められます。会計処理もあらかじめ早期決算化しておかなければ上場審査で予実差異を分析する時間が足りなくなってしまいます。
また、上場後も「内部統制報告制度」による報告義務がありますが、これらの審査・報告を全て、自社で作成した財務諸表で行わなければなりません。
したがって「最新」「スピーディ」「精度の高い」が会計ソフト選定のキーワードです。
中小企業と大企業における会計ソフト選びの違い
中小企業と大企業では会計ソフトに求められる機能に大きな違いがあります。
中小企業では、会計ソフトと法人税申告ソフトだけで経理から税務申告までこなすことができるケースがほとんどです。
しかし、大企業になると「有価証券報告書」のように、外部の利害関係者に向けた財務内容の報告義務が課題となります。また企業内部でも、会計、生産管理、労務管理など管理しなければならない項目が増えてきます。
このようなニーズから、基幹情報を統合的に管理できるERPパッケージを導入するケースが増えているのは必然の流れといえるでしょう。
中小企業者でも将来的に事業規模を拡大し大企業を目指している方は、業務の効率化やリアルタイムでの情報管理ができるERPと、ERPをサポートする会計ソフトを今から選択すべきです。

比較検討し自社にあった会計ソフトを選ぼう
現在の会計ソフトは、会計のデータを利用して税務申告や販売管理、財務分析、資金繰りなどができる多機能なものが増えてきました。しかし、せっかく高いコストをかけても機能を活かしきれないようでは導入する意味がありません。まずは複数の会計ソフトを実際に操作し、自社の経営スタイルや事業規模で必要となる機能が何なのかを把握したうえで、経理レベルに合わせた会計ソフトを選びましょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
マネーフォワード クラウド会計Plus導入事例
マネーフォワード クラウド会計Plusは多くの成長企業にご導入いただいています。
本資料では、選定過程や導入効果など導入企業様の声をまとめました。導入に成功した企業について知りたい!という方におすすめです。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
青色申告1から簡単ガイド
個人事業主で会計ソフトをお探しの方におすすめです!
「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。
自分で法人決算!決算書の作り方ガイド
会計ソフトにご興味がある、1人法人の方や、中小企業の経理の方におすすめなのがこちらのガイドです。
本書では、各決算書の概要や具体的な作り方をわかりやすく解説しています。 また、作成した決算書の提出先や「マネーフォワード クラウド会計」で簡単に作成する流れも紹介しています。
よくある質問
そもそも会計ソフトとは?
企業の財務内容を数値化するスキルである「簿記」を、パソコンを使って効率的に管理するためのソフトです。詳しくはこちらをご覧ください。
会計ソフトの種類とは?
パソコン用会計ソフトの種類は、パッケージ会計ソフト、クラウド、ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)に大別できます。詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業が導入するべき会計ソフトの選び方は?
自社の経営スタイルや事業規模で必要となる機能が何なのかを把握したうえで、経理レベルに合わせた会計ソフトを選ぶことが大切です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
会計ソフトの関連記事
中小企業の関連記事
新着記事
請求書支払いの効率化はどう進める?手順と自動化のポイントを解説
Point請求書支払いの効率化はどう進める? 請求書支払いの効率化は、業務フローの標準化とシステムによる自動化の組み合わせで実現できます。 受領形式をPDF等の電子データに統一 A…
詳しくみる請求書を一括で振込できる?マナーや手数料の負担、効率化の手順を解説
Point請求書を一括で振込できる? 同一取引先への複数請求書は、事前に合意があれば合算して一括で振り込めます。 内訳を明記した支払通知書の送付がマナー 振込先口座が異なる場合は個…
詳しくみる振込代行サービスとは?比較ポイントや手数料を安く抑える方法を解説
Point振込代行サービスとは? 企業の送金業務を外部へ委託し、手数料削減と経理業務の効率化を同時に実現する仕組みです。 大口契約の活用により手数料を半額以下に CSV連携で入力業…
詳しくみる振込代行サービスのセキュリティは安全?仕組みや管理方法を解説
Point振込代行のセキュリティは安全? 銀行同等の暗号化と法的な保全措置により極めて安全です。 全通信をSSL暗号化し盗聴・改ざんを防止 倒産時も信託保全で預かり金を全額保護 社…
詳しくみる振込手数料を削減するには?法人のコスト対策と見直し術を解説
Point振込手数料を削減するには? 振込手数料の削減には、ネット銀行への移行や振込代行サービスの活用が最も効果的です。 ネット銀行活用で窓口より約30〜50%のコスト削減が可能 …
詳しくみる振込作業を効率化するには?経理の支払い業務をラクにする方法
Point振込作業を効率化するには? 銀行APIや全銀データを活用し、会計ソフトと銀行口座をシステム接続することで実現します。 API連携で手入力とログインの手間を削減 AI-OC…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引