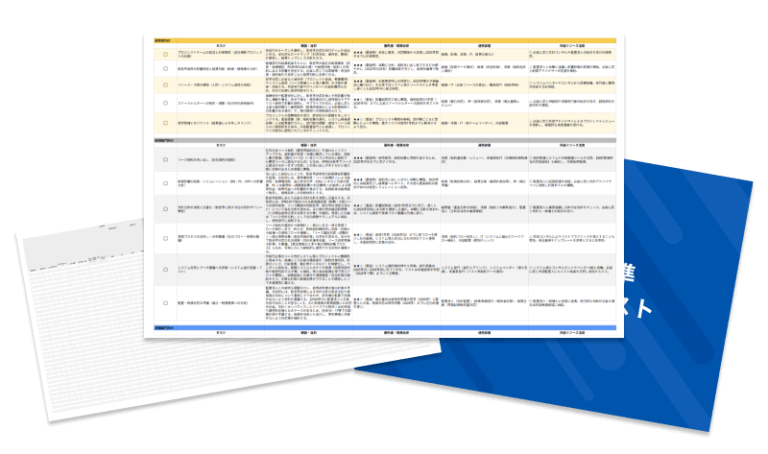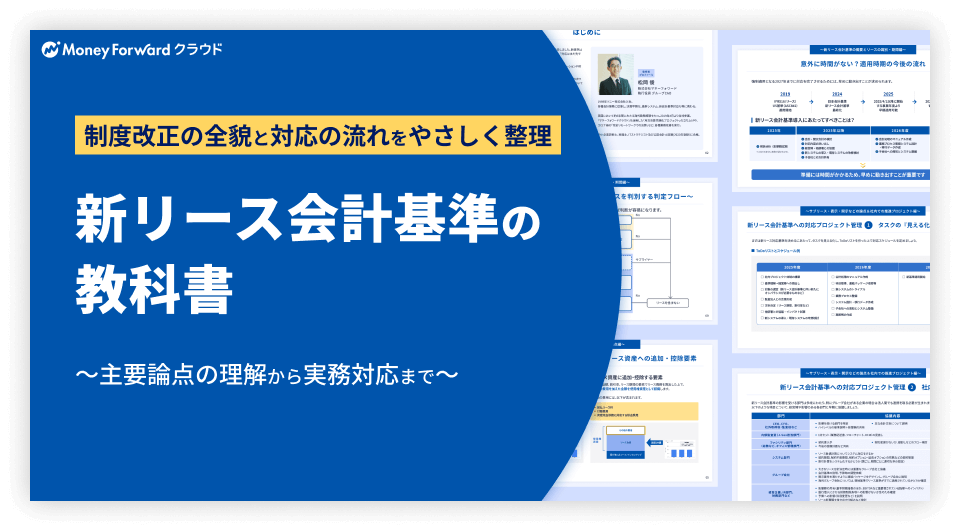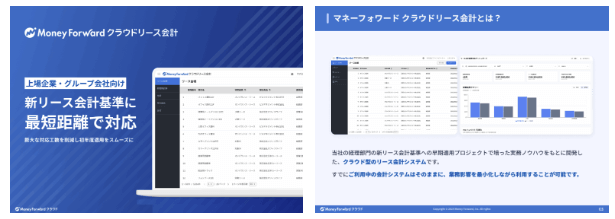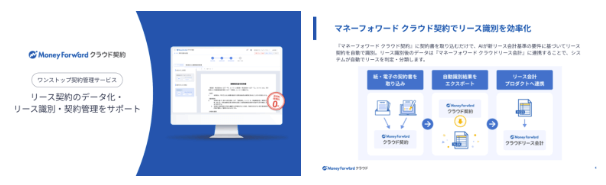- 更新日 : 2025年7月22日
【新リース会計基準】無形固定資産やソフトウェア、クラウドへの影響・実務対応は?
「新リース会計基準」が公表され、2027年4月1日以後に開始する事業年度からは、一部の企業に対して強制適用されることとなりました。
新リース会計基準では、従来の会計基準からリースの定義が見直され、リースの範囲が大きく拡大することが想定されます。
ここでは、新リース会計基準の概要や、ソフトウェア・クラウドサービスなどへの適用の要否について解説します。
目次
新リース会計基準とは?
2027年4月から強制適用が始まる新リース会計基準に向けて、対象企業は計画的な準備が求められます。
新リース会計基準の考え方や現行の会計基準との違いを正確に理解し、企業としての然るべき対応策を検討しましょう。
新リース会計基準の概要
新リース会計基準とは、2024年9月13日に企業会計基準委員会が公表した「リースに関する会計基準」および「リースに関する会計基準の摘要指針」の総称です。新リース会計基準導入の主な目的は、国際的な会計基準であるIFRS16との整合性を図ることです。
この新リース会計基準は、特に借り手側の会計処理を抜本的に変えるものです。従来のリース会計における「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の区分を廃止し、すべてのリースを「使用権の取得」と捉える新しい会計モデルを採用しています。
具体的には、原資産(リースの対象となる資産)の使用権を取得した際に、借り手側は「使用権資産」と「リース負債」をそれぞれ貸借対照表へ計上することになります。この新しい基準については、連結財務諸表だけでなく、個別財務諸表にも適用されます。
新リース会計基準は、2027年4月1日以降に開始する連結会計年度および事業年度の期首から強制適用が開始されます。また、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度や事業年度の期首から早期適用することも可能です。
現行の会計基準との比較
これまでのリース会計では、リース契約を「ファイナンス・リース」もしくは「オペレーティング・リース」に区別して、それぞれ異なる会計処理を行ってきました。
現行の会計基準において、ファイナンス・リースは、リース対象となる資産の実質的な購入であるとみなし、通常の売買取引に準じた方法による会計処理を基本としています。その一方でオペレーティング・リースについては、賃貸借取引とみなし、毎月支払うリース料を単純に費用計上する方法が採用されています。
それに対して新リース会計基準では、国際基準であるIFRS16に則って、借り手の立場においては、従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別を取り払っています。
つまり、すべてのリース契約について「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することになります。これまでは、オペレーティング・リースがオフバランスとされていましたが、状況が一変して、財務諸表の透明性が高まることが期待されています。
なお、資産計上された「使用権資産」は減価償却費、負債として計上された「リース負債」は、利息相当額がそれぞれ経費計上されることで、各事業年度に費用配分されます。
ただし、貸し手に関しては、従来どおり、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を維持することが認められています。
新リース会計基準におけるリースの定義
新リース会計基準におけるリースの定義は、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」とされています。
これは、従来の「資産の賃貸借」という定義から、「使用権の移転」に重点を置いた内容へ移行していることが伺えます。
また、IFRS16とのコンバージェンスを図るため、新リース会計基準では「特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約」の場合には、その契約にリースが含まれているとみなす必要があります。
したがって、新リース会計基準では、サプライヤーと顧客間で締結した契約の中身を確認し、契約の中にリースに該当するものが含まれているかどうかを識別しなければなりません。
リースを含む契約と認められる場合には、原則として借り手と貸し手は「リースを構成する部分」と「そうでない部分」に分けて会計処理を行うこととなります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準の教科書
新リース会計基準を理解するにはこの資料!
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
クラウドサービスやサブスクリプションビジネスに新リース会計基準は適用される?
ITツールやAIの発展が目覚ましい近年では、クラウドサービスやサブスクリプション型のサービスを導入する企業も少なくありません。
その一方で、新リース会計基準によって、それらのサービスが「リース」に該当する場合には、企業側の経理負担が増加することも予測されるため、慎重な対応が求められます。
契約に「リースが含まれるか」の判断基準
新リース会計基準は、必ずしも「リース契約」と称される取引だけでなく、クラウドサービスやサブスクリプションビジネスにも適用される可能性があります。
新基準を適用すべきかどうかを検討する場合には、杓子定規な考え方に基づいて判断するのではなく、個々の契約の内容を精査したうえで、契約内に「リースが含まれるか」を慎重に見極めることが重要です。
契約がリースに該当するかどうかについては、以下の2つのポイントに基づいて判断します。
- 経済的便益
顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか - 使用の指図
顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有しているか
これらの両方を満たす場合、その契約はリースを含むものと判断されます。反対に、クラウドサービスやサブスクリプションビジネスで使用する資産をサプライヤーが支配している場合には、その契約はリースではなく単なる「サービス契約」とみなされます。
なお、新リース会計基準では、契約がリースを含むかどうかについては、契約締結時に判断することとされています。契約期間中に契約条件が変更されない限り、リースの有無の判断を見直す必要はありません。
SaaSの場合の判断例
SaaS(Software as a Service)などのクラウドサービスでは、サプライヤーから顧客に対してソフトウェアへのアクセス権のみを提供する形態が一般的です。顧客はソフトウェア自体を所有したり、その使用方法を自由に決定したりする権利を持っていないため、リースには該当せず、単なるサービス契約とみなされるケースが多いでしょう。
具体的にはSaaS契約の場合、顧客はサプライヤーが管理・支配するクラウド基盤上のソフトウェアにアクセスする権利のみを有している状態が一般的です。ソフトウェアの更新時期や方法、稼働させるハードウェアの選択はサプライヤー側が行うため、顧客はソフトウェアの使用に関する意思決定権を持っていない状態と判断されます。
また、ソフトウェアのアクセス権限のみを有している場合には、そのソフトウェアによるサービスを支配している状態とも異なるため、無形固定資産にも該当しません。
ただし、クラウドサービスやサブスクリプションビジネスでは、IaaS(Infrastructure as a Service)やPaaS(Platform as a Service)など、取引形態も多様化しています。顧客がソフトウェアのカスタマイズや稼働環境を自由に選択できる場合など、顧客側がソフトウェアを実質的に支配しているとみなされるケースでは、リースに該当する可能性も十分に考えられます。
したがって、実務では、契約の名称で判断するのではなく、契約ごとに内容を精査し、リースや無形固定資産、サービス契約のどれに該当するのかについて慎重に見極めることが重要です。
実務上の注意点
新リース会計基準の導入によって、リースの識別に関する定めが新設されたことで、現行の会計基準ではリース契約に該当しなかった取引がリースに含まれる可能性も十分に考えられます。
特にクラウドサービスやサブスクリプションサービスでは、契約内容によって新リース会計基準の対象となる可能性も想定されるため、適用漏れが生じないように注意が必要です。
したがって、以下の手順に沿って、それらの契約がリースに該当するかどうかを慎重に判断し、リースに含まれる場合には新基準に基づいた会計処理を行いましょう。
- リースの識別
契約内容を詳細に分析し、「資産が特定されているか」や「その資産の支配権が顧客にあるか」を精査し、リースが含まれるか否かを判断します。 - リースを構成する部分とそれ以外の部分の区分
借り手と貸し手は、原則として、契約内容のうちリースを構成する部分と構成しない部分に分けて適切な会計処理を行う必要があります。このような考え方は、そのリース取引がファイナンス・リースとオペレーティング・リースのいずれに該当する場合でも共通です。ただし、簡便的な方法として、借り手に関しては、リース部分と非リース部分を区分せずに会計処理することも可能です。
ソフトウェアやその他の無形固定資産に新リース会計基準は適用される?
新リース会計基準では、リースの定義が見直されたことによって、現行の会計基準よりもリースの範囲が拡大します。
それによって、これまではリースに含まれなかった取引が新基準の下ではリースに該当するケースも増加するものと考えられます。
以下では、ソフトウェアやその他の無形固定資産に関して、新リース会計基準の適用対象に含めるべきかどうかについて確認しましょう。
新リース会計基準の適用除外とは?
新リース会計基準には、適用が除外される取引や資産が存在します。具体的には、以下の3つが適用除外とされています。
(1)実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第35号」という。)の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得
(2)企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)の範囲に含まれる貸手による知的財産のライセンスの供与。ただし、製造又は販売以外を事業とする貸手は、当該貸手による知的財産のライセンスの供与について本会計基準を適用することができる。
(3)鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生型資源を探査する又は使用する権利の取得
このうち、ソフトウェアの機能提供に関しては、2の「知的財産のライセンス供与」に含まれるものとされており、収益認識会計基準の範囲に含まれることから、新リース会計基準の対象範囲からは除かれています。
ソフトウェアや無形固定資産への適用は任意
ソフトウェアのライセンス供与に関しては、原則として新リース会計基準の対象範囲からは除外されています。
ただし、リース事業を営む企業のように、貸し手が製造業や販売業以外の事業を行う場合には、ソフトウェアの提供が利息相当額の獲得のための金融取引として活用されていることを考慮して、新リース会計基準を適用することも可能です。
また、その他の無形固定資産のリースについても、IFRS16との整合性の観点から、新基準を適用するかどうかはあくまで任意とされています。
新リース会計基準の実務対応で留意すべきポイント
新リース会計基準の強制適用を迎えるにあたって、各企業は新基準対応に向けた準備を整えることが必要不可欠です。
新基準の適用開始前に、以下の2つのポイントについて重点的に確認しましょう。
既存の契約内容の確認
新リース会計基準によって、ファイナンス・リースだけでなく、オペレーティング・リースについてもオンバランス化が求められます。そのため、オペレーティング・リースの既契約分がある場合には、新基準への対応が欠かせません。
また、新基準ではリースの定義や識別方法が見直されたため、既存の取引契約においても、新たにリースとみなされるケースもあるでしょう。そこで、まずは既存の契約内容を精査して、新基準の下でリースに該当するかどうかを検証することが重要です。
特に、不動産賃貸借契約やレンタル契約などについても、新基準ではリース取引に該当する可能性があるため注意が必要です。
さらに、契約内容に関しては、リース部分と非リース部分の分類や、リース期間および延長・解約オプションの有無についても確認が必要です。新基準の内容を正確に理解したうえで、慎重に対応しましょう。
会計システムの対応
新リース会計基準では、オペレーティング・リースも含めて使用権資産とリース負債を計上する必要があるため、既存の会計システムのままでは対応できない可能性があります。
新基準に対応するためには、使用権資産やリース負債、減価償却費、利息費用などの自動計算を行い、月次や決算時の会計処理を効率化することが重要です。また、短期リースや少額リースに関する簡便的な会計処理にも対応するなど、柔軟な経理システムの構築が望ましいです。
さらに、新リース会計基準では、財務諸表の注記事項も複雑化しているため、新基準に基づいた記載項目を正確に作成できるよう、必要な情報をスムーズに集計できる機能も求められるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新リース会計の関連記事
新着記事
法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の種類を体系的に整理し、それぞれの税率や計算の仕組み、さらには…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率を知ることです。 本記事では、会社の規模による法人税率の違い…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引