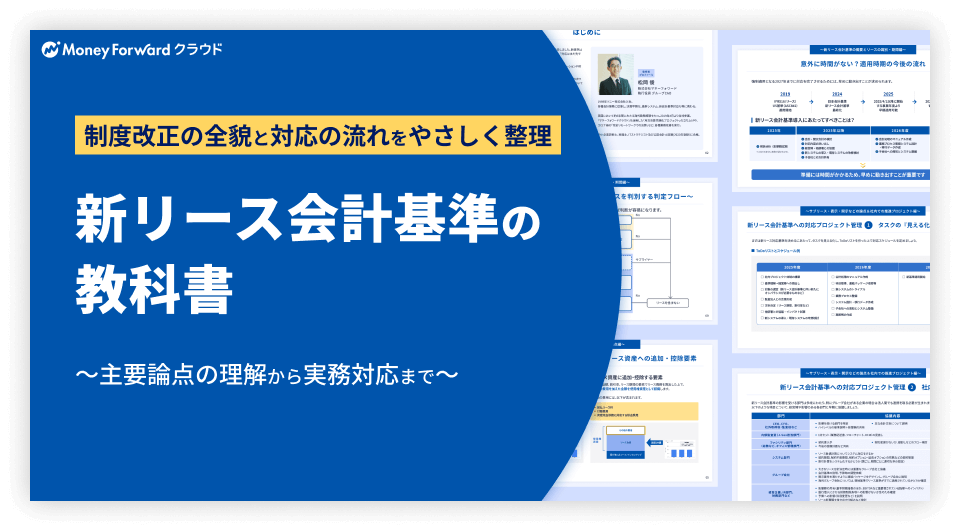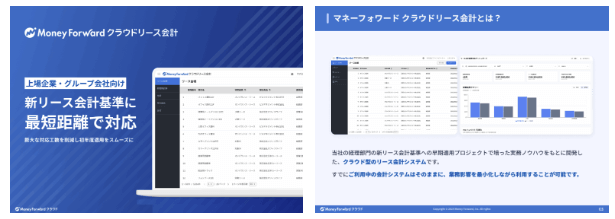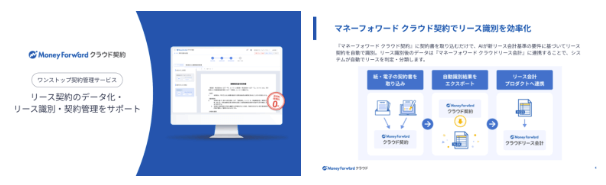- 更新日 : 2025年11月12日
購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性があるため、資金繰り改善を目的に導入されるケースもあります。
この記事では、購入選択権付リースの基本的な仕組みから、他のリースとの違い、会計処理や税務上の取り扱い、そして契約前に知っておくべきメリット・デメリットまでわかりやすく解説します。
目次
購入選択権付リースとは?
購入選択権付リースとは、リース契約の一種で、契約期間満了時にリースしていた物件(資産)を借主が購入する権利(オプション)を持つ取引のことです。これにより、利用者は資産を「返却」「再リース」に加えて「購入」するという第三の選択肢を得られます。
通常のリースでは、契約期間が終了すると物件をリース会社に返却するか、再リース契約を結ぶのが一般的です。しかし、この買取選択権付リースでは、一定期間資産を利用した上で、その価値や事業への貢献度を完全に見極めてから所有するかどうかを最終判断できます。そのため、高額な設備投資のリスクを低減しつつ、本当に必要な資産だけを効率的に確保することが可能になります。特に、IT機器や特殊設備は購入選択権付リースの活用が多い分野とされています。
ファイナンス・リース取引との違い
ファイナンス・リースは、実質的に資産の所有に伴うリスクと経済的利益が借手に移転するリースを指します。他方、購入選択権付リースは、リース期間終了時にリース資産をあらかじめ定められた価格で購入できる権利(購入選択権)が付いたリース契約をいいます。両社は違った観点での分類になりますが、購入選択権付リースは、一般的にはファイナンス・リースの一形態と考えられています。
ファイナンス・リースとは、分割払いによる資産購入と同等の経済的実質をもつリース形態であり、「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」の2種類に区分されます。購入選択権付リースにおいてその権利行使が確実なものは、会計上・税務上は原則として「所有権移転ファイナンス・リース」として扱われます。
オペレーティング・リース取引との違い
オペレーティング・リースとの違いは、資産利用の目的にあります。購入選択権付リースが将来の資産所有を視野に入れた長期的な利用を目的とするのに対し、オペレーティング・リースはレンタルに近い短期的な資産利用を目的としています。
オペレーティング・リースは、リース会社が物件の残存価額を高く設定することで月々の支払いを抑える場合が多いのが特徴です。一方、購入選択権付リースは、最終的に所有する可能性を前提としており、資産を長期にわたって利用することを想定しているため、契約期間や会計・税務上の取り扱いが大きく異なります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準の教科書
新リース会計基準を理解するにはこの資料!
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
購入選択権付リースを利用するメリットは?
購入選択権付リースには、初期投資の抑制、税務上の恩恵、柔軟な意思決定など、企業経営において多くのメリットがあります。
初期投資を抑えつつ将来の所有が可能になる
最大のメリットは、多額の初期費用を用意することなく必要な資産を導入でき、将来的に自己資産にできる点です。設備や車両を一括で購入する場合に発生する大きなキャッシュアウトを防ぎ、企業の資金繰りを安定させることができます。
特に、創業期のスタートアップや大規模な設備投資を行う製造業などにとって、手元資金を温存できることは事業の安定と成長に直結します。購入選択権付リースを活用すれば、資金を運転資金や他の成長分野への投資に回しつつ、事業に必要な高性能な資産を利用し、事業が軌道に乗った段階で購入を検討するという、戦略的な財務運営が可能になります。
資産価値を見極めてから購入を判断できる
リース期間中に資産の実際の性能や陳腐化のリスクを評価し、合理的な判断のもとで購入を決定できることも大きな利点です。特に技術の進歩が速い分野では、数年後には資産価値が大きく下落するリスクが伴います。
例えば、最新鋭の工作機械を導入した場合でも、契約満了時に「当初の予定通り購入する」「価値が下がったので返却し、新しいモデルを再リースする」といった柔軟な選択が可能です。この「待てる」という選択肢は、不確実性の高い現代の経営環境において大きな強みとなります。
リース期間や残価設定の交渉が可能になる
契約内容にもよりますが、リース期間やリース期間満了時の購入権行使価額(残価)について、リース会社と交渉できる場合があります。事業計画に合わせてリース期間を法定耐用年数より短く設定したり、将来の市場価値を予測して有利な条件で残価を設定したりすることで、より柔軟な資産計画を立てることが可能です。
購入選択権付リースのデメリットや注意点は?
メリットの多い購入選択権付リースですが、総支払額や会計処理の複雑さなど、契約前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。
原則として中途解約ができない
購入選択権付リースは通常、ファイナンス・リースに該当しますが、ファイナンス・リース契約は原則として契約期間中の解約が認められていません。リース契約は、リース会社が借主のために物件を購入し、その代金とコストをリース期間全体で回収する仕組みだからです。
万が一、事業内容の変更などでリース物件が不要になった場合でも、残りのリース料全額に相当する違約金(解約損害金)を支払う必要があります。契約を結ぶ際には、事業計画を慎重に検討し、契約期間を通じてその資産が本当に必要かどうかを見極めることが極めて重要です。
総支払額が割高になる可能性がある
リース料にはリース会社の金利や手数料などが含まれるため、一括で購入する場合と比較して総支払額は高くなるのが一般的です。最終的に購入権を行使した場合の支払総額は、現金での一括購入よりも割高になります。
ただし、この差額は、初期投資を抑え、支払いを平準化するための「金融コスト」と捉えることができます。単に総支払額の大小だけでなく、資金繰りの安定化や手元資金を他の投資に活用できる機会利益なども含めて、総合的に判断する必要があります。
会計処理・税務処理が複雑になるケースがある
購入選択権付リースは通常、ファイナンス・リースに該当し、会計・税務上「売買取引」として扱われるため、資産計上や減価償却といった複雑な処理が必要です。単にリース料を費用として計上するだけのオペレーティング・リースとは異なり、貸借対照表(B/S)への資産・負債の計上が求められます。
リース開始時の仕訳、決算時の減価償却計算、リース料支払時の仕訳など、経理担当者には専門的な知識が求められます。顧問税理士などと連携し、適切な処理を行う体制を整えることが重要です。
購入選択権付リースの会計処理と仕訳例
購入選択権付リースは、その権利行使が確実なものは「所有権移転ファイナンス・リース取引」に該当し、売買取引に準じた会計処理が行われます。
1. リース資産・負債の計上
まず、リース取引を開始した時点で、リース資産の見積現金購入価額と、将来支払うリース料総額の現在価値のうち、いずれか低い方の金額で資産と負債の両建てで計上します。
例:リース資産の見積現金購入価額が3,000,000円、リース料総額の現在価値が3,200,000円の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 3,000,000円 | リース債務 | 3,000,000円 |
2. 減価償却の計算方法
次に、計上したリース資産は、自己所有の固定資産と同様の方法で、定められた耐用年数にわたって減価償却を行います。
例:耐用年数5年(定額法の償却率0.2)、定額法で償却する場合(残存価額ゼロ)
決算期に、この600,000円を減価償却費として費用計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 600,000円 | リース資産減価償却累計額 | 600,000円 |
3. リース料支払時の仕訳
毎月(または毎年)のリース料支払時には、負債として計上したリース債務を取り崩します。
例:年間リース料が650,000円(元本相当600,000円、利息相当50,000円)の場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース債務 | 600,000円 | 現金預金 | 650,000円 |
| 支払利息 | 50,000円 | ||
4. 購入権を行使した場合の会計処理
リース期間満了時に購入権を行使し、物件を購入した場合、リース資産を正式な固定資産勘定に振り替えます。
例:購入権行使価額10万円を支払った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 機械装置 | 100,000円 | 現金預金 | 100,000円 |
※上記は簡略化した仕訳例です。実際の処理は契約内容や企業の会計方針により異なりますので、必ず専門家にご確認ください。
購入選択権付リースの利用がおすすめのケース
購入選択権付リースは、特定のニーズや状況を持つ企業・個人事業主にとって、非常に有効な資産導入手段となります。 特に、以下のようなケースでおすすめです。
最新設備を試してから導入を決めたい企業
技術革新のスピードが速い業界で、高額な最新設備を導入する際に、まずはリースで試用し、性能や費用対効果を実証してから購入を決定したい場合に最適です。
IT関連機器、医療機器、研究開発用の測定器などは、数年で陳腐化するリスクがあります。購入選択権付リースであれば、一定期間利用してその価値を完全に見極めた上で、長期的に利用価値があると判断した場合にのみ購入に踏み切ることができます。
将来的に事業拡大を見込むスタートアップ企業
創業当初で資金的な余裕はないものの、将来の事業拡大を見越して高性能な資産を確保しておきたいスタートアップ企業に適しています。
手元資金を温存し、事業の運転資金に充てながら、事業の成長に必要な生産設備や業務用車両などを利用できます。そして、事業が軌道に乗り、収益が安定した段階で購入権を行使して自己資産化することで、財務体質の強化を図ることが可能です。
中古車など、状態を見極めてから購入したい個人事業主
特に中古の資産(例:中古トラック、中古重機)を導入する場合、個体ごとの品質のばらつきが懸念されます。リース期間中に実際の稼働状況やメンテナンス履歴を確認し、問題がないことを確かめてから購入できるため、購入後のトラブルリスクを軽減できる場合があります。
購入選択権付リースを理解し、賢く資産を導入しよう
本記事では、購入選択権付リースの仕組みからメリット・デメリット、具体的な会計処理に至るまでを詳しく解説しました。このリース手法は、初期投資を抑えつつ事業に必要な資産を導入し、将来的に所有する選択肢も残せる手法です。
ただし、総支払額が割高になる可能性や、会計処理の複雑さといった側面も理解しておく必要があります。自社の事業計画や財務状況を十分に考慮し、購入選択権付リースの特性を深く理解した上で、最適な資産導入の方法を選択することが、持続的な企業成長の鍵となるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
軽量鉄骨の耐用年数や減価償却費計算を詳しく解説
軽量鉄骨は、その用途や鉄骨の厚みによって耐用年数が変化します。購入する際には、事前に耐用年数を確認しておくことが必須です。本記事では、軽量鉄骨の建物の耐用年数や減価償却費の計算方法…
詳しくみる償却保証額とは?減価償却の定率法との関係や計算方法をわかりやすく解説
償却保証額は、定率法の減価償却で最低限確保すべき基準額です。定率法はもうひとつの減価償却の手法である定額法と比較すると計算が複雑になりやすいため、償却保証額などについてわかりにくさ…
詳しくみる楽器の耐用年数と減価償却費計算を解説
楽器は時間の経過とともに価値が減少する減価償却資産であるため、減価償却が必要です。本記事では、楽器の減価償却費の計算方法や仕訳について解説します。耐用年数についても解説しているので…
詳しくみる固定資産税(償却資産)の減価償却を正しく理解していますか?減価償却の国税と地方税の違いとは
10万円以上の資産を購入すると、減価償却により購入価額を期間按分します。 ただし、国税(法人税等)と地方税(固定資産税)では償却額に差が生じることをご存知でしたか? 今回は、それぞ…
詳しくみる固定資産の減損に係る会計基準とは?金融庁の最新情報をわかりやすく解説
固定資産の減損に係る会計基準とは、固定資産の減損損失を計上するときのプロセスを定めた会計基準のことです。財務諸表の正確性を保つため、基準が設けられています。対象となるのは、有形固定…
詳しくみる固定資産の取得価額と減価償却の基本を解説
固定資産は、取得価額をもとに減価償却(取得価額を耐用年数にわたって資産から費用に計上していくこと)を行います。固定資産の取得時には、本体価格だけでなくさまざまな費用がかかるのが一般…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引