- 更新日 : 2026年2月18日
振込手数料がかからない方法とは?振込方法や注意点を徹底解説!
会社の規模が大きく振込機会が増えると、振込手数料も相応の負担です。また、個人でも振込回数が多くなると、負担が大きくなっていきます。
なるべく手数料をかけたくないけれど、どの方法が良いのかわからない…と感じていませんか。本記事を読むことで、振込手数料がかからない方法や、おすすめの口座・サービスが明確になります。
本記事では、
- 振込手数料が発生する仕組み
- 振込手数料を削減できる方法
- 利用目的別のおすすめパターン
について解説しています。振込にかかる無駄なコストを減らし、業務効率もアップさせたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
振込手数料がかからない方法はあるのか?振込手数料が発生する仕組み
振込手数料がかからない方法は少ないですが、存在します。本章では、振込手数料の基本的な概要や仕組みと種類について解説します。
振込手数料とは?
振込手数料とは、銀行間でのお金のやり取りにかかるサービス利用料です。振込を行う際、利用している銀行から相手の銀行へ資金を動かすために、手数料が発生します。
振込手数料は、原則として振込を行う側(支払う側)が負担します。ただし、双方の合意があれば、受け取る側が負担する場合もあります。
振込手数料の相場は?
振込手数料の相場は、利用する銀行や振込方法、金額、振込先によって大きく異なります。特に、窓口、ATM、インターネットバンキングの3種類では料金体系が大きく変動します。
窓口での振込は手数料が最も高額になる傾向があり、他行宛の振込では3万円未満で600円台から、3万円以上で700円台からが相場です。なお、近年では振込金額に関係なく、一律に振込料を定める銀行も増えてきました。
ATMでの振込は窓口よりも安く、他行宛の現金振込では3万円未満で300円台〜、3万円以上で500円台〜が目安です。キャッシュカードを利用すると現金振込よりも安くなることがあります。
最も手数料を抑えられるのはインターネットバンキングです。多くの金融機関で、他行宛振込が100円台、あるいは特定の条件を満たすと無料になるサービスも提供されています。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
請求業務50倍でも1名で対応!売上増加を支える経理効率化の秘訣
債権管理・請求業務効率化が必要と言われも日常業務に追われていて、なかなか改善に向けて動けないというご担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本ガイドでは、請求業務の効率化が必要なのか・効率化することで本業に集中することで得られるメリットを詳しくご紹介しています。
経理担当者向け!Chat GPTの活用アイデア・プロンプトまとめ12選
債権管理担当者や経理担当者がChat GPTをどのように活用できるか、主なアイデアを12選まとめた人気のガイドです。
プロンプトと出力内容も掲載しており、コピペで簡単に試すことも可能です。お手元における保存版としてでだけでなく、従業員への印刷・配布用としてもぜひご活用ください。
経理担当者向け!Excel関数集 まとめブック
経理担当者の方をはじめ、ビジネスパーソンが知っておきたい便利なExcel関数集を初級~上級までギュッと網羅。
新人社員の研修用などにもお使いいただけます。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。
会計士監修!簿記の教科書
簿記のキホンについて最低限知っておきたい情報をギュッとまとめた保存版のガイドです。
仕訳例や勘定科目がついており、はじめての方でもイメージをつけながら読むことができるようになっています。
振込手数料がかからない方法3選
振込手数料がかからない方法を3選紹介します。ただ、振込手数料がかからない=振込手数料が無料になる方法は少なく、手数料を抑える方法を実践的に活用することで、コストの節約が可能です。以下に主な方法を紹介します。
1. 取引先に口座を合わせてもらう
同一金融機関への振込であれば、多くの銀行で手数料が無料です。取引先に自社と同じ銀行・支店の口座を開いてもらうことができれば、月数万円のコスト削減も可能です。
特に振込件数が多い企業にとっては、1件あたり数百円の手数料が積み重なり大きな負担となるため、口座を揃えるだけで経費削減の効果があります。
さらに、同銀行内であれば振込反映も即時に行われる場合が多く、資金管理のスピードや安心感といった面もメリットです。
2. 取引先に合わせて自社支払口座を新設する
取引先が特定の銀行を指定している場合、自社側でも取引先の銀行と同じ銀行口座を新しく開設することで、同一金融機関となり手数料が無料にできます。
特に大口の支払いがある取引先や、継続的に支払いが発生するパートナー企業に対しては非常に効果的です。
複数の銀行に口座を持つことは一見手間のように思えますが、実際にはネットバンキングで一元管理できるため運用も難しくありません。小さな工夫で手数料分の無駄をなくし、長期的なコスト削減に直結します。
3. 社員の給与振込口座を同銀行かつ同支店にする
社員の給与振込にかかる手数料も、同じ銀行、かつ同じ支店に統一することで、振込手数料が無料になる場合があります。無料とならなくても、他行宛に比べて低額に抑えられるケースが多いため、経費削減の効果は十分に期待できるでしょう。
社員にとっても同銀行を利用することで即時に給与が反映されるメリットがあり、利便性の向上にもつながります。導入にあたっては社員への説明や同意が必要ですが、企業・従業員双方にメリットがある方法として検討に値します。
振込手数料を削減できる方法3選
振込手数料を完全に無料にするのは難しいものの、工夫次第で手数料を抑えることは可能です。本章では、頻繁な振込業務を担う中小企業や個人事業主に向けて、実際に活用しやすい3つの方法を具体的に紹介します。
1. 振込代行サービスを利用する
振込代行サービスを利用すると、複数の振込をまとめて業者に一括で依頼できるため、銀行への振込件数を減らし、結果的に振込手数料を大幅に削減できます。
特に月に数十件〜数百件といった大量の支払いが発生する企業では、1件あたり300円程度の手数料が積み重なると年間数十万円単位のコスト差につながるため、導入効果は大きいといえます。
一方で、サービス利用時には業者の信頼性や資金管理の仕組みをしっかり確認しておくことが重要です。振込資金を一時的に業者に預ける必要がある場合もあり、残金を預けっぱなしにできない点も注意が必要です。
2. パーチェシングカードを利用する
パーチェシングカードは、取引先や仕入先への複数の支払いを一旦カード会社に集約し、月に一度カード会社へまとめて支払う仕組みです。個別の振込が不要になり、振込手数料を削減できるだけでなく、支払い処理がシンプルになります。
たとえば、毎月30件の外注費や仕入代金をそれぞれ銀行振込で処理していた場合、1件300円とすると、月9,000円、年間では10万円以上のコストになります。
パーチェシングカードを活用すれば、カード会社への支払いは月1回のみで済むため、振込手数料の大幅削減が可能です。
ただし、利用できる取引先が限られる場合もあるため、カード払いに対応しているか事前に確認することが導入のポイントとなります。
3. 振込手数料が安いネット系法人口座を活用する
ネット系銀行の法人口座は、他行宛でも数百円から、場合によっては100円台で振込できるケースもあり、振込件数が多い企業にとって大きな節約効果が期待できます。
さらに、ネット銀行はAPI連携やCSVアップロード機能が充実しており、会計ソフトや給与計算システムと自動連携できることが多いため、手作業による入力が不要になり、業務効率化にも直結します。
ただし、ネット銀行は窓口対応がないため、現金の取り扱いが多い業種ではメインバンクとの併用が必要です。用途に応じて、既存の銀行とネット銀行を組み合わせて活用するのが現実的な運用方法といえます。
振込手段の選定とリスク管理
振込業務には複数の手段があり、手数料・操作性・速度・運用コストなどそれぞれにメリット・デメリットがあります。
自社の振込状況や体制に合った選び方をすることは、コストの無駄を防ぎ、トラブルのリスクを最小限に抑えるうえで非常に重要です。本章では、適切な振込手段の選び方と、内部統制やリスク対策のポイントを具体的に解説します。
各振込方法の特徴を理解する
振込方法によってコスト構造や操作性、入金スピードなどが大きく異なる点を把握しましょう。たとえば、ネットバンキングは窓口よりも手数料が安く済む一方、操作に不慣れな場合には入力ミスの懸念があります。
また、使用する金融機関やサービスによっては月額固定費が発生する場合や、CSV一括処理に対応しているか否かで作業負荷も変わってきます。仕様や制約を、自社の振込件数や頻度などと照らし合わせて、最適な手段を選定することが大切です。
振込ミスや誤送金を防止する
入力ミスや名義不一致による誤送金トラブルは、対応に多くの時間と信用リスクが伴います。トラブルを未然に防止するために、振込前に複数人による承認フローや二重チェック体制を整えることが不可欠です。
また、銀行によっては振込エラーを自動検知する機能が用意されており、システム連携できる会計ソフトや専用ツールを導入すれば、より精度を高めることが可能です。
トラブルを防ぐ工夫は作業者の負担軽減にもつながり、日常的なミス防止の習慣化を後押しします。
社内のセキュリティと権限を適切に管理する
ネットバンキングは便利な反面、ID・パスワードの漏洩や不正アクセスなど、セキュリティ面での注意も必要です。多要素認証やワンタイムパスワードの採用、振込作業者と承認者の権限分離など、アクセス管理の適切化が基本です。
また、万が一の不正送金に備えて、利用する銀行・システムの補償範囲を事前に確認しておくことも重要です。さらに、従業員への定期的なセキュリティ教育を実施することで、リスク意識を全社的に高めることができます。
トラブル時の対応フローを整備する
システム障害やネットバンクのトラブル時に振込ができなくなるリスクもあります。トラブル時のリスクを軽減するためにも、複数の振込経路(たとえばメインバンクとサブ口座)を持ち、代替手段を用意しておくことで柔軟に対応できます。
また、誤送金時には即時に連絡・確認が取れる銀行窓口や責任者の連絡先を明確にし、社内で対応マニュアルや連絡フローを共有しておくことが必要です。
さらに、定期的にシミュレーションを実施しておくと、いざという時の行動がスムーズになります。
振込手数料がかからない方法に関するよくある質問3選
中小企業の会計担当者やフリーランスの方々からよく寄せられる疑問を3つ厳選し、それぞれについて実務的な視点で解説します。大口振込のコスト、頻繁な振込の負担、トラブル時の対応の3点を順に解説します。
Q1:100万円以上の振込手数料はいくらですか?
100万円以上の高額振込にかかる手数料は、利用する銀行や振込手段によって大きく異なります。都市銀行(例:三井住友銀行、三菱UFJ銀行など)では、振込金額に関係なく、窓口での他行宛だと法人口座で600〜1,000円程度かかることが一般的です。
ATMを利用すると手数料は抑えられますが、ネット銀行なら法人口座の他行振込でも100円台〜200円台という場合もあり、特に低コストで済ませられるという点で注目されています。
Q2:月に複数件の振込でも無料にできますか?
少額とはいえ1回ごとに300円程度かかると、月に100件以上の振込業務では手数料が膨らみます。完全無料にするのは難しいですが、ネット銀行を活用することで他行宛振込でも1件150円程度まで下げられる可能性があります。
ただし、月数回のような回数限定で無料になるケースはあるものの、すべての振込を無料にすることは現実的ではありません。振込件数が多い業務の場合は、件数に応じた振込コストの総額と効率も視野に入れて対策を検討する必要があります。
Q3:振込ミスやトラブル時の対応はどうなっていますか?
誤送金や金額間違いなどの振込トラブルは、発生後の対応が迅速・丁寧であるかが信頼性に直結します。多くの銀行では、組戻し処理が可能で振込後すぐに連絡すれば返金対応が受けられることもあります。
また、電話やチャットなどのサポート体制の有無や、誤送金の金額や口座情報などを迅速に提示できるシステムの有無も重要な選定ポイントです。
併せて、会計ソフトとの連携で操作履歴が追える仕組みや、振込前チェック機能があるサービスを選ぶことで、トラブルを未然に防ぐ安心体制を築くことも有効です。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
最後までこの記事をお読みの方に人気のガイド4選
最後に、ここまでこの記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。こちらもすべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
インボイス制度 徹底解説(2024/10最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025年10月 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
マネーフォワード クラウド請求書Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド請求書Plusは、営業事務・経理担当者の請求業務をラクにするクラウド型請求書発行システムです。
作成した請求書はワンクリックで申請・承認・送付できます。一括操作も完備し、工数を削減できます。
マネーフォワード クラウド債権管理 サービス資料
マネーフォワード クラウド債権管理は、入金消込・債権残高管理から滞留督促管理まで、 広くカバーする特定業務特化型のクラウドサービスです。
他社の販売管理システムと連携して、消込部分のみでのご利用ももちろん可能です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
定額課金とは?従量課金、継続課金との違いを解説
定額課金は、近年注目を集めているビジネスモデルの一つです。一定期間ごとに固定料金を支払うことで、サービスやコンテンツを利用できる仕組みです。従量課金や継続課金とは異なり、消費者・企…
詳しくみるスループット会計とは|会社の利益を最大化する戦略を解説
「スループット会計とはどのようなものだろう」「原価計算とどこが違うか知りたい」 このような疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。 スループット会計は、自社のボトルネックに注目し、…
詳しくみる集金代行会社とは?選び方、メリット、活用事例について徹底解説
集金代行会社とは集金代行会社は、企業や個人事業主がスムーズに資金回収を行うために利用するサービスです。集金代行を利用することで、煩雑な入金確認や未払い対策の手間が軽減し、業務を効率…
詳しくみる約束手形の支払期日は60日に短縮!当日持ち込みの方法や3営業日を過ぎた場合の対応も解説
約束手形は日本の企業間取引で広く使われていますが、その取り扱いを誤ると資金繰りや信用に大きな問題が生じます。特に、支払期日のルールや銀行への持ち込み手続きを正確に理解しておかないと…
詳しくみる与信管理の方法を解説!理想的な与信管理のコツや与信とは何かを紹介
掛取引を行う上で重要となるのが、取引先の与信管理です。 理想的な与信管理とは、すべての取引状況を正しく把握し、与信リスクを定期的に見直しながら適切に管理をすること です。 本記事で…
詳しくみる流動資産とは?主な種類とチェックポイント
簿記上における「資産」には種類があり「流動資産」「固定資産」「繰延資産」の3つで構成されています。中でも流動資産については、その意味や対象を正しく理解できている方は意外と多くないか…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引
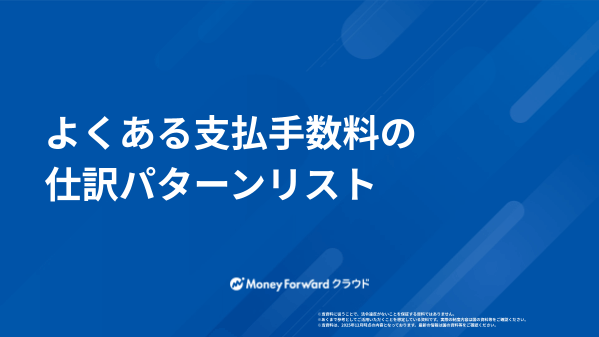






.png)

