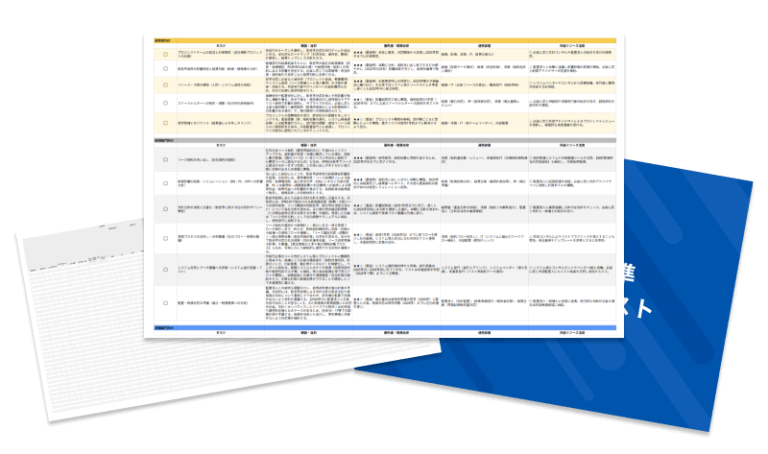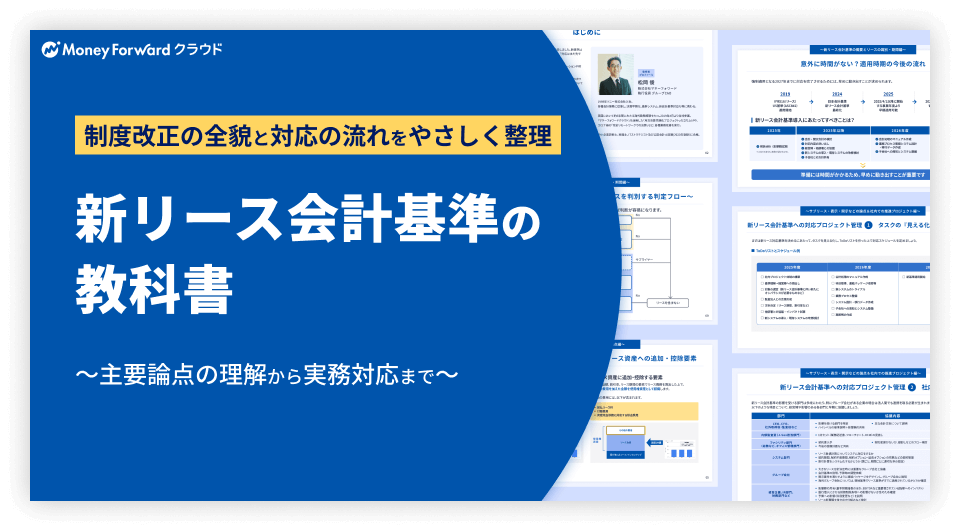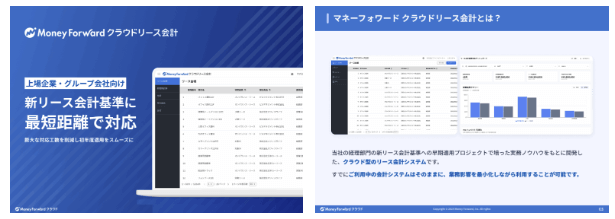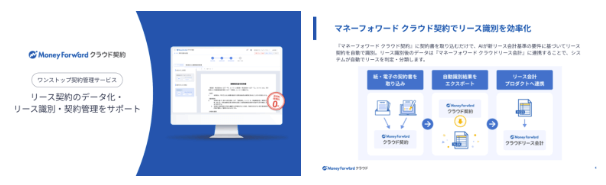- 更新日 : 2025年12月30日
隠れリースとは?新リース会計基準で知っておくべきポイント
「隠れリース」とは、契約書上は「リース」という名称ではないものの、その経済的実態が新基準のリースの定義に合致する契約を指します。これには、従来サービス契約や業務委託契約として処理されてきた多種多様な契約が含まれる可能性があり、その特定と評価は極めて複雑かつ資源を要する作業となります。
本基準の適用は、企業の財務諸表に甚大な影響を及ぼします。資産と負債の同時計上による貸借対照表の拡大(いわゆる「グロスアップ」)は、自己資本比率や総資産利益率(ROA)などの主要な財務指標を悪化させる可能性があります。
一方で、損益計算書上では、従来の賃借料が減価償却費と支払利息に置き換わることで、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)が見かけ上増加するという、一見して直感に反する影響も生じます。
目次
隠れリースとは?
「隠れリース」という用語は、法的な形式や契約書の名称が「リース」ではないにもかかわらず、その経済的実態が新基準におけるリースの定義に合致する契約を指すものです。
旧基準下では、企業はファイナンス・リースの判定の数値基準を回避するように契約を設計することが可能でした。例えば、契約を「サービス契約」「業務委託契約」「アウトソーシング契約」といった名目にすることで、実質的には特定の資産を長期間使用する権利を得ていても、会計上はオペレーティング・リースとしてオフバランス処理することができました。
リースとして再評価され、資産・負債として計上される対象となりうる
しかし、新基準が導入する「使用権モデル」に基づく原則的アプローチは、契約の形式的な名称を問わず、経済的実態を評価することを要求します。これにより、これまで単純な営業費用として処理されてきた膨大な数の契約が、リースとして再評価され、資産・負債として計上される対象となりうるのです。
この会計基準の変更は、投資家やアナリストからの長年の要求に応える形で進められました。彼らは、オペレーティング・リースという名のオフバランス・ファイナンスが、企業の真のレバレッジやリスク・プロファイルを覆い隠していると主張してきました。投資家は、財務諸表の注記情報から企業のリース債務を独自に推計する必要があり、企業間の比較可能性を著しく損なっていました。新基準は、企業が解約不能な資産使用の対価を支払う義務を負っているならば、その義務は負債であり、それによって得られる使用する権利は資産であるという、経済的実態に即した考え方を強制します。
したがって、「隠れリース」の問題は、新たな現象ではなく、これまで会計基準が見過ごしてきた経済的実態が、透明性向上の要請によってついに財務諸表上に可視化されるプロセスそのものなのです。
この記事をお読みの方におすすめのガイド3選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
新リース会計基準の教科書
新リース会計基準を理解するにはこの資料!
新リース会計基準への対応を進めるにあたって「何を」「どのように」運用変更する必要があるか、基礎から実務まで、じっくり見直すことができます。
新リース会計基準に最短距離で対応するなら?
2027年度から適用される新リース会計基準に対応した、クラウド型のリース会計システムです。すでにご利用中の会計システムはそのままに、業務影響を最小化しながら利用することが可能です。
本資料では、特長や各種機能についてご紹介いたします。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理、大丈夫ですか?
リース契約の洗い出しに時間がとられていませんか?
マネーフォワード クラウド契約なら、契約書を取り込むだけでAIが新リース会計基準の要件に基づいてリース契約を自動で識別。
リース契約のデータ化・リース識別・契約管理をサポートします。既存のシステムとも連携してご利用いただけますので、他社会計システムや固定資産管理システムをご利⽤の企業もお気軽にご相談ください。
隠れリースの定義と発見手法の詳細は?
新リース会計基準への対応における最も重要かつ判断を要するプロセスは、既存および新規のすべての契約を精査し、新基準におけるリースの定義に該当するか否かを判定することです。
このセクションでは、その技術的なフレームワークと実務的な指針を詳述します。
1 中核原則:特定された資産の支配
ある契約がリースを含むかどうかは、その契約が「特定された資産」の使用を「支配する権利」を顧客に移転するかどうかによって決まります。この判定は、以下の二つの重要な問いに、いずれも肯定的に答えられるかどうかに集約されます。
- 契約に「特定された資産」は存在しますか?
- 顧客はその資産の使用を「支配する権利」を有していますか?
2 判定基準1:「特定された資産」テスト
資産がリース対象となるためには、契約において明示的または黙示的に特定されている必要があります。これは、シリアル番号、資産の物理的な所在地、あるいはその他の固有の識別子によって示されます。
ここで極めて重要な役割を果たすのが、供給者の「代替権」の評価です。供給者が使用期間を通じて、その資産を実質的に代替する権利を有している場合、その資産は「特定された資産」とは見なされません。
代替権が「実質的」であると判断されるためには、供給者が資産を代替する「実行可能性」と、代替によって利益を得る「経済的インセンティブ」の両方を備えている必要があります。これは非常に高いハードルです。例えば、資産の修理やメンテナンスのために一時的に代替する権利は、実質的な代替権とは見なされません。また、代替に際して顧客の同意を必要とするような契約条項も、供給者の代替権が実質的ではないことを示唆します。
具体例として、データセンター契約を考えてみましょう。特定のシリアル番号が付されたサーバーラックを顧客が専有的に使用する契約は「特定された資産」が存在する可能性が高いです。一方で、標準的なクラウド・コンピューティング・サービスのように、供給者が負荷状況に応じて多数のサーバー群の中から動的にリソースを割り当てる契約では、顧客が使用する物理的資産が特定されていないため、リースには該当しません。
3 判定基準2:「支配する権利」テスト
特定された資産が存在する場合、次に顧客がその資産の使用を支配する権利を有しているかを評価する必要があります。この「支配」は、以下の二つの要素が同時に満たされることで成立します。
- 資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利: これは、顧客がその資産が生み出す便益(製品、サービス、キャッシュ・フローなど)の主要な享受者であることを意味します。
- 資産の使用を指図する権利: これがしばしば決定的な要因となります。顧客が使用期間を通じて、資産を「どのように」そして「何の目的で」使用するかを決定できる場合、顧客は使用を指図する権利を有していると判断されます。
この分析の焦点は、資産の使用に関する重要な意思決定を誰が行うかにあります。もし顧客がこれらの意思決定を行うのであれば、顧客が支配していることになります。たとえ供給者が資産を操作するとしても、その操作方法が契約や顧客の指示によってあらかじめ定められている場合には、実質的な支配権は顧客にあると見なされる可能性があります。
4 リースとサービス契約の境界線
新基準は、企業に対して、資産の調達(リース)と、成果物の調達(サービス)とを明確に区別することを強います。サービス契約と判定された場合、新リース会計基準の適用対象外となり、引き続きオフバランス処理が継続されます。
この判断は、データセンター利用契約、製造委託契約、輸送サービス契約など、特定の資産の使用が不可欠なサービスにおいて極めて重要となります。
この基準の導入は、会計部門の役割を、過去の取引を記録する「スコアキーパー」から、調達や契約プロセスの段階から関与する「プロアクティブなビジネスパートナー」へと変貌させます。なぜなら、供給者の代替権が「実質的」かどうかの判断には、供給者の事業運営能力や経済的インセンティブに関する深い理解が必要であり 、また、誰が「使用を指図する権利」を持つかの判断には、契約書の文面だけでなく、資産が現場で実際にどのように使用されているかというオペレーションの実態把握が不可欠だからです。これらの情報は会計部門単独では持ち得ず、調達、IT、法務、そして事業部門との恒常的な連携によってはじめて得られます。したがって、企業は、契約締結「前」にその会計上の影響を評価するための、恒久的かつ部門横断的な業務プロセスを構築する必要に迫られます。これは、財務コントローラーの機能を、望ましい会計成果を達成するために契約構造に影響を与えることができる戦略的パートナーへと昇華させる、重要なガバナンス上の変革を意味します。
表1:リース識別判定フレームワーク
| ステップ | 判定項目 | 判断基準と考慮事項 | 判定結果 |
|---|---|---|---|
| Step 1 | 特定された資産の存在 | Q1: 契約において、資産は明示的または黙示的に特定されているか? (例:シリアル番号、所在地、型番など) | No → サービス契約(リースに非該当) Yes → Step 1-2へ |
| Q2: 供給者は、実質的な資産の代替権を有しているか? ・供給者は資産を代替する実務的な能力を持つか? ・供給者は資産を代替することで経済的利益を得るか?(利益 > コスト) ・代替に顧客の同意は不要か? | Yes → サービス契約(リースに非該当) No → 「特定された資産」が存在。Step 2へ | ||
| Step 2 | 使用の支配権の移転 | Q3: 顧客は、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか? | No → サービス契約(リースに非該当) Yes → Step 2-2へ |
| Q4: 顧客は、特定された資産の使用を指図する権利を有しているか? ・顧客は、資産を「どのように」「何の目的で」使用するかを決定できるか? ・資産の使用に関する重要な意思決定権は顧客にあるか? | No → サービス契約(リースに非該当) Yes → リース契約に該当 |
このフレームワークは、抽象的な基準を実務的な判断プロセスに落とし込むためのツールです。一貫した適用を通じて、リース判定の正確性と監査可能性を高めることが、新基準遵守の第一歩となります。
企業内に潜む「隠れリース」の例は?
「隠れリース」の探索は、既知のリース契約リストを見直すだけでは不十分です。むしろ、これまで費用として処理されてきた多種多様な契約ポートフォリオの中に埋もれている可能性が高いです。
このセクションでは、企業が「隠れリース」を発見するための具体的な探索領域を、非網羅的ではありますが広範な例示とともに示します。
1 不動産および施設関連
不動産関連契約は、新基準下でリースと判定される最も典型的な例です。
- 明白なリース: オフィスビル、店舗、工場、倉庫の賃貸借契約。
- 潜在的な隠れリース:
- 特定の駐車スペースの長期使用契約。
- 特定の広告看板スペースの独占的使用契約。
- 第三者倉庫内の特定の区画を長期間、排他的に使用する契約。
- データセンター内の特定のサーバーラックを専有する契約。
2 情報技術(IT)関連
ITインフラやサービスに関する契約は、「隠れリース」の温床となりやすい領域です。
- 明白なリース: PC、サーバー、複合機などのレンタル・リース契約。
- 潜在的な隠れリース:
- ITアウトソーシング契約の中で、顧客専用のサーバーやネットワーク機器が割り当てられ、その使用を顧客が実質的に支配している場合。
- 特定の物理サーバー群を顧客が占有する形態の「プライベートクラウド」や「専用ホスティング」サービス契約 。
- SaaS(Software-as-a-Service)契約であっても、そのサービス提供のために特定のハードウェアが黙示的に顧客に割り当てられ、供給者の代替権が実質的でないと判断される稀なケース。
3 オペレーション、製造、物流関連
企業の根幹をなす事業活動に関連する契約にも、「隠れリース」は潜んでいます。
- 潜在的な隠れリース:
- 製造委託契約: 顧客が特定の生産ラインや工場全体を独占的に使用し、その稼働を指示する権利を有している場合。
- 物流・輸送契約: 顧客の指示のもと、特定のトラック、船舶、航空機が専属で輸送業務に従事する契約。
- エネルギー供給契約: 特定の太陽光発電所や風力発電所から生み出される電力のほぼすべてを、特定の顧客が購入する権利を持つ電力購入契約(PPA)。
- 設備関連サービス契約: 顧客の敷地内に設置された特定のセキュリティシステム、空調設備、発電機などを長期間使用する権利を含む保守・管理契約。
これらの「隠れリース」の探索は、法務部門や財務部門だけで完結するものではありません。
その多くは、「ITサービス費」「運送費」「広告宣伝費」といった営業費用勘定で処理されており、契約自体もIT、物流、マーケティングといった各事業部門が管理しています。したがって、既存のリース台帳のレビューは全く不十分であり、真に網羅的な発見プロセスには、総勘定元帳データから特定のベンダーへの定額支払いを抽出するデータマイニングや、各部門の予算責任者への積極的なヒアリングを通じて、対象となりうる契約を洗い出す「宝探し」のような地道な作業が不可欠です。この発見フェーズこそが、プロジェクト全体で最も時間と労力を要する部分です。
隠れリースと、財務諸表とKPIへの影響は?
「隠れリース」を特定し、オンバランス処理することは、企業の財務状況と経営成績の表示に、深く、時には直感に反する影響を及ぼします。このセクションでは、その具体的なメカニズムと、主要な財務指標に与える影響を詳細に分析します。
1 オンバランス会計のメカニズム
リース契約を資産・負債として計上する際の会計処理は、以下のステップで行われます。
- 当初測定:
- リース負債: 将来支払うべきリース料総額を、一定の割引率を用いて現在価値に割り引いて計算します。この計算には、リース期間(行使することが合理的に確実な延長オプションおよび行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間も含む )と、
割引率(貸手の計算利子率を知り得る場合は当該利率により、知り得ない場合は借手の追加借入利子率 )の決定が不可欠となります。 - 使用権資産: 当初測定時のリース負債の額に、借手が支払った初期直接費用や前払リース料などを加算し、受領したリース・インセンティブを減算して算定します。
- リース負債: 将来支払うべきリース料総額を、一定の割引率を用いて現在価値に割り引いて計算します。この計算には、リース期間(行使することが合理的に確実な延長オプションおよび行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間も含む )と、
- 事後測定:
- リース負債: 原則として利息法に基づき、残高に利息を認識して増加させ、リース料の支払額を減額させます。これにより、毎期「支払利息」が費用として計上されます。
- 使用権資産: 所有権が移転すると認められるリース取引の場合は自己所有の同一の資産と同様の方法により減価償却費を計算し、所有権が移転すると認められないリース取引の場合はリース期間にわたって定額法で減価償却され、毎期「減価償却費」が費用として計上されます。
2 貸借対照表の変貌:「グロスアップ」効果
これまでオフバランスであったオペレーティング・リース(隠れリースを含む)を資産(使用権資産)・負債(リース負債)として計上することにより、企業の貸借対照表は総資産と総負債の両方が大幅に増加します。これは「グロスアップ」効果と呼ばれます。
このグロスアップは、企業の財務健全性を示す主要な指標に直接的な影響を与えます。
- 負債比率・有利子負債比率: 負債総額が増加するため、これらのレバレッジ指標は上昇し、企業がより多くの負債を抱えているように見える可能性があります。
- 自己資本比率: 自己資本の額は変わらない一方で、分母である総資産(または負債純資産合計)が増加するため、自己資本比率は低下します。
実際にIFRS第16号を先行適用した海外の小売業などでは、負債総額が10%から100%以上増加した事例も見られ、特に不動産賃借の多い業態ではその影響の大きさがうかがえます。
3 損益計算書とキャッシュ・フローの再構築
- 費用の前倒し計上(フロント・ローディング): リース期間全体で認識される費用総額は、旧基準のオペレーティング・リース処理と変わりません。しかし、費用の期間配分のパターンが変化します。定額で計上される減価償却費と、リース負債の残高が大きい期間初期に多く計上される支払利息の合計額は、リース期間の初期に大きく、後期になるにつれて小さくなる傾向があります。
- EBITDAの増加: 新基準がもたらす影響の中で、最も重要かつ誤解を招きやすいのがEBITDAの増加です。
4 財務制限条項、格付け、業績評価指標への波及効果
- 財務制限条項(コベナンツ): 多くの融資契約には、負債比率の上限やインタレスト・カバレッジ・レシオの下限といった財務指標に基づく制限条項が含まれています。新基準の適用による指標の変動が、意図せず条項に抵触するリスクがあるため、金融機関との事前の協議・再交渉が不可欠となります。
- 信用格付け: 格付機関は会計基準の変更を理解しているものの、報告されるレバレッジ指標の上昇が、企業の信用力に対する市場の認識に悪影響を与える可能性は否定できません。
- 業績評価指標: 総資産の増加に伴い、ROA(総資産利益率)は低下します。また、EBITDAや営業利益に連動する役員報酬制度は、会計上の見かけの利益増加によって意図しない過大な報酬支払いを引き起こす可能性があるため、評価指標の再設計が必要となる場合があります。
特にEBITDAの増加は、経済的実態の改善を伴わない会計上の表面的な効果に過ぎません。経営陣は、この見かけ上の利益改善が、実際のオペレーションの収益性向上を意味するものではないことを、投資家やアナリストに対して明確に説明するという、重要なコミュニケーション上の課題を負います。
この説明責任を果たさなければ、市場が企業の株価を誤って評価するリスクが生じます。したがって、経営陣は、新旧基準間の調整表を開示するなど、企業の真の基礎的収益力を示すための補足情報を提供し、市場との対話を積極的に行うことが求められます。
表2:財務影響の設例分析(適用前 vs. 適用後)
(前提:年間賃借料100の店舗を5年間賃借する小売業。割引率3%。簡便化のため税効果は無視)
| 項目 | 適用前(オペレーティング・リース) | 適用後(新リース会計基準) | 影響と解説 |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表(当初) | |||
| 使用権資産 | 0 | 458 | リース資産をオンバランス化します。 |
| 総資産 | 増加なし | 458 増加 | 総資産が大幅に増加します。 |
| リース負債 | 0 | 458 | 将来の支払義務を負債計上します。 |
| 総負債 | 増加なし | 458 増加 | レバレッジが上昇します。 |
| 自己資本比率 | 変化なし | 低下 | 総資産の増加により比率が悪化します。 |
| 損益計算書(1年目) | |||
| 営業費用(賃借料) | 100 | 0 | 賃借料は計上されなくなります。 |
| 減価償却費 | 0 | 92 (458÷5) | 使用権資産の償却費を計上します。 |
| 支払利息(営業外費用) | 0 | 14 (458×3%) | リース負債に係る利息を計上します。 |
| 費用合計 | 100 | 106 | 費用の前倒し計上により、初期は費用増となります。 |
| 営業利益 | 100 減少 | 92 減少 | 支払利息が営業外費用のため、営業利益は増加します。 |
| EBITDA | 100 減少 | 増加なし (※) | 賃借料が減価償却費に置き換わるためEBITDAは増加します。 |
| 主要経営指標 | |||
| ROA(総資産利益率) | 変化なし | 低下 | 総資産の増加により指標が悪化します。 |
(※) EBITDA = 税引前利益 + 支払利息 + 減価償却費。適用前は税引前利益が100減少し、EBITDAも100減少します。適用後は税引前利益が106減少し、支払利息14と減価償却費92を加算するため、EBITDAへの影響はゼロとなり、結果として適用前比でEBITDAは100増加します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
新リース会計の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引